金毘羅参り
長男の兵太郎が10歳になり、娘のイトも6歳に成長した。兵太郎は、祖父の源蔵から釣り竿の作り方を習うのに熱心である。イトはというと、祖母のミツとお手玉遊びに夢中。久しぶりに仕事場を離れて母屋にいても、伝のやることがなくて落ち着かない。文政5(1822)年の夏も終ろうとする頃であった。
若君の乳付に八丁島村のお杉を送り込んだ後、疲れがどっときて仕事場にも出たくなかった。そんな時、思いがけない人物が訪ねてきた。兄の敏造である。祖母ヨシノが死んですぐ出家し、京都の寺に入った。その後16年間音沙汰がなかったが、人の噂では、辛抱強く修業に励んでいると聞いていた。兄は2歳年上だから、もう37歳になっているはずである。薄衣に編み笠と金剛杖(こんごうつえ)・頭陀袋(ずだぶくろ)が似合う行脚中(あんぎゃちゅう)の僧侶であった。
僧名を「大量」と名乗っている敏造は、先ず父と母に深々と頭を下げて重なる親不孝を詫びた。源蔵とミツは恨みの一つも言わず、ただ息子の無事を喜んでいる風である。
「お伝にも苦労をかけたの」
生まれつき自分とは性格の異なる兄を、伝が慕うことはなかった。ここにきて慰められても、何の役にもたたないことだった。
「兄しゃん、今頃何しに帰ってきた?」
ひと通りの勤めに区切りがついた頃合を見計らって、伝が切り出した。
「修行で四国から九州に渡り、寺々を回りながら各地の有り様を見てきたところだ。相次ぐ凶作で、どこのお百姓も食うや食わずの暮らしをしている。そんな時、僅かなりともお役に立てればと、お百姓さんと一緒に仏に祈ることにしている。一昨日に肥後から筑後に入ったばかりだ。積もる親不孝を詫びないで、このまま京に戻るわけにもいくまい」
大量は、旅先での面白い話や厳しい現実を語った。
「九州に渡る前、弘法大師ゆかりの四国八十八カ所を隈なく回った。大師が幼少の頃より、ふるさと四国の寺々で修練なされた足跡を辿ってみたかったからだ。すると、己が犯した罪の大きさを知り、いかにすれば仏に許してもらえるかを考えるようになった」
話を聞いていくうちに、兄が自らに問うた「己の罪」と二男の浅吉を死なせた自分の罪が重なってしまう。
「兄しゃん、四国のどこのお寺さんに行けば、胸の中のもやもやば払いのけてもらえるとじゃろうか」
「まずは、お大師さまがお生まれになった讃岐の善通寺さんをお尋ねしたらよかろう」
伝が弟子のユキエとアキを伴って四国に旅立ったのは、それから3年後の秋だった。「せっかく他国を旅するなら」と、手織りの中でもなるべく目立つかすりを旅装束にした。小倉から船に乗って讃岐の港へ。金毘羅宮の参道に面した旅籠(はたご)に着いたとき、久留米を発ってから1週間が経っていた。3人は、慣れない旅で痛めた足を、代わる代わる擦り合った。
「素敵なお着物ですね。どちらの織物でしょうか?」
大部屋の向こうから声をかけてくる女がいる。歳の頃なら伝より5、6歳上だろうか。
「・・・ああ、これですか。私が織ったものです。私の住む筑後では、加寿利と言うとります」
得たりとばかり、伝が答えた。
「藍と白地の按配(あんばい)が鮮やかですね。失礼しました。私は伊予の国は垣生村(はぶむら)(現愛媛県松山市)から来たものです。私も、白木綿(しろもめん)や縞などを織って暮らしているのですが・・・。どうしたらこんなに美しい柄が織れるものか、よかったら教えていただけませんか」
人懐(ひとなつ)こい仕草に初対面とも思えず、女性に下絵描きから糸括りまでの行程をかいつまんで話した。普段なら企業秘密に類するところだが、これが旅先での気の緩みとでもいうのだろうか。
翌日早く、伝とユキエらは、金毘羅宮本宮に通じる長い階段を登り始めた。まず本宮までが750段。「せっかく行くなら奥の社まで行かなきゃご利益が薄かろう」と考え、合わせて1300段を登りきった。「階段を登りながら、己を見つめろ」と兄は言ったが、なかなかその心境には達しない。
.gif)
金毘羅宮の長階段に続く参道
このお宮さんのもともとは、漁師や船乗りの信仰から始まったらしい。それが江戸時代に入ると、いろいろな願いを込めて日本全国から参拝客が押し寄せるようになった。
.gif)
善通寺の五重塔
森の石松が親分の代参で金毘羅宮に行く途中、三十石船上で「飲みねえ、食いねえ、鮨食いねえ」と吐く台詞(せりふ)は、あまりにも有名である。
伝とユキエらは旅籠でもう1泊した後、弘法大師誕生の寺といわれる善通寺に出向いた。寺院の規模の大きさに驚くやら感心するやら。悩みごとや願いごとを持ち寄ってくる遍路姿の老若男女の真剣な顔つきに、圧倒されるばかりであった。
「なかなか、仏さまに許してもらえそうになかね」。2日目の夜、伝はしみじみユキエに漏らした。心の底から仏に縋(すが)ろうとすることができず、仏前で手を合わせていても、つい久留米の作業場のことが気になるし、道ゆく人のなりふりに気をとられてしまう自分が情けないと。
さて、参道脇の旅籠で話しかけてきた女性であるが、名前を鍵屋カナ(1782〜1869)といい、現在の伊予絣を考え出した本人である。彼女は垣生村(はぶむら)に帰ると、讃岐の宿で聞いた久留米のかすり織り手法を手がかりに、一味違う織物を生み出すべく試行錯誤を繰り返した。
藁葺屋根(わらぶきやね)の葺(ふ)き替えを見て閃(ひらめ)くものを感じた。すすけた押し竹を括っていた縄をはずすと、そこだけが新竹のように鮮やかな模様を描き出している。その理屈を活かして完成したのが、久留米絣と並び称される「伊豫(いよ)かすり」であった。当初の伊豫かすりには、カナの出身地名をとって「今津鹿摺(いまづかすり)」と名づけられたという。
久留米藩は、財政窮乏を凌(しの)ぐために、領民に対して更なる難題を押し付けた。町人からは多額の税をとり、困窮する農民からも苛酷なまでに年貢を納めさせた。倹約のために、着るものは自前で賄えとも指導した。農民は、お上に言われるままに朝早くから田んぼに出て働き、夜は僅かの灯りを頼りに、家族が着るものを縫った。
伝が織った木綿布の大半は、これら働く農婦の着る作業着になり、布団地ともなった。農婦らは、例え着ているものが泥だらけになろうとも、少しでも美しくて洒落(しゃれ)たものを身につけたいと願うもの。そこで伝は、彼女らが好みそうな柄の布を織ることに腐心した。
年月は下って文政11(1828)年。伝、齢(よわい)四十の峠にさしかかる頃、兵太郎20歳で、イトも16歳に成長していた。
兵太郎を織屋の跡継ぎにするのは当然として、イトには、自ら編み出した「お傳加寿利」の技術を引き継いでもらわなければならない。
この5年の間に、母のミツと父の源蔵が相次いで黄泉(よみ)の世界に旅立っていった。これもまた時代の移り変わりだと考えることにしている。これからは自分が井上家の当主としての責任も担わなければとも。
「母さんがお前の歳頃には、加寿利の織り方ば考え出して、弟子もいたもんだ」
伝はイトに対して、ことあるごとにはた織り技術の向上を促した。少しでもやる気が見えなかったり、よそ見をしたら、容赦なく物指(ものさし)が飛んだ。弟子たちには、その時の伝が夜叉にも見えたという。
飽くなき研究
久しく姿を見せなかった紺屋(こうや)の佐助が現れた。
「いい加減にせんと。おイトちゃんにまで嫌われるが」
見るに見かねたユキエが通報したに違いない。
「でもね、イトが頑張らないと、こちらまで駄目になってしまいそうだもん。イトはうちの命じゃけんね」
「おイトちゃんにそげんはた織りが上手になってもらいたかなら、いっぺん、他人の飯ば食わせてみたらどげんね」
「あげな甘ったれ娘ば預ってくれるお人好しが、どこの世界においでじゃろか?」
「松屋の庄兵衛さんはどげんね。あの人ならお伝の気持ちもようわかっとるし、おイトちゃんば引き受けてくれるはず」
佐助は、言いたいことを言い終わると、さっさと帰って行った。
「おイトちゃんは、なかなか筋がよか」
ある時、まじめな顔で庄兵衛が報告した。「あの娘(こ)が、本当に?」と聞き返したくなるくらい驚いた。
「やっぱりお伝さんの娘たいね。この頃では、新しか柄ば次々に考え出しよる」
イトのやる気の報は、伝の意欲を煽(あお)ることにもなった。作業場では、50人の弟子たちが働いている。伝の教えを受けた弟子の数は、孫弟子も含めて既に500人を超えたと、ユキエが教えてくれた。作業場を巣立って在方(田舎)に戻っていった弟子たちが村の娘たちの先生になって、次なる織り子を育てている者もいる。
右手に2本の梳き櫛(すきぐし)を持ったまま、隅の腰掛台に座りこんで考え込むのが、伝の新しい柄を考える時の癖(くせ)である。傍(かたわ)らには必ず餅米の飴(あめ)とおこしを置いている。目は図柄に据えて、左手は重箱と口を単純に往復させる。口が静かに閉じられていることはまずない。甘いものを食べ過ぎるせいで、常薬の「ボレー」なる胃薬をいつも服用していた。
伝の絵がすりは、儀右衛門が考え出した板締め技法が基になっている。まず、作業台の両端に相対する形で釘を打ち、持っている2本の梳き櫛を2尺ばかりの間隔に置いて、これを板に打ちつけ、櫛の歯に糸を掛け渡し、渡した糸に画を描いていく。
より複雑な図柄になると、なかなか思うようにいかない。こんな時、細工屋の儀右衛門に相談してみたらとも思うが、「手間賃をいくらくれる?」と跳ね返ってきそうで、つい尻込みをしてしまう。儀右衛門一家が京都に移転するのは、それから間もなくである。
庄兵衛の店に修業に出ていた娘のイトが戻ってきた。伝は、戻る早々注文を受けている作業を娘に任せた。
「お母しゃん、うちにも新しか柄ば考えさせてくれんね」
言われて伝は、「お前なんかに・・・」とも言えなくなった。
「よかよ、いっしょに考えよう」
この頃から、伝とイトによる二人三脚の織屋稼業が本格化する。
若者からの挑戦状
伝が庄兵衛の店に出向くと、身の丈6尺にも及びそうな若者を紹介された。齢の頃なら30歳を過ぎたくらいだろうか。背を丸めるようにして立っている。
「どうしてもお伝さんと話がしとうて・・・」
大塚太蔵(おおつかたぞう)と名乗る男は、文化3(1806)年に三潴郡津福村(みずまぐんつぶくむら)(現久留米市)の農家に生まれたと言う。子供の頃から百姓が嫌いで、あるお侍さんに取り入ったのが縁で、殿さまの参勤交代にお伴をした後、江戸に住むことになった。
太蔵は子供の頃から絵を描くことが大好きで、江戸滞在中もあちこちの店を覗(のぞ)いたりして勉強を怠らなかった。そんな太蔵の熱意を汲んだ主人は、彼を足軽に取り立ててくれた。
やっとのことで武士の身分を得たものの、長年続く痔病が障害となって思うように武道に励めず、士籍を返上して久留米に帰ってきた。
実家に戻ってからも、田んぼに出ることはなかった。母親や妹の仕事を手伝ってはた織りをしているうちに、いつしか、自身がかすり織りの面白さにはまり込んでしまった。この男、井上伝とは年齢にして18の差があり、引き合わせた庄兵衛からも8歳弟分である。
「あんたのような大男が・・・」と言いかけて、その先の言葉を飲み込んだ。
「・・・いざり機に座り込んでいる姿はおかしか」と口から出そうになったのだが、さすがにそれは相手に失礼だと思ったからだ。
「よかですよ、遠慮なさらんで。男がはた織りはおかしかと、言いたかとでしょう?」
伝は、幼い頃祖母に「男は体を使って外で働くもの。女が家ではた織りをするのは、男に尽くすため」と教えられたことを忘れないでいる。
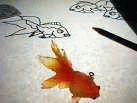
友禅染
「伝さんの思われるとおりかも知れまっせん。ばってん、江戸にいるとき見た、着物の柄の美しさが頭から離れんとですよ。それで・・・」
「でもね、かすりは襖(ふすま)や掛け軸に絵を描くようなわけにはいきませんよ」
伝は、目の前の男の頭の中を整理してやりたいと思うが、うまく言葉にならない。
「伝さんが作りなさる加寿利は、簡単な模様ば並べただけのもので変化に乏しかです」
さすがに伝の堪忍袋が破裂寸前となった。相手は、母や妹のはた織りを手伝う程度の経験しか持たない男である。物心ついてからすぐにはた織りを始めた先輩に吐く台詞(せりふ)ではない。
「あたしに話したかことがあるとじゃろ。それば先に言わんね」
伝は、大人気もなく感情が高ぶっている自分に気がついている。
「はい、加寿利ば編み出されたお伝さんには大変失礼だとは思いますばってん・・・」
相手の男はあくまでも冷静である。「・・・何を喋ってもよかよ」と言ってはみたものの、伝は次なる展開の見当すら見つけられない。
「絵とか文字ば、もうちょっと自在に織れんものかと」
話しの途中で庄兵衛が、「控えなさい、太蔵」と咎(とが)めるのを、逆に伝が抑えた。
「お殿さまにお供して江戸に上がったとき見たとです。友禅染(ゆうぜんぞめ)の花や鳥や風景の模様ば。鮮やかな色ば使うて・・・」
「ばってん、友禅は布地の上に直に絵を描いていくもんじゃろ。かすりは、下絵に合わせて糸ば括り、藍汁で染めてから織っていくもの。まさか、友禅のごたる絵を、かすり織りにしろと言うんじゃなかろうね」
「不可能ですかね、お伝さんの腕をしても」
絶対不可能と言い切るのも面白くないし、その場はこれからの研究課題だということにして話を打ち切った。
「今度在方に帰るノシが挨拶したいそうです」
作業場では指導者格のトシコが取り次いだ。ノシは3年前に福島の稲富村(現八女市)から父親に連れられてやってきた娘である。文化9(1812)年生まれと聞いているから、17歳になったばかりだろう。
「あんたがここに来たのは、十四(歳)の時じゃったもんね。よく頑張ったね。これからは、覚えたことば忘れんごとして、父ちゃんや母ちゃんば楽させてやらなきゃね」
教練を終えて巣立っていく弟子たちに贈る、いつもながらのはなむけの言葉であった。それまでうつむき加減だったノシが、背中をピンと伸ばした。
「うちは、近いうちに、先生より上手なかすりの織り手になります」
突然の弟子からの挑戦に、伝は思わず身を引いた。
「どげな風に・・・?」
「先生でもできんかったかすりば織るとです」
師を越えて見せるという小娘に、伝はいきなりカウンターパンチを喰らった思いであった。
「ノシが言うとる、師匠の私でもできんかったもんちは、いったいどげなかすりね」
「先生が織りなさるものより、もっと細かくて美しか柄のかすりば織りたかとです」
なるほど、伝が子供の時から作り上げてきたのは、模様にしても絵がすりにしても比較的柄が大きかった。
「ノシが考えとるかすりの柄は、どのくらい細かいものじゃろか」
「蚊が飛んどるくらいに小さか柄です。それ以上は、今はまだ言えません。ばってん、必ずやります」
蚊が飛んでいるほどに小さな柄など、これまでに考えたこともなかった。しかも、師が織るものより、もっと美しいかすりを織ってみせると宣言する目の前の弟子。伝は、反発する以前に寒気のようなものを覚えた。
織り手としては素人同然の太蔵と、作業場から今卒業していく弟子から、まさしく果たし状を叩きつけられた格好の伝である。
最も身近な娘の腕前も、やがて自分の技量を追い越そうとしている。
|
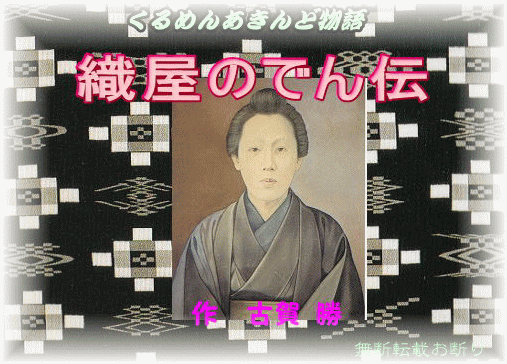
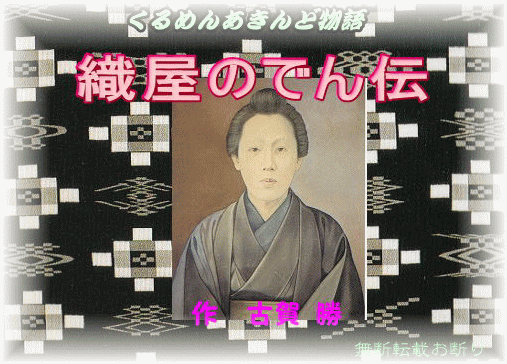
![]()