|
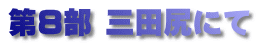

高杉の死後、望東尼はただぼんやりとした日を過ごしていた。楫取素彦が手配してくれた手伝いの娘・トキとの世間話が、唯一の安らぎの時間にもなっていた。
「谷梅(高杉の別名)さんが逝って、もう10日だね。待っていなさるだろうね、わたしが会いに来るのを。早く行かなきゃ」
うつろな目で庭を眺めながら呟いた。そばにいるトキが反応した。
「出かけましょうよ、お供しますから」
1.gif)
高杉晋作の墓所
高杉が眠る吉田村(現下関市大字吉田)まで北へ6里、男の足でも5時間はかかる。若いトキの体力を頼りに朝早く出立して、長府の茶店で昼ご飯をいただいた。宿泊先は、吉田村の庄屋・野原清之助宅。これも、楫取の手回しである。庄屋の家に着いたのは、陽も完全に沈んだ時刻であった。
翌朝、庄屋に案内されて、高杉の墓前に額づいた。
「やっとお会いできましたよ。貴方がいなくなって、本当に寂しゅうございます」
そばにいる庄屋にもトキにも悟られないように、俯いたままで10日ぶりの再会を告げた。事前の心配とは逆に、不思議と涙は出てこなかった。
墓標と敷地は、山県有朋が高杉の愛妾・ウノに贈ったものである。東行の墓名は、高杉晋作の号名。
※山県有朋:明治・大正時代の政治家。元奇兵隊の幹部を経て、維新後首相となる。
高杉晋作亡き後、途方に暮れる望東尼を支えたのは楫取素彦とヒサ夫妻である。病床にあった高杉は、難を逃れて長州に来た望東尼の面倒を、楫取に託していたのであった。楫取は、藩主毛利敬親(もうりたかちか)のそばにあって、藩(国)事に奔走する毎日である。
.gif)
楫取素彦の墓(防府市)
高杉の四十九日法要も過ぎた頃、望東尼のもとに楫取がやってきた。楫取は彼女がより安心して過ごせる場所として、居を山口(現在の山口市)に移すよう促した。「ここなら、妻のヒサも十分にお世話ができる」からとも言ってくれた。山口からだと、萩往還(国道262号)を北へ10里進んだところに萩城が建つ。
山口における滞在先は、湯田温泉郷の吉田屋であった。吉田屋は、この地にあって由緒ある家柄である。身に余る厚遇であると、改めて高杉に感謝するのであった。
吉田屋に落ち着いて間もなく、今度は藩主敬親の遣いが現れた。正装である。遣いは、十三代藩主からだと、一服の反物を差し出した。姫島の牢獄から一転して、藩主からの下賜を授かるとは、想像すらしなかった栄誉であると望東尼は感謝した。
湯田の郷を出て、西へ1里も歩くと鼓の滝に行き着く。名前の通り、飛沫を跳ね上げながら落ちる水のさまは、鼓に合わせて踊る龍のごときである。心行くまで自然の美を楽しみながら、歌人としてこの上ない贅沢な時を過ごした。
わすられぬ心づくしのなかりせば湯田のたゆたに物を思はじ
この歌は、身に余る藩主からの恵みを受けて、湯田の里に落ち着いた気持ちを詠んだものである。
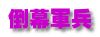
心に落ち着きを取り戻すとすぐに、在りし日の平尾山荘と若き同士たちのことが気にかかる。
特に孫の助作のことが心配でならなかった。だが願いも空しく、助作は城下に造られた獄中で帰らぬ人になったと知らされた。助作の獄中生活は2年近くに及んだと言う。
浮雲はまだ晴れやらぬ身なれども露の心は世には残さず
助作の辞世の句である。嫌疑が晴れないままの身ではあるが、少しも心をこの世には残すまいと詠んでいる。助作に続いて実姉の吉田タカも没したと知らせが届いた。続けさまの故郷での不幸を聞いても、駆けつけられないこの身がもどかしい。
その間にも、世の中の動きは激しさを増していた。倒幕派雄藩と幕府存続を唱える藩が日本列島を二分したまま、一触即発の緊張状態が続いていたのだ。270年もの間続いた德川の世である、それも当然の成り行きなのかも知れない。
慶応3(1867)年9月19日。江戸時代最後の時節となった。野村望東尼は62歳になっている。
坂本龍馬らの仲介もあって、薩摩と長州藩が手を結び、倒幕のための密議が熱を帯びていた。討議に加わったのは薩摩側が大久保利通や西郷隆盛であり、高杉亡き後の長州からは桂小五郎らであった。その密議で、倒幕のための出兵に関する合意がなされた。薩摩藩兵は、9月25日までに三田尻の港に到着し、長州軍と合流する。その後は共に東上して、幕府の主要人物が集まる大坂城を攻める算段であった。長州藩はお隣の安芸藩にも働きかけ、薩長芸の三藩連合軍の出兵という予定もできあがりつつあった。
※薩長同盟:幕末1866年。薩摩・長州両藩が結んだ同盟。両藩は1863年8月18日の政変以来反目していたが、第2次長州征伐の頃から、大久保利通・西郷隆盛ら討幕派が藩論を動かした。土佐藩の坂本龍馬らの仲介により、長州藩の木戸孝充らと折衝して同盟が成立。幕府に対抗して両藩の相互援助を約し、以後武力討幕派の勢力が台頭。
9月23日。望東尼は、三田尻港に向かう長州兵を見送るべく、萩往還に赴いた。倒幕を目指して進む若者らは、かつて平尾山荘に出入りしていた福岡藩の若者と重なる。もう少し自身が若ければ…、自分が病弱でなければ…、それより何より、この身が男であったなら。「間違いなくこのような部隊に身を置いていたであろうに。そして幕府を、この手で打ち負かす役の一翼を担っていたろうに」と、声を震わせながら若い兵士らを励ました。

湯田郷に戻った望東尼を、内儀風女性が待っていた。楫取素彦夫人のヒサである。初対面である彼女、実は高杉晋作や桂小五郎などが学んだ松下塾吉田松陰の実妹であった。
「早くお訪ねするようにと、主人から言われていたのですが…」
遠慮深そうに挨拶する姿は、いかにも楫取素彦の夫人に似つかわしいと感じる。
1.gif)
湯田温泉井上公園(七卿滞在地)
「私も、三田尻におられる荒瀬百合子先生に習って、少しばかりですが…」
和歌を勉強中であると、ヒサは自己紹介した。
「荒瀬先生も、貴女にお会いしたいとおっしゃっていました」
三田尻は、長州軍が薩摩軍と合流する予定の港町である。長州軍の参謀には、ヒサの夫である楫取素彦が任じられているとも聞かされていた。
望東尼は、出来ることなら自分も三田尻まで出かけて、若い兵士らを見送りたいと思っている。三田尻では、防府の天満宮に額づいて、彼らの戦勝を祈願するつもりであった。心を込めて詠んだ和歌を、信仰する天神さま(菅原道真)に捧げて祈願したかった。
「きっと、荒瀬先生も喜ばれますわ。早速使いを出して、その旨伝えておきます」
近々再会することを約束して、ヒサは帰って行った。
9月25日早朝。望東尼は、藤 四郎にも告げず萩往還に向かった。藤四郎に言えば、「ご自身の歳をいくつだとお思いか」、「病み上がりだということをお忘れか」ときつく叱られるに相違ない。自身、年齢や病弱のことを気にしていないわけではない。それよりも、杖一本を頼りの一人旅では、心細くないわけがない。それでも、湯田郷で倒幕の吉報を待つだけでは、その方が耐えがたい。「もしも私が若かったら…、男だったら…」の気持ちがそうさせるのである。
往還に出て鰐石橋を渡る頃には陽も昇り、川底から吹き上げてくる風が冷たかった。萩往還は、日本海側の萩城を起点として、瀬戸内海の三田尻まで、ほぼ直線的に結ばれている。この道は、大名行列のためだけではなく、一般庶民にとっても、「陰陽連絡道」として重要な役割を果たしてきた。

往還を行き交う人々も、商人風であったり武士であったり、百姓や遊び人風まで様々である。一里塚や茶店などもそれなりに整備されていて、老女の一人歩きもさほど心配ではなかった。吉田屋を出て3里ほど歩いて、景勝地の鳴滝に着いた。そこで疲れをとっている間も、日暮れが気になる。途中いくつかの峠道を越えるときなど、足が重くて道ばたに座り込むこともしばしば。夕刻が迫っての、勝坂峠の上りはさすがに堪えた。座り込んでいるところを、通りがかりの百姓の荷車に乗せてもらった。
a.gif)
萩往還勝坂峠付近
百姓と別れた後は、また一人旅になる。ここで留まっていては、天満宮まで行き着くことなどおぼつかない。気持ちを高めて、また歩き出した。茶をすすりたいが、次の茶店がなかなか近づかない。そんな時は道端を流れる小川の水がありがたかった。老体を心配してくれて、道中の話し相手をしてくれる娘に手を取ってもらうこともあった。
次の峠道にさしかかったとき、追い越してくる屈強な男に「大丈夫かい」と声をかけられた。「松崎の天神さま(防府天満宮)まであとどのくらい?」。力ない声で尋ねると、「3里ほどかな」。男は、「もとは侍だったが、今は浪人」だと断りながら、手を引いてくれた。
「あんたはお坊さんらしいが、その言葉だと地のもんじゃないね」と、男が問うた。「筑前の博多の出ですよ。生業は和歌を詠む歌人ですがね。見ての通り仏に仕える身ながら、なかなか俗世とも縁が切れなくて…」
そんな会話も長くは続かず、分かれ道が来たら男は別の方に走り去った。再び一人旅に戻ると、両の足が絡まって先に進まなくなった。泣きたくなって座り込むと、なぜだか福岡城下の平尾山荘が瞼の裏に浮かんでくる。助作亡き後、野村本家は取り潰しになったのだろうか。早く帰って、私がなんとかしなければ」と、気持ちが空回りする。考えることは、兄弟喧嘩や塾の師に叱られたことなど、遠い昔の出来事ばかり。目の前がぼやけて、膝から崩れかかったところまでは覚えている。
|

1.gif)

1.gif)
![]()