|
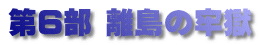

姫島全景 アカ□=姫島牢獄 アオ○=姫島漁港


望東尼を乗せた船が姫島の桟橋に着いた。夜が明けて間もないというのに、数人の島民が唐丸籠を取り巻いた。中には、見覚えのある女房や娘の顔も確認できた。
唐丸籠が浜定番(はまじょうばん)屋敷に入った。暫時屋根の下で待たされる。そこで出された冷や飯も、白湯だけでは喉を通りそうにない。昼過ぎから裏庭の白州に引き出され、藁茣蓙(わらござ)に座らされた。
「ここに直れ」。屋敷の小役人が指さした。しばらく待つと、上方からかすれ声が降ってきた。「面(おもて)を上げい」と叫んでいる。自分を見下ろしているのは、かつて弟の部下であった小島源五右衛門であった。小島は、望東尼に挨拶をしたいような眼差しを向けた。だが、すぐに険しい顔に戻り、「流刑囚の心得」を形式的に読みあげて、さっさと奥に引っ込んだ。
小役人に両脇を抱えられ、再び唐丸籠に押し込まれた。連れて行かれた先は山の中腹に建てられた粗末な獄舎である。降りたって南方を眺めると、眼下に白波の立つ海が見える。玄界灘である。慶応元(1865)年11月15日。晩秋の真昼時であった。
これから寝起きする獄舎は、まさしく囚人が住むに相応しい小屋である。四角い建物の屋根には、薄っぺらな瓦が置いてあるだけ。縦1間半(2.7㍍)、横2間(3.6㍍)の広さに、寝起きするための畳が1枚と敷板が置かれている。そのすぐ隣に雪隠(せっちん)(便所)があり、またその隣が警護室になっている。
a.gif)
姫島獄舎跡(望東尼御堂)
護送してきた役人は、望東尼の身辺を念入りに調べた。自殺の恐れのある刃物や、火災のもとになりそうな蝋燭などを隠していないか点検するためである。望東尼を獄に閉じ込めた後、役人は外から頑丈な錠前をかけたあとすぐに立ち去った。役人が警固室に寝泊まりしないことを知り、安堵した。
長かった一日が終わりに近づき海岸線に陽が沈むと、月明かりが板戸の隙間から差し込んでくる。表の草むらで鳴く虫の音や、頭上から聞こえる梟の鳴き声がもの悲しい。「痛い!」思わず自身の声が獄中に籠もった。忍び込んできたコオロギが、脛に食いついたのだ。与えられた薄い布団と周囲の茣蓙を重ね合わせて身にまとった。寒さを偲ぶためである。牢屋に忍び寄る虫や残り蚊に悩まされながら、一睡も出来ない夜が過ぎていった。
東の空が明るくなると、村人らしい中年の男がやってきて板戸を開けた。彼方に見える波頭が、目に飛び込んできて眩しい。村民との接触は、役所が委嘱している食事を運ぶ村の女が一人だけ。それも、無用な会話は許されていないらしく、用を済ますとさっさと獄舎を離れていった。格子戸から眺める対岸は、福吉あたりの唐津街道筋か。その奥に浮嶽(うきだけ)(805㍍)が、気持ちよさそうに居座っている。点在する藁葺き屋根の家屋から聞こえる牛や雄鶏(おんどり)の鳴き声がうるさい。

2.gif)
姫島漁村風景
いかに役人が村人との間を裂こうとも、時間が囚人との距離を縮めるもの。島の女たちは、魚の天日干しなど仕事の合間に獄舎の前庭に集まって来る。そこでは、子供のことや亭主の稼ぎについて自慢し合っている。最初は小声で、そのうちに他人の耳など気にしなくなった。武家屋敷では、おおよそなかった下世話の話まで飛び出して、大口開けて笑い合う女たち。
しばらく経つと、朝晩食事を運ぶ村の女・シノとも会話を交わすようになった。最近顔色が良くなったと言って嬉しそうに語りかけてくる。望東尼は、シノに頼んで筆立てを用意してもらった。姫島での日記を書くためである。
入牢して二十日が経過した頃、獄中の柱に書き込んだ心境が残っている。

次にこの獄舎に入る人よ、耐えがたく辛いと思うのは最初の二十日間だけのことですよと、いとも前向きな歌である。
この頃、囚われの身であった馬場文英が京都の牢獄から釈放されたと、見回りに来た小役人が耳打ちしてくれた。そのうちに、野村の本家からも、差し入れが届くようになった。
「これ、ババには甘すぎて駄目だから、お子たちに食べさせて」
朝食を運んでくる際、シノに差し入れられた駄菓子を差し出した。ある時は、シノが桑野喜右衛門という以前の役人を覚えていると言い出した。
「その者はこの尼の三つ違いの弟だよ」と応えると、「あらまあ」の連発。後は、以前からの知り合いでもあるように、口が軽くなった。厳重に禁止されているはずの蝋燭を、「書き物に必要だろうから」と、こっそり敷き布団の下にしのばせた。夜になって火を灯すと、世界が変わったかのように明るくなった。この句は、人との繋がりの大切さを仏の光に見立てて詠んだ句である。
暗きよの人やに得たるともし火はまこと仏の光なりけり
時間は過ぎていく。狭いながらも獄舎が以前からの住処であるような、居心地に変わるものかと我ながらびっくりする。シノに限らず、寄ってくる主婦や娘とも格子越しに、会話するようになった。一日に一度の役人の見回りさえ気をつけておけば、彼女らとの間に、獄舎の壁はあってないようなものになっていった。
.gif)
姫島の村落
ある日、別の獄に繋がれている囚人が、二人連れでやってきた。脱獄の恐れの少ない囚人に対しては、監視も緩やかになっているらしい。無精髭が顔中を覆う男は、望東尼が旧友ででもあるように、親しげに話しかけてきた。島を囲む海は、何にも増して頑丈な監獄塀の役目を担っているのだ。
ある時は漁師の男がやってきて、釣り船の進水を祝った和歌を詠んでくれとねだった。望東尼は、新しい舟の航海の安全と豊漁を祈念して、和歌を贈った。
望東尼が唐丸籠に乗せられて上陸した際、桟橋で見かけた女の子も気安く話しかけてきた。名前をウメと言い、望東尼のことを「おばあちゃん」と呼んだ。あどけない幼女が、本当の孫のように思えてきた。年が明けると島人たちは、シノを通じて海の幸・山の幸が入った雑煮を運んでくれた。
獄舎には、いろいろな生き物が侵入してくる。ねずみ、百足、蜘蛛、蟻など。いちいち怖れたり怖がっていたら、ここでは生きていけない。彼らも大切な仲間なのだと割り切って、安全な場所に逃がしてやったりもした。

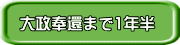
入獄から半年ほど過ぎた慶応2(1866)年6月。幕府による15万の軍勢を擁しての第2次長州征伐が始まった。だがこのとき長州藩にとって、「八月十八日の変」では敵方にあった薩摩藩との間に薩長連合(同盟)が成立していた。そのため、長州征伐の幕府からの命令が出ても、薩摩藩は動こうとしなかった。それでも幕府軍は、四方(小倉口・石州口・大島口・芸州口)から長州軍を攻めたてた。だが攻める幕府軍も、旧式装備では7千の長州軍に勝つことは出来ない。そこで幕府は、将軍家茂の死去を機に征討を中止することにしたのだった。
その時、小倉口の戦いで指揮を執っていたのが高杉晋作であった。
12.gif)
小倉城から持ち帰った戦利品の大太鼓
(下関厳島神社)
時は更に過ぎて行く。慶応2年(1866年)の9月。福岡藩を脱藩した後、長州下関にいた藤 四郎が病床の高杉晋作に告げた。
「平尾山荘の主である望東尼が、筑前姫島の牢に入れられています。いつ何時命を奪われるかも知れません」
老尼の救助を願い出た。玄界島に流された同士2名が、突然首を斬り落とされたことが、藤 四郎の焦りを誘っていたのである。
四郎の差し迫った訴えを聞いた高杉は、望東尼救出を決意した。高杉にとって、わずか10日間の滞在ではあったが、望東尼は命の危機を救ってくれた恩人である。別れ際には、「お世話になったご恩はけっして忘れません」と誓ったうえで、気持ちを吐露する漢詩も置いてきた。望東尼からは、山荘を出る際一晩かけて縫い上げた旅衣を着せてくれた。
山荘を出る際高杉は、福岡藩や長州の俗論派から命を狙われていた。その際、月形洗蔵が主導して福岡藩領から脱出させ、無事長州の同士に引き渡してくれた。長州の正義派は、高杉の帰国後、すぐさま俗論派を追放することに成功したのであった。
藤 四郎から望東尼救出の相談を受けた高杉は、直ちに作戦に必要な同士を集めさせた。まずは、姫島と周辺海域に詳しく、海流や海路、風向きなどに長けた者、脱出に必要な船舶と船頭を都合できる者など、作戦に必要な要員の確保である。
「脱出後は、海の流れと風が頼りだ。対馬藩の浜崎領に行けば、そこには船問屋が2軒あるはず。対馬の同志に手頃な船と船頭を調達するように」
高杉は、頭に浮かぶことを次々に口に出した。
「姫島に上陸する以前に、獄にいる望東尼殿に知らせる必要がある」とも指示した。突然牢獄に突入すれば、望東尼本人も驚くだろうし、救出隊が味方なのか敵なのかさえ疑われるだろう。藤 四郎は、言われた役目を果たせる同志を思い浮かべた。

夏の盛りも過ぎた8月の末。陽が落ちて、出入り口の戸を叩く音がする。望東尼が振り向くと、戸の隙間から紙切れが1枚。「9月10日夕刻、救助に参上 四郎」と書かれていた。「まさか、あの四郎では」と直感する望東尼の心が躍った。慶応2(1866)年9月10日の夕刻であった。
船幅いっぱいに帆を張った船が、姫島の船着場に碇を下ろした。夕飯支度の時刻であり、海辺に人影はない。船から下りたのは男が6人。船には2人の船頭が残った。
1.gif)
牢獄前の庭
男らは、上陸すると3人ずつの二手に分かれて、島の中央に座る鎮山に向かう急坂を登っていった。藤 四郎と博多商人の権藤幸助、それに長州藩士の泉三津蔵は望東尼が入っている獄舎へ。権藤幸助は商人だが、攘夷派の藩士との交わりが深く、藤
四郎に誘われて作戦に参加している。事前に脱獄の予告文を投げ入れたのもこの男である。泉三津蔵は、日頃高杉晋作に仕える長州藩士で、玄界灘の海流や季節風に詳しいことから指名された。
望東尼が繋がれている獄舎に到着した藤 四郎は。周囲の様子をうかがった後、獄中に向かって声をかけた。
「ハハウエ、お迎えにあがりました」。中から呻くような声が返ってきた。
藤 四郎ら3人は、持参した木槌で錠前を叩き壊した。
「おお、四郎かえ」
先を競うようにして侵入してきた3人を迎えた望東尼が、真っ先に質した。
「長州の高杉晋作どのの計らいで、ハハウエを救いに参りました。ここにいるのは、同志の権藤幸助と泉三津蔵です。細かいことは後ほどゆっくりと…。手荷物は最小限にして、さあ、参りますぞ」
促されて望東尼が立ち上がろうとするが、膝に力が入らない。
「おつかまりください、手前の肩に」と、権藤幸助。
船着場まで歩けと言われても、1年近くも座りっぱなしで、足が萎えていて思うように動かない。背中を向けた権藤には、かすかながら見覚えがあった。いつしか平尾山荘に志士らと連れだってやってきたことがある。その時、珍しい茶菓子を差し入れてくれた。
「して…、私をこれからどこに連れて行くのですか?」
「長州の下関まで」
「長州」と聞かされても、そこがどんなに遠いところなのかさえ、考えが及ばない。
陽が唐津の海に落ちていく。近所の民家から漏れているわずかの灯りと、遠くで点滅する漁り火が道標(みちしるべ)であった。背負われて急坂を下りていく際、下から上ってくる女とすれ違った。獄に夕飯を届けに行くシノであった。
「あのう」、見知らぬ男の背中に負われている望東尼に声をかけた。
「おシノさん、もうご飯はいらないよ。わたしはこれから遠いところに行くけれど、心配いらないからね。島のみなさんに、くれぐれもよろしゅう伝えて」
事情を察したシノは、桟橋に急ぐ望東尼を、声を押し殺すようにして見送った。
一方、定番屋敷に向かった小藤平蔵と多田荘蔵、吉野応四郎の3人。小藤は福岡藩を脱藩し、多田と吉野は対馬藩を脱藩した、いずれも長州領内に居留する志士である。定番屋敷に着くなり、小藤平蔵が屋敷の表戸を叩いた。玄関に現れた定番役の坂田が、しきりと小首を傾げている。
「我らは、藩奉行の命により参上いたした。この度、朝廷からの命令があり、入獄している野村望東を釈放するために参上した。尼僧の身柄は、当方で城まで届ける故、心配ご無用」
小藤が、声を大にして相手を威嚇した。眠気覚めやらぬ坂田は、何事が起こったのかさえはっきりしない様子。
「そんなはずはない。囚人の管理は定番役の拙者の仕事。しばし待たれよ。当方より真偽のほどを確かめる故」
「何を申すか!この期に及んで…」
小藤は、坂田と押し問答しながらも、一向に慌てる風はない。
その時である。港の方から「ズドーン」と、銃砲の轟音が響き渡った。
「何事じゃ、あの音は?」
坂田が庭番に質すがはっきりしない。
「困ったご仁じゃ」
小藤は、坂田嘉左衛門を睨み付けた後、多田と吉野を促すと、いっせいに山裾めがけて駆け下りていった。
「どうもおかしい。あの者らは、本当に奉行の遣いなのだろうか。もう一度問い詰めなければ…」
坂田は着替えた後に、目をこすりながら出て行った。坂田が小役人と一緒に船着き場に駆けつけたとき、望東尼らを乗せた帆船は、暮れかかった彼方の仏崎岬に隠れるところであった。
.gif)
姫島から仏崎岬望む
「しまった、遅かったか!」
地団駄踏む坂田嘉左衛門。こうして藤 四郎らによる望東尼救出作戦は成功した。高杉晋作が組み立てた作戦と藤 四郎らの実行力が、見事に的中したのであった。
藤 四郎らは、鎮山の頂が見えなくなって、ようやく帆掛け船の舳先で胸をなで下ろすのだった。

望東尼は、用意されていた布団に横たわったまま、頭上で点滅する星座に魅入っていた。
「こんな一本柱の帆掛け船で、波の荒い玄界灘を乗り切れるのかね。風だって、必ず順風とは限らないでしょう」
「そこは心配ご無用に願います。船は、南から北へ流れる対馬海流に乗っております。それに今は都合のよい南西の風が吹いております故」
藤 四郎が説明した。
「この船に乗っているのは、誰と誰?」
望東尼の問いに藤 四郎は、一人一人を指さしながら答えた。
.gif)
玄界灘
藤 四郎・小藤平蔵(以上福岡藩脱藩者)、多田莊蔵・吉野応四郎(以上対馬藩脱藩者)
泉 三津蔵(長州藩士)、権藤幸助(博多商人)の名前を挙げた。
「今、船はどの辺を走っているの?」
船頭が口を挟んだ。
「先ほど先方で大きな船が横切ったから、玄界島を通過したところですかね」
しばらく沈黙が続いた。気がつけば望東尼は、俯いたまま寝息をかいている。
藤 四郎が声を上げた。
「ハハウエ、拙者はこれから宗像沖の大島に上がります」
「何のために?」
望東尼には訳の分からないことである。
「大島の牢獄に捕らえられている、助作殿を救い出すためです」
「孫の助作ですか?会いたいな」
突然の話に、すっかり目を覚ました望東尼が起き上がった。
「肝心の牢獄が何処にあるのか、わかっているの?」
「それも心配ご無用です。拙者は6年前に、脱藩の罪で大島の牢獄に繋がれたことがありますから」
大島には、宗像大社の中津宮が祀られている。牢獄は、この島の北東部に造られていると言う。
藤 四郎は、権藤幸助を伴って下船した。間もなく戻ってきた時、助作ではないほかの男を連れていた。
「どうしたの、うちの孫は?」と、激しく問い質す望東尼。
「この者の話だと、助作殿は流罪ではなかったのです。城下の枡木屋に入れられたままだそうです。この者は、やはり脱藩の罪で流罪になった澄川洗蔵と言います。脱獄を望んだので連れて行くことにしました。ハハウエには、期待だけ持たせて、お気の毒です」
一同、うなだれる老尼を励ますばかりであった。
大島を離岸した船は、再び波荒い玄界灘に出た。南西の強い風を受けて、時を待たずに響灘へと突き進んだ。
|

1.gif)

1.gif)
![]()