|
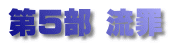

御馬屋後(おうまやのうしろ)(現中央区赤坂3丁目付近)に建つ浦野家での謹慎暮らしが始まった。「謹慎」と言えばまだ聞こえはよいが、実態は「座敷牢獄」と同じようなもの。ここは、自身が嫁入り前まで暮らした家である。藩庁からのきつい申し渡しもあり、勝手に外出することは許されない。広い座敷で、見張り役の総領吉之助と二人が睨めっこしているばかりであった。
「伯母上・・・」
退屈そうな伯母に、吉之助が語りかける。
.gif)
望東尼生誕地付近(福岡中央区赤坂)
「どこにどのような目があるかも知れぬ」と、望東尼が小声で遮った。
「吉之助よ、たまには外に出て、弓射場(ゆみいば)でも覗いてみたいの」
今度は、伯母の方から話しかけた。するとすぐに、吉之助が身構える。
「駄目ですよ。伯母上が変な気でも起こしたら、浦野家はたちどころに取り潰しですからね。しばらくの辛抱です、我慢しましょう」
「分かっていますよ。ただ、おまえの名前を呼んでみたかっただけ」
それだけの会話を交わすのにも、気を遣わなければならない窮屈な自宅謹慎であった。

福岡城内堀
謹慎中も、藩庁から取り調べの達しが届く。取り調べの場所は、お城を半周して、博多湾に向かったところの中名島町である。おおよそ半里(2㌔)の道のりを駕籠に乗せられて行くことに。体力に自信がない望東尼は、駕籠に揺られるだけでもすぐに疲れる。付き添いの吉之助にねだって、海の見える日陰で一休みすることにした。現在の長浜公園あたりだろうか。湾からの風が気持ちよく、いつまでもここにいたいと駄々をこねたくもなる。
取り調べは、年老いた尼僧を気遣ってか、部屋の中で淡々と進められた。
「今回取り調べを受けている者は、いずれも、包み隠さず素直に答えておる。貴僧も、お仲間を思う心があるのなら包み隠さず答えられよ」
「何をお訊きになりたいのです?」
と応じたところで、役人の声色はますます優しさを増した。
「山荘に出入りしておった者の名前を聞かせてくれまいか。それから、中村円太の枡木屋脱走について、知っていることがあればすべて教えてほしい」
「申し上げたら、いま捕らわれている者たちを、自由の身にしてくれますか」と、念を押した。
「貴僧の願いを聞いてくれるよう、お奉行に申し伝える故」
そこで望東尼は、平尾山荘に出入りしていた若者の名前を連ねた。そのことが、後の大弾圧に直結する誘導尋問であろうとは微塵も考えず、知りうることをすべて申し立てた。

高杉晋作の帰国後、長州藩では俗論派(佐幕派)の勢いが衰え、正義派つまり倒幕思想が勢いを増すことになっていた。そんな尊攘派の勢いを削ぐべく、幕府は総司令官に将軍德川家茂(いえもち)を据えて、第二次長州征討に打って出たのである。
第二次長州征討を知らされた福岡藩主・黒田長溥は、謹慎を申し渡している志士たちを即刻処分するよう言い渡した。世に言う乙丑の獄(いっちゅうのごく)本番の始まりである。

加藤司書像
尊攘派が拠り所にしている家老の加藤司書や月形洗蔵ら21名に切腹及び斬罪が言い渡された。その他16名には流罪が。併せて100名を超える志士に対する処分も断行された。
中でも加藤司書への断罪の報は、福岡藩中に衝撃が伝わり、志士らの間に動揺が深まった。
それは、慶応元(1865)年10月23日の夕刻であった。加藤司書は中老の隅田清左衛門屋敷にお預けの身となった。隅田家では、急遽設えた座敷牢に司書を迎えることに。屋敷の周辺には、警備の役人が多数配備された。
2日後、切腹決行の夜である。墨田家では、最大級のご馳走を司書に差し出し、これまでの働きを労った。夜遅く大目付がやってきて、「天福寺にて切腹」の君命を言い渡した。そこで加藤司書は、墨田清左衛門に対して深々と頭を下げた後、護送用の網駕籠に乗せられて死出の旅路についたのであった。
一方、望東尼の孫・野村助作には、流罪の判決が言い渡された。流される先は宗像沖の大島だと聞かされた。
そして望東尼には、「姫島流罪牢居」の刑が告げられた。望東尼は、判決文を聞かされて涙が止まらなくなった。取り調べの際に、あれほど同士に対する罪はないことにして欲しいと頼んだのに。正直に事実を述べれば、許してくれると信じていたのに。全身全霊を傾けての訴えは、黒田のお殿さまにまでは届かなかったのか。まして他の同志に比べて自分への罪が死罪でないのはどうしたことか。打ち首ではなく島流しということでほっとするどころではない。恥ずべきことだとも思えた。
そしてもう一つびっくりしたのは、流される先が筑前の姫島だと聞かされた時だ。福岡藩は、死罪に次ぐ罪人に設けた「流罪先」として、姫島・玄海島・大島・小呂島など、近郊の離島に牢獄を設けた。
姫島には望東尼自身何度か足を踏み入れていたことがある。今は亡き弟桑野嘉右衛門が姫島勤務だったときのこと。誘われて姫島に渡った時、和歌の師匠である大隈言道と二人連れだった。
玄界灘に浮かぶ姫島は、岐志港から7㌔西に浮かぶ離島である。周囲3.8㌔、面積0.75平方キロほどの小さな離れ島であった。
あのとき望東尼と言道は、愛宕神社下の海岸を、港まで語り合いながらの旅であった。海が荒れていて船を出せないという船頭に従って、村長(庄屋)の屋敷に泊めてもらうことになった。望東尼はそのときの心境を詠んでいる。
旅ごろも香月の浦にいつまでか立うらぶれん波もわがみも
ようやくたどり着いた姫島では、漁師や家族とのふれあいなど、楽しい思い出が詰まった旅となった。この姫島に、次は自身が囚人となって、荒波を渡ることになろうとは・・・。

福岡長浜海岸

慶応元年(1865年)11月14日の夕刻であった。浦野家門前に唐丸籠が運び込まれた。唐丸籠とは、囚人を載せて護送するための駕籠のこと。「籐丸籠」とも書くそうだ。籐を編んで作った、闘鶏用のシャモを飼う籠に似ているところから付けられた名前だとか。
赤坂(あかさか)御馬屋後(おうまやのうしろ)の実家から岐志の港までの8里(30キロ強)を、夜を通して望東尼を護送する。岐志港に到着後は、船で姫島まで運ぶことになる。籠の舁き手は前後に二人の守人。囚人は、最初から最後まで籠の中。排便も籠の底に開けられた小穴を大小共通で使う。外から物珍しそうに見つめる目もお構いなし。これ以上ない惨めな晒しものである。気位の高い400石取りのご新造さんには残酷過ぎる。顔から火が出るような羞恥心も関係なく、籠は西方に向かって歩き出した。
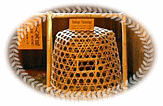
唐丸籠
「せめて港まででも…」見送りたいと訴える者には、「後の祟りが恐ろしいから」と、吉之助が押しとどめた。結局、身内から5人が、籠の後を着いていくことになった。籠は唐人町から唐津街道に出た。
室見川を渡って振り返ると、川向こうから城下の灯が見送ってくれている。生まれてこの方馴染んできた、お城や福岡の街とも今生のお別れになるかも知れぬ。多くの志士らと出会った平尾山荘を、今後誰が面倒見てくれることやら。月形洗蔵-平野国臣など、山荘に出入りした面々が脳裏を駆け巡る。亡き夫貞貫と、「ここでのんびり和歌を詠もう」と誓った山小屋である。夫の幻影が浮かんだ途端、もう一人が顔を出した。10日間だけ山荘に匿った、優男ながら眼光の鋭い高杉晋作である。
籠は彼女の感傷も知らぬげに、海岸通りから愛宕下へ、更に生の松原を経て博多湾へと進んでいった。風が出たのか、海岸に打ち付ける飛沫が頬を濡らした。拭き取ることもままならず、目を閉じたままで我慢した。それより、師走間近の海辺は、頬を殴る風が耐えられないほどに痛い。
一行が岐志の港に着いた時、東の空では大きな星が休みなく瞬いていた。一行は、船乗り場からほど近い庄屋の家で、しばし休息をとることになった。以前師匠の大隈言道と連れだって姫島に渡った折立ち寄ったのも、この庄屋の屋敷であった。そのとき、庄屋に頼まれて和歌を贈ったことを思い出した。
.gif)
岐志の港
役人は、守人に厳重な警護を言い渡すと、自分だけさっさと眠りこけた。後ろから付いてくる身内は、ここから今来た道を戻っていった。
静かな寝息を立てる守人の隙を見て、庄屋が筆と紙を差し出した。「今のお気持ちを一句」詠んでいただきたいとの願いである。
舟でするきしの浦波立かへりまたこの家にやどるよもがな
目を覚ました役人が、守人の頭を叩いた。「凪いでいる間に船を出すぞ」と声をかけ、望東尼を再び唐丸籠に押し込んだ。桟橋まで見送ってきた庄屋とその家族が、「お身体をお大事に」と手を振っている。行く末を察知しているかのように、声は上ずりがちであった。
桟橋を出るとき凪いでいた引津湾は、出港後玄界灘に出た途端、うねる波が襲いかかる荒海と変じていた。
「大丈夫だって、こんくれえの波じゃひっくり返ることはなかけん」
艪を漕ぐ船頭は、荒波に揺さぶられる様を楽しんでいる風にも見える。船酔いがひどい望東尼は、籠の中とあって横になることもできずにもがいた。
「夜が明けますぜ」と船頭が叫んだ。お盆を伏せたような姫島が、目に飛び込んできた。まさしく、これからの辛苦を予告するような島影であった。
|

1.gif)

1.gif)
![]()