.gif)
太宰府の延寿王院
五卿に拝謁
福岡藩内の尊攘派は、三条実美(さんじょうさねとみ)ら五卿(三条実美・三条西季知・東久世通禧・壬生基修・四条隆謌)の筑前下向を支持して、各方面に働きかけた。まずは、実質長州藩内に囚われの身である五卿とその後ろ盾である長州藩主に賛意を求めることである。月形洗蔵ら尊攘派は、長州の萩や湯田まで出向いて関係先の説得にあたった。彼らの行動は功を奏して、5人の公卿は五つの藩(福岡・薩摩・肥後・佐賀・久留米)が分担して預かることに決まった。そして五卿の落ち着き先は、太宰府の延寿王院(えんじゅおういん)ということになった。延寿王院とは、安楽寺天満宮(現太宰府天満宮)の宿坊のことである。
五卿が長州を発って太宰府に到着したのが、慶応元年(1865年)1月であった。五つの藩が分担して警備する中、五卿は王政復古の日までこの地で暮らすことになったのである。
尊攘派の動きを嫌う幕府は、福岡藩主黒田長溥ら5藩の藩主に対して、直ちに五卿を江戸に送れと命じてきた。命令を受けた五つの藩は、たまたま筑前入りしていた薩摩の西郷吉之助(隆盛)を交えて協議した。結果、幕府の命令をきっぱり拒否することになった。
望東尼は、念願であった公卿への面会を実現すべく、延寿王院に出かけた。五卿が太宰府に入った2ヶ月後の3月25日である。
延寿王院は、天満宮の大鳥居を潜ってすぐのところ。恐る恐る門番に来意を告げると、間もなく館内に案内された。奥の間で待つことしばし、現れたのは三条実美であった。世が世なら、福岡藩士の後家ごときが面会できる立場ではない。
正面に座った三条公は、お眉墨もお歯黒もない簡素な袴姿であった。聞き及んでいた公家の身繕いとはほど遠いものである。
「よう来はりましたな」との挨拶だけで、多くを語らない。望東尼にとって、直接三条公に声をかけてもらっただけで十分である。天にも昇る感動を覚えたまま門外に出た。後日三条実美からは、扇子と手紙が贈られてきた。尊皇派を自認する望東尼にとって、これ以上の名誉はない。早速差し出した礼状には、
空蝉(現世の人間)の世の障りがちにて心に得まかせ侍らず
の句を添えた。
「もし…」
三条公と別れて延寿王院の門外に出たとき、後から見知らぬ武士に声をかけられた。
「どちらさまで?」と伺うと、男は丁寧に頭を下げた。
「小田村文助と申す長州藩士でござる。先頃は、我が藩の高杉晋作が大変お世話になり申した。もしかしてと、失礼ながら声をかけた次第」
小田村文助とは、後に望東尼が深く関わることになる、後の楫取素彦(かじとりもとひこ)のことである。小田村は、先頃枡木屋の牢獄を脱走した中村円太らを、対馬藩の飛び地である田代藩邸(現鳥栖市田代)に匿った人物であった。
「この度は、天神さまにお詣りでしょうか?」
「いえ、公卿さまにご挨拶を」と言うなり、小田村は延寿王院の門の中に消えていった。
1.gif)
旧陶山一貫宅三条実美手植えの松
望東尼はその足で、通古賀(とおのこが)に住む陶山一貫を訪ねた。陶山は、当地で開業する医者である。一方陶山は、尊皇攘夷運動の熱心な活動家でもあった。陶山は、延寿王院に謫居中の五卿を訪ねては、みやこのことや同士の活動など近況を報告している。五卿を政治の世界と結びつかせる貴重な尊皇派の連絡係であった。陶山一貫の屋敷跡には、現在も三条実美手植えの松(途中植え替えがなされている)が保存されている。

十一代福岡藩主黒田長溥
藩主の決断
高杉晋作の平尾山荘逗留を境にして、尊皇攘夷派志士らの山荘への出入りがますます頻繁になった。出入りするのは福岡藩士ばかりとは限らない。領内での正義派と俗論派の対立から逃れてきた対馬藩の重役なども。中には、脱藩した他藩の浪士や英彦山の僧まで混じっていた。
いかに周辺に人家が少ないとはいえ、出入りする人の多さは住民の話題にならないわけがない。いつしか、山荘が浮浪の輩の巣になっているとの噂まで広まった。尊攘派の動きに、それまで見て見ぬふりをしてきた藩主・黒田(くろだ)長溥(ながひろ)の気持ちも、尋常ではいられなくなった。
黒田藩主は、もともと五卿の太宰府受け入れに積極的ではなかった。そのため、藩主と尊攘派贔屓の家老たちとの間にできた溝は、抜き差しならぬところまで深まっていたのである。
※黒田長溥(くろだながひろ):筑前国福岡藩十一代藩主。蘭癖大名と称され、藩校修猷館を復興させるなど名君と呼ばれた。
この度の長州征伐結果に不満を持つ幕府が、いよいよ第二次征伐に動いた。そのことが、福岡藩の立場をますます窮地に追い詰める結果となる。尊攘派による老重臣の暗殺、中村円太の牢破り、五卿の受け入れなど、尊攘派による意に反する出来事が続き、その上、平尾山荘への不逞の輩の出入りの噂まで広まったのである。藩主の堪忍袋も限界に達したのだった。
そんな折、望東尼にとって、怖れていたことが現実となってしまった。京都にいる馬場文英が、京都所司代に拘束されたとの情報が届いたのである。大文字屋当主比喜多五三郎亡き後、跡を継いだ息子の比喜多源二までもが捕まったと聞かされたのだ。
京都所司代は、京都での出来事が短時日の間に福岡の攘夷論者の許に届き、福岡の情勢が京都の反体制派に届いている、そのカラクリを徹底的に追求した。人脈を手繰っていくと、馬場文英が平野国臣を匿った事実まで突き止めたのだった。
馬場の捕縛は、幕府が第二次長州征討を打ち出した時期と重なる。馬場と比喜多源二は、京都周辺に滞留していた平野国臣と同じく、六角の牢獄に封じ込まれた。そこで、望東尼と馬場の連絡ルートは完全に断ち切られることになった。
「ここも、無事ではいられませんよ」、と孫の助作が望東尼に耳打ちした。尊攘派の志士たちの思想的柱である家老の加藤司書だって、無事ではいられまい。
藩庁から睨まれているだろう志士たちは、どの者も、国を憂い、正しい道を導き出すために運動してきた若者である。もし、藩庁から尋問を受けることがあれば、正々堂々と自分らの正義の考えを述べれば済むこと。例え尊攘派に理解を示さない役人でも、そのうちに分かってくれるはず。望東尼は、そう信じ、必要以上に怖れることはないと、助作に言い聞かせた。
時代が慶応元(1865)年に入ると、福岡藩尊攘派弾圧の波はそこまで押し寄せていたのであった。
濡れ衣
望東尼の気持ちは落ち込むばかりであった。気晴らしに、曾孫と戯れようと野村本家に出かけた。やがて夏を迎える時期である。
近くの神社でひとしきり遊んだ頃、玉垣の向こうから野村家の女中が駆け込んできた。何事かと問うても、口もとを震わせるばかりで、はっきりしたことを言わない。とりあえず、幼な子を彼女に預けて家に戻った。
帰るなり、嫁から一通の書状を見せられた。それは本家を継いでいる助作に対する藩庁からの召し文(呼出状)だった。「戒めがある故出頭せよ」とだけ書いてある。座敷に入ると、助作が既に身支度を済ませて祖母の帰りを待っていた。召し文に書かれている「戒め」の意味が分からないと、助作はぼやいている。しばらく経って助作は、実家の浦野吉之助と連れだって出かけていった。
大詰めを迎えた歌集『向陵集』の編纂も気になるが、ここは当主助作の祖母として野村家を護らなければならない。親類の者が続々集まってくる中で、夜中になっても戻らない孫をひたすら待ち続けた。
夜明けも近くなる時刻、吉之助が一人で戻ってきた。右手に藩庁から渡された仰せ文を握っている。誰に対する文かと見てびっくり。対象は、助作ではなく望東尼自身だった。
「疑いの義あり。次なる沙汰があるまで、親族の家で謹慎するように」とのこと。その間、望東尼を身内の者がしっかり見張るようにとのお達しであった。仰天する望東尼は、このときの心境を日記「夢かぞえ」に書き記している。
世を捨てし身にさしかかるうき草の濡れ衣、墨の衣に引き重ねつる事ども、いと畏(かしこ)しとも思いわきがたし
頭を丸め、仏門に入った我が身に、思いもよらぬ濡れ衣が掛けられようとは。それも、信頼する福岡藩からのお達しである。とても、畏まって承服できることではない。怒りは心頭に達した。その後助作を待つ時間の長かったこと。たったの半日が、1年にも思えた。
東の空が白みかける時刻、助作が戻ってきた。助作は、祖母への謹慎言い渡しを知らされていないらしく、まずは自らの今後について語った。自身にも謹慎を言い渡されたというのである。助作は現役の藩士であるため、見張りも公の守人がつくと言う。
「謹慎を受けるのは、そなたと私だけではなかろう」
祖母の問いには答えず、助作はそのまま寝間に入っていった。
座敷牢
夜が明けて、望東尼は実家の浦野家に移された。慶応元年(1865)年8月15日である。久しぶりの実家なのだが、懐かしさや親兄弟への思い出など感傷は湧いてこない。実家の跡取り浦野吉之助が見張り役となり、二人は複雑な面持ちで向き合った。
「嫌疑がかかる者を、身内の甥っこに見晴らせるとは情けない藩庁だね。だって、私に何かあったら、おまえらのせいにするって言うことだろう」
望東尼は、藩への恨みを吐き出した。今回厳しい「戒め」を受けるのは、名前を挙げるだけでも半端な人数ではなかった。
月形洗蔵、筑紫衛、鷹取養巴、森安平、万代安之丞、江上栄之進、伊能茂次郎海津亦八、 伊丹真一郎、今中作兵衛、真藤善八、尾崎逸蔵など。
山荘で我が子同様に接してきた者ばかりである。この日、藩に拘束された武士は、望東尼と助作を加えて総勢14名に上った。その他足軽などを含めると、39名が「戒め」を受けることになった。
悲しいことに、望東尼を頼って和歌の弟子入りをした、瀬口三兵衛まで連れて行かれたという。三兵衛は、今朝も、山荘の庭に咲く草花を届けてくれたばかりである。
「どうして? なぜなの?」
自分の周囲にいた人たちが、ことごとくしょっ引かれたと聞くと、望東尼の頭は真っ白になり、ただ座敷に額を付けて呻くばかりであった。
嫁入り前まで暮らした家であるのに、勝手に外出することも許されない。広い座敷で、見張り役の吉之助と二人が睨めっこしているばかりであった。
「伯母上・・・」
退屈そうな伯母に、吉之助が語りかける。
.gif)
現在の望東尼生誕地付近(福岡中央区赤坂)
「どこにどのような目があるかも知れぬ」と、望東尼が小声で遮った。
「吉之助よ、たまには外に出て、弓射場(ゆみいば)でも覗いてみたいの」
今度は、伯母の方から話しかけた。するとすぐに、吉之助が身構える。
「駄目ですよ。伯母上が変な気でも起こしたら、浦野家はたちどころに取り潰しですからね。しばらくの辛抱です、我慢しましょう」
「分かっていますよ。ただ、おまえの名前を呼んでみたかっただけ」
それだけの会話を交わすのにも、気を遣わなければならない窮屈な自宅謹慎であった。
謹慎中も、藩庁から取り調べの達しが届く。場所は、お城の反対側、内堀の先である。駕籠に乗せられて、おおよそ半里の道のりを行く。体力に自信がない望東尼は、駕籠に揺られるだけでもすぐに疲れる。付き添いの吉之助にねだって、海の見える日陰で一休みすることにした。現在の長浜公園あたりだろうか。湾からの風が気持ちよく、いつまでもここにいたいと駄々をこねたくもなる。
あ.gif)
福岡城天守台跡
取り調べは、部屋の中で淡々と進められた。
「今回取り調べを受けている者は、いずれも、包み隠さず素直に答えておる。貴僧も、お仲間を思う心があるのなら包み隠さず答えられよ」
「何をお訊きになりたいのです?」
と応じたところで、役人の声色がますます優しさを増した。
「貴僧の山荘に、出入りしておった者の名前を聞かせてくれまいか。それから、中村円太の枡木屋脱走について、知っていることがあればすべて教えてほしい」
「申し上げたら、いま処分を受けている者を、皆自由の身にしてくれますか」と、念を押した。
「貴僧の願いを叶えてくれるよう、御奉行に申し伝える故」
そこで望東尼は、平尾山荘に出入りしていた若者の名前を連ねた。そのことが、後の大弾圧に直結する誘導尋問であろうとは微塵も考えず、知りうることをすべて申し立てた。
尊攘派が勢いを増す長州藩を取り締まるべく、幕府が第二次長州征討に打って出た時期である。藩主の黒田長溥も、幕府の征討に呼応して、謹慎中の志士たちの処分を早めるよう言い渡した。世に言う乙丑の獄(いっちゅうのごく)本番の始まりである。
流罪牢居言い渡し
尊攘派が頼りにする家老の加藤司書や月形洗蔵ら21名に切腹及び斬罪が言い渡されたのは、まさしくその時期であった。切腹・斬首の他にも16名に流罪が、併せて100名を超える志士への処分が断行された。
それは、10月23日の夕刻であった。切腹を言い渡された家老の加藤司書は、中老隅田清左衛門屋敷にお預けの身となった。隅田家は、急遽設えた座敷牢に司書を迎えた。屋敷の周辺には、数多くの警備の役人が配備された。
2日後、切腹決行の夜。墨田家では、最大級のご馳走を用意して司書に与えた。その夜遅く大目付がやってきて、「天福寺にて切腹」の君命を言い渡した。そこで加藤司書は、墨田清左衛門に対して深々と頭を下げた後、護送用の網駕籠に乗り込み、死出の旅路についたのである。
望東尼の孫・野村助作には、流罪の判決が言い渡された。流される島は宗像沖の大島だと、吉之助に聞かされた。
そして望東尼には、「姫島流罪牢居」の刑が告げられたのである。望東尼は、判決文を聞かされて涙が止まらなかった。取り調べの際に、あれほど同士に対する罪はないことにして欲しいと頼んだのに。正直に事実を述べれば、許してくれると信じていたのに。全身全霊を傾けての訴えも、黒田のお殿さまにまでは届かなかったのか。他の同志に比べて、自分への罪が死罪でないのは何故なのか。島流しということでほっとするどころではない。恥ずべきことだとも思えた。
そしてもう一つびっくりしたのは、流される先が筑前の姫島だということであった。福岡藩は、死罪に次ぐ罪状として設けた「流罪」の先として、姫島・玄界島・大島・小呂島など、近郊の離島に牢獄を設えている。姫島には自身一度だけ、足を踏み入れている。今は亡き弟桑野嘉右衛門が、かつて姫島勤務だった時のことだ。その弟に誘われて姫島に渡った。島への伴は、和歌の師大隈言道であった。
玄界灘に浮かぶ姫島は、岐志港から2里足らずの西に浮かぶ離島である。周囲3.8㌔、面積0.75平方キロの小さな島である。あの時望東尼と言道は、愛宕神社下の海岸を、語り合いながらの旅であった。海が荒れていて船を出せないという船頭に従って、岐志港近くの庄屋の屋敷に泊めてもらうことになった。望東尼はそのときの心境を詠んでいる。
旅ごろも香月の浦にいつまでか立うらぶれん波もわがみも
思い出が詰まった姫島に、また来るときは、囚人となって海を渡ろうとは・・・。
|
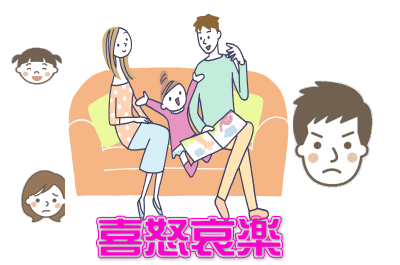
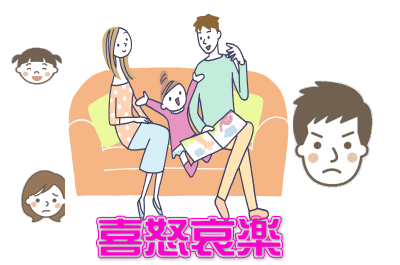
![]()
.gif)