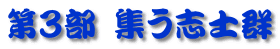

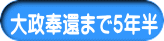
文久2(1862)年6月。望東尼は九州小倉に上陸した。半年ぶりの帰郷である。久方ぶりの九州は、別世界に降り立った気分であった。
この間に実家の野村家は、貞和から孫の助作に代が移っていた。住居も林毛町から下警固村の立益町(りゅうえきのちょう)に移っている。立益町は、現在の地下鉄桜坂駅付近である。
平尾山荘に着くと、早速野村家の家族が集まってきた。彼らには、大切に持ち帰った土産話を披露した。話を聞こうと、藩の若者も集まってくる。
皆が帰ったあと、一人山荘の庭石に座り込んであたりを見渡した。どうしてここだけがこんなに静かなのだろうと、不思議な感覚にとらわれる。
彼女の帰郷を追いかけるように、京都の馬場文英から便りが届いた。激しい政情の移り変わりが、こと細かに記されていた。馬場は、福岡に住む志士たちの動向も気にしているようだ。
そんな折、野村家の家督を継いだ孫の助作が、中村恒次郎なる青年藩士を連れてやってきた。青年に年齢を聞くと、23歳だと答える。助作より1歳上である。
「おハハウエ、私にも京都の話を訊かせてください」と、子供がねだるような言葉付きで挨拶した。平尾山荘にやってくる若者は、望東尼のことを「ハハウエ」と呼ぶようになっている。中村は、京都での尊皇攘夷派の活動ぶりを知りたいようだ。最近起こった大蔵谷回駕の一件や寺田屋騒動のことなどには、特に興味がありそう。
望東尼は、蘇る記憶をなるべく正確に伝えようと心がけた。日を置かずして、望東尼の山荘には幾人もの若者が寄って来るようになった。助作から事情を聞きつけたのだろう。いずれも、自分とは母子ほどに年齢差のある青年ばかりである。彼らは、望東尼の話を聞きながら、誰憚ることなく尊皇攘夷論を戦わせた。口から泡を飛ばす青年らに、望東尼も危うさを感じることはなかった。立派な志士の卵たちである。

望東尼が上方から帰国して、一年が経過した文久3年のこと。山荘に平野国臣が尋ねてきた。望東尼にとって、大蔵谷回駕の事件のこともあって、彼のことは忘れられない人物の一人になっていた。風貌は想像していた以上に武士らしくない体裁である。月代(さかやき)は剃っていないし、長刀だって刃を下に向けて腰に吊り下げているだけ。望東尼も、平野国臣が大蔵谷回駕事件後福岡藩に身柄を拘束され、枡木屋(ますこや)の獄に閉じ込められているところまでは聞かされていた。
枡小屋の牢獄:幕末期に福岡藩が橋口町(現天神4丁目日銀付近)に造った牢屋のこと。
「枡小屋に閉じ込められているはずの貴方が、どうして私の目の前にいるのです? 大蔵谷の一件は、私もそれなりにわかっているつもりです。貴方は、薩摩の島津久光さまの名前を騙って、黒田のお殿さまに建白書を渡したのでしょう。黒田のお殿さまだって、貴方を易々とお許しになるとも思えませんよ。いったい、その間に何があったのでしょう」
1.gif)
平野国臣像(福岡西公園)
「ありがたいことに、朝廷からのお力添えがありましたようで・・・。3ヶ月前に無罪赦免になったのです。拙者ごときに、朝廷がどうして働きかけをしてくださったのか、そこのところはようわからんのです」
ひと通りこれまでの経過を聞かされたあと、望東尼が問うた。
「貴方が本日拙僧の前に現れたわけは?」
「福岡藩からの命により、これから京に上ります。京都では、馬場文英殿に会いしたいと思っています。そこで、御尼に紹介状を書いて欲しいのです」
平野国臣の上京の目的の一端が尊皇攘夷のためだとわかり、望東尼は早速、馬場文英宛てに紹介状を書いた。
大蔵谷回駕の後、福岡藩による尊皇攘夷派に対する監視はますます厳しくなっている。志士たちの中心にいる月形洗蔵もその一人である。月形は、望東尼が生まれた御馬屋後(おうまやのうしろ)の数軒東側に住んでいて、幼い頃からよく知りあった仲である。3年前に、藩主に対して参勤の中止などを求める建白書を提出したこともある人物。その時藩主の黒田長溥は、藩政批判の罪で、月形をはじめ30名余に島流しの処分を科した。だが間もなく、全員の処分が撤回された。これまた朝廷からの働きがあったためであった。このときの処分を歴史家は、「辛酉(しんゆう)の獄(ごく)」と呼んだ。

.gif)
平野国臣や月形洗蔵らは、藩の取締りにより捕まった後も早期に釈放された。すべて、朝廷からの指示でなされたことであった。ところが、それまで優位に働いていた朝廷における尊皇攘夷派の公卿らは、一日にしてその力関係を逆転させられることになる。8月18日を境に、尊皇攘夷派の中でも急進派だった三条実美ら七卿が、朝廷を追われることになったからである。朝廷を追われた公卿らは、雨の中を草履と簔だけの姿で、ともにみやこを追われる長州藩の兵士ら2000人とともに、西に向かったのであった。
※八月十八日の変:1863年。幕末、公武合体派が尊攘派の公卿らを朝廷から追放した事件。長州藩を中心に尊攘急進派が朝廷を動かして統幕計画を進めたので、公武合体派にあった薩摩藩が京都守護職らと画策して、8月18日に朝議を一変、長州藩の御所警護を取り上げて三条実美ら急進派公卿をみやこから追放した。実美らは長州藩内に逃げ込み(七卿落ち)、尊攘討幕運動は一時頓挫することになる。
望東尼にも馬場文英から、「八月十八日の変」とその後の平野国臣や志士らの動きについて動静が伝えられた。平野は、新撰組の追っ手を逃れて但馬へ向かった。更に平野国臣は周防国三田尻を目指すことに。みやこを追われた実美ら七卿に会うためである。更に播磨へと移動する。三田尻を発つにあたり、平野は望東尼に宛てて自らの歌を添えて訣別の書状を送っている。
幾度か捨てし命の今日までも残るは神の助けなるらむ
平野はその後豊岡の藩士に捕まり、京都の六角の獄に移された。その後、新撰組の手で処刑された。
※六角の獄:平安時代に建設された京都の牢獄。正式には「三条新地牢屋敷。宝永大火のあとは、六角獄舎、または六角牢といった。
中村円太も同時期に、脱藩の罪で捕縛されて、枡木屋の獄(福岡)に繋がれた。平野国臣が処刑され中村円太まで獄に繋がれていると聞き、望東尼は居たたまれなくなった。自分が女でなかったら、もっと若かったらの思いが、なおさらのごとく気持ちを暗くさせるのである。


年号は文久から元治(1864年)に移り、春まだ浅い3月24日のことである。福岡藩内で二つの大事件が起きた。
一つは、藩の老臣・牧市内が地行ヶ浜(現PayPayドームあたりの海岸)で暗殺されたこと。牧を斬ったのは勤王志士であった。
もう一つの事件は、深夜、枡木屋に繋がれている中村円太が脱獄したこと。脱獄を手引きしたのが、二人の福岡藩勤王志士であった。
二つの事件は、それまでどちらかと言えば優柔不断に見えた福岡藩主の態度を、決定的に幕府寄りの立場に追いやってしまうことになる。
中村円太が脱獄したその夜。10名の藩士が平尾山荘に集まっていた。談合の途中で、中村恒次郎と小藤平蔵が席を立った。二人の行き先は枡木屋である。牢獄に押し入り、予め示し合わせていた獄吏に扉を開けさせると、繋がれている中村円太を解放した。小藤は、福岡藩を脱藩するまで、枡木屋牢の獄吏として働いていた経験があり、獄を開いた人物とは同僚の仲だった。
同じ日に、重臣の暗殺と勤王派人物の脱獄という大事件が重なったから大変である。福岡藩の上層部はもちろん、対立する勤王派と公武合体派を穏便に並立させようと考えていた藩主黒田長溥は、冷や水を浴びせられることになった。
望東尼の気がかりは、山荘での談合中、車座から抜け出した中村恒次郎と小藤平蔵のその後の行方であった。中村円太と二人の足取りについては、山荘に現れた若者の一人が教えてくれた。脱獄に成功した中村円太と、円太を救い出した弟の恒次郎と小藤平蔵は、事前の打ち合わせ通り同士の家に匿われて難を逃れていた。
その後3人は、対馬藩の飛び地である肥前国田代宿(現鳥栖市)まで逃げた。そこで長州藩士の小田村文助と名乗る長州藩士に出会う。小田村は、3人に長崎まで同行することを勧めた。長崎に着いた3人は、商船に乗せられて長州の三田尻港まで送り届けられたという。ここに登場する小田村文助こそ、望東尼にとって後の人生を決定づける存在となるのである。

月形洗蔵が山荘にやって来て、長州の志士を匿って欲しいと願い出た。元治元年(1864年)11月11日のこと。匿って欲しい人物とは高杉晋作だと言う。高杉といえば、先頃、四国(英・仏・米・和蘭)連合艦隊による下関攻めに敗れた後、和解交渉の長州藩正使となった大物政治家ではないか。
翌日山荘に現れた高杉晋作は、想像していた豪傑風とは似ても似つかぬ優男であった。望東尼は、初対面の男の顔と仕種を一見して、強烈な衝撃を受けた。5年前にこの世を去った夫新三郎貞貫と、姿形だけでなく仕種まで似ていたからだ。そんなはずはないと自らに言い聞かせながら、改めて高杉晋作と向き合った。
.gif)
高杉晋作
望東尼は、初対面の男の顔と仕種を見て、強烈な衝撃を受けた。5年前にこの世を去った夫新三郎貞貫と、姿形だけでなく仕種まで似ていたからだ。そんなはずはないと自らに言い聞かせながら、改めて高杉晋作と向き合った。
「このような破れ小屋でよかったら・・・」
「このような破れ小屋でよかったら・・・」
昨年(文久3年)3月。高杉は、藩主から下関防御の役を任されたことがある。高杉は、その機を逃さず下関界隈に建つ功山寺で騎兵隊を結成した。その後高杉は、藩の許可を得ずに藩を飛び出し京に上ったため、脱藩の罪で野山獄に閉じ込められることに。イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四カ国連合艦隊が下関を攻めにかかったその時であった。
※奇兵隊:長州藩の非正規軍隊。門閥に関係なく、農商人を編入して実力主義をとったことで知られる。
※下関砲撃事件:1863年~64年。幕末、長州藩の攘夷実行に報復する英・米・仏・蘭4ヵ国連合艦隊が下関を砲撃した事件。長州藩は、降伏後の交渉で四国艦隊と講和を結ぶべく、高杉を牢から出して、長州藩正使に抜擢した
※野山獄(のやまごく):江戸時代、長州藩萩に造られた獄屋敷のこと。
「勝手なものですね、お上のなさることは。気に食わなければ牢に入れ、場面が変われば外国との交渉という大役を担わせるのですから」
望東尼が、深くため息をついた。
四国連合との交渉が一段落すると、長州藩内ではまたまた正義派と俗論派の論戦が始まった。幕府に対して抗戦を主張するのが「正義派」。幕府に恭順であるべきと主張するのが「俗論派」である。その時正義派をリードしていたのが高杉晋作であった。
激しい論争に敗れた正義派の志士は、次々に失脚していく羽目に陥った。四国連合との和解交渉後、萩の自宅に籠もっている高杉晋作の身辺にも危険は迫った。萩を抜け出して下関の豪商・白石正一郎邸に身を寄せていた高杉に対して、そこに居合わせていた中村円太が筑前行きを申し出た。中村は、長州藩士の小田村文助に誘導されて三田尻港に上陸した後、下関の白石邸に滞在していたのである。
高杉は中村円太の申し出に従って馬関(関門)海峡を渡った。門司の港に着いた後、肥前国の田代宿に向かった。田代は対馬藩の飛び地であり、攘夷派の勢いが強い土地である。
狭い山荘で他藩の若い男と同居することは、望東尼自身辛いことであった。そこで、自分は立益町の野村家に寝泊まりしながら、山荘に通うことにした。野村家から山荘までの距離は半里に満たない。女の足で通うにも、それほどきついことではなかった。山荘での高杉の世話は、瀬口三兵衛に頼んだ。
.gif)
旧対馬藩田代代官所跡(現田代小学校)
高杉は田代宿に滞在中、佐嘉(佐賀)藩主の鍋島閑叟に尊皇攘夷論を説きながら、倒幕の戦いに加わるよう説得を試みた。だがそれもうまくいかず、逆に高杉の身が危険にさらされることになる。前途を悲観した高杉は、福岡藩の月形洗蔵を頼った。月形は高杉に、野村望東尼が住む平尾山荘に隠れるよう勧めた。
「それで、当山荘においでなさった・・・」
話はそこで途切れて、沈黙の時間が過ぎていった。その間望東尼は、目の前の男の表情を見つめたままであった。
「貴方には奥さまは?」
とっさに口から出た質問であった。
「萩に置いたままです」
この話は、次には進まなかった。
その頃長州藩内では、俗論派の勢いがますます増幅していた。正義派3人の家老が、禁門の変を引き起こした責任をとらされて切腹するに及んだ。それだけでは済まない。俗論派は、更に4人の参謀を打ち首の刑を処した。このままでは、藩内の正義派は決定的に追い込まれることになる。
※禁門の変:幕末(1864年)。長州藩兵による兵乱。蛤御門の変・元治の変ともいう。前年の八月十八日の変で失墜した勢力を回復するため、尊皇攘夷派志士が長州藩を動かして京都に出兵。御所を護る薩摩と会津・桑名諸藩兵が、蛤御門周辺で戦った後敗走。京都は大火となり、長州藩は朝敵とされて、長州征伐が起こるきっかけになった。
平尾山荘に隠れている高杉は、同士からの報告を受けて衝撃を受けた。一時も早く長州に戻らなければならないとの、衝動に駆られた。
「今帰藩したら、待ち伏せしている俗論派の餌食になるだけですぞ」
止める月形洗蔵の声も高杉の耳には届かなかった。
「悲しいね、せっかく世の中のことを学ばせていただいたところだったのに・・・」
望東尼は、高杉の滞在が10日足らずでは、もの足りないと悔しがった。高杉が去った後まで自分のことを忘れないよう、その証を差し出したいと考えた。そこで望東尼は、夜を徹して高杉が着る旅衣を縫った。両袖の裏生地は、自身が身につける襦袢の袖を切り取って縫い付けた。翌朝、旅立つ高杉に着せかけてやるときのときめきを詠んだ一句である。
谷梅ぬしの故郷に帰り給ひける形見として夜もすがら旅衣を縫いて贈りける
ここでいう「谷」とは、高杉晋作の別称である。高杉もまた、山荘を去る際に、望東尼に漢詩を書き残している。その中の一首である。
|
山荘留我更多情 山荘我を留めて更に多情
賦呈
東洋一狂生東行拝具(高杉晋作の署名)
望東君
|
高杉は、突然飛び込んできた「危険人物」を、嫌がりもせず受け入れてくれた恩を終生忘れまいと誓った。そして、平尾山荘を去って行った。このときの高杉晋作との切ない別れは、望東尼の記憶から遠ざかることはなかった。
平尾山荘を後にする高杉晋作は、月形洗蔵らの身を挺しての援護で、無事長州藩に戻っていったのであった。
|

1.gif)

1.gif)
![]()