◎真夏の読書 トーマス・マン「ヨセフとその兄弟」
からkindle本まで

いつまでも暑い。地球の「熱帯化」を実感している。イスラエルとアメリカがイランの核施設を爆撃した6月中頃から、今年は一気に酷暑に入った感じだ(伊那谷でも35℃前後の日々が続いている)。それでもまだしばらくは、午前中は畑に出て外仕事をし、午後昼寝をして読書、夜は一杯飲んでyoutubeを見て早寝するというルーティンで過ごしてきた。しかしそれも次第に困難になり、8月に入ってからは朝5時半に起きて体操と犬の散歩をし、8時過ぎまで畑仕事をしたら家に引っ込んで遅い朝食を取る。あとはもう最低限必要な用事以外は外出せず、家にこもってぐだぐだと本を読んで過ごしている。ちなみによほど耐えられない昼下がりのピークの時間以外は、窓を全開にして扇風機だけかけて冷房も入れない。これで何とか過ごしている。
そんななか、この真夏の2か月近く、ひたすらトーマス・マンを読んできた。きっかけとなったのは、「ヨセフとその兄弟」四部作・全3巻(「ヤコブ物語」「若いヨセフ」「エジプトのヨセフ」「養う人ヨセフ」)だ。まずは7月の読書日記から。
*
7/13 冥途の土産の読書
トーマス・マン「ヨセフとその兄弟」第2巻(第三部エジプトのヨセフ)まで読了。ここでひと息。
読み始めてから約2週間。あと1巻を読み上げるのがもったいないぐらいの気持ちだ。こんな素晴らしい作品だとは知らなかった。たしかにまわりくどくて眠くなる部分もある。神学的歴史的知識がないとよくわからない部分も多い。しかし大きな交響曲のようなゆったりした流れがあって、ときにそれが盛り上がり一気にクライマックスに達したかと思うとまた引いて静かな流れとなり、また眠くなりかけたところでぐっと波が盛り上がって引いていく。この繰り返しに身をゆだねていると、この小説を読むことが何か日々の生活の精神的な支えになっていることに気づく。
そもそもは1か月前、井筒俊彦の「コーランを読む」を読んで、イスラームの一神教を理解するには旧約聖書の「アブラハム、イサク、ヤコブの神」がわからなければだめだと思ったのがきっかけだろうか。その後、イランの核施設の爆撃と報復(12日戦争)があり、その間、去年から積読状態だったイスラエルが舞台となるリュドミラ・ウリツカヤ「通訳ダニエル・シュタイン」を手に取って複雑な思いで読んだ。そして再び井筒俊彦の「神秘哲学」を途中まで頑張って読んだところで、ふとネットで「ヨセフとその兄弟」の古本が目に留まったのだ。
トーマス・マンはこの冬、「ファウスト博士」を再読しかけてやめたところ。購入した「ヨセフとその兄弟」(筑摩書房全3巻 大判2段組み各600頁超)も、はたして読み通せるかどうかわからなかったが、読み始めてみるとこれが凄い。あらゆるディテールを微に入り細を穿ち描きこんであり、それがどっしりとした手応えにつながる。おもしろくてやめられなくなった。「老練の作家マンが亡命の運命にもてあそばれながらも実に十六年間毎日休むことなく書き続け、しかも原稿用紙を一枚書くごとにたのしくてならず、早く翌朝が来て先を執筆するときにならぬかと次の日を待って書いた」(小塩節)という話がとてもよくわかる。
こんな大作を古希を過ぎるまで知らずにいたとは…。いまとなっては、まさに「冥途の土産の読書」である。眼の飛蚊症がだいぶひどくなっているが、まだこれぐらいの活字なら何とか読めそうだ。あと1巻。楽しみだ。
*
結局、それから約1週間、全部で17日間かけて全3巻を読み終えた。翻訳にして四百字約1万枚。「戦争と平和」より長い。しかしこの歳になって、これだけ読み応えのある小説と出会える経験はそうざらにない。気の遠くなるような太古の時間の流れ、呼吸、リズム、歴史感覚。3000年前のパレスチナやエジプトがどういう世界であったのか、ガザやヘブロンがどういう土地であったのか、イスラエルとはそもそも何であったのか…。
ちなみに17という数字は、作品中でもいろいろな場面で出てくる象徴的な数字で、ヨセフの故郷ヘブロンからエジプトのメンフィスまでの陸路の旅の日数であり、テーベからナイル川を下って要塞監獄のあるツァウイ・レーまでの船旅の日数でもある。またヨセフが彼を嫉んだ10人の兄たちから井戸の底に投げ込まれたのが17歳の時、それから17年を経て年老いた父親のヤコブと奇跡的な再会を果たすのである。
全巻を読み終えてから、旧約聖書の創世記とコーラン第12章「ヨセフ物語」を改めて読んだところで、たまたまアマゾンのセールで電子書籍専用のKindle端末を買った。初回購入特典でKindle unlimited読み放題3ヵ月無料というのがついてきて、検索してみると結構トーマス・マンの小説も読める。学生時代に読んで以来、一度も読み返したことのない「魔の山」の岩波文庫(全4巻)がまだ取ってあり、久々に書棚の奥から取り出して頁をめくってみたが、この細かい活字でまた全部読み返すのはさすがにきついと思った。ではせっかくだからKindleの大きな文字で読んでみるか、ということで圓子修平訳をダウンロードして読み始めた。すると、これが結構読みやすいではないか。専用端末だから、スマホより軽量(158g)で片手でも持てる。文字の大きさや字体、画面の明るさも微調整でき、付箋や線引きも使える。立ち上げもかんたんでページめくりもすいすいいく。十年ぐらい前に試して、あまりの使いにくさに投げ出してまったKindle fire7とはえらい違いだ。
強いて難点を言えば、文字を大きくすると一画面に表示される情報量が少なくなるから、頁めくりが頻繁で前後や全体を把握しにくいこと。遡って一部分だけ確認したり読み返したりするのが難しいこと。本の厚みがないから、短編なのか長編なのか読んでいてよくわからないことetc…と、挙げていけばいろいろあるが、おっ、なかなかいいじゃない、結構楽に読めるぜ、というのが率直な感想だった。
そうして、あの観念的な議論をところどころ読み飛ばしながらも「魔の山」を約50年ぶりに通読。そうか、こういう小説だったんだなとあらためて思い返し、続けて「ブッデンブローク家の人々」(川村二郎訳)を、これもKindle本で50年ぶりに再読。結構集中できて、いま読み返すと「ブッデンブローク」の方がずっと面白いことがわかった。そして「トニオ・クレーガー」「ヴェニスに死す」とすべてを電子本で読み返すという不思議な読書経験をした。
やはり「ヴェニスに死す」は何度も観たヴィスコンティの映画の印象が強烈に残っていて、原作では主人公が作曲家ではなく作家だったことすら忘れていた次第。それでも映画の各シーンをひとつひとつ確認してたどり直すような読書は楽しかった。(ただ電子本で読むと何か読後の印象が薄いというか、記憶に残らない感じがするのはなぜだろう? 慣れの問題かもしれないが…)。
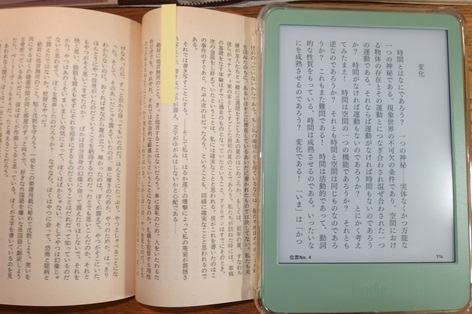
さて残るはこの冬、再読しかけて挫折したあの「ファウスト博士」である。この岩波文庫版(全3巻)を初めて読んだのは長野の山村に移り住んだ30代の初め頃、ということはランプの灯りで読んだことになる(Kindleの対極だな)。ニーチェをモデルに、梅毒に侵された作曲家の主人公と悪魔との対話の部分がどうしても読み返したくて手に取ったのだが、そこにたどりつくまでのクラシックの音楽理論の抽象的な議論にどうしてもついていけず、おまけに文庫の小さな活字も読みにくくて、途切れたままになっていた。今回もあれこれ探したがKindle本はなく、古い文学全集本かこの岩波文庫版で読むしかないことがわかった。
前回途切れたのは、ちょうど主人公アドリアン・レーヴェルキューンの最初のピアノの先生が、「ベートーベンはなぜピアノ・ソナタ作品111に第三楽章を書かなかったか」を皮切りに連続公演をするあたりである。クラシック音楽に縁のない読者は、だいたいこの辺で振り落とされる。そのあたりは覚悟して読み始めた。トーマス・マン自身、亡命先のアメリカで、やはりドイツのフランクフルトから亡命してきた哲学者で音楽家のアドルノに何度も話を聞きながら推敲を重ねた音楽理論だから、そうかんたんに理解できるわけがないのだ。(ちなみにアドリアンの作曲法のモデルはシェーンベルク)。
しかし音楽理論の抽象的な議論やサロンでの退屈な会話の部分は文字面だけ追って読み過ごし、どんどん先へ進んでいくと、中巻の中頃でアドリアンの遺された手記として、身を切るような冷気とともについに悪魔が登場する。そして主人公と長い会話が交わされ(文庫本で50頁余り)、愛の不可能と引き換えに芸術の高揚が約束される。この辺はやはり凄みがある。小説中の時間では、これが書かれたのが1911〜12年頃のイタリア山中の宿でのこととなっている。
この後に、語り手たる主人公の幼馴染ゼレヌス・ツァイトブロームは「三重の時間」ということに注意を促す。「読者は三重の時間の秩序、すなわち読者の時間、伝記作者たる私の時間、及び歴史的な時間、とかかわり合うことになる」。これをこのシーンに即して言えば、主人公アドリアンが悪魔と会話を交わす第一次大戦前夜のヨーロッパという時間。語り手ツァイトブロームがそれを書き写し、ナチス政権下で生きている1944年という時間。さらに言えば、それを亡命先の米国カリフォルニアで書いている作者トーマス・マンの時間。そしてそれから80年後、ガザの大虐殺とウクライナ戦争、殺人的な異常気象が進行する2025年の世界で、読者である自分がそれを日本語の翻訳で読んでいるいまという時間である。これは連続的につながっていると考えざるをえない。それが恐ろしいところだ。
時間という主題はトーマス・マンの小説では「魔の山」から「ヨセフとその兄弟」まで繰り返し現れるが、初期の「ベニスに死す」の砂時計の挿話が、この「ファウスト博士」の悪魔との対話でも出てくる。そう、砂時計のくびれた部分は非常に狭いから、初めのうちは一見して全然減ったように見えない。ただ一番おしまいになると、砂粒は一気に早く流れ落ちてしまうのである。
さてこの後、アドリアンはミュンヘン郊外の田舎の屋敷にこもって旺盛な創作力を発揮し、代表作「デューラーの木版画による黙示録」などで世の注目を浴びる。しかし求婚の失敗に続き、目に入れても痛くないほど可愛がった5歳の甥っ子が脳膜炎で急死して以後人が変わり、生の謳歌たるベートーベンの「第九」を取り消すための、生の没落の交響曲「ファウスト博士の嘆き」の完成に没頭する。そしてその発表の場で、悪魔との契約とこれまでのいきさつを語り、ついに発狂する。1930年、44歳の時だ。それを物語る書き手の時間は1945年4月、ヒットラーがついに自殺を遂げ、ホロコーストが終わった時である。
これ以外にも、実在や虚構の様々な人物が登場して、思わぬ伏線から恋愛がらみの自殺や殺人事件などが起こり、小説的な展開も随所に溢れる現代文学なのだが、正直言って読んでいて苦しくなる小説である。トーマス・マンも、これはほとんどドイツ人としての自らに課した義務もしくは遺作として書いたのではないかと思う。そこが「毎日書くのがたのしくてならなかった」という前作の「ヨセフ小説」とはぜんぜん違うところだ。「ファウスト博士」の今日的意義はますます深まっていると思うが、また読み返すのはつらいな。(「ヨセフ」はぜひまた読みたい)。
それにしても文庫の小さな活字を一日追っていると、さすがに眼が疲れる。飛蚊症もひどくなった。年取って、いつまでこんな読書が続けられるのかと思ってしまう。Kindle本はたしかに読みやすいけれど、読める本が限られているのが難点だ。無料の青空文庫などを除けば、値段も紙の本と1割程度しか変わらないし、読み終わったからといって古本で売るわけにもいかない。可能性は開かれているが、まだまだ発展途上のアイテムだなと思う。