子らの旅立ち
伝が四十(歳)台半ばの頃。日本全国に飢饉(ききん)が蔓延(まんえん)し、世の中は疲弊(ひへい)しきっていた。歴史的にも有名な、天保の飢饉(てんぽうのききん)である。
「あっちこっちで騒動が起こっておるらしかね」
伝はユキエを相手に、これからの暮らしを心配している。
「米が半分も収穫できんで、飢え死にする人も相当出ておるそうです」
久留米に住む彼女らにとっても、飢饉はけっして他人事(ひとごと)ではなかったのである。
「逆に久留米の町は、最近の大雨で、今年も不作じゃろね。これからの世の中、どげんなるもんやら」
「そうですよ、お伝さん。目が少しばかり薄うなったから言うて、弱気になっとったら、ご飯が食べられんごとなりますけん」
同年代のユキエは、自分にも言い聞かせるようにして、伝を元気づけた。
そんな時、伝にとって考えもしなかったことが起こった。20歳に成長した長男の兵太郎が、幼馴染の娘と恋仲に陥ったのである。相手は、原古賀(はらんこが)で機屋(はたや)を営む稲益屋の娘ミサキであった。彼女は一人娘であり、将来は婿養子をとることが決定づけられているという。
「冗談じゃなかばい。こっちだって、兵太郎には嫁ば迎えるとじゃけんね」
この件ばかりは一歩も譲れないと、伝が息まいた。もし、そんなことを許せば、兵太郎を「お傳加寿利」の織り元後継者にと思ってきた構想が崩壊してしまう。
母親が反対しても、息子だって一歩も引かない。「許してくれんなら、ミサキと駆け落ちばするだけたい」と脅す始末。こんな時、父親がいてくれたらと思うのだが、それもないものねだりであった。
「兄(あん)しゃんの言うとおりにしてやらんね、お母しゃん」
傍らで母と兄の激しいやりとりを聞いていたイトが割って入った。

伝愛用のハサミ
「ばってん・・・」
「うちが養子さんばもらえば済むことじゃろう。うちはこれからもずっとお母しゃんのそばにおるけん」
「そんなら、材料の仕入れやら機屋さんとの話しは誰がすると? 他に男手はなかとよ」
「そのうち養子さんが決まったら、そん人にやってもらえばよか。それまでは、お母しゃんとうちがやればよか」
イトの兄を庇(かば)う気持ちが通じて、伝はしぶしぶ兵太郎の言い分を承知した。伝は、とうとう娘と二人暮らしになってしまった。
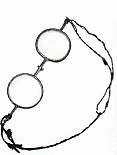
井上伝愛用のメガネ(地場産くるめ展示)
そうこうしているうちに、イトの婿になる相手が見つかった。佐助の店で働いている儀助である。兵太郎の祝言の翌年のことだった。伝にとって、イトの結婚は何にも勝る幸せなことだった。
太蔵の絵がすり
「伝さんが作りなさる加寿利は、簡単な模様ば並べただけで、変化に乏しかち思うとです。絵とか文字とか、もうちょっと自在に織れんもんか・・・」
かすり織りの大先輩に対して言い放った大塚太蔵(おおつかたぞう)。生意気を言ってしまった手前、後には引けなくなった。それからというもの、かつて江戸で見た、友禅織のあの微妙な絵柄と多彩な色彩が脳裏から離れない。
あのように複雑で鮮やかな図柄を、糸を染めて織るかすりで再現できないものか。太蔵が食台に白紙を載せて、独り言を呟(つぶや)きながら、白鷺が餌を食む姿を描いている。
井上伝の絵がすりは、細工屋の儀右衛門が考え出した板締め技法が基になっている。つまり、思い描いた絵柄を平面の板に彫り、その板の上に必要なだけの白糸を張る。糸を張ったその上から、もう1枚の板で押さえつけて藍汁(あいじる)に浸ける。そうすれば、彫刻された凹部は藍色に染まり、凸部は染まらない。それぞれの糸が染まったことを確かめたら織り上げていく。それが井上伝の板締め技法である。
「兄(あん)しゃん、何も板締めにこだわらんでも・・・」
はた織りの手を休めて、妹のスミが太蔵の手元をのぞき込んだ。
「どういうことな、スミ」
「わざわざ板ば彫らんでもよかろうもん」
「・・・・・・」
それだけのヒントで理解する能力は、今の太蔵にはない。苛立つスミが食台に白糸を並べ始めた。
「この糸の上に、直接絵ば描いたらどげんね」
「絵ば描いた後は、どげんすると?」
「しぇからしかね、兄しゃんは。その後は自分で考えて」
答えを示さないまま、スミはまた杼を送り始めた。はた織りが好きなくせに、妹を頼りきっている自分が情けないと、太蔵は自らを責める。
そんな時、太蔵は、傍らにあった形付(かたつき)の小布(こぬの)に描かれた模様が気になった。
 .gif)
絵糸書きと絵台(地場産くるめ展示)
スミが言うように、直接糸に絵を描く。そうしたら、もっと自在に絵模様が描けるはず。そのために、台上に原糸数百条を並べて絵を描いた。その後に、そっと台を取りはずす。斑模様(まだらもよう)に墨が付いた糸を、別の白糸で括って染めた。染め上がったところで括り糸を解くと、括ったところは白いままで残っている。その糸を織ってみる。藍染めの布に白い絵柄が浮かび上がって見える。かすかにではあるが、太蔵が思い描いている絵がすり模様が見えてきた。更に方法を変えながら、「太蔵の絵がすり」が少しずつ完成に近づいていった。
いよいよ絵がすりが完成すると、恥ずかしがるスミを説き伏せ、出来たての絵がすりの着物を着せて久留米の街を歩かせた。
「青い空に白い花が咲いとるごとある」と、道行く人が振り返った。
「兄(あん)しゃん、それならば・・・」
今度はスミの方から兄に、高良大社の祭礼時に合わせて市場に出品することを勧めた。スミの思惑はぴたりとあたり、街の芸者衆から芸名を織り込んだ太蔵織りの注文が舞い込んだ。
.gif)
あ代表的絵がすり「高砂の翁媼」(複製)
(久留米絣技術保存会所有)
それから日をおかずして、太蔵のもとに、赤間関(下関)の太夫の使いだという優男(やさおとこ)が現われた。「ぜひとも・・・」と言って注文したのが、太夫の名前に和歌を添えての織物だった。それは、男社会に生きる太夫の見栄でもあった。
「念願叶(かな)って武士になれたあの時より、絵がすりを成功させたときの方が何倍も嬉しかった」と、後日太蔵は身内に語っている。
「太蔵さんの絵がすりが、ばさらか(大変)評判になっとるげな」
ユキエが、元気のない声で伝に語りかけた。
「あの大男が、とうとうやったばいね」
伝は、大塚太蔵が庄兵衛の店で大見栄を切った時のことをよく覚えている。「伝さんの絵がすりは変化に乏しか」の一言で、己の頭が激しく揺すられたことも。細工屋の儀右衛門に考えてもらった板締めの技法を、あの男は簡単に乗り越えてしまった。これも、時代の流れだと考え、ユキエの挑発には乗らないことにした。
自分が加寿利を生み出した少女の頃を振り返ってみる。色褪せた布地を見て、ところどころに残る斑模様(まだらもよう)に惹かれた。布を解(ほど)いて、1本1本の糸に残る藍の剥(は)げ跡を元に、別の白糸で括(くく)って藍汁に浸けた。染め終わった糸で織ってできた模様が、世の評判を呼んだのだった。
あの頃の伝には、若さに加えて祖母という最良の師匠がついていた。また周りには、幼馴染の紺屋(こうや)の佐助や、新しい器械を創りだす細工屋の儀右衛門がいた。そんな環境が整ったところで「お傳加寿利」が誕生したのだった。
大塚太蔵もまた、得意の絵心を生かして、絵がすりの開発に立ち向かった。妹のスミという良き協力者を得ての成功であった。藍地の中に白色を際立たせる絵模様を、自在に変化させたのである。
だが、太蔵の絶頂期も長くは続かなかった。38歳でこの世を去ることになったからである
ノシの小かすり
「うちは近いうちに、必ず先生より上手なかすり織りになりますけん」と、師匠の前で言ってのけた小娘がいた。稲富村(現八女市)から出てきた弟子のノシである。彼女は、伝のもとから独立して後、となりむら川向うの国武村(現八女市国武)に住む牛島家の太七と結婚した。
嫁入り先は貧農で、その日暮らしにも事欠くさまであった。新妻のノシは、まず家計を支えるために、井上伝のもとで覚えたはた織りに励んだ。
日銭稼ぎの間も、「先生を超える織り手になる」決意を忘れてはいなかった。
男も女も、年寄りも子供も、貧乏人も、共通して誰もが着用するかすりを実現するにはどうすればよいか。

代表的小がすり「蚊絣」
(久留米絣技術保存会所有)
まずは、今でも月に5反程度しか織れない速度を、もっと早められないか。普段着としての、男に似合う「小柄」を織るにはどうすればよいかと。
そんなある日、隣家の小屋の解体作業が目に映った。屋根に上った男が、梁(はり)に被せた編薦(あみごも)を剥(は)がした。すると、長年編薦の下にあった縄の跡が、細かい筋目まで白くはっきりと梁の上に浮かび上がっている。
「この細かい筋目をかすり織りに応用出来ないか」
ノシの長考が始まった。細かい柄を編みだすためには、糸の括りも細くなければならない。それならばと、木綿針を使って緯糸を細かに編んでいく。それを藍汁に浸けた。乾いたところで編んだ糸を解くと、藍に染まった部分と染まらないところが、編薦の模様と同じようにか細く記(しる)されている。その糸をはたにかけると、自分の目を疑うほどに、美しい小がすり模様が出来上がった。まるで、小さな蚊が飛んでいるようである。井上伝の板締めでもない、大塚太蔵の絵台を使った手法でもない、牛島ノシ独自の木綿針を使った緯糸縊(よこいとくび)りの小がすり模様が創り出されたのであった。ノシの緯糸編み技法は、それまでかすり1反の緯糸を編むのに2日かかっていたものを1夜で成し遂げ、月に8反もの小がすりを請け負うことに繋がったのである。
ノシは、自ら考え出した小がすりの技法を「屋根板がすり」と名づけた。微妙な小柄の屋根板がすりに機屋が慌て、問屋が動いた。そして、新しい柄を好む市中の消費者が興奮した。
福島の町(現八女市中心部)では、1人で月に8反ものかすりを請け負うノシのことを、「八反屋」と呼んだ。国武村に住む小がすりということから、「国武かすり」の商号もつけられた。
.gif)
現在の八女市南国武
ノシが創りだした織物は、彼女のもとへの弟子志願者が急増するという形で現れた。新たに建てた別棟の作業場には、染め方と織り方合わせて十数人の娘がひしめくようになった。時間の経過とともに、ノシの弟子たちもまた、家庭に戻ったり嫁入り先ではた織りに精を出すことになる。
国武村から上妻・下妻の全郡へ。あらゆる村のほとんどの家からはた織りの音が聞こえるようになる。弘化3(1846)年、ノシ30歳半ばの脂の乗り切った頃であった。

晩年の牛島ノシ
(久留米絣技術保存会提供)
通外町の作業場で、叱られて涙を浮かべながらはたに向かっていたあの小娘が、ついに師匠も及ばない緻密な小がすりを織る手法を考え出し、1人で月に8反もの大量生産にも成功したのである。
.gif)
牛島ノシ顕彰碑
(八女市南国武)
伝はここでも、ものを創りだす若者の、頭の柔らかさと行動の大胆さに舌を巻いた。古くなりかけた自分の頭脳とどう向き合えばよいのか、深刻に考えさせられるこの頃でもあった。
師をも驚かせるほどの技術革新を成し遂げた牛島ノシ。息子や孫の代まで、織屋として、またかすりを売り歩くあきんどとして、久留米では、欠かせない存在となる。
ノシ女史は、明治20(1887)年に75歳で没した。
|
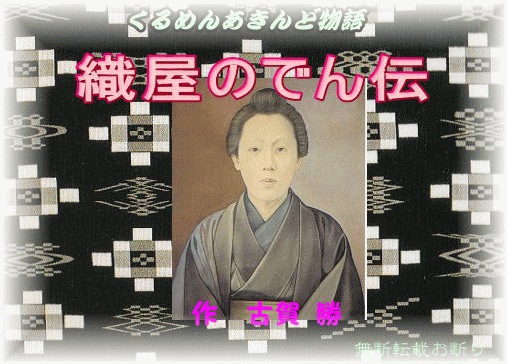
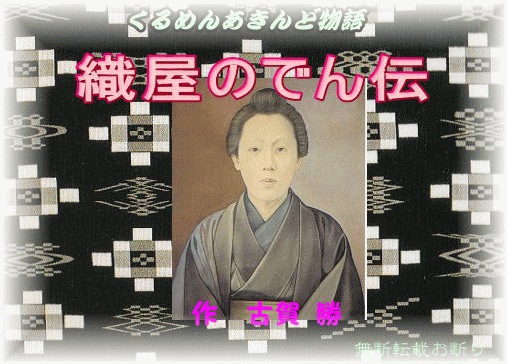
![]()
![]()



