| 開拓に総力

田植えを終えた千町無田から望む、左から黒岳・平治岳・三俣山
明治37年(1904)、入植から10年が経過した。青木牛之助が大分県から「10年間で150町歩の開拓」を義務づけられた期限の年である。
最近の開拓村は、再び新規の入植者も増えて、総勢43戸に膨らんでいる。先が見えずに脱落した者の分を新しい入植者が補って、やっと明治27年の鍬入れ時の規模にまで戻ったのであった。
しかし、できあがった耕地では、未だトウモロコシやソバ、大豆などが主流である。本格的な水稲栽培は先延ばしになったままだ。ここにきてもなお、現金収入の方法として硫黄運搬が主力をなしていた。
牛之助は、稲作の目途が立たないことに焦りを覚えている。開拓団の財政は、種籾や肥料を買う金が決定的に足りない。「タジリ」の品質の悪さから、つくって売る、売った金で次の生産の基礎を築くという巡り合せがどうも噛み合わない。野菜栽培だけでは、開拓団の将来に展望を持つことはできない。それにもまして悩み事は、開拓面積が思ったほどに広がらないことであった。
10年目を迎えて、大分県知事との契約条件である150町歩には遠く及ばず、100町歩を超えたばかりであった。
この日も、川島利三郎や田中栄蔵などを呼んで、開拓の速度を上げるための方策を考えていた。
「このままじゃ、1年や2年契約を延ばしてもらっても、とても間に合いそうになかな」
まず、硫黄運搬をしばらく休んで、「若者と牛馬をすべて開拓に向けるべきだ」と牛之助が主張する。「昔の極貧暮らしに逆戻りしかねない」と、さすがの長老たちも、牛之助の言うことに頷こうとしない。
「馬鹿もん、、せっかく拓いた畑ば、期限までに間に合わないから返上しますとでも言うとか」
牛之助は、やり場のない苛立ちを長老らに向けた。硫黄運搬から若い労働力を取り戻す、各家族の生活のことを考えると、協議はなかなか先に進まなかった。
ここが開拓団の踏ん張りどころである。田川与吉の家では、長男の為治が20歳、次男の好夫が17歳に成長していた。この家族も、ハルの弟良吉を加えて、若者が硫黄運搬に駆り出されている。与吉は牛之助から、「今後は日銭稼ぎをやめて開拓に全力をあげるよう」申し渡されたと為治に告げた。いま硫黄運搬をやめれば、この先また食うに事欠く暮らしに戻らなければならない、と為治がむきになった。
「大丈夫だ、うちの残り面積はそげん残っておらんけん。村の皆んながその気になりゃ、千町無田はすぐに開拓団のもんになるたい。あと1年辛抱すりゃ、米つくりにも目途が立つち、青木先生が言いよらしたけんな」
そばで夫の力説を聞いていたハルの目が、「もうすぐ耕地が開拓団のもんになる」のくだりで輝いた。
田川家では、「開拓に総力」の指令を実行に移した。それからというもの、間もなく還暦を迎える与吉が真っ先に起きるようになった。良吉と為治が目を擦りながら与吉に続いた。そんな男たちを、とっくに起きて朝食の支度を済ませたハルが笑顔で迎えた。
入植当初は、比較的水分の少ない所から耕地に替えていったために、残っている未開地は未だ沼同然である。草を刈り溝を掘るのも、これまで以上に力の要る仕事であった。
その間、野菜を収穫するのは、女手のハルとトヨエの仕事となった。収穫した野菜は、良吉が車力に積んで中村の町に売りに出かけた。朝暗いうちに始める作業は、星が輝く時間まで続いた。
こうして、開拓の終盤は、信じられないほどのスピードで進展した。森山辰次郎や井上平八の家でも、田川家と同じ光景が繰り広げられた。
寒冷地米
開拓民が一丸となって励んでいる頃、牛之助は、次なる水稲栽培の準備に余念がなかった。飯田村の農会長をしている時松三治がやってきた。時松も高原での稲作りには人一倍熱心で、牛之助の良き助言者である。彼は、米づくりに適した種籾を探して東奔西走中だった。
「青木先生、東北地方では、寒さに滅法強か水稲の品種が開発されたそうです。あの寒かとこでできるんなら、飯田高原でもできるとじゃなかですかね」
時松は、「試作するならこれしかない」と言い切った。牛之助の気持ちが動いた。時松は牛之助の意を受けて種籾の入手にとりかかった。そしてついに、秋田県の極早生品種「関山」の種籾が手元に届いた。
地元産の「タジリ」に見切りをつけた後、各地から何度も種籾の見本を取り寄せたが、苗さえもなかなか育ってくれなかった。そうなると、更に失望して脱落者が出る。次なる品種を求めて借金を繰り返す。そんな模索の中で、ようやく手に入った「関山」であった。

収穫間近の千町無田
今度は苗の生育も順調で、思ったほどに害虫もつかず、台風の難も逃れて、やっと予定した量の収穫を得た。
「これからは、米を売って生活ができる」
「もう心配はいらん」
石に噛り付くようにして開拓を続けた者たちから、安堵の声が漏れた。水稲栽培に目途が立ったことで、千町無田から去った者の回帰の速度も早まった。そんなことがまた、開拓の速度に弾みをつけた。
青木牛之助は、大分県との開拓許可条件から1年3カ月遅れた明治38年(1905)6月21日、大分県知事あてに「成功届」を提出した。
| 耕作面積 |
156町7反3畝 |
| 道路・川敷 |
15町2反2畝 |
| 合計 |
171町9反5畝 |
大分県は、開拓された千町無田の土地を、川島利三郎ら48名(戸)に払い下げると通知した。知らせを聞いた入植者は、誰かれ構わず手を取り合って喜んだ。ある者は、嬉しさのあまりに泣き崩れる者もいた。「これも、水天宮さんと青木先生のお陰たい」
自分の土地
明治40年(1907)8月。出資額と開拓の実績に応じての土地の分配が始まった。開拓民が生まれてこの方夢に見てきた、自分の土地を手にする瞬間である。その日はまた、彼らが親代々苦しんできた「水飲み百姓」から解放され、晴れて「本百姓」を名乗れる記念日ともなる。
あの忌まわしい大洪水から18年、先発隊が初めてこの 地に鍬を入れてから数えても、13年の歳月を要している。 地に鍬を入れてから数えても、13年の歳月を要している。
開拓村は、牛之助の恩に報いるために、朝日神社の境内に「青木牛之助氏開墾記念」の石碑を建立することになった。写真:朝日神社境内に建てられた青木牛之助氏記念碑
田川与吉が記念碑建立の祝宴から戻ると、家の中には灯もついていなかった。襖の向こうに、妻のハルが一人、宙を見据えたまま座っている。
「どうした?」
与吉の声で我に返ったハルが、振り向いた。
「ああ、帰っとったですか」
ハルの気持ちは、未だ夢の中のようだ。
「私らが拓いた畑が、みーんな自分のもんになったとですね」
「ああ」
与吉は、頭にめっきり白いものが増えたハルの横に座ると、ささくれだった妻の手の甲を無造作に撫でた。
「子供たちがよくついてきてくれましたね」
ハルは、夫に手を握られたことなど結婚以来なかったと思いながら、心地よさそうに目を閉じていた。
その頃森山辰次郎の家を、2人の子供を連れた井上平八の嫁のトキコが訪ねていた。男の子は、入村してすぐに生まれたあの時の赤ん坊である。名前を宇太郎とつけ10歳になると言う。もう一人は、宇太郎から2年後に生まれた女の子であった。
「大きくなったね」
シマは、トキコの子供たちを自分の孫のように可愛がっている。宇太郎が生まれた時、末息子の耕吉が10歳を過ぎて間もなくであった。その耕吉が今では、上の学校に進んで農業を勉強している。月日のたつのは早いものだと、シマはつくづく思う。
入植して間もなく、村は思わぬ台風の襲来を受けて、大混乱に陥った。どこの家でも食うものがなくなり、子供たちはボロ着のままで、「腹が減ったよ」と泣いていた。
だが、大方の入植者は、開拓を諦めなかった。「将来、自分の土地を持ちたい」一心で、馬小屋より粗末な掘立小屋の暮らしにも耐えた。風呂がなくて、汗臭い体も我慢した。悪いことは重なるもので、寅五郎の家が一瞬にして消失した。焼け跡からやっとのことで立ちあがった井上家では、トキコが出産した。それは真っ暗やみの中の一筋の光明であった。
産婆のいない山中で、シマは見よう見真似の代役を果たした。生まれたばかりの赤ん坊を取り上げたあの瞬間の感動を、一生忘れることはないだろうとシマは考えている。
「じいちゃんが亡くなって何年になるかね」
入植の日、南ノ平の高台で、茫然と眼下の沼地を見下ろしていた定吉のことを、シマは訊いている。

「はい、もうすぐ5年になります。皆さんにご迷惑をおかけしました火事以来、じいちゃんは黙り込んだまま一歩も外に出んようになってしもうて。そのせいですかね、ボケが始まり、『ちっごんみった(筑後の水田)に帰りたか』ちばっかり言うて死にました」
トキコは、夫の祖父が80歳で他界したことが遠い昔のことのように思えると言いながら涙ぐんだ。シマにとっても、入植してからの苦しかった歳月が、夢のように思えて仕方がなかった。
鍬入れから13年間の開拓事業ではあったが、土地の分配を受けた48人(戸)のうち、当初から参加している者は少ない。最終的な分配は、最高10町歩から最も少ない者で2畝あまりと、大きな開きが出てしまった。
当初入植する者には、1人あたり3町歩を限度として受け付けた。この間脱落者が出るたびに出資金を返還し、その分既入植者にも追加出資を許したので、分配に開きが出るのも仕方のないことであった。
分配が大方終了する時点で、玖珠郡の郡長から牛之助に、地元困窮者十数名を千町無田に受け入れてほしいとの要請があった。牛之助は、開拓許可を得るために走り回っていた時の、玖珠郡役場からいただいた恩義を忘れてはいなかった。
「千町無田の住民が増えることは結構なことです」
牛之助は、拓かれた土地のうち、自分名義のすべてを格安で譲ることにした。
筑後に帰る
青木牛之助は、開拓地の分配が終了したとき、自分の難民救済事業も節目を迎えたことを自覚した。
「俺も還暦を過ぎた。もう限界だろう。長男の始も嫁を貰って子供もできた。息子に千町無田開拓の指導者として後を任せることに不安はない。一人で久留米の留守宅を守るツルには、これから先は心配をかけないようにしたい」
ふるさとに帰って、隠居する気持ちを固めたのであった。
「先生はずうっとここにおってくださると思うとりました」
牛之助が千町無田を離れる前の晩、川島利三郎や田中栄蔵など開拓当初からの長老たちは、開拓事務所に集まって名残りを惜しん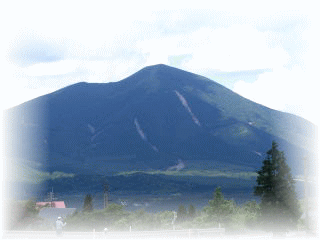 だ。事務所も今では、広くて立派な木造建築に変わっている。 だ。事務所も今では、広くて立派な木造建築に変わっている。
「俺がおらんでも大丈夫だ。お前たちにはこげん広か土地があって、若かもんが立派に育った。それに赤ん坊もたくさん生まれたじゃなかか。子供たちは素敵な学校に通い、千町無田の強力な予備軍になっとる。何の心配もなか」
牛之助は、集まった一人一人の肩を叩き、頭を下げた。外に出て、高原の空を見上げた。完全に暮れない彼方に、熊本県との境に聳える湧蓋山が、影絵のように見えた。写真:飯田高原の西方に聳える湧蓋山
豊後と筑後の境界・虹峠を、牛之助は何十回跨いだことか。今度が最後になるかもしれない。そんなことを考えていると、一挙に通り過ぎるのがもったいないような気にもなった。
懐かしい筑後平野は、久しぶりの牛之助を歓迎するかのように日本晴れだった。大石堰を見下ろす筑後川べりに腰を下ろした。現地調査のため、初めて千町無田に出かけるとき休んだ場所だ。今日も18年前と同じように、向こう岸近くを四連筏が、流れに任せてゆっくりと下流を目指している。目の前の景色は、あの時と何も変わっていなかった。
.gif)
現在の大石堰
かつて、人や家畜の命を容赦なく奪った筑後川が、今度は、生き死にの境にあった何百人もの農民の命を救ってくれた。被災した後、断腸の思いで故郷を捨てた者たちが、筑後川を遡っていき、死に物狂いで水源の湿地帯を開拓した。今ではそんな彼らも、すっかり山の人間になりきっている。ましてや、物心ついてすぐ移住したり、開拓地で産声を上げた子供たちにとって、筑後は先祖が生きたというだけの他国同然にみえるだろう。
川が人間の運命を変えた。一方、川は人間に限りなく勇気を与えてくれた。そんな筑後川も、時が過ぎて人間が恩を忘れたら、また大目玉を食らわすに相違ない。
大石堰に別れを告げて、すぐ下流の吉井の町に出た。筑後平野に下りたって気がついたことだが、街道の道幅が随分広くなった。曲がりくねっていた道もまっすぐに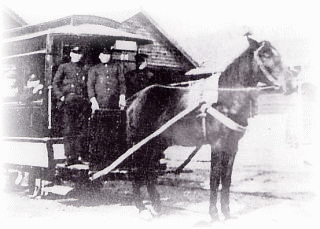 伸びている。道路の真ん中には軌道が敷いてあり、頑強な馬が客を乗せた車両を牽いていた。線路の脇を、談笑しながら人が歩いている。写真:明治30年代の馬車鉄道 伸びている。道路の真ん中には軌道が敷いてあり、頑強な馬が客を乗せた車両を牽いていた。線路の脇を、談笑しながら人が歩いている。写真:明治30年代の馬車鉄道
この鉄道、明治36年に吉井から田主丸までの間に開業した「筑後馬車鉄道」である。客車は15人乗り。客車を牽く馬が石油発動機に代わるのは、牛之助が出あった翌年のこと。路面を走る鉄道は、やがて久留米まで伸び、更には吉井から日田に通じた。現在のJR久大本線の前身である。
牛之助が標高900メートルの千町無田に籠っている間に、筑後平野は大変貌を遂げていたのであった。
自宅では、妻のツルが、今度こそは夫が自分のもとに落ち着くだろうと確信して出迎えた。留守中、1日も欠かさず、神棚に開拓の成功を祈ったことや、毎度の私財の持ち出しで苦労したこと、息子と娘を女手だけで育て上げたことなど、忘れてしまったかのような涼しい顔であった。
自宅に落ち着いた後の牛之助は、昔からの趣味だった和歌を詠み、屏風を貼ってそこに墨絵を描く。襖が売れた時には、その金で酒を買いにやらせた。20年前の生活に戻ってみて、ようやく自分の人生を取り戻した気分であった。
千町無田開拓に立ち向かう前と今を比較して決定的に違うのは、もう充分に生きたという充実感であった。それは、明治維新以来、ずっと胸に仕えていたもやもやから完全に解放されたということだった。そんな強靭な精神力の持ち主である青木牛之助も、一升徳利だけは死ぬまで傍から離さなかった。
大正12(1923)年、牛之助は愛妻ツルに見送られて天国へ旅立った。享年77歳であった。
牛之助の訃報を聞いた千町無田の川島利三郎や田中栄蔵、石崎熊蔵らは、寄り集まって幾晩も泣き明かしたという。
終章につづく
|