|
第8部 再会と別れ
白石正一郎邸
望東尼らを乗せた帆船が、馬関海峡(関門海峡)から吐き出されてくる船群を横目に、その先の小瀬戸へと進んで行く。
.gif)
下関竹崎浦港
「もうすぐですけん、辛抱してください」
小藤四郎が、望東尼の背中をさすりながら励ました。慶応二年九月十七日の夜中である。船は長州藩士の泉三津蔵に導かれて、竹崎浦に着いた。丸一昼夜の船旅であった。着いた船着場は、白石正一郎邸の浜門(裏門)にも繋がっている。
白石正一郎とは、竹崎浦を拠点にする、荷受け問屋を営む豪商である。併せて、尊王攘夷派の志士たちに、金銭的援助など強力な後ろ盾にもなっている。三年前に結成された奇兵隊は、この白石邸から踏み出したのであった。結成を主導したのは高杉晋作である。
「ようおいでなさった。尼どののことは、高杉さんからも、よろしゅうやるように言われております。遠慮なさらず、まずはお身体をお労りください」
望東尼は、主人からの挨拶の間も、この場所にいるはずの人がいないことに気を揉んだ。平尾山荘で別れた高杉晋作のことである。
高杉は既にこの場所を離れていて、十日前に赤間町に建つ入江和作宅に居留していた。入江和作とは、下関界隈で酢の製造業を営む豪商のことである。
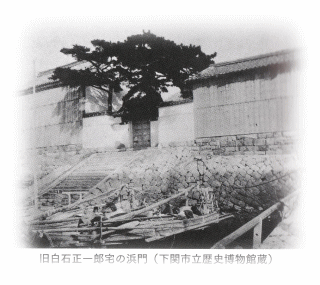
主人の白石正一郎は店の者に言いつけて、日頃客人が使う離れの間へ案内させた。白石邸の女たちは、総がかりで望東尼の入浴や着替えを手伝った。伸び放題になっていた頭髪を丁寧に剃ってくれた。風呂から上がり、用意されていた布団に横たわった途端、意識は遠い夢の世界に迷い込んでいく。
気がつけば、陽は真上に上がっていて、枕元には藤 四郎が座っていた。
「相当にお疲れでしたね」
望東尼が、二日間眠ったままであったことを、藤 四郎は告げた。
「ここはどこ?」
下関の白石邸に着いたことも、すっかり忘却の彼方に遠ざかっているようだ。代わりに、姫島での島民との語らいや、獄中に忍び込んでくるクモやアリなどとも、うまく付き合ってきたこと、また遠くに見える対岸の灯りや浮(うき)嶽(だけ)の威張り腐ったようにして居座っている姿などが、思い出の中の全面に躍り出てくる。
「ここは、竹崎浦(現下関市竹崎町)で荷受け問屋を商う小倉屋さんのお屋敷ですよ。このお屋敷には、高杉さんの口利きで泊めてくださったのです。ご主人さまは、ただ今遠方にお出かけだそうです」
白石邸は、この時代、商家には珍しい書院造りの建物であった。
高杉の療養
「して・・・、高杉さまの看護は、どなたがなさっているのかしら」
「今一緒におられるのは、おウノさんという、以前花街にいらしたお方です。齢は二十二歳だと聞いています。その内に、医者の石田精逸さまの勧めで、桜山付近の『東行(とうぎょう)庵(あん)』にお住まいを替わられるそうです。東行とは、高杉さんの別のお名前です。すべては、高杉さまの療養のためです」
そこまで問うたところで、望東尼の頭痛が激しくなって話は途切れた。獄中や長船旅での疲れで寝込むことになり、望東尼は高杉を訪ねる気力さえ失せていた。
下関に着いて一ヶ月が経った十月中旬、望東尼が滞在する白石邸に客が訪ねてきた。来訪者は小田村文助と名乗った。
「本日は、当藩藩主からの意向を伝えるために伺いました」
突然、「長州藩主」と言われても、返答のしようがない。
「藩主より、お尼どのに特別の配慮をなすようにとの命を受けました故」
藩主より配慮の命とは、「望東尼どのに応分の待遇を与えること」であった。地獄から天国へとはこういうことを指すのか。長州藩主の意図を完全に理解しきれないまま、ありがたくお受けすることにした。
小田村文助は、その直後に「楫取素彦(かとりもとひこ)」と改名している。楫取は後に、明治時代を代表する官僚となり、後世に名を残した人物である。特に群馬県政(知事)時代、富岡製糸場を見事に立ち直らせた実績は、後の世まで語り継がれている。
「長州藩として、尼どのから受けたご恩は、決して忘れてはならないことです」
小田村は、深々と頭を垂れた後去って行った。小田村が言う「受けたご恩」とは、平尾山荘に高杉晋作を匿ったことを指している。望東尼に対する長州藩からの「応分の待遇」は、「二人扶持」支給ということであり、生活の保障を約束するものであった。
託す言葉
下関上陸から一ヶ月が経った十月。望東尼はようやく疲れと頭痛から解放された。そこで思い切って、桜山近くの「東行庵」に高杉を訪ねることにした。平尾山荘で見送ってから、二年が経過している。もちろん、高杉に寄り添う愛人ウノとは初対面である。未だ娘盛りの面影を残す、色白で小柄な美人であった。
「お体の塩梅はいかがですか?」
これからの暮らしのことなどを話題にしながら、場がほぐれていった。高杉は、今後の暮らしについて話しだした。
「今住んでいる桜山には、僕の発案で昨年完成した招魂社があります。ここには、世を変えるために命を惜しまなかった、奇兵隊諸君の霊魂を祀っております。奇兵隊の働きがあってはじめて、長州は幕府の悪政を正すまでの力を持つことが出来たのですから。その陰には、福岡藩や対馬藩諸君の力添えがあったことを忘れてはいけないのです。小田村君(後に楫取素彦)にも、その点をくれぐれもと申し伝えております」
望東尼はその時、自分も高杉の看病に付く一翼を担うべきだと決心するのであった。
慶応三(1867)年。時代は、二七〇年続いた德川幕府が崩壊する年に突入する。春本番を迎えた二月、長州藩主毛利敬親から「二人扶持」が支給されることが正式に伝えられた。
去年今年(こぞことし)かなたこなたにまどひつつ徒(いたず)らにのみすぐす春かな
そうなると、筑前国から渡ってきて身の安全が保証される我が身が、もったいないような気持ちにもなる。
望東尼は、白石邸を離れて入江和作邸の離れに移った。これも、高杉が声をかけてくれたものであった。高杉もまた、街中の妙蓮寺そばに建つ林算九郎宅の離れに移り住むことになった。高杉晋作、人生最終の居住地である。
望東尼は、高杉を看護するために、林算九郎宅に泊まり込むことになった。それからの彼女は、ウノと二人がかりで、看病に明け暮れる毎日が続くことになる。望東尼の願いは、「もうこれ以上、わたしに寂しい思いをさせないで」と祈るばかりであった。
梅の便りも聞こえる時節になっている。縁側で目を閉じたまま思考を巡らせている高杉に、望東尼が声をかけた。
「何かよいことでもあったのですか」
高杉が手許に記したものを差し出した。
「今思っていることを歌にしました。わたしの句に、続きをお願いします」
これこそ、高杉晋作が「命の親様」と慕う望東尼に対する、生涯でたった一度きりの甘えであったのかも知れない。
面白きこともなき世におもしろく…
枯れ枝のように細くなった手で筆を執り、気持ちを表した上の句であった。「面白いことのないこの世にあって、面白く生きていくには、どうしたらよいものか。貴女ならどう考えますか」と、問うたのである。
すみなすものは心なりけり
周りの状況がどうあるかということではなく、あなたがどう思うかを考えるべきであると、望東尼は答えたのであった。下の句を記しながら望東尼は、心の中で、「貴方はこのような身体で、よくぞここまで頑張りました。新しい世づくりの最大の立役者、つまり『日本第一の人』は貴方ですよ」と讃えたのである。
高杉は、疲れで倒れそうになる身体を直してもらいながら、老尼の手を握り締めた。
望東尼とウノの切ない願いも叶わず、高杉の最期が迫った。高杉は、細い右手を差し出して、望東尼の手を呼び込んだ。
「望東さん、お願いだから・・・」、そこまで言って、握った手が畳に落ちた。追いかけて望東尼が握り返す。
「僕にはとうとう、新しい世を確かめることが出来なかった。命の親さまである貴女の目で見届けて欲しいのです」
後は、かすかに動く高杉の口もとをなぞりつつ、解釈するしかなかった。高杉は、己の力ではなしえなかった幕府に替わる新しい世を確かめることを託したのであった。

高杉と望東尼の連歌(防府天満宮)
高杉晋作は大勢の同志に見守られながら、静かに息を引き取った。二十九年という、いかにも短い人生であった。倒幕と大政奉還の夢が叶うまで、残すところあと半年を残す時である。そばで大泣きする同士や望東尼から離れて、別室に佇むウノは、一人忍び泣いていた。
奥つ城のもと
高杉は、愛する人や多くの同士に見守られて、黄泉の国へ旅立った。星空のもと、下関から小月を経て吉田村まで、六里に及ぶ野辺の送りである。参列者は三千人。全員が松明をかざしての行進であった。棺が墓所となる清水村の清水山山頂に到着したのは、夜も十時を過ぎていた。
行列の進む先々で、高杉の死を悼む人々が見送った。望東尼の脳裏では、高杉の死は、夫貞貫との永久の別れのときとも重なった。
後日、ウノ(出家して梅処尼)が書き残した文が残っている。
「高杉は自分にとって「命の親様」である望東尼殿のために、部屋をきれいにしつらえ、何の不足もないようにしました。私は当時二十二~二十三歳でしたが、既に六十歳を超えていた望東尼殿を母親のように慕い、貴女さまの指示に従って高杉を看病致しました。最期は三人で住んでいましたが、望東尼殿が風邪を引いて寝込んだときなど、三階に望東尼殿が、一階には高杉が寝ていました。私は、高杉と望東尼殿が寝込んだまま詩と歌のやりとりをするので、階段を昇ったり降りたりして、さすがに足が疲れました」と。

出家後のウノ(法名は梅居尼)
高杉の死後、望東尼は高杉夫人のマサに対して、次の歌を柩に入れてほしいと託した。
奥つ城(き)のもとに我が身はとどまれど別れて去(い)ぬる君をしぞ思う
だがマサ夫人は、預かった歌を柩には入れてくれなかった。夫人にも、他人には絶対に見せたくない意地のようなものが存在したのであろうか。
愛孫の訃報
高杉の死後、望東尼の心は虚ろなままで、時だけが過ぎていった。楫取素彦が手配してくれた手伝いの娘・トキとの世間話が、唯一の安らぎの時間にもなっていた。
「谷梅(高杉の別称)さんが逝って、もう十日だね。待っていなさるだろうね、わたしが行くのを。早く行かなきゃ」
うつろな目で庭を眺めながら呟いた。そばにいるトキが反応した。
「出かけましょうよ、お供しますから」
高杉が眠る吉田村(現下関市大字吉田)まで北へ六里、男の足でも五時間はかかる。下関を朝早く発って、長府の茶店で昼ご飯をいただいた。宿泊先は、吉田村の庄屋・野原清之助宅だと、楫取素彦から知らされている。庄屋の家に着く頃には、陽も完全に沈んでいた。
翌朝、庄屋に案内されて、「東行墓」と記された墓標に向き合った。「東行」は、高杉の別称である。
「やっとお会いできましたよ。貴方がいなくなって、本当に寂しゅうございます」
そばにいる庄屋にもトキにも悟られないように、十日ぶりの再会を告げた。事前の心配とは違って、不思議と涙は出てこなかった。墓標と敷地は、山県有朋が高杉の愛妾・ウノに贈ったものであると、後日聞かされた。
高杉の四十九日法要も過ぎた頃、楫取素彦がやってきた。彼は望東尼の今後の住処を、山口(現在の山口市)に移すよう促した。「そこなら、妻のヒサも十分にお世話が出来る」からとも言ってくれた。山口には、楫取素彦の屋敷があるし、萩往還(国道262号)を北へ十里進めば萩城も聳えている。
1.gif)
楫取素彦夫妻像(防府天満宮)
山口での落ち着き先は、湯田温泉郷にある由緒正しい吉田屋であった。身に余る厚遇だと、改めて高杉に感謝するのであった。
吉田屋に落ち着いて間もなく、今度は藩主毛利(もうり)敬(たか)親(ちか)の遣いだという侍が、正装で現れた。遣いは、藩主からだと述べて、一服の反物を差し出した。藩主からの下賜を授かるとは、想像すらしなかった栄誉であると感謝した。
湯田の郷を出て西へ一里も歩くと、ご当地名所の鼓の滝に行き着く。飛沫を跳ね上げながら落ちる水の様は、名の通り、鼓に合わせて踊る龍のごときであると。心行くまで自然を楽しみながら、この上ない贅沢な時を過ごすことが出来た。
望東尼が湯田温泉郷の吉田屋に落ち着いて間もなく、悲し過ぎる知らせが、藤 四郎からもたらされた。どんなに離れて暮らしていても、気持ちだけは常に身近な存在であった孫の助作の訃報である。
福岡城下に設けられている枡木屋の獄中で、帰らぬ人になったという。なんて言うことだ。夫野村貞貫に始まり、大志を抱いて日本国中を駆け巡った平野国臣、そして高杉晋作に次いで、可愛い助作まで・・・。指を折りながら数える助作の年齢、「二十四歳か、まだ大人になったばかりじゃないか」。
いずれも、自分より先に逝ってはいけない、掛け替えのない者ばかりである。取り残された我が身を、これから何処に連れて行けばよいものか。ため息をつく気力さえ失ってしまう。
「ハハウエ、長生きしましょうよ。そのお方たちが見ることができなかった輝かしい世界を、代わりに私たちが見届けようではないですか」
高杉の死後、ことあるごとに下関から通ってきてくれる藤 四郎。間もなく始まる幕府に替わる新しい世の中へと、誘う気持ちを吐き出しながら勇気づけた。時は確実に、藤 四郎が予告する場面に近づいていたのである。
浮き雲はまだ晴れやらぬ身なれども露の心は世には残さず
助作の辞世の句である。嫌疑が晴れないままの我が身ではあるが、少しも心をこの世には残すまい、と詠んでいる。追いかけるように、実姉の吉田タカも没したと、知らせが届いた。続けさまの身内の不幸を聞かされても、駆けつけることさえ出来ないこの身が恨めしい。
松陰の妹
慶応3年9月、大政奉還の大号令まであと三ヶ月。野村望東尼の年齢は六十二歳である。
坂本龍馬らの仲介もあって、薩摩藩と長州藩が手を結び、倒幕のための密議が熱を帯びていた。討議に加わったのは薩摩側が大久保利通や西郷隆盛であり、高杉亡き後の長州からは桂小五郎らであった。
討議では、倒幕のための出兵に関する合意が成立した。薩摩藩兵は、9月25日までに三田尻の港に到着し、長州軍と合流する。その後は東上して、幕府の主要人物が集まる大坂城に攻め入る算段である。長州藩のお隣安芸藩にも働きかけ、薩長芸の三藩連合軍の出兵という予定もできあがりつつあった。
長州軍の総大将は毛利親信(長州藩一門家老右田毛利家の当主)、参謀は楫取素彦、総指揮官は山田市之丞まで決っていた。
9月23日。望東尼は、倒幕戦争に向かう長州兵を激励するべく、吉田屋を出て山口の萩往還に出た。三田尻港に向かう軍兵らの出陣は、かつて平尾山荘に出入りしていた若い福岡藩士らの勇姿と重なる。もう少しこの身が若ければ…、自分が病弱でなければ…、それより何より、自分が男であったなら。「間違いなく勤王倒幕のための部隊に、この身を置いていたであろうに。そして幕府を打ち負かす役割の一翼を担っていたろうに」と、声を震わせながら、若者らを激励した。
湯田郷の吉田屋に戻った望東尼を、女の客が待っていた。楫取素彦夫人のヒサである。初対面である彼女、実は高杉晋作や桂小五郎などが学んだ松下村塾での教育者であった吉田松陰の実妹であった。
「早くお訪ねするようにと、主人から言われていたのですが…」
遠慮深そうに挨拶する姿は、いかにも楫取素彦の奥方に似つかわしく上品である。ヒサ夫人はすぐに話題を歌人である望東尼に移した。
「私も、三田尻におられる荒瀬百合子先生に習って、少しばかりですが…」和歌を勉強中であるとも、自己を紹介した。
「荒瀬先生も、先生にお会いしたいとおっしゃっていました」
三田尻は、長州軍が薩摩軍と合流する予定の港町である。望東尼も、出来ることなら三田尻まで出かけて行って、もう一度若い兵士らを激励したいと思っている。三田尻では、防府の天満宮に額づいて、彼らの戦勝を祈願するつもりだった。心を込めて詠んだ和歌を、信仰する天神さま(菅原道真)に捧げて祈願したかったのである。
「きっと、荒瀬先生も喜ばれますわ。早速使いを出して、その旨伝えておきます」
近々再会することを約束して、ヒサは吉田屋を後にした。
9月25日早朝。望東尼は、藤 四郎にも連絡せずに萩往還に向かった。藤 四郎に言えば、「ご自身の歳をいくつだとお思いか」、「病み上がりだということをお忘れか」ときつく叱られるに違いない。自身、年齢や病弱のことを気にしていないわけではない。それよりも、杖一本を頼りの一人旅では、心細くないわけがない。それでも、湯田郷で倒幕の吉報を待つだけでは、その方が耐えがたかった。
「もしも私が若かったら…、男だったら…」の気持ちがそうさせるのである。(第9部に続く)
|

