
|
ダシール・ハメット 『マルタの鷹』
文中にあるハメットの人生観が凝縮されるこの一節は見逃せない。
2005/05/29
「少しも古さを感じさせないハードボイルドの古典」と賞賛するのにはそれだけの理由がある。
数年前まで『マルタの鷹』を『鷲は舞い降りた』や『ナバロンの要塞』のような戦争冒険小説と思っていた程度に本格ハードボイルドには疎いものだったが、昨年暮れからの原尞復活の余韻が後を引いていて、チャンドラーの『長いお別れ』を読み、そしてこの「ハードボイルドの創始者」と言われる1929年の「古典」を読む気になった。
ダシール・ハメット。実際に7年間探偵社で仕事をした経験がある本物の私立探偵。軍隊入隊、結核による療養、物書きとしての貧窮の生活、筆を取れない長いスランプ、反政府運動、服役を含む赤狩りの犠牲者、非国民扱いと彼は亡くなるまで四面楚歌のマイナーな作家であった。彼の作品が日の目を見たのは亡くなった後であったという。
見わたせばハメットは「ハードボイルドの創始者」としてだけではなく、「私立探偵小説の始祖」とか「純アメリカ産文学の巨匠」とまで神格化されている作家だとわかった。もはやなにももの申すことはないほど「ハメット論」、「マルタの鷹・論」は出尽くしているようだ。あとがきにある小鷹信光氏の「解説」は熱狂的ファンとしての心情と評論家・訳者としての見識があってちょっとした読み物になっている。
マルタの鷹。エルサレムの聖ヨハネ・ホスピタル騎士団=ロードス騎士団がスペイン王カルロス五世からマルタ島を下賜された見返りに贈呈した黄金の彫像。この秘宝の争奪戦に巻き込まれる私立探偵サム・スペード。最近はやりの「ダ・ヴィンチ・コード」の向こうを張ったかのようなプロット。「すこしも古くささを感じさせない」という常套句がぴったりとあてはまる。当時は相当過激な表現であったかもしれないが適度な濡れ場と適度な暴力は今読んでも適度な刺激で読者を楽しませてくれます。
|
サム・スペード。理不尽な権威に超然とした実行力と強靭な精神力で自分を貫く矜持。誇りをかけるところに伴う反倫理的行動、斜に構えた人間観察と歯に衣を着せぬ物言いなど、われわれがやりたくても踏み込めない人物像がそこにある。
ただこれは本格ハードボイルド主人公に共通する魅力なのだが、サム・スペードは加えて実に興味深いキャラクターをのぞかせるのだ。
それは、スペードが相手役の女に語る、ある長いエピソードに見いだされる。
事業に成功し資産も蓄え、妻と二人の子供と平穏なアメリカンライフをおくっていた男が突然蓄財を家族に残したまま、無一文で蒸発する。悪事に関わりなく、仕事の問題もなく、女もいない。そして5年がすぎる。不可解のままに過ごした夫人が別の町に男を見かける。そして帰宅を願う夫人の依頼を受けたスペードは男にこの間の事情を尋ねる。
その日、道を歩いていたときに落下物があって危うく一命を落とすところであった。
その瞬間、男は人生のなんたるかを悟った。
「よき市民であり、よき父であり、よき夫であるような男だった。それまで知っていた人生とは、きちんと秩序の保たれた、まっとうで、理に適ったものだった。ところが天から降ってきた一本の鉄梁が、人生は根源的にそんなもんじゃないということを垣間見させてしまったのだ。」
男は真の人生とは破滅と隣り合わせにあることに気づいて愕然とした。
「垣間見てしまったこの新しい人生のほんとうのすがたに自分自身を適応させる以外に、二度と心の安らぎは得られないだろと悟ってしまったのだそうだ」
そして明日の見えない流浪の旅に出た。
おもしろいなぁ、仏にならんとする菩薩の道か、1929年のアメリカのマイナーな作家がねぇ。これはまるで東洋的な発想ではないですか。
アメリカの高僧にでもなったのかと思いきや、なんてことはない。
この男は数年を経て、二人目の女房と子をなしてふたたび秩序ある世界で幸せに暮らしているのだ。
「やっこさん捨ててきた同じ生活の溝にはまりこんでしまったことにさえ気づいていなかったようだ。やっこさんは天から降ってくる鉄梁のたぐいに備えていたが、それ以上降りかからなくなると、こんどは降りかかってこないほうの人生にわが身を適応させたんだ」
スペードはつぶやく
「だが、そこんところが、おれはいつも気に入っている」
「おれはいつも気に入っている」!!!???
「小市民的調和などクソくらえ」
とこの男を張り倒すのがハードボイルドの常道だと思うのだが………。
このエピソードはストーリーとは無関係なのだ。
脈絡なくヒョッコリと挿入されている。
異物がいったん引っかかって、すぐスッと胃の中に納まった。だが緊張と安堵がないまぜになってその感覚が喉元に残っている。そんな味わいのある一節だった。
これはスペードのせりふではない。ハメットの苦悩に満ちた生活実感からでた本音だろう。
日本のことだが、十年前までは多くの人は、明日という日は今日の延長にあるものとしてそれを疑うことはなかった。ところがある日突然、たとえば勤めていた会社がなくなっていた。そして底なしの深淵をのぞくハメになったものだ。
その実感はまだなまなましいものとして残っているだけに、このエピソードにある人物の生き方について、ふがいないとか、無様だとかで一笑に付すことはできやしない。
時代に逆らうことにともなうある種のカッコよさ、時代に逆らったことによる手ひどい代償、そして何とかして生きていかねばならない現実とすべてを経験したハメットがつぶやく「気に入っている」との一言にはこの作品の「古さを感じさせない」ところの本質があるような気がした。
そしてわたしは70数年の時をこえてハメットを身近に感じたのである。
たまたま、宮部みゆき『日暮らし』を読んだ直後だから蛇足は承知であえて、日常の平凡な生活をかけがえのないものとする表現方法のへだたりは月とすっぽんほどある。 |
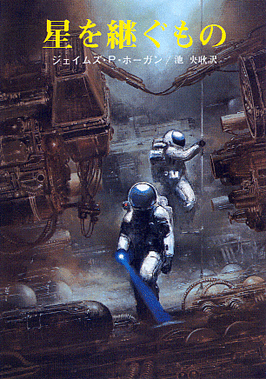
|
ジェイムズ・P・ホーガン 『星を継ぐもの』
ハードSFの代表作とされるこの作品の「古臭さを感じない」ところ
2005/06/08 |
月面調査員が真紅の宇宙服をまとった死体を発見した。綿密な調査の結果、この死体は何と死後五万年を経過していることがわかった。やがて木星の衛星ガニメデで地球のものではない宇宙船の残骸が発見された。関連は? この一作をもって現代ハードSFの巨星となったホーガンの傑作長編。
本格SFを手に取るのは久しぶりです。まだ空想科学小説と呼ばれていた頃から大好きだったから、ヴェルヌやウェルズやドイルに夢中になった少年時代に始まり、E・E・スミス、アイザック・アシモフを読んでいた頃から、小松左京、光瀬龍あたりまでだったでしょう。その時々でSFの楽しく感じたところは違っていたのかもしれません。それをSFと呼んでいいならこれまでの傑作の一番は小松左京の「日本沈没」であったなぁと思うのです。その程度ですから「ハードSF]とはどんなものかしらと興味を持っていました。
この死体はなにものかと地球規模のプロジェクトが組織される。遺留品は数少ない。あらゆる先端学問が動員され分析が始まる。放射性炭素年代測定法、原始生物学、宇宙創生論、地球物理学、進化論、記号解読学などなど。数々の仮説を検証し、彼が地球にたどりつく経緯を明らかにしていく。
ストーリーは単純でその分析プロセスを丹念に描くだけの小説だった。
ここまで科学理論を徹底したSFにはお目にかかったことがない。ミステリーで言えば非現実で、ためにする状況をしつらえ、そこでおこる事件を論理一筋で解明するパズル型の謎解き作法に近い。この場合「論理一筋」による読ませる説得性が作品の評価を左右する。
ハードSFの代表作といわれる作品だ。ここで取り上げられている「現代科学理論の粋」は私のようなシロウトにはチンプンカンプンで本物なのかどうかは判断しようがないのだが、読んでいるといかにもそれらしく引き込まれてしまった。
地球人が木星の衛星にたどり着く頃の未来を想定しているから、これも現実的未来であって、登場する宇宙船、装備、機器類、科学技術にも今の水準と途方もなくかけ離れた感じがしないのも「本物らしさ」を高めている。
書かれたのが1977年だから「古くささを全く感じさせない」との評価はまったくそのとおりだった。
宇宙戦争のバトルシーンも巧みに織り込まれ、宇宙規模の大どんでん返しもあって、懐かしい空想科学小説のなごりと気の利いたラストは楽しく読めるところでもある。
ただ、そのアイデアと技巧など名人の手際のよさには感心するものの、結局こしらえものにすぎないと、今更このジャンルにのめり込める歳ではなくなった自分の老化がすこしさみしい。
古臭さを感じさせないとのことに関連することだが、
この小説の世界では核兵器の寡占によって地球規模の平和と繁栄が謳歌されている。「恐怖の均衡」、今でも立派に通用するところがあります。
又終章では生物学者が高らかに宣言する。
われわれ人類は今、押しも押されぬ太陽系の支配者として、5万年前のルナリアンと同じように恒星間空間のとばくちに立っている。というわけで、諸君、恒星宇宙はわれわれが祖先から受け継ぐべき遺産なのだ。ならば行ってわれわれの正当な遺産を要求しようではないか。われわれの伝統には、敗北の概念はない。今日は恒星を、明日は銀河系外星雲を。宇宙のいかなる力も、われわれを止めることができないのだ
1977年、ベトナム戦争後の米国人にあった幻滅を消し去ろうとした新大統領カーターの胸の内を見るようであった。がこれもブッシュにも当てはまるというものだ。
|

|
A・J・クィネル 『トレイル・オブ・ティアズ』
冒険小説の第一人者 A・J・クィネル氏がなくなられました。つつしんで哀悼の意を表します。
2005/07/20 |
本日の日経紙、死亡記事にこうありました。
英国の冒険小説作家。マルタ観光局日本地区代表事務所に19日までに入った連絡によると10日、肺がんのためマルタ・ゴゾ島で死去、65歳
英バーミンガム近郊の町に生まれ、1980年代に「燃える男」で作家デビュー。ほかに「スナップショット」『サンカルロの対決」などの作品がある。「燃える男」は2004年の映画「マイ・ボディガード」の原作となった。(共同通信)
日経紙の死亡記事に外国のミステリー作家が取り上げられることはあまりないのではないか。この記事からもご本人が日本に関心の深かった方だったことがうかがわれます。
クィネルといいますと一般には次のように紹介されていまして謎めいた作者でした。
(クィネル〉1940年アフリカのローデシア生まれ。国籍不明の匿名作家として1980年に「燃える男」でデビュー。他の著書に「ブラック・ホーン」「地獄からのメッセージ」など。
マルタ島を根城にする元傭兵のクリーシーが活躍するシリーズはおそらくこれだけでしょうがすべて読みました。いずれも冒険小説としては傑作でした。
『燃える男』『パーフェクトキル』『ブルーリング』『ブラックホール』『地獄からのメッセージ』
これはこの順序で読まれるとよろしい。
彼の日本に紹介された最も新しい作品は『トレイル・オブ・ティアズ』だと思います。2000年の作品ですからその後は発表がなかったのでしょう。
2000年8月1日のなぐり書きを再紹介します。
クィネルの作品は元傭兵のクリーシーが主人公で活躍する「クリーシーシリーズ」ものと『メッカを撃て』『スナップショット』のように独立した物語とに分けられるのだが、いずれも、とてつもない巨大勢力を持つ悪玉との対決、攻略の面白さが醍醐味だ。
新作の『トレイル・オブ・ティアズ』は独立系であるが、期待通り、連日の暑さのなかで消夏用として清涼効果満点の作品である。荒唐無稽といえばその通り、いつものパターンといえば否定するつもりもないのだが、勧善懲悪のわかりやすい対決構図はボーっとさせられる熱気のなかで読むに、ふさわしい。
クィネルの作品は昔の東映やくざ映画……「仁義なき闘い」以前の「任侠もの」、健さんが活躍したあの様式美……ここにある日本人的共感性と同じような味わいがあるんですね。
あたりはずれなくどの作品も傑作と言っていい質の高い冒険小説で、なぜかなと考えるに、大長編がないんですね。上・下刊とある大ボリュウムのどちらかというと水増しされた冒険小説にあたってがっかりすることがあります。密度が高い、スピード感を満喫する、このためには長すぎるのは難しいかもしれません。
参考 『トレイル・オブ・ティアズ』
拉致された世界的な脳外科医はどこへ、そして何のために? 巨大国家アメリカの深部で暗躍する国立人間資源研究所の極秘プロジェクトとは? 現実にあった事件を題材に、クローン技術悪用をテーマとするハード・アクション。
|