
|
大鐘稔彦 『孤高のメス 外科医当麻鉄彦』
文庫本全六巻。友人に紹介されて読んだものだ。作者はまったく知らない人だった。
大鐘稔彦。
1943年愛知県生まれ。京都大学医学部卒業。早くより癌の告知問題に取り組み、「癌患者のゆりかごから墓場まで」をモットーにホスピスを備えた病院を創設、手術の公開など先駆的医療を行う。「エホバの証人」の無輸血手術をはじめ手がけた手術は約6000件。現在は淡路島の診療所で僻地医療に従事する。小説やエッセイなどの著書多数。
2007/05/31
|
帯封にある二村雄次・名古屋大学大学院医学系研究科外科教授の推薦の辞によれば
日進月歩で医療が高度化していくなかで、もっとも大切な「患者のためになる医療とは何か」を、現役の医師である著者が自らの分身である主人公(当麻鉄彦)を通して世間に問いかけている。この本が多くの読者に理解され、多くの患者さんが、公正な医療を受けられるようになることを望んでやまない。
そして幻冬舎のコピーは
ここにもうひとつの白い巨塔がある。彼は神ではない。しかし磨き上げたメスが奇蹟をも起こす。臓器移植という最先端医療をめぐり、壮絶な人間ドラマが繰り広げられる。
さすがに本職の外科医が著した小説だけにいくつもの手術シーンには迫力があって血みどろになって病んだ内臓と格闘するメスさばきの冴えは門外漢のわたしにだって伝わってくる。他の医師には見放されたものの命を救う、まるで神の手をもつヒーローである。保身と出世欲だけで、彼の腕に嫉妬する大学のおえら方が彼の前に立ちはだかる。しかし、医療技術は旧態然とした医学界の掟を覆して進まねばならないのだ。著者の最先端医療へのチャレンジ精神が熱く語られる。山崎豊子『白い巨塔』、手塚治虫『ブラックジャック』の向こうを張ったらしく、正義の外科医がさまざまな妨害と戦いつつ日本で始めて生体肝移植に成功するストーリーだった。
ただし、小説としてははなはだ面白くない。彼を敵視する人たち、あるいは彼を慕う女性たちをはじめ登場人物がすべて類型的であった。さらに最大の欠点は臓器移植の問題点の指摘がまったく欠落していることにある。臓器移植が成功するか否か、つまり安全性だけが問題となった当時に著者の視点がとどまってしまったようだ。
日本国内でドナーが少ないから臓器を求めてフィリピンへ渡る移植患者が増えているという。そしてドナーの多くは「謝礼」目的とする貧困層だ。臓器を買う人、売る人、仲介して稼ぐ人。臓器移植のこうした現実は是認できない。また臓器移植に限らず生殖医療、クローン技術の医学への応用、延命医療など生命を人間が扱うことに伴う倫理上の問題も重たいものがある。宗教とは縁のないものだがそう思う。
こうした視点を持たないただ熱情だけで突っ走る主人公は一体なんなのだろうと疑問に思った。ところがこの作品はもともと漫画雑誌に連載されていた劇画を小説にしたものと著者あとがきに書いてあった。幻冬舎の出版物にはときどきくわせものがあるがこの作品もその類だな。
帚木蓬生の作品『エンブリオ』、かなりグロテスクで、医学犯罪小説といってもよいが極論にある真実をついていた。
|
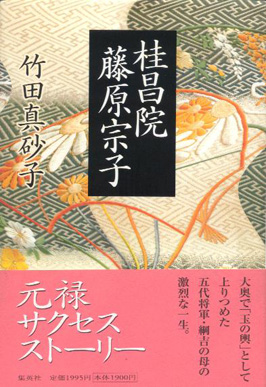
|
竹田真砂子 『桂昌院藤原宗子』
桂昌院 1627‐1705(寛永4‐宝永2)
3代将軍徳川家光の側室、5代将軍綱吉の生母。関白二条光平家司本庄宗利の養女。名は宗子。秋野、お玉の方と称す。家光側室六条有純の娘お梅の方の縁で江戸へ下り、家光の寵をうけて綱吉を生む。1680年(延宝8)綱吉が将軍となって後、江戸城三丸に住み、三丸殿と称された。綱吉の厚い孝敬をうけ、1702年(元禄15)従一位に昇り、また弟本庄宗資をはじめその一族中幕臣として栄進する者も多かった。深く仏教に帰依し、僧亮賢、隆光等を信頼し、そこから生類憐みの令を極端に助長するなどの弊害が生じたといわれている。 嶋 達也
平凡社世界大百科事典より。
2007/06/19 |
「三つ子の魂百まで」とはよく言ったものである。お玉、「玉の輿」の語源とも言われる人物。八百屋の娘であるといわれるが実の父は定職を持たない流れ者風情の舎人であった。生まれながらの性分、幼児期に備わった体質をそのまま過激に押し通して5代将軍の母・桂昌院にまで上り詰める。自立した個性を求める現代人に置き換えたとしても尋常な個性ではない。つむじ曲がり、ひがみっぽい、負けん気が強い、他人を見下す、敵愾心のかたまり、見栄っ張り、あまのじゃく、恩知らず、嫉妬深く猜疑心が強い、ひどくヒステリックなエゴイスト。と、人間としては負の性情で固まった人格だといえよう。大奥入りしてからも変わらない。この負の性情を生きるためのエネルギーとした女である。規範、人倫という言葉にはおよそ縁のない成り上がり者である。いつまでたっても品格は備わらない、知性は見えない。大奥に君臨したとはいえ春日局のように幕政を掌握するだけの才覚はない。ただし、並以上の美貌に自信をもち、男を喜ばせるテクニックには長けている。そして桁はずれた強運の持ち主である。段取りを踏む上昇志向というよりはその場その場での上昇願望を一生貫き通しえた女性である。全編を通じこの凄まじい個性の生き様に圧倒される。実に嫌味の権化といえる人格なのだが、しかしよくもここまでやったものだと拍手を送りたくなるのが本作品の醍醐味であろう。
三つ子の魂はお玉だけではない。主人公の周囲の人たち、母のおくる、姉のこん、そして六条家の姫・瓏子もまたそれであり、これら際立った個性の競演を大いに楽しむことになる。
特に瓏子の存在感は大きい。貧乏公家の娘、幼い頃からのお玉の主人、男色の家光にあてがうべく春日局に見出された隠し球、家光の側室、大奥の取締役梅の局。お玉とは対極にある個性である。美人とはいえないが公家の姫として作法、教養、常識 文芸をそなえ、俗人とは別世界にある貴種である。感情を表に出さずあらゆる境遇をおっとりとして受け入れる女性である。瓏子はお玉のすべてを飲み込む。お玉は瓏子のすべてに歯向かう。瓏子とお玉のもつれ合いは愛憎混沌とした思いの発露なのであろう。お玉がついに気づかなかった瓏子の慈愛、瓏子の本性としてのしたたかさ、そして瓏子に対するお玉の屈折した感情表現に著者の筆の冴えが見える。
他人ばかりか身内までも敵視したお玉である。一方誰からも信頼されることはなかった。感情のおもむくままにわがままのし放題で最高の地位に就いた女性である。挫折の経験もせずに生涯を終えた。こんなにもはなもちならないサクセスストーリーは読んだことがなかった。にもかかわらず主人公に親近感を覚えるのだ。それはお玉が孤独という絶対的寂寥感を犠牲にして立っているからではないだろうか。幼児期の濃密な描写に比べ綱吉が将軍に即位したのちは著者自身が感情を抑制し事実の記述のような文体に変化する。その行間には、ある意味で気の毒な一生だったんだなと感じられるところが多かった。瓏子が去り、母は狂い、こんはお玉を拒絶した。どうしようもない寂しさに彼女は覆われていたにちがいない。そして寂しさを自覚できない個性に、滑稽と同居している哀れさを感じた。
|

|
京極夏彦 『前巷説百物語』
「これが百物語のはじまりでございます」
「今、明かされる真実 又市、いかに御行となりしか」
と既刊・巷説百物語シリーズで活躍した小股潜りの又市が御行となるまでその前歴をなぞっている。『巷説百物語』『続巷説百物語』『後巷説百物語』を読んだ読者であるなら勢いで手にしたくなる一冊だろう。
2007/06/26
|
妖怪変化なんてもんは事実としては存在しないのかもしれない。だが人間の心のもちようでは見える場合もあるだろうとこれは心理学的解釈。また怪異現象が起こったと巷間信じられている背後にはそれだけの真実が存在するものなのだ。これは民俗学的解釈でしょう。本著に登場する本草学者が語る。
「在る筈のないもの――天地の摂理に反したるものというのは、これは大抵ない。というかないんですよ。ただねあって欲しいもの、在るべきだと考えられるもの、というのはね、これはないのに在るんですな。」
この妖怪観が一貫しているところでシリーズが上質に仕上がっていた。
『巷説百物語』では「小豆洗い」「白蔵主」「舞首」「芝右衛門狸」「塩の長司」「柳女」「帷子辻」いずれも当時全国的に言い伝えられている妖怪変化が登場した。おそらく当時の一般庶民の多くはその存在を信じていたのだろう。妖怪、化け物どもは怪異現象をみせて人間世界に人殺し、人攫いなどの悪さをする。そのとき、小股潜りの又一を頭にいただく、愛すべき小悪党があらわれ、この怪異は民間伝承を騙った人間がたくらんだ悪質な犯罪と喝破し、こちらも妖怪変化を仕立てる罠をもって極悪人を懲らしめるという痛快なお話のかずかずだった。江戸時代の庶民の生活にある恐怖感がそのまま表現されているところで、このシリーズの面白さの原点だといえる。
直木賞を受賞した『後巷説百物語』では明治維新、文明開化の座標軸で40年前の又市たちが仕掛けた「天火」「山男」「赤えいの魚」「手負蛇」「五位の光」「風の神」などの事件を回顧する趣向だった。語り手である老人・百介の周囲の若者は文明開花の申し子であり端から怪異現象を信用してない。百介だってそれは承知だがあまりにも合理的・論理的な思考が幅を利かせるようになった世の中を疎んじるところがあって、彼は妖怪たちの横行していたあいまいな昔の日本の風土を懐かしむように語るのである。そこは寒々しくなった現代の効率社会を生きる私たちが共鳴するところでもあった。
前三作はいずれの妖怪たちも存在感をもって個性的働きをしていた。ところがこの『前巷説百物語』では「寝肥」「周防大蟆」「二口女」「かみなり」「山地乳」「旧鼠」と妖怪が登場するにはするがいきいきとした妖怪ではないのが残念だった。又市が仲間に加わる「損料屋」、今で言うリース業者であるが、その裏は銭をいただいて晴らせぬうらみごとを晴らしてやるいわば仕掛け人稼業だった。その仕掛けとして大道具小道具の工作物で怪異現象の効果を狙う手の内が端から明らかにされている。その作りものも効果も大変不自然である。物語とはしっくり調和しないのだ。作者が無理をして妖怪話をこじつけたとしか言いようがない。だから読者には肝心の「在るかもしれぬ、ないかもしれぬ」のあいまい世界が映し出す怪異性が伝わってこない。怪談話の遊戯である「百物語」の本来の味わいはかけらもなくなってしまった。
池波正太郎が原案になるテレビドラマ必殺シリーズ、あるいは鬼平犯科帳シリーズのどこかにあった、殺し屋同士の暗闘に近い組み立てで、そう割り切れば読めないことはないだろうが、それならストーリーの緻密さ、活劇の迫力では池波正太郎に分があるというもの。
化け物や怨霊、幽霊や生霊などよりはるかに怖い存在は人間であるってことなんだろうが今ひとつ感心できなかった。
|