
 |
|
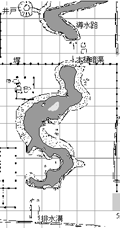 |
第二章 曲水の宴
満天の星明かりに浮かび上がる広大な藤原屋敷の庭内には人影こそ途絶えているが、そよかぜの奏でる木々の葉ずれや池に住まいする生き物の水音には春の宵の浮き立つ生命の息吹が満ちて、日暮れまで催された宴のなごりであろう脂粉の余香が生け垣までただよい、寝所の睦言までが洩れ聞こえるようで、いつにないなまめかしさにつつまれている。長さ30間、最大幅3間の細長く屈曲した池には純白の玉石が敷きつめられ、夜目にも光輝をはなち、周囲の巨大な石組みは池中の島と調和して荒磯の様を思わせ、その間に配置されたツツジの蕾も今、膨らみつつある。都を囲む山々のめぐみと言うべき清流を邸内ひきこむ水路にも玉石が敷かれ、池の畔の幾重にも湾曲したあたりではせせらぎの音がちろちろと絶え間ない。
中国では,陰暦3月上巳の日に禊(みそぎ)をし,穢れをはらい水に流す習俗があった。のちには流れに臨んで宴を開き,杯を浮かべ,その杯が自分の前を流れすぎないうちに詩を作り,詩ができなければ罰杯を飲まされるという遊びに発展した。これを曲水の宴とよぶ。藤原館でもこの遊びが3月3日の恒例行事となっていた。公卿方の二十人あまり、名だたる歌詠みたちが老若男女を問わず、水辺に集い、杯を流れに浮かべて即興の歌を披露しあうのであるが、これをはやしたてるだけの公達、姫君の数ははるかに多く、華やかに装い、流行の髪型、化粧も念入りに、あでやかな笑顔と人目を惹く仕草、気のきいた会話で妍を競うのだった。陽が西の山際にさしかかる頃には、歌詠みたちも酒がまわると、風雅にはほど遠い卑猥な俗歌に哄笑の渦が巻き起こる始末である。水路に落ちて嬌声をあげる女に手をさしのべれば腕をひかれて共に水に濡れ、そのままに耳元で口説きごとをささやく男がでれば、待ちかねたかのように戯れあう幾組かがあちこちに見え隠れする。これら痴態の長引く影もやがては宵闇にとけて、あとには喧噪の余韻のみが残る静寂が訪れる。 振舞酒に酔いしれたのであろうかいつもは規律どおりに怠りない護衛のものも今宵の巡回は目こぼしのようであってそんな屋敷に赤蟲が忍び込むのは造作ない。人一倍大柄な赤蟲の影がのそりと池の表にゆれればおびえて跳ねるのは鯉ぐらいのものか。剛毛におおわれた分厚い胸板は心臓の鼓動でふるえ、酒臭い鼻息も荒げて、先の宴席でしめしあわせた女の待つ飼い葉小屋へと急ぐさまは発情した種付け馬さながらにどこか滑稽であった。 勢い余って小屋の引き戸が大きな音を立てる。静になさいませと涼やかな声に、それよそれよその通りと剽軽に相づちを打てば引き戸の右手からさながら雪のように白い指が袖にからみ暗闇に引き込まれる。 |
|
「長きことお会いできませなんだ、赤蟲様…」国の有様をご覧になるとて、白雲の立つ山の木々が露霜によって色づく頃、その山を越えて遠い旅を行くあなたをみおくるわれに、春になったら、桜の花が咲くときには 空飛ぶ鳥のように早く帰えるとの優しい言葉を信じて今日まで胸を焦がしておりました。もう桜の花は散ってしまったではありませんか………と恨み声にて涙ぐむ。
小屋の暗がりは干し草がむれて早春の冷気をさえぎり、寄り添う二人の影は熱を帯びておぼろに揺らめいている。飾り紐が解かれ、蝶型に結い上げた黒髪が腰あたりまではらりと落ちる。その香気が赤蟲の体臭と混じりあって、二人は突き上げてくるものをもはや抑えきれない。山藍で摺り染めた衣の帯を解く手ももどかしく、どちらからともなく、どうと重なり合えば草いきれが小屋中に満ちた。 繭の白さにかがやく女人の胸元をわけながら「わしとても同じ気持ち。そちとふたりでこのように肌合わせる夢をみて幾夜すごしたことやらのう。三日の道を二日とかけずただひたすらに………」桜散るとも、龍田道の岡辺の道に、紅の躑躅が映える時には必ずと神明に誓い、いそぎにいそいではせきたれば、二つの丘の躑躅は桃の色に染まっているがまだこのように堅いではないかと蕾に触れる。身をくねらせるそのぬくもりを掌に確かめながら、紅の裳裾の長く引いたのをたぐれば曲水の瀬にひたった様で、「おや、こんなに濡れていますよ」と耳元に口を寄せる。 「赤蟲様とどのようにあしびきの長き夜を過ごしたらと思うばかりで、どうしたのでしょうこのように濡れたままなのですよ」とからだを開いて 「もうなりませぬ、なりませぬ………」と赤蟲の肢体を引き寄せるのであった。 赤銅のからだをおこした座臥にほんのりと染まった雪肌をのせれば星明かりに映えて紅の裳はあたかも大輪の紅蓮のひろがるがごとくに、そこにおわすは一組の歓喜天か。高く低く浮遊しすれば、はく息が白く乱れてゆれのぼり、かそけき衣擦れと枯れ草の葉ずれに太く細くと声が相和し、妙なる天上の音曲もさぞやと夜陰の庭園に、さらにはひょうひょうと吹かれる松の梢にまでしみいる風情があった。 飼い葉小屋の引き戸がおおきく音を立てた時分から星空を眺めて泉水の渕にたたずんでいた人影が「痴れものめが」と舌打ちした。女の声であった。とげはなくむしろ子供のやんちゃにあきれかえる響には人物の風格がにじんでいた 「怪しいものが庭先より忍び込み、遠国の豪族より預かりの大切な娘を手込めにしている大事にこのていたらくはなにごと」と柳眉を逆立て、酔いしれた衛兵をたたき起こした。 「いささか問いただしたいことがあるゆえ縄目にしてわれの寝所へひったててまいれ」と吐き捨てるように命じた女人はこの館の主、不比等の正室、娼子である。 部屋の四方を煌々と照らし出す燈火のまばゆさとしたたかに殴打された後頭部の痛みに、まだ生きているわいと気づいた赤蟲が床に手をついてあたりをうかがう。手首を縛られていたのかの縄で擦られたあとがひりひりと赤く腫れ上がっている。不始末をとがめられた衛兵たちが周章狼狽したあげくの仕打ちはよほど酷かったのであろう。 「目が覚めたか、高橋虫麻呂!」 めったに呼ばれたことのない本名で叱咤された。 凛乎として睥睨する女人の影に娼子の姿を認め、この無頼の男も居ずまいを正した。 「これはこれは奥の室様にはご機嫌うるわしゅうぞんじあげます。高橋虫麻呂、西国にてのご用をつとめ、ただいま参上いたしてございます」 とぼけて低頭したがなにしろばつが悪い。しかも悪友の宇合が逃げ回っていた口やかましい母御である。相手が悪い。 赤蟲は「西国巡回の記はあらためまして大臣(おとど)に上程いたします」と早々に立ち去ろうと膝を立てた。 「なにやら心地よう夢にたわむれておったようだが」 とくだけた口調で呼び止めた娼子は笑みを浮かべている。 「たとえ鄙のおなごとのまぐあいであってもこの館ではほどよいゆかしさがあっていいものを、野卑な声など張り上げて。歌人蟲麻呂の名が泣こうぞ」とおかしさをこらえきれず口に手を当てて笑っていた。今宵不比等は側室と閨を共にしている。そのはねかえりでもないだろうが、娼子はこのように浮き立つ素顔をだれにも見せたことはなかった。 かねて娼子はこの下級貴族であり異色の詩人である虫麻呂にひとかたならぬ関心を持っているのだが、この男の実像についてなにも知るところはなかった。この屋敷に嫁いでくるまえから食客のように出入りし、無頼の輩然とした風体でいながら不比等の寵愛は厚い。不比等の命なのか判然としないままに各地を旅しているようである。どこへなんのために流浪しているのか。年の頃が同じ宇合と二人で幼い頃から野山に遊ぶ仲であったとは聞いているがその素性を誰に尋ねても答えがない。いや不比等以外に誰も知らないのだと娼子は確信している。 知っていることといったら館で顔を合わせるときにいつもむさいなりをして酒臭い息をしていること、無類の好色漢で特に長い髪の女人には目がなく、必ずその一つかみを切って譲り受ける奇妙な癖があることぐらいか。宴の席では杯が流れてしまって満足に歌を作れないぐらいだから歌人としての才能も人並み以下ではないのかしらと首を傾げて、しかし、憎めない男よと仏のようにやさしいまなざしの髭面をのぞいた。 「蟲麻呂、そなたに折り入って頼み事があるのだが聞いてくれぬか」 高橋虫麻呂については平凡社「世界大百科事典」に次のように記述されている。 万葉歌人。生没年不詳。作歌活動の時期については,養老年間(717‐724)から天平4年(732)へかけてとする説と,天平4年以降とする説とがあって未詳。長歌14首,短歌19首,旋頭歌1首。作者に異説ある長・短歌各1首。権勢家藤原宇合(うまかい)の知遇を得たらしい。旅にある歌がほとんどで,その間地方の自然や伝説,民俗行事に触れて秀作をあまた成し,《高橋虫麻呂歌集》(逸書)を編んだ。よく〈旅の歌人〉〈伝説歌人〉などと呼ばれるがその本質は繊細な孤愁をにじませ,あこがれ出る心を歌い上げる浪漫的作者として異色の万葉歌人である。叙述にあたっては,名詞と動詞をたたみかけるように用いて事物の動きや事態の進展を活写し,華麗な饒舌ともいうべきスタイルを成す。〈……立ち走り叫び袖振り こいまろび足ずりしつつ たちまちに心消失(けう)せぬ 若かりし肌も皺みぬ 黒かりし髪も白けぬ ゆなゆなは息さへ絶えて 後遂に命死にける 水江の浦の島子が 家所(いえどころ)見ゆ〉(《万葉集》巻九の〈水江浦島子(みずのえのうらのしまこ)を詠む歌〉)。 つづく |
|
|
|