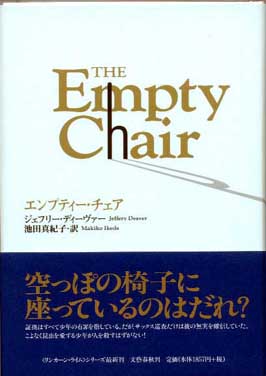
|
ジェフリー・ディーヴァー 「エンプティ・チェア]
リンカーン・ライムシリーズ最新作のできばえは?
2001/11/3
|
四股麻痺科学捜査官とNY市警の女巡査が明かす異常殺人事件の謎「ボーン・コレクター」
棺おけの前で踊る死神の刺青をした連続殺人鬼を追うライムとサックス「コフィン・ダンサー」
ご存知のこのシリーズ第三作目である。
今回は「証拠はすべて少年の有罪を指している。だが、サックス巡査だけは彼の無実を確信していた。こよなく昆虫を愛する少年が人を殺すはずがない」である。
前二作が都会型の凶悪犯罪しかも頭脳犯相手に追う者、追われる者の知恵のせめぎあいにクールでドライな直線的な緊張感が全編を貫徹し、理屈ぬきの興奮を味わううことができる第1級のエンタテイメントであった。「エンプティー・チェア」も徹夜も辞せずといっきに読ませる点、作者の力量は衰えをしらない。
しかし、読者はわがままである。作者がマンネリ感を排除すべくしてする工夫・作為がかえって私の期待感を裏切ることになる。テレビドラマ「水戸黄門」もそうだ。あれは石坂浩二のインテリ然となって、ちっとも見る気にはならなくなった。「新宿鮫」も鮫島が模範警官になったからつまらなくなった。
ライムとサックスのセックス関係の進展などはどうでもいいのだが、今回の犯罪が地方共同体型のどちらかというと頭脳プレイではなく腕力戦と変貌し、なにか「OK牧場の決闘」並みのガンプレイに力点がおかれ、それならスティーブン・ハンター描くところの「ボブ・スワッガーシリーズ」に軍配が上がるというものである。
「空っぽの椅子に座っているのはだれ?」
などと実証主義犯罪学一辺倒から精神分析犯罪学、あるいは女の第六感主義犯罪学をとりいれるくだりになると緊張感が薄らいでくる。
そして訪れる衝撃のラストシーン、これはいい。これはいつものパターンだからむしろ期待通りでいいのである。エンディングメロディーが流れるその瞬間に(始めてこれらの作品を読まれる読者には最後までページを繰ることを忠告しておこう)………。
|
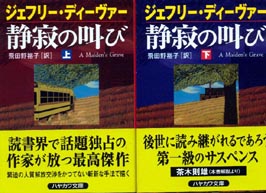
|
ジェフリー・ディーバー「静寂の叫び」
ちょっと期待はずれですが 2000/03/20
|
ジェフリ−・ディーヴァーの「ボーンコレクター」以前の作品なのですね、これは。
聾学校の生徒と教員を乗せたバスが脱獄囚にのっとられ、廃屋同然の食肉工場に監禁。FBI危機管理チームが人質解放に向けて交渉を開始する。全体の構想はいいんですが。途中、何度か退屈してしまうところがありました。凶悪な脱獄囚やテロリストが集団の人質を取って立て籠もる。その救出活動を描くストーリーは映画でもお馴染みで私はこの手のものが好きなんですね。このイメージの「刷り込み」があるためにやや悠長な感じをもってしまうのだろうと思います。ダイハード、沈黙のなんとか、スピード、ダーティーハリーやらシュワルツェネッガーものいずれも戦闘シーンやヒーローの超人的行動が見せ場。パワー対パワー、アクション、アクションの連続。もちろん小説にもジェットコースター的にストーリーが展開するのがある。
ところがこれは犯罪者と「交渉者」の手の込んだ心理ゲームによって人質解放を最低限の犠牲でもって進めていくプロセスに力点が置かれます。日本警察の人質救出は犠牲者をひとりたりとも出さないことに主眼がおかれているような気がします。あちらはできる限り犠牲を少なくするとの観点でことに臨む、ここに違いがある。アクションではなく心理サスペンス、この着想が大変ユニークで面白い展開をみせてくれます。ただ全体に長すぎるんだろうと思います。ラストの急展開は相当なものですからその伏線と考えれば良いかも知れない。
|

|
ジェレミー・ドロンフィールド『飛蝗の農場』
もうこの手のサイコサスペンスは卒業にしたい。
2002/11/04
|
作者ジェレミー・ドロンフィールドはイギリスウェールズ地方の出身で考古学を専攻した人だという。この作品は彼が1998年のデビュー作でその年の英国推理作家協会賞最優秀処女長編賞の「候補作」だそうだ。
英国のミステリーには独特の雰囲気がある。舞台となる地域の歴史・風土の描写が調和のとれた背景としてテーマをあざやかに浮き彫りにするところである。
この作品の舞台はヨークシャーのホーワース近く、付近に住む人のいない孤立した農場、愛憎劇『嵐が丘』にひろがる荒野である。この荒涼たる土地にジャガイモ畑と羊の飼育、飼料にするバッタの群れを飼って世捨て人の生活を営む女性が一人で住んでいる。過去から逃れようとしても悪夢にうなされる毎日、その精神もこの地と同じように荒んでいる。ヨークシャーはまた女性11人連続猟奇殺人、ヨークシャー・リッパーの舞台でもある。ミステリーの世界では最近でもこの事件について形を変えながら繰り返し描いている、そういう土地柄でもある。
彼女の前に記憶喪失になったらしい、しかも連続女性殺人の犯人かもしれない、そんな怪しい男が登場する。過去を独白するのだがこれが真実なのか嘘なのか妄想なのか。この男に惹かれた孤独をもてあます女性は半信半疑ながらも彼におぼれていく。さて………。
物語のスタートは謎の提起、重厚な風景描写といい、大いに期待させるものがあったのですがすぐに落胆させられました。男の過去を少しずつ切り取って時間の流れには忠実でなく、それを女との生活描写の間にはさみこむ叙述形式を取るから読者は何がなんだかさっぱりわからなくなる。精神異常者の心理分析を謎解きにつかったり、そこで生まれる妄想とか悪夢を現実とないまぜにしてした叙述のトリックで読者を惑わせる手法はもうげっぷが出るほど飽きがきている。そんな使い古された小手先のテクニックは上等なミステリとはもはや言えまい。ラスト、これが驚愕のドンデンガエシとは………。
サイコサスペンスの新作などもういやだ、いやだ。読むまい。解説の三橋暁氏によればこれはまぎれもなくサイコロジカル・スリラーというジャンルに属する。20世紀末のミステリ・シーンに大きなブームを巻き起こしたサイコロジカル・スリラーはどうやらトマス・ハリス『羊たちの沈黙』で終わったらしい。この意見には賛成します。新刊ではなく、ブックオフで買った本なのでまだしも救われた。しかしこの作品は今年のランキングに高位ではいる可能性が高いようだ。
|