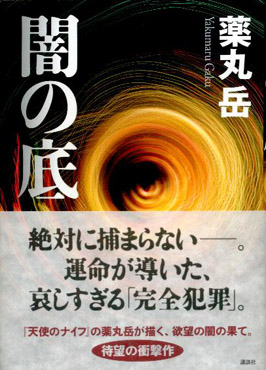
|
薬丸岳 『闇の底』
このところ悲惨な事件が連続している。小中学生のイジメによる自殺、肉親による幼児虐待と殺傷。幼い命の非常事態宣言であろう。これという対応措置がないままに狂気だけが蔓延しつつあるようで不安と焦燥感が日本全体を覆っている。
2006/11/14
|
そして『闇の底』で薬丸岳はこの暗澹の世相を背景に強烈な反則パンチを繰り出した。
前作『天使のナイフ』では刑事罰の対象にならない少年たちに妻を殺された主人公の「殺してやりたい」との無念の叫びには読者の共感を呼ぶところがあった。また刑事罰を受けない少年たちの「贖罪」とはなにかと問題提起するミステリーの好著だった。
今回も「殺してやりたい」幼児性愛の犯罪者たちと犠牲者の家族が何人も登場する。しかし前作とはまるで趣が異なる。
少女を犠牲者とした痛ましい性犯罪事件が起きるたびに、かつて同様の罪を犯した前歴者が首なし死体となって発見される。身勝手な欲望が産む犯行を殺人で抑止しようとする予告殺人。狂気の劇場型犯罪が日本中を巻き込んだ………。
憎んでも憎みきれない犯罪者。そいつらに天罰を下すと宣言し実行する「男」。そして「男」を追う刑事・長瀬もまた妹を陵辱殺害された過去を持つ。
頻発する幼女殺害事件がありが未解決のままに当局は性犯罪へ抑止力を喪失しつつあった。警察側の捜査の混乱。幼女たちが殺害されるたびに「男」は凄惨な犯行を実行する。被害者家族の怒りと捜査への不信感。その焦燥を埋め合わせるかのような「男」の犯行。長瀬刑事と先輩たち警察側の視点で捜査状況が、妻子を持つこの「男」の視線で彼の日常生活と犯行現場が、交互に語られる。さらに妹を殺害された少年・長瀬の記憶に残る当時の情景、心境がフラッシュバックする。この巧みなストーリー展開はなかなかの緊迫感があり、引き込まされた。
「男」の本当の動機はなんなのだろうか。この「完全犯罪」はどのように破綻するのだろうか。この謎解きもまた魅力的な設定だった。
どんでん返しのラストもまた非常にショッキングだ。
むしろあきれ返った。
『天使のナイフ』のような鋭い問題提起を期待していたために私はひどい消化不良に陥り嘔吐感を禁じえなかった。そして読んでいる最中は語りのうまさに気づかなかったのだが、本格ミステリーだとすれば欠陥と言っていいところがやたらに気になってきた。この作品は一時流行したノワールなサイコサスペンスとして理屈抜きにのめりこんでいれば咀嚼できるのかもしれない。しかし背景は抜き差しならない深刻な現実である。
なんでもありの無作法なミステリーには感心できません。
|

|
貝塚茂樹 『韓非』
数人の仲間と「韓非子」を読んでいる。中国文学の権威・村松暎先生と雑談を交わしながら全編を通読するのではなく、先生が用意された解釈なしの原文テキストで「孤憤」「説難」「和氏」「姦劫弑臣」「五蠹」までを読んだ。五十五篇の大著のなかからどうしてこの篇をとりあげ、この順序で読むのかわからないままに先生の洒脱な語りぶりとおとぼけにすっかりのめりこんでいた。これらは韓非子の自著であり、韓非子思想の枢要をなすものなのだろう。
2006/11/23
|
比喩が巧みであり、論理的であり、感情は時に高らかに時に慎ましやかに起伏に富んで、しかも鬱屈と沈痛の心情に憂国の気が満ちている。なるほどこれを読んで秦の始皇帝が感激したわけだ。なにしろ専制君主が国家を支配のために必要とする合理的システムが指摘されている。
それまで理想とされた仁や徳の政治ではない、倫理性を希薄化した法治政治である。歴史上初めて全中国を支配する秦の中央集権体制の基礎となる理論だからだ。それだけではない、二千数百年をいまのわれわれの生活の中にその同質性を見出し驚くことになる。現代民主主義体制といえどもある意味で支配・被支配の構図にあり、会社社会も同様の関係にあるから、韓非子のこれらの編を読むものはいくつもの指摘を現実感覚で飲み込むことができる。善悪の基準よりは利害得失の選択で人は動くものだとして組織内の人間の心理をつまびらかに分析するその合理性は非情なまでに研ぎ澄まされている。
貝塚先生は歴史学者である。韓非の伝記がほぼ漢の司馬遷『史記』の叙述に限られしかもその叙述が必ずしも史実ではないと指摘される。順不同に収められた『韓非子』五十五篇の内容を分析し、各篇の成立年代を推定、韓非の思想発展プロセスをたどっていく。古今、日中の韓非子研究、最近発掘された古代文書などに独自の切込みをいれる分析の成果がこの著述であるが、この過程は難解でありついていくことができない部分も多かった。また貝塚先生のこの著作にいささかでも口をさしはさむ見識など持ち合わせてはいない。ただ素直に自分なりに理解できる範囲で読んだ。いくぶんかでも韓非子に触れたことがあるからだろうか、つい最近塚本青史『始皇帝』を読んだこともあるだろう、研究論文を読むつもりで手にとったのだが、思いがけずに面白くあれこれと興味の尽きない読み物だった。
韓非の思想を現代という座標軸にたって歴史的観点で学ぶ。そのための格好の書であるといっても間違いではないだろう。たとえば私の読んだ「孤憤」「説難」篇は青年韓非が道術によって国家の政治原理を基礎づけた道家思想から実定法による国家統治の技術論へとの思想革命をはっきり示した自画像のようなものだされる。こうしたヒントを得て原文を読み返せば、なるほど!と、七雄割拠の戦国から秦が大帝国を完成する時の流れに密着してこの篇の本質を実感できることになる。
ただ、私が面白いと思ったのはそれだけではない。韓非を主人公とした大歴史ロマンを読んだような、司馬遷『史記』にある韓非子伝記よりははるかにスリリングで波乱に満ちた人物像を思い浮かべることができたからだ。韓非の祖国韓は隣接する強国秦の脅威に運命は風前の灯であった。貧乏公子だった韓非。政治の実権からほど遠い貴族。吃音で華やかな舞台に登場できない才子。人間観察を通じて社会の積弊をえぐり法治主義こそが国家の強化・安定を可能にすると論断する。しかし、韓王へ内政強化策を提言するも受け入れられずに鬱々の孤独。燕、趙、斉、衛、魏、楚の合従か。秦との連衡か。そして秦は李斯の遠交近攻の策をとり韓への攻撃を開始する。この国際的緊張関係の中で韓非子は秦へ乗り込む。司馬遷の言うように始皇帝から招請されたのではない。秦の韓侵略を阻止する調略をもって秦へおもむいたのだとする。その役割を看破され毒殺されたのだと。
これこそ歴史大ロマンでなくてなんであろう。
|

|
浅田次郎 『蒼穹の昴』
その続編だと思われる『中原の虹』を読む前に再読しておく価値はあった。浅田次郎初期の大傑作。
2006/12/04 |
読んだそのときには心に留まった作品でもエンタテインメント系の長編小説となるとうまいタイミングでもなければ二度読む気にはなれないものですが、この作品の続編にあたる『中原の虹』が目下刊行中とあってまさにタイミング到来、再読しました。1996年に読んだ浅田次郎の初期の作品です。
「この物語を書くために私は作家になった」
とキャッチコピーはオーバーな表現に思われましたが、そんなことはなかった。この大ロマンの構成の妙に驚かされた記憶があります。
必ずや汝は西太后の財宝をことごとく手中におさめるであろう。中国清朝末期、糞拾いの貧しい農民の少年春児は老婆の予言を信じて宦官になるのですが、宦官になるために「男」を切り落とす浄身はこれほどの凄惨な施術だとは、いやぁ生き地獄のこのくだりはいつまでたっても忘れることはできません。
地獄といえば科挙の試験のすさまじさもこの作品ではリアルでした。
梁文秀、汝は長じて殿に昇り、天子様の傍らにあって天下の政を司ることになろう………
とこれも老占い師の予言。文秀は科挙トップ登第を果たすのですが、夢うつつに合格答案の作成に導く奇跡も忘れられないところでした。
物語は
「都で袂を分かち、それぞれの志を胸に歩み始めた二人を待ち受ける宿命の覇道」
なのですが、彼らの周囲にある脇役たちがいいんですね。そこには男と女の美しい愛の形、兄弟愛、師弟の恩愛、男同士の友情、差別されたものたちの連帯など感動のエピソードが次々に展開されます。登場人物のほとんどが善人なのですね。悪者をあえて挙げるなら、これらの人物群に悲劇をもたらす時の流れなのでしょう。そして逆境にあって運命を切り開いていく勇気を至高のものとして謳いあげている作品なのです。
ところでこの作品の人物造形でもっとも秀逸なのは西太后ですね。漢の呂后、唐の則天武后と並んで中国史上三大悪女といわれたこの烈女、咸豊帝の妃で、世継ぎを生み、咸豊帝の死後に政権を握った。そしてわが子同治帝と甥の光緒帝の二代にわたり、皇太后として権力を振るい続けた。呂后や則天武后の専横は15年ですが、西太后は47年間と長きに渡って君臨しています。一般的には内憂外患にあえぐ落日の清朝にあって、権力の座を維持するため武力、謀略、暗殺で内外の勢力と綱渡りの糾合を繰り返してきた血も涙もないワルモノの代表です。だが浅田次郎はそうはしなかった。西太后は清の最盛期を築いた乾隆帝の亡霊がその歴史的役割を与えた宿命の人なんです。
帝が政をなし、官が民をしいたげる五千年の歴史、そちは鬼となり修羅となって、国を覆す。そちが未来永劫に悪名を残してこそ、未来永劫この国の民は救われる。夜叉の仮面を被った真の観世音として生きよ。
と、つまり中国が五千年の君主専横政治に終止符を打ち、近代的な民主主義国家に飛翔するための積極的捨石の役割でもって登場させているのです。この発想の豊かさ、その新鮮さ、ドラマチックであります。
洋務派で忠節の士・李鴻章の武力と政治力を背景にした西太后。しかし日清戦争の敗戦後,李鴻章は政治の表舞台から退く。文秀の属する光緒帝派の発言力は増し、98年、康有為ら変法派とともに光緒親政のクーデターが行われた。これに対し宦官のトップランクに立った春児は西太后の信任が厚い。彼女は袁世凱の武力を背景に戊戌政変を起こして新政を失敗させ、変法派を処刑・追放、光緒帝を幽閉して,三たび垂簾政治を始めた。文秀は日本に亡命する。
『蒼穹の昴』はこのあたりで完結しています。
浅田次郎の独創的な歴史デザインにより、歴史小説の趣はありません。帝国主義列強の貪欲な素顔はなく、歴史観を云々する類ではありません。伝奇小説風な華やかな妖しさが全編に流れ、私たちが忘れがちな本物の愛と勇気、義理と人情を浮き彫りした壮大な人間ドラマと言えるでしょう。
|