
|
アガサ・クリスティー 『そして誰もいなくなった』
たまには本格謎解き小説の傑作中の傑作を
2003/02/12
|
孤島の豪邸に10人の男女が招かれるが主の姿はない。全員が集まった広間にどこからともなく怪しい声が響き、10人が過去に犯した隠された罪状が暴かれる。各人の部屋には「マザーグースの子守唄 10人のインディアン」の歌詞が書かれた羊皮紙が掲げられている。ダイニングルームにはインディアンの人形が10個、飾られている。そして子守唄の歌詞どおりに殺人が進行し、人形はそのたびに壊れていく。
とにかく読者に対する作者のサービス精神、これがただものでない。何が凄いったってはじめに「犯行の意図はここにあるぞ」「これからこんなことが起こるぞ」と読者に披瀝するのであり、ここまで挑戦的なミステリーにはめったにお目にかかれるもんじゃあない。マジックではそうなのだがマジシャンは次におこる現象を観客に絶対に説明することはない。マジックの真似事が好きな私にしてみればこのタブーがわかっているだけにここで仕掛けられるトリックの鮮やかさにおそれいるばかりである。
「10人のインディアンの少年が食事に行った。一人が喉を詰まらせて9人になった」
「9人のインディアンの少年が遅くまでおきていた。ひとりが寝過ごして8人になった」
殺人鬼はこの10人のなかの誰かなのだ(実は島にはもう一人隠れ潜んでいたなどという子供だましのタネあかしはない)。謎解きの面白さだけではない。うずまく疑心暗鬼と不安の無駄のない描写に息を詰まらせる。すなわちこれは第1級のサスペンスでもあるのだ。
ラストは「1人のインディアンの少年があとに残された。彼は首をくくり、あとには誰もいなくなった」………とその通りになってしまうのであるから、では犯人はだあれと、摩訶不思議!呆然となる。
外界と隔絶されたいわば巨大な密室でおこる連続殺人プラス「見立て殺人」(ミステリーの特殊用語でこの場合のように子守唄にみたてた様式を伴う殺人を言う)である『そして誰もいなくなった』の類型作品は数多くあって最近では山田正紀『ミステリ・オペラ』、笠井潔『オイディプス症候群』、マイケル・スレイド『髑髏島の惨劇』があげられる。三つとも一昨年、昨年のミステリーベストランク入りした作品ではあるが、比較すればこのオリジナルの傑出ぶりがますます際立つのである。
「見立て」は読者が何に見立てているのかわかりやすいものでなければならないと思う。マザーグースのこの唄はイギリス人なら誰でも知っているものらしい。日本で言えば「とうりゃんせ」「はないちもんめ」「かごめかごめ」といったところか。わかっていてはじめてストーリー展開に興趣がわくのである。一番目は食事中に殺されたな、では二番目は寝ていて殺されるのだろうなどと。ただしこの唄を知らない日本人読者でもはじめに紹介があり、しかも短い歌詞であるから違和感は全くない。
アガサのサービス精神の一番のあらわれはなんと言ってもこの本の重量が軽いことである。中編小説に仕上げていることだ。余計な叙述を一切そぎとり、著者はもっぱらトリックの鮮やかさ一本で読者を圧倒する。「え、そうだったかな」「まさかそんなこと書いてあったかな」と解決の章を読み尽くすまでにはなんどもなんどもページをめくり返すことになります。軽量であるからこそ可能になる吟味だ。そしてこれは作者に対する読者の礼儀であって、このめくりかえしをやってこそ、トリックの醍醐味を満喫できる仕掛けなんですね。最近流行の「巨編」とか「超大作」となりますと作者本人しかわからない「見立て」解説でくどくどと原稿枚数を嵩上げし、本の重量は手に持っているだけで腱鞘炎になるぐらいだから、めくりかえしの礼儀などのっけから期待されていない感があって、解決編の鮮やかさが欠落してしまうのです。本格謎解きは「軽い」のに限る。
|
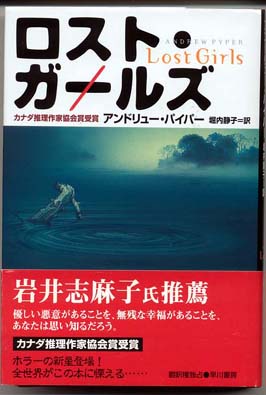
|
アンドリュー・パイパー 「ロスト・ガールズ」カナダ推理小説界のレベルは?
2001/05/23
|
ミステリー作家にとって、いかに型破りの探偵役を創造し読者を魅了するかはその作品やそのシリーズの売れ行きを大きく左右するだけに実に大きな課題であり、腕の見せ所だ。
最近ではコーンウェルが才色兼備の女性、検死官スカーペッタで読者層を広げたし、ディーヴァーは四股麻痺の自殺願望者、元刑事ライムの強烈な個性を作り出した。ハリスの「羊たちの沈黙」におけるハンニバル・レクターなどは定石破りの代表、グロテスクこの上ないが、魅力的である。
しかし、探偵像づくりのため奇をてらうに精一杯でちっとも面白い作品になっていないのもある。和ものであるが、幼女連続殺人魔を探偵にした「ハサミ男」や右脳をなくしたサイボーグが探偵役の「脳男」など何とか賞受賞でもうんざりさせられる作品はままある。
カナダ推理作家協会賞と銘打ったアンドリュー・ハイパー「ロスト・ガールズ」ではヘロイン中毒の辣腕?弁護士が探偵役として登場するが、ハードボイルドの名作にはアル中であって魅力的な探偵はよくおりますがね、出張するのにポットいっぱいのヘロインを持ち歩かなければ幻覚、幻聴に襲われるようでは、コミカルものなら、ともかくよほど作者が巧者でないと、いい作品にはならないですね。
しかも、日本ではこの作品は「ホラ−の新星登場」と紹介され、あとがきの三橋何某は「主人公を不安に陥れる怪異現象の数々が、やがて少女たちの失踪に静かにシンクロしていく。この作品によって恐怖小説が本来持っていた恐怖の根源に迫る力を回復したといっても過言ではない」と。これは間違いでしょうね。
子供を湖に招き寄せる幽霊伝説のある町が舞台で、そこで少女が失踪、犯人として、これもよくある設定で、ロリータ・コンプレックスの変態教師が逮捕される。真犯人は?はたまた幽霊か?「怪異現象」は起こるのですが、私はこれが怪異現象なのか、麻薬中毒患者に特有の幻聴、幻覚の類なのか、このあたりがミソだな、文体もダークだし例によって、幽霊伝説を利用した完全犯罪に違いないなどと興味を一点に絞り込んでいるために「本来の根源的恐怖」なんてものはいささかも感じないのです。
むしろコピーとしては「無限の闇にさまよう主人公の精神の荒廃をえがいて、世紀末カナダ社会を覆う不毛の深層を抉る驚愕の傑作サスペンス」と表現するいい加減さのほうが、まだ塩梅がいいようだ。
最後まで何が何だかわからない。これでもカナダ推理作家たちのレベルで、どこか共感するメッセージがあったのだろうと好意的に受けとめておこう。
|
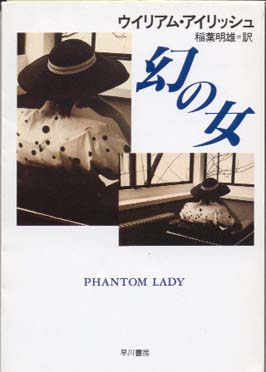
|
ウイリアム・アイリッシュ 『幻の女』
昭和25年に江戸川乱歩が驚愕をもって紹介した本書はわが国ミステリー界に新しい潮流をもたらした、いわば戦後ミステリーの原点といわれる作品である。
2003/08/26 |
初めて読んだのだが、なるほど、その後主流になる清張ミステリーに共通するものがここに見出される。
戦前の探偵小説は横溝正史に代表される、村落共同体を舞台にする怪奇性と機械的トリックを組み合わせた謎解きパズルであった。これに対し新しい流れは、犯罪の動機にフォーカスした人間の心理や社会・風俗性をえがき、リアルなストーリーの展開と文学性の加味、そして舞台は戦後巨大に膨れ上がる都市社会である。
「夜は若く、彼も若かったが、夜の空気は甘いのに、彼の気分は苦かった」大都会に群がる人々がアイデンティティーを失った孤独、夜の闇にうずくまる魔性が生むミステリーであることを象徴する冒頭の一節である。半世紀を経てなお読むに違和感をおぼえない空間を提起した印象的な一文である。
妻殺害の容疑で死刑宣告をうけた株式ブローカーの男。その時間、彼はバーで出会った帽子の女と食事、観劇で過ごしていた。何人もの目撃者はいるはずであったが………。
ストーリー展開はいまも使われている手法のタイムリミットサスペンス。「死刑執行前百五十日」から「死刑執行後一日」まで23章としてカウントダウンされながら進む。そして有力な証言者が次々と殺害される。読者は主人公同様絶望的状況に陥る。決定的なアリバイを証明できる幻の女は現れるのか?
この巧妙な語り口は今流のジェットコースターサスペンスであり、そのスピード感に古臭さは微塵も感じられない。さらにトリックも物理的なものから、心理的、叙述的なものまでちりばめられて、この作品にアイデアをえたと思われるその後のミステリーも数多い。ミステリー好きにはまさにエポックメーキングとしての価値を味わう、読んでおくべき傑作である。
ただし終盤の解決のくだりでは現実性、必然性からみて無理なところが目につくのだが、それとても最近の新本格派と言われる謎解き小説にみられるいかがわしいご都合主義にくらべればとりあげて言うほどのことではないだろう。
|