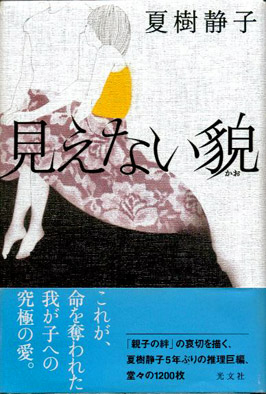
|
夏樹静子 『見えない貌』
夏樹静子さん、1938年生まれというからわたしよりも6歳先輩だった。そう気がつけば初期の作品『蒸発』を傑作だなと感じたことや『Wの悲劇』なども懐かしく思い出される。その後二時間ものテレビミステリーでしかお目にかからなくなったが、久々に5年前の『量刑』ではベテランの新境地ここにありと再び輝きを取り戻していた。
2006/12/12 |
人妻、不倫、弱い女の心に潜む妖しさ、親子の情愛、これが夏樹静子なのだが、この類型はいまではマンネリミステリーの代表テーマかもしれない。『量刑』もそうだし、この『見えない貌』でもこれがなお一貫している。しかしそれでも二時間テレビドラマのような使い古された退屈な作品になっていないところにベテランミステリー作家の持ち味を発見する楽しさがあった。
「メル友とつながっていなければならないほど寂しくて孤独だった」
若き人妻・晴菜が殺害される。母は「見えない貌」への復讐を決意する。
「母・朔子は殺人者を自ら追いつめるが………。思いもかけぬ第二の事件が待っていた!」「これが命を奪われた我が子への究極の愛」
とうかつにはあらすじを述べられないので装丁帯にあるキャッチコピーの引用にとどめるが、それだけのひねりをきかせた全体構成からなる密度の高い上等のミステリーだった。
携帯電話だけでつながったメル友、出会い系サイトの怪しい魅力、その危うさへの警告という今日性を取り上げていること自体にそれほどの目新しさは感じないがまもなく70歳にならんとする女流作家の社会に対する実直な姿勢、またネットシステムに対する旺盛な研究意欲に敬意を表する。
それよりも第一の山場からの「思いもかけぬ」大逆転の展開がみごとだ。
さらに前半は朔子を中心とする心理サスペンス、後半を本格法廷ミステリーと硬軟の調和が実にうまい。
この後半では『量刑』と同じ作者の主張がある。神ならぬ生身の人間が真実を求めその結果が判決となるのだが、それがはたして真実なのかと。『量刑』では判事の立場でこれを描いていた。今回は弁護士であった。
弁護士の立場に立った法廷ミステリーの醍醐味は真っ黒な被疑者を無罪に持ち込むドラマチックな展開にあるがその期待は裏切られない。
「『親子の絆』の哀切を描く、夏樹静子5年ぶりの推理巨編」
だと思う。
親子の絆なんてなんぼのものよと、親子の殺し合いが日常化するほど酷薄な関係になってしまったのが今だ。いまさらそれの「哀切を描く」のはノスタルジーに他ならないのだけれどこの物語にある子を思う親の気持ちに素直に同調できる私はそれだけの年代なのかもしれない。
|

|
川端康成 『雪国』
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」
中学だっただろうかいや高校だったろう、おそらく国語の試験問題かあるいはクイズかもしれないのだが、冒頭がこの文章で始まる作品名は?とかこの作者は?あるいはこの長いトンネルとはどこのトンネルでしょう?またはここでいう雪国とはどこを指しますか?などこの一節だけでいくつもの問いがあったものだ。なかには「国境」に振り仮名をつけよという作者本人がルビを振っていないのだけど偉そうにする質問もあった。池部良と岸恵子が主演した豊田四郎監督作品を見たようなおぼろげな記憶がある。
2007/01/03
|
「この指だけは女の触感で今も濡れてゐて、自分を遠くの女へ引き寄せるかのやうだと、不思議におもひながら、鼻につけて匂へひを嗅いでみたりしていたが………」
と最初からひどく官能的なのだが小説をぱらぱらと読んだ限りでは期待した駒子と島村の情交シーンは実際にそれはあったのかしらと思うぐらいに源氏物語風だったとこれは鮮明に印象に残っていた。川端先生がノーベル文学賞を受賞されたので代表作でもとこれを読んだときにも特段の感銘はなかったように思われる。
その程度の『雪国』であったが、どういう風の吹き回しか11月末にあらためてこれを読み、上野の森に出かけたときのことだ。
混雑していたため順路を逆に回った。たくさんの木彫りの仏様を見た最後に圧倒的存在感を持って十一面観音菩薩がやさしくおわしました。渡岸寺の十一面観音様である。その周囲には宇宙の根源からでも吹いてきたかのような緩やかな大気の渦があるのだろう、腰を少しくねらせたお姿から流れるようにふんわりと裳裾がそよいでおられる。いや宇宙の根源はこの仏様そのものなのでしょう。宇宙生命の鼓動をわが鼓動として拝むものたちにその律動を感じさせるそんな存在でありました。私の心が透明になったからでしょうか、普段なら雑踏の中の公園としか感じられなかった上野の森が黄色く、赤く、柿の色に染め上がって別世界のように美しい風景がそこにはありました。
川端の描いた「雪国」とはこんな世界なのかもしれないと不思議な直感があった。そこは仏のおわす彼岸なのだろう。駒子は島村にとって女ではなく仏、永遠のやさしさを宿した母性、慈母観音なのではないか。駒子は宇宙の呼吸を呼吸している存在。
わたしが圧倒されたのは駒子がきれいねえとつぶやく天の河の描写だった。その凄艶なまでの美の中に島村の体はふうと浮き上がる。
「裸の天の河は夜の大地を素肌で巻かうとして、直ぐそこに降りて来てゐる。恐ろしい艶めかしさだ。」
「しかも天の河の底なしの深さが視線を吸い込んでいった。」
二人のうしろから前へと流れ落ちる天の河、濡れた瞼に満ちる天の河、大地を抱こうとしておりてくる天の河。
「さあと音を立てて天の河が島村のなかへ流れ落ちるやうであった」
天の河へむかって浮揚する島村はラストで天の河を吸収する。深遠な宇宙の真理と同化したのかもしれない。
わたしは幼い頃だったが仰ぎ見た冬の天の川を知っている。天空を端から端まで首を巡らせるとただでさえクラクラとめまいがしたものだ。だからもはや目に触れることがなくなった天の川ではあるが、潜在する記憶があるからだろう、高等遊民の島村がこの宇宙の美の極致を神秘体験する情景にはぞくぞくと鳥肌の立つ思いで威圧された。天の川を見たことのない人には気の毒な描写だと思う。
文学とはそういうものなのだろうが読書する年齢によって印象が異なる。いや読む人ごとに異なる印象を残すものだろう。たまたま今回は渡岸寺十一面観音に接したゆえの印象なのかもしれない。そして恥ずかしいことだが葉子という女性の存在がこの期におよんでよくわからない。何年か先に読めばそのときには確かなものが浮かび上がるかもしれない。それこそが文学というものの手ごたえなのだろう。
|

|
司馬遼太郎 『空海の風景』
5年ほど前のことだ。すでに経験のある友人に誘われて秩父三十四ヶ所の霊場巡礼をしたことがある。延5日の行程であったが未知の経験だけに忘れられないいろいろな印象があった。白装束を着衣したかなり本格的な詣だった。空海に関連することでは菅笠に「同行二人」と書かれているのだがそれが「弘法大師とともに」をさすことなどそのときはわからなかった。ひとつひとつの霊場で般若心経を誦する。般若心経の解説を読めば形而上的な宇宙観・世界観の思考体形の一部、勘どころを繰り返し述べた大衆向けの教えであると素直に知ることができる。ただ「色不異空 空不異色」の論理を飛躍して唐突に登場する最終句、「言葉」としては不釣合いであって、あたかも怪鳥の叫びのような「ギャアテイ、ギャアテイ、ハラギャアテイ、ハラソウギャアテイ、ボジソワカ」だけは自分が口にするにしても唇を震わせる薄気味悪い響きに摩訶不思議の実感があった。それは神秘的呪力をもつ真言の一種であり、この真言の力をもっとも重んじたのが真言宗であり、空海なのだとこれも後で知ったことだ。この新しい経験で空海という人物にひどく興味を覚えた。
2007/01/04 |
ある大学の社会人向けの講座に「空海」があって今週から受講する。そこで泥縄を承知で予習のために空海研究でなにを読もうかと思ったが、学問というよりは楽問を好む身であるからと、この小説風の空海研究を読んでみた。
「構想十余年、司馬文学の頂点を示す画期作」
とのキャッチコピーがあるが、司馬遼太郎が丹念な空海研究を土台にその個性で切ってみせたドラマチックな文学だった。
空海は並みの人間ではなかったとほとほと思い知らされるドラマが展開する。
若くして「一個の塵に全宇宙が宿る」世界観を感得し、即身成仏してみずから国家をいや宇宙を動かし現世の利益を追求しようとした男の話だ。旧来の仏教では忌みごとである生命への執着、煩悩をありのままに肯定する野生児だ。あくどいばかりの願望を体質にした怪物。宇宙の意志と交感する密儀を求めて入唐する冒険者。兜率天におわす弥勒菩薩に侍らんと生涯を旅した夢追い人。そして長安の文化人たちを驚嘆させる詩文家、書道家としての天分。長安を背景とするにふさわしい国際的文化人。建築土木に通じ、政治勢力をあやつり灌漑事業の先頭に立って利益を地元誘導する山師。桓武天皇時勢の政争をたくみに泳ぎきる政治家的才覚と自己顕示。
司馬遼太郎はこの多面的人物を立たせる「風景」、それは時代性でもあるし普遍性でもあるのだが、これをつまびらかに描いている。時代考証と大師伝説を巧みに融合させ、司馬遼太郎独自の史観、人間観でもって謎の多いこの人物を読者の前にリアルに浮かび上がらせている。
「天才とは99%のパースピレーション(発汗)と1%のインスピレーション(霊感)である」
と成功者だから言える万人受けの名言があるが、そうでもないだろうと実感するのが人生ゲームの先がはっきり見えた年代者である。
司馬遼太郎は空海が呪術を巧みに操ったとは決して言わない。空海は真言の力を会得したわけだが今はやりの華やかな陰陽の妖術を使っていたとは思わない。ただ、生命や地位の危機また危機の人生にあった空海がそれでも成し遂げることができた大偉業のプロセスをふりかえれば、決して努力と才能ばかりではないぞと、運があったのだと。わたし程度ではどれだけ強運に恵まれた人物なんだろうとうらやましく、そこでとどまってしまうのがオチなのだが、いくつもの難を乗り越え若き日の夢を実現したこと、それ自体が奇蹟であって、とすれば大衆が空海の教えはともかくその人そのものを信仰の対象にしたことは当然のことだったのかもしれない。
「どういう場合でも理性を失いそうにない人文学者」が著者にこんなことを語ったと述べた箇所が作品のスタート部分にある。
「自分のように讃岐育ちの者にはとても空海を人として論ずることはできない。人以上の存在だと思ったときにはじめて気持ちが安らいで多少空海について語ることができる」
読み終えて司馬遼太郎の書きたかった人間空海がこれだったかと気づいた。
|