
|
町田康 『告白』
灰神楽三太郎・森の石松・八尾の浅吉を合計した大馬鹿者の一生。国定忠治も思わずニヤリとするだろう。
2005/05/14
|
明治26年河内水分で36歳の農家の長男・城戸熊太郎が同じ村の住民に金を騙し取られ、妻を寝取られた恨みからその相手を含む村民10人を惨殺したという事実を題材にしている。といわれてもそんな事件があったことなど知らなかった。
「人は人をなぜ殺すのか。河内音頭のスタンダードナンバー<河内十人斬り>をモチーフに、町田康が永遠のテーマに迫る渾身の長編小説
このように紹介されると殺人というのは人間の本源的な行為であって、人殺し願望の普遍性みたいなものを哲学する小説のような気がして、それならば、息が詰まりそうな重苦しい純文学なのだろう。と、町田康の作風をまったく知らなかっただけにいささか緊張感を持って手にとったものだから、冒頭からの軽快でひょうきんな、それは現代の風俗・流行・ギャグを巧みに織り込んで古典落語を語る立川談志風で、しかも汚い、ガラの悪いで知られている河内弁でのそれだから、露骨で、どぎつく、猥雑な長広舌には思いがけない面白さがあって驚かされた。
城戸熊太郎の人物だが、わたしはどうしても、小学生のころ聞いていた浪花節に登場するヤクザ者、しかも三枚目という異色のヒーローをイメージしてしまうのだ。
ドジで、間抜けで、でたらめで、そのうえ寝坊でオッチョコチョイ。これは相模太郎の浪曲にある次郎長一家の一人・灰神楽三太郎である。
それと、酒と喧嘩に明け暮れて、乱暴者と異名をとる。人情、からめばついホロリ、馬鹿は死ななきゃぁ〜なおらぁない〜と遠州・森の石松がいる。
もうひとり。今東光というよりも勝新太郎が男を上げた「悪名」、農民のせがれにして無類の暴れん坊、酒と博打と喧嘩に女。滑稽な野放図さと一直線のバイタリティーで大活躍する、同じく河内は八尾の浅吉でしょう。
この三人を足し上げたような「大馬鹿者」が熊太郎である。その出来損ないぶりには大いに笑わせられる。
素直で、純情で、思いやりが厚い青年なのだが、百姓仕事はトンと身につかない。家にいては寝ている、外では酒をくらっているか喧嘩と博打にうつつを抜かしているのだから農村共同体では厄介者・除け者である。何をやっても思うように運ばないのだ。たとえ善意からのことであっても、誤解される。村娘にナンパしたって痴漢と間違えられる。賭場では大金を巻き上げられる。子供を助けたところが賭場荒らしにされてしまう。悪徳商人を懲らしめるはずが相手を間違えてお門違いのゆすり、たかりをやらかす。やることなすこと大騒動が持ち上がり、それがますます誤解を生み、悪循環が大きくなっていく。
熊太郎はこのように読者から見るといくつもの喜劇的事件を起こすのだが、その都度、彼の内心の弁明が語られる。
熊太郎がなぜ同村の農民を多数惨殺し破滅するにいたったのか。町田は独白スタイルで熊太郎自身の内心にある矛盾だらけの思念を徹底的に解析していく。
灰神楽三太郎、森の石松、八尾の浅吉と共通項の多い熊太郎であるが、たった一つ異質な精神構造がある。それは熊太郎が「極度に思弁的、思索的」なのだ。具体的行動の基にある自分の複雑な思念はレベルの低い河内弁に変換できない。したがって農村共同体の構成員には理解できないのだ。熊太郎はそう思い込んでいる。そこに破滅へ向かわざるを得ない熊太郎の悲劇があると町田は理屈をつけて語る。
「文化の発展過程で普遍的に発生する精神の摩擦をテーマにした異色のエンタテインメント」といえないことはない。
また、理解されないことで社会からドロップアウトしていく現代の若者像につうじるところもある。さらに誰しも自分の気持ち・思いを正確に言葉にできないときに、ひどいもどかしさを実感しているものだから、熊太郎がキレルに至る過程はワカルワカルといいたいところだ。
ただし、町田のこの理屈っぽい語りはくどすぎるのである。時代に先駆けたインテリゲンチャの悩みとでもいいたいのなら、私には奇をてらった作者の勝手な技巧の産物に思える。
ところで八尾の浅吉は熊太郎と同じ馬鹿をしてもカッコよく「古い任侠精神で弱気を助け強気をくじく」ことができた。それは村社会を離脱して別な世界で生きたからやれたことだ。人を殺すことだってやっている、次郎長一家の三枚目にしても世間相場が彼らの生きかたをどこかで評価したからとにかくヒーローにしてもらえたのだ。
熊太郎には農村共同体サイドが評価するなにものも持ち合わせていなかった。にもかかわらず最後までそこにとどまった。それが悲劇だったのだ。
単純に「馬鹿は死ななきゃ直らない」というお話である。
|

|
安部龍太郎 『天馬、翔ける』
NHK大河ドラマ、陽光に輝き真っ白な駿馬が翔ける。颯爽の貴公子・多感の若武者・軍事の天才・波乱の生涯。非業の最期を遂げる義経の人物像は「判官贔屓」の言葉どおり国民大衆がいまなお追慕しつづける完成された日本型英雄である。おそらく放映中の大河ドラマもNHKだからこの枠をはずすことはないだろう。一方の頼朝については疑心暗鬼・優柔不断・嫉妬妄想・陰険嗜虐のイメージが刷り込まれている。
2005/03/23
|
安部龍太郎『天馬、翔ける』も二人にそなわるこのイメージを過半は踏襲している。著者は人物そのものに著者独自の思い入れを投入することを極力回避している。主役は不可逆な時代の流れであって、ドラマチックではあるが義経も頼朝もその流れの中で一定の役割を果たすに人材に過ぎない。
既成の人物像にそなわる善悪の魅力を活かしながら、しかし冷静に時代背景をかぶせれば、読者をうならせる新しい人物像が浮かび上がる。意欲的な作品である。ある部分で偶像義経の破壊である。それは政治家頼朝の積極評価につながるものだ。判官贔屓の大衆心理はまだ生きているのだから、トンデモ本、歴史考証の書ならともかく、大衆小説としてはかなり異色の作品といえよう。そして読後、義経ファンである私もこのふたりの実像はこんなものだったろうと素直に受けとめられた傑作である。
物語は兄弟がそれぞれの地で平家打倒の決意を固めるところから始まる。これまで読んだ源平合戦ものにはない、異色の冒頭にまず驚かされた。
関東武士団の糾合から始まり、平氏をバックにした朝廷支配をくつがえし、土地所有の制度を根本から変革すること。時代はそのための長期戦略、深謀遠慮、権謀術数、人材登用、軍備増強すなわち新たな歴史への移行するための政治力の求心を必要としていた。伊豆の地で政治家頼朝が立ち上がる。
すでに農地は公田よりも開発領主によって開かれた田畑の生産力が圧倒していた。しかし院、公家、寺杜の支配下にあって開発領主=豪族=武士にはその土地の領有権がなかった。平氏はこの制度を保護する立場にあった。多くの武士たちはこうした境遇から脱し、一所懸命の地を守ってくれる棟梁の出現を待ち望んでいた。頼朝の役割は朝廷と掛け合って彼らの所領を安堵させること、命をかけた戦争で奪った土地を差別なく分け与えることにあった。
源義経は奥州の地にいた。京の都より後白河法皇の院宣が届く。いわく、平家を討伐せよと。父のあだを討つ、その宿願を胸に義経は出奔。
ここで描かれる義経は当初、やはり颯爽とした軍神として登場する。時が彼に与えた役割は平家殲滅の軍事である。知られた数々の名場面を繰り広げながらひたすら平家を滅亡の淵に追いやる。彼にとってこの戦は歴史を変えようとする展望からではなくて単なる仇討ちにすぎない。電光石火・勇猛果敢が猪突猛進になりそして多くの場合は軽挙妄動、さらに勝っためには手段を選ばぬその戦術とかなりイメージはダウンする。特に後白河法皇に盲従するふがいなさ、政治力の欠如にはいかんともしがたいものがある。
後白河法皇の神通力と「大天狗」といわれる怪人ぶりはすこぶる魅力的である。また奥州藤原一族は日本の先住民族の末喬で、神話時代に渡来した大和朝廷に追われた蝦夷の頭領と設定し、その勢力の全国展開も独特なところが随所に描かれ、物語を楽しくさせている。
武士団の統率者としてもまだ不安定な頼朝。旧体制を死守せんと陰謀を巡らす後白河。独立国家を目指す奥州藤原。この三すくみの権力闘争に翻弄される義経。
四者それぞれ、周囲にある女性たちとの色模様も華やかさをそえているが、やはりこの四者対立構図の複雑に変転する展開が読みどころでしょう。
|
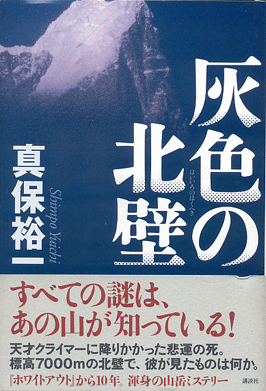
|
真保裕一 『灰色の北壁』
「山岳ミステリー」!! この作品は真冬、豪雪の山奥。そこのダムを舞台にしたデビュー作『ホワイトアウト』という傑作冒険小説の類ではない。
2005/05/03 |
アルピニズム alpinism、近代登山は、山に登ること自体に限りないよろこびを見いだし、登山が肉体と精神に与えるものを汲みとり人生のうるおいとすることを目的とする。宗教的な登山や戦争のための登山と異なり、登るという行為以外に目的をもたない点において近代登山はまさしくスポーツであり、ハイキングのような軽登山も高度の技術を要する岩壁登攀(とうはん)や氷壁登攀も登山である
平凡社世界大百科事典より
多くの山男たちはこのスピリットで山と付き合っているのだろう。そしてより高く、より新しく、より困難な登山のなかに喜びと楽しみを求める。
そのテーマであれば山岳ロマンと言っていい、アルピニスト賛歌だが………。
夢枕獏の『神々の山嶺』では山は愛すべき山というよりは、人間を拒み続ける侵すべからざる神々の山であり、この不可侵の山と闘争する狂気のアルピニストを描いた傑作であった。
しかし、『灰色の北壁』の登場人物は愛すべきクライマーたちである。いや喜怒哀楽をわれわれと共有する普通の人々である。
山岳ミステリーと称された作品はこれまでもいくつかあったが、それらは山を背景にした犯罪を描いた小説であった。これはそれらともちがう。真保裕一の新しいジャンルであり、しかも全三編の短編集、いずれも粒ぞろいの傑作だ。
「黒部の羆」
北アルプス、剣岳。ロープで繋がったふたりだけのパーティー。彼らは何のためにこの山に登ったのか。ひとりが白い急壁面で滑落し宙吊りとなって意識を失う。目撃者のいないドラマの展開。死を賭して、一人救助に向かうのは北峰ロッジの管理人、元県警山岳警備隊員。彼もまた運命的な山岳ドラマの経験者なのだ。
「灰色の北壁」
ヒマラヤ、カスール・ベーラ。この前人未到の「ホワイトタワー」を南東稜から無酸素単独で征服した男、御田村良弘。そしてそこの北壁登攀こそが世界のアルピニストに残された課題であった。19年後、御田村の妻を奪った男、刈谷修がついにその北壁を単独無酸素で制覇した。しかし、山岳ジャーナリストの「私」は刈谷の写した山頂からの証拠写真に疑問符をつけたノンフィクションを発表する。汚名の晴れぬまま刈谷はカンチェンジェンガで死亡する。
「雪の慰霊碑」
息子は冬の北笠山で遭難死した。世間はそれを冷たく扱った。妻も死んだ。人生の折り返し地点はとうに過ぎた。会社にも家庭にも居場所を見つけることができなくなった52歳。ただ一つやらなくてはならないことがあった。山の経験のない父親が冬の北笠山の遭難現場を訪ねることだ。死を覚悟した登山と悟った息子の元恋人はその父を追う。彼女を慕う息子の従弟もまた山に踏み込んでいく。
岩壁からの墜落、落石、雪崩、疲労など山に立ち向かうプロセスは迫力にあふれている。そして大自然の偉大さと対照的に人間の愚かしさが浮かび上がる。
人間に潜む野心、功名心、敵愾心、欲望、嫉妬、憎悪が暴かれれば、うわべのきれいごとは色あせ、醜悪なものが露呈される。それは純粋なアルピニストだと信じていた読者が目を背けたくなる事実だ。
そこがミステリーである。
アルピニスト賛歌ではない。
それでも最後は人間賛歌だ。
じわりと感動で目頭を熱くさせられる。
ヒューマニズムの感動なら「黒部の羆」
謎の意外性と男の真心への共感は「灰色の北壁」
彼はなぜ山に登ったか。女の愛の行方。残されたものは何もないはずのオヤジの決意。哀感が胸を打つ「雪の慰霊碑」
|