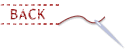
人通りの多い繁華街の駅で、少女は大きな蒼い瞳を期待に輝かせ、たった一人の男性(ひと)を待っている。
その表情は、本当に嬉しそうで、輝いていて、誰もが彼女に目を奪われずにいられない。
青緑色の瞳は百面相。
デートについて思いを巡らせているのだろうか、その表情はころころ変わって、飽きさせない不思議な魅力を持っている。
栗色の髪が、時折、風に揺れて、くすぐったそうに少女は身体を捩った。
ふと、彼女は時計を見る。
約束の時間は、とうに三十分は過ぎている。
(仕方ないわ…。アリオス忙しいものね…)
少女は、そわそわと彼方此方を見つめながら、まるでダンスをするかのように足はスッテップを踏んでいた。
(お腹すいちゃった・・・。アリオスは今日、どこに晩御飯は連れて行ってくれるかな…)
ふふと幸せそうに笑って、彼女は再び彼を待つ。
(お腹すいたな…)
空腹に耐えられなくなったのか、少女は、アジアンテイストの籐の鞄から、いかにも甘そうなキャラメルを取り出し、口に入れた。
(おいしい〜)
とろけそうな表情で彼女が信号を見ると、そこには焦りながら信号待ちをしている彼の姿が見えた。
ラフなスーツを着こなし、クラクラするほど魅力的な彼女の大切な男性がそこにいる。
信頼と、愛情に溢れる眼差しを、彼女は彼だけに向ける。
その眼差しに気がついたのか、彼は口角を僅かに上げて微笑むと、手をすっと上げる。
少女も銀の髪の青年に応じて、元気いっぱい手を振った。
信号が変わった瞬間、青年は、少女に向かって、全速力で掛けてくる。
「悪ぃ遅くなった! オリヴィエの野郎が中々離してくれなくてよ」
「うううん、大丈夫」
少女は、太陽のような微笑を青年に向け、安心させる。
「ナンパされなかっただろうな?」
明らかな所有の言葉に、彼女はふんわりと微笑んだ。
「アリオス、こんなんじゃ誰も声を掛けないわよ? だって、“あなたのもの” だって、宣伝しているようなものでしょ?」
少女は、すっかり突き出し、誰もが気付くお腹に手を触れる。
「そうだな…。ところで、腹へらねえか?」
「うん。空いた」
「俺も」
「だったら、これ食べる? 今、私も食べてるんだけれど」
少女が差し出したのはカルシウム入りの甘いキャラメル。
彼は甘いものが苦手なせいか、苦笑いする。
「美味いのか、それ?」
わざと怪訝そうな眼差しを彼女に向け、意地悪げに言った。
「大丈夫よ! 美味しいの! それにこれ食べるとカルシウムが取れるしね?」
「そうか・・・。じゃあ、味見だな?」
良くない微笑を浮かべると、彼はそのまま身体を屈め、その顔を彼女に近づける。
「ちょっと、アリオスっ! ここどこだと…ン…!!」
こんな抗議でひるむ彼ではない。
青年は、夕方のターミナルで、堂々と妻である少女の唇を深く奪い、味わいつくす。
いつの間にか、少女も知れに応えて、華奢な腕を彼の首に回していた。
唇が離され、少女の唇から甘い吐息が漏れる。
「----美味かったぜ? アンジェ。最高の食前デザートだな」
「もう…、アリオスのバカ・・」
真赤のなって恥ずかしそうに俯く彼女がひどく愛しい。
「さあ、行くか? 俺の子供のためにも、おまえにはいっぱい食べてもらわなきゃな?」
「うん」
彼女は、彼の逞しい腕に華奢な腕を絡めて、彼が車を停めている場所までともに歩き出す。
二人のキスが、他の恋人たちの情熱に火をつけたことを知らずに-----------------