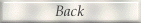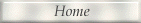REASON TO BELIEVE
後編
一度、壊れたガラスは、元に戻らないの…?
その日、アンジェリークは家には戻らなかった。
取り乱している彼女を一人にしてはおけないと、レイチェルが、自分の家に泊まるように薦めたのだ。
そんなことになっているとも知らないアリオスは、何度も、それこそ数え切れないほど、彼女の自宅と携帯に電話をしたが、一向に繋がらなかった。
「アイツ…、何やってやがるんだ」
電話をして不在のたびに、彼の酒量は重ねられる。
飲んでも、飲んでも酔うことは出来ない。
むしろ虚しくなるだけで、心の空洞がどんどん広がってゆく。
それを埋めてくれるのは、"あの笑顔"しかない。
彼の目に、大事そうにサイドボードに飾られた、赤いヴェルヴェっトの小さな箱が映った。
アリオスはそれを手に取ると、誓うように呟く。
「嫌いといわれても、俺は、おまえを、絶対に離さないから」
レイチェルの部屋に入ってからといううもの、アンジェリークは泣きながら何度も愚痴っていた。
「だって、アリオスが悪いの・・・。アリオスが」
肩を引き攣らせながら、アンジェリークは涙声でレイチェルに語る。
「ったく・・・、自分から"別れる"って宣言しといて、大声で泣くんだから…」
レイチェルの口からは呆れたような溜め息が漏れ、クシャリとアンジェリークの癖のない栗色の髪を撫でた。
「だ…、だって、浮気していたかもしれないのに…!!!!」
アンジェリークは泣きながらああ言ったが、それは絶対無いとレイチェルは思った。
あんなにアンジェリークにメロメロでどうしようもない彼が、そんなことをするはずがないと。
現に、アンジェリークと一緒に出かける日を、アリオスと壮絶なバトルで奪い合っているのだから。
きっと何らかの事情が裏に隠されているのだろう。
知らぬが仏って言うけど…
アリオスの肩を持つのは、少し癪に触るけど、それでもアンジェリークの笑顔を見るためならば仕方ない。
レイチェルは、覚悟を決めて、アンジェリークに微笑みかけた。
「アリオス先生も、その女性のことを言わなかったのは、何か考えがあっただけかもしれないじゃない? 泣いてないでサ、素直に謝っちゃえば?」
「嫌だもん。自分から先には、いや!!」
「意地っ張りなんだから…」
強情を張るアンジェリークに、レイチェルは苦笑する。
「もう、犬も食わないわよ。あなたたちは…」
こっそりとアンジェリークに聴こえないようにレイチェルは呟き、微笑を含んだ視線を彼女に向けた。
いじっぱりのお姫様と、苦悩する王子様の夜は、かくも長く過ぎ行く。
---------------------------------------------------------------------------------------
言い過ぎて、酷い事を言ってしまったと、心の奥底からは思っていた。
しかし、レイチェルにああいってしまった以上は、自分から降りるわけには行かず、アンジェリークは臍を噛んでいた。
真っ赤に腫らした目で学校に行くと、偶然、駐車場から出てきたアリオスにばったりと鉢合わせした。
彼も、彼女同様、昨夜は眠れぬ夜を過ごしたらしい。
少し疲れきった表情が、総てを示していた
一瞬、二人は互いを見詰め合ったが、アンジェリークが露骨に顔を逸らすことで、眼差しの語らいは終わりを告げる。
すっかり俯いてしまった彼女に、アリオスは居たたまれない苦い思いがした。
こんな切ない気持ちになったことは、一度もなかった。
「おはようございます、アリオス先生!」
レイチェルの明るく元気な挨拶も、アンジェリークが笑っていなければ、彼にとって意味はないのだ。
「…おはよう…ございます…」
顔を見ようとしない彼女の力ない言葉と態度は、アリオスの心に深い影を落とす。
「おいアンジェ…」
どうしても話がしたくて、彼女を捕まえようと、彼はその細腕を掴もうとした。
「や・・・」
アンジェリークは体を翻してレイチェルの影に隠れてしまい、露骨に拒否をする。
アリオスにとって、それはなによりも苦痛だった。
顰められた眉、強張った頬。
そして何よりも彼の冴え冴えとした瞳が、衝撃の強さと、怒りの度合いを表していた。
拒絶された以上、ここではこれ以上のことは出来ない。
アリオスは踵を返して、職員室のある校舎へと歩いていってしまった。
その後ろ姿を見つめながら、アンジェリークは大きな瞳から大粒の涙をこぼす。
「泣くなら、あんなこといなけりゃいいのに…」
「だって…」
困ったように眉を顰めると、レイチェルは親友の方をそっと抱いてやった。
-------------------------------------------------------------------------------------------
ショートホームルームはおろか、授業中すらもアンジェリークはアリオスと目を逸らしたままだった。
廊下で逢えば避けられるし、中庭で逢えば逃げられてしまう。
まったく、取り付くしまなどなく、気がつけばこの状態が、一週間近く続いていた。
アンジェリークはすっかりやつれてしまい、表情から笑顔が消え、アリオスはアリオスでいつも不機嫌そうだった。その証拠に、彼は"親衛隊"を近づけようともしなかった。
「何、参ってんだ?」
「ああ、クサレ校医か」
授業中の静まり返った保健室。
この時限の授業がないアリオスは、気分転換がてら保健室のベットに腰掛けていた。
校医のオスカーもその横に腰をかける。
「最近、あのお嬢ちゃんとはどうなんだ? おまえがメロメロの」
オスカーの単刀直入な台詞に、アリオスは自嘲気味に笑うと、ふいに表情に暗い影を落とした。
「アンジェリークに…、泣きながら”大嫌い”って言われて、それ以来口も聞いてねぇ。本気じゃねぇとは思うが、ああ、露骨に、”嫌い”って態度を取られると、こっちの自信が萎えちまう」
「俺もおまえに10000点だな」
「はぁ? んな”オヤジギャグ”ばっか言ってるともてなくなるぜ? いまどきの女子高生にわかるわけねえよ」
「そうか?」
「そうだ」
少しだけアリオスは笑顔を取り戻す。
「----まあ、冗談はこれぐらいにしておくが。お嬢ちゃんが、”大嫌い”とおまえに泣きながら言ったっていうことは、脈はあるぜ? 女は、自分が本当に嫌いな相手にそんなこと言うわけないからな。むしろ、好きな相手に言うもんだからな。"果報は寝て待て”そのうちいいことあるぜ?」
「ああ。----だけどこうなった責任は、おまえにもある、オスカー!!!」
甘さを含んだ笑顔をアリオスはフッと浮かべたが、それを直に引っ込め、オスカーを睨む。
「な、何だよ」
「おまえ、うちのクラスの生徒に、俺が大学に転任することを言ったらしいな? 俺のアンジェはそのことでも怒ってる」
アリオスはオスカーの白衣の胸倉を軽く掴んだ。
「ちょ、ちょっと待って、誤解だ! たまたま、俺がジュリアス教頭とおまえが一年で大学部に転任するのはおしいという話をしたたら…、偶然、聞かれただけだ!!!」
「そうか」
あまりにもあっさりと白衣を離されてしまったので、オスカーは姿勢をぐらつかせた。
「ったく、乱暴な」
わざと息を荒くしていたが、オスカーの瞳はしょうがないとばかりに笑っていた。
「----で、あれはどうした?」
「え?」
「指輪だ。指輪。俺の方の金髪のアンジェリークを指輪選びに貸してやっただろ?」
「喧嘩した日に渡そうと思っていたが、機会がなかったから、そのまま。あの時、俺が大学部に行くことを告げるつもりだった」
アリオスは寂しそうに笑うと、銀の髪をサラッと揺らせて、首を横に振った。
「じゃあ、指輪を強引にでも渡してしまって、仲直りのきっかけにしてしまえよ」
「----そうだな」
手を組んで考えるように、アリオスは宙を見ていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
土曜日の午後は、レイチェルはクラブがあり、アンジェリークは一人、家までの道のりをとぼとぼと歩いていた。
無意識に、アリオスとの待ち合わせに使っていた公園にいつのまにかきていた。
彼と喧嘩をした(一方的に)ベンチが目に入り、自然と涙が出てくる。
後悔だけがこみ上げてしまい、胸が締め付けられるような痛みを覚える。
「ホントは、大好きなのに…」
大きな木の下の、いつものベンチでアンジェリークは腰をかける。
そこから見える風景は、先週と何も変わらないのに、色あせて見える。
アリオスと二人なら、どんな風景もばら色に映っていたのに。
一度壊れてしまえば、もう二度と戻らないの…?"
涙が込み上げてきて、とうとうアンジェリークはその小さな手で顔を覆ってしまった。
「あれ、あなたは?」
可愛らしく温かな声がした。
その声に導かれるように、アンジェリークはゆっくりと顔を上げた。
「ああやっぱり!! アリオスさんの可愛い人ね?」
声の主は、柔らかな金の髪の少女だった。碧の瞳は優しく輝き、その笑顔は、明るく、慈愛に満ちている。
ひょっとして、アリオスと一緒にいたのはこの人かもしれない。
そう思うと、アンジェリークは少し構えてしまう。
「そんなに緊張しないで? 私はオスカーを通じてあなたとアリオスさんのことを知ったの」
少女は優しく笑いながら、アンジェリークの隣へと腰掛けた。
「オスカー先生の?」
「そう!! オスカーは私の恋人で、このあいだ、アリオスさんに頼まれて宝石店に行ったの。年頃の女の子は、どんな宝石が好きかってアドヴァイスするために、ね! 栗色の髪で、青緑の大きな瞳を持っている恋人のためにって…」
少女の言葉に、アンジェリークは息を飲んだ。
だから、アリオスは”言えない"と黙っていたのだ。
今度は、先ほどとは違った意味での涙が、大きな瞳から零れ落ち彼女は両手で小さな顔を覆う。
心からの謝罪の念と、深い後悔の波が押し寄せてきて、胸の奥が痛くなる。
ごめんなさい、本当にごめんなさい…。アリオス!!
「どうかしたの? 大丈夫?」
顔を覗き込まれて、アンジェリークは僅かな力で、首を横に振る。
「いいえ、いいえ。どうもありがとうございます」
もうこうしてはいられない。
アンジェリークはすくりと立ち上がると、金の少女に大きく一礼する。
「有難うございました!!!」
アンジェリークはすぐさま踵を返すと、その場を走り去ってしまった。
彼女の行動に、少女は暫くはあっけに取られていたが、その口元に温かい笑みが浮かんだ。
「これで、オスカーの失敗はチャラよ? アリオスさん」
もう許してはもらえないかもしれない・・・。だけど、一言でも謝ろう。
アンジェリークは、アリオスのマンションへと向かい、彼の部屋のドアの前で、待つことにした。
灰色の冬の寒さの中、彼女は手をこすり合わせて暖を取りながら、ひたすら彼の帰りを待つ。
アリオスは、フェンシング部の顧問をしており、隔週で土曜日は練習があった。
今日はその練習の日だった。
判ってはいたが、はやく彼に逢いたくて、アンジェリークはこの場所で待っていた。
お昼も食べずに、ただひたすら待ちつづけていた。
暫くして、空からは、白いものが降ってきた・・・。
「雪・・・」
----------------------------------------------------------------------------------------
夜もすっかり降りてきた。
アリオスは、独身らしくスーパーに寄ってからの帰宅だったので、彼が帰ってきたのは7時を過ぎていた。
いつものようにエレヴェーターを降りると、自分お部屋の前に、人影が見える。
一瞬、彼は目を疑う。
もしかして、あの人影は・・・。
アリオスは、慌てて部屋の前へと急ぐ。
アンジェリークもまた、薄暗い明りの元に輝く銀色の髪を見つけ、立ち上がる。
「アリオス!」
彼の姿がドアの前に現れると、アンジェリークは尽かさず彼に抱きついた。
「アリオス!! アリオス!!」
「アンジェ・・」
自分の胸にようやく飛び込んできてくれた彼だけの天使を、愛しげに、優しく抱き返す。
「ごめんなさい…、ごめんなさい…、あんな酷いこと言っちゃって!!聞いたのの全部!! あの金の髪の女性から!!」
彼の胸が、彼女の温かい涙で濡らされる。
「もう、いいから」
彼は言葉の代わりに彼女の顎に手をかけると、この上なく優しいキスをした。
「冷えてるな、おまえ。温めてやるから、部屋に入れ」
「ん・・・」
抱きしめられたまま、アンジェリークはアリオスの部屋へと入ってゆく。
リヴィングに入り、ラヴソファに腰をかけると、この時間の隙間を埋めるために、彼らは、どちらからともなく唇を重ねあう。
互いの情熱で互いの体と心を温めるために、深く、激しく口づけ合う。
ようやく離されルト、アンジェリークはアリオスの広い胸に体を預けた。
「待ってろ。おまえに渡したいものがあるから…」
「うん…」
彼は名残惜しげに一旦ソファから立ち上がり、サイドボードに飾ってあった赤いヴェルヴェットの小箱を持ってきた。
彼女の隣に再び腰掛け、その小さな手を取る。
「あの日、本当はこれを渡そうと思ってた。俺がこれをおまえに渡せば、俺はスモルニィを辞めなければならねぇ。だから、最初からの一年契約で終えて、大学の講師として行くことに決めた。学校からは、残れといわれたが、俺はおまえがはやく欲しいから、この結論に達した」
アリオスの優しく、温かな愛を、手を通してアンジェリークは感じる。
「別に、俺は、おまえを”お子様”だなんて思っちゃいねえ。でなきゃ、あんなことスルかよ?」
恥ずかしさと嬉しさがアンジェリークの心にこみ上げ、思わず涙が出る。
「泣くのははやいぜ。俺に一言だけ言わせろよ」
そういった彼はいつもと違い、真摯な光を湛えた視線で彼女を射る。
「おまえさえよければだが…、将来の約束だけでもしてくれねぇか」
心の中にあった、この数日間の苦しみが、涙となって、アンジェリークの瞳から零れ落ちる。
同時に喜びも交じり合う、嬉しいものだ。
「嬉しい!!!」
アンジェリークは返事の変わりに、彼の首に手を回し、抱きつく。
彼も自分の気持ちを伝えるために、激しく抱き返す。
「後3日しても、おまえが、ああだったら、強引にでも指輪を渡そうと思ってた」
「ごめんね・・・」
「もう、いい」
彼は甘さを含んだ艶やかな優しい微笑を浮かべながら、ゆっくりと体を離すと、彼女の左手を取った。
「これをしたら、もう離さねえからな」
「うん」
アンジェリークの左手薬指に入ったのは、彼女の瞳と同じ、青みがかったエメラルドだった。
「綺麗…、ありがと…」
「ああ」
二人はどちらかともなく、抱きあい、唇を重ねあう。
深く、激しく、情熱的に。
唇が離されると、アリオス彼女を抱き上げてベットへと連れてゆく。
「アリオス、晩御飯は?」
「晩メシよりおまえが食べたい。ずっと、おわずけ食ってたんだからな。今夜は帰さねえし、たっぷりかわいがってやるからな」
「も…、バカ…」
翌日、アンジェリークは、体の全身がけだるくて、起きることすら出来なかった。
アリオスも、彼女を可愛がりすぎたのか、同じだった・・・。
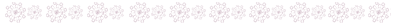
コメント
2500番のキリ番を踏まれたヒナ様のリクエストによる、「TEACHER’S PET」の設定で、「アンジェリークに別れを切り出されて、おろおろするアリオス。だけど最後はハッピーエンド」
話でした。いかがでしょうか、ヒナ様。リクエスト通りに言っているかどうか、若干不安です。
言ってなかったら、tinkの「ゼロブレイク」をかましてください。
作中で、オスカーにこともあろうかオヤジギャグを言わせて見ました。
若い方は多分笑えません(笑)
昔、tinkもまだまだ子供だった頃にやっていた、クイズ番組「クイズダービー」を見てた方にしか判らんねたです。
すみません。反省します。