夕食も終わり、女王ではなく一人の少女として寛ぐ時間がやってきた。
今夜の彼女はどこかそわそわしている。
窓の外から、オカリナを吹く音がして、少女は窓を開けた。
途端に、彼女の顔に満面の笑みが広がる。
「約束通り誘いにきたぜ?」
「アリオス!!」
弾むように響く少女の声。
それもそのはずで、木陰から現れた、愛しい人が階下のバルコニーの下で待っている。
その青年は、女王陛下の禁断の恋人----
厳かな月の光に銀色の髪が照らされて、 神々しくさえ見れる。
「待ってて、すぐに降りていくから」」
「ああ」
窓を閉め、少女はいそいそと青年の元へと駆けつける。
少女の名はアンジェリーク。新宇宙の女王であり、”エレミア”を育てる少女。
青年の名はアリオス。かつて彼女の故郷を侵略した皇帝だった。
2人の禁断の恋は、紆余曲折を経て、今ようやく形になりつつあった。
幸せの形へと----
「アリオス!!」
青年を見つけるなり、その名を愛しげに呼んで、アンジェリークは彼に抱きついた。
咽喉をクッと鳴らしながら、アリオスは彼女をしっかり受け止める。
「おいおい、今何時だと思っていやがる。こんなことされたら、俺の理性が持たねえだろ?」
からかうように笑みを浮かべた翡翠と黄金が対なす瞳に見つめられて、彼女は首まで真赤にした。
「----だって…、逢えたの嬉しかったんだもん…」
拗ねるように言う彼女が、彼はもっと見たくていつも苛めてしまう。
「ほら、拗ねてねえで、行くぞ?」
自然に彼に小さな手を繋がれるのが、ひどくアンジェリークは嬉しかった。
「ねえ、どこに行くの?」
彼女の期待は否が応でも高まり、紺碧の瞳は喜びとときめきで輝いている。
彼女の笑顔を見るたびに、彼は心が澄んでゆくような気がする。
「どこに行くかは、言えねえな」
「もう! 意地悪!!」
体をついっと捩って頬を膨らませる仕草をするが、その目は笑っている。
「ほら」
彼は忍び笑いをすると、力強く彼女を引っ張り、目的の場所に導いてくれる。
その力強さが、彼女には心地よかった。
もっと強く引っ張ってもいいよ…、アリオス
「うわあ!! 行きたかったの!!」
目的の場所に着くなり、少女は感嘆の大声を上げた。
そこは日向の丘----
湖を望めるその場所は、夜になると星と月の光に照らされて、とても幻想的な雰囲気になる。
「おまえ。こういううの好きだろ?」
「うん…、けれどね、アリオスと一緒に見れば、もっともっと感動できるの」
純粋な瞳に見つめられて、彼は温かな微笑を彼女に送り、その想いに応えた。
「今日は恋人同士でいっぱいね…。私たちもそう見えるかしら…」
少し恥らいながら、うっすらと頬を桜色に染めて囁く少女が、 彼は可愛くてしょうがない。
少しからかってみたくなり、彼にうっすらとよくない微笑が浮かび上がる。
「アリオス?」
「こうすりゃあ、誰でも俺たちが恋人同士だと思うぜ?」
「え!?」
瞳を大きく見開いたときには、もう間に合わなかった。
長身の彼は少し身体を屈めると、そのまま掠めるような、羽根でも触れたような口づけをした。
「…バカ…」
甘い囁きが、彼を咎めるように漏れるが、その響きは彼を高まらせても、決して罪悪感を感じさせない、甘い砂糖菓子のようなもの。
「行くぜ? ここよりもっといい場所があるからな」
「うん、連れて行って」
彼の手をしっかりと握り返して、彼女は彼の後を着いてゆく。
ずっとこうしていたいな…
それは小さな彼女の願い。
彼もその小さな手を通じて感じ取り、握り返す。
自分も同じ気持ちだと----
アンジェリークは、突然、可愛らしいくしゃみをして、身体を震わせた。
「おい、大丈夫か!?」
「うん、へいきらよ」
言いながらも、彼女は寒そうに身体を抱きしめる。
「ったく、平気じゃねーじゃねーか」
言葉が乱暴でも、その行動が優しいのがアリオスのいいところ。
彼はすぐに、着ていた革のブルゾンを脱ぐと、それをぶっきらぼうにも彼女に差し出した。
「着ておけ」
「え…、でもそれじゃあアリオスが寒いわ」
躊躇いがちにアンジェリークは眉根を寄せる。
「ヤローがそんなこといちいち気にするかよ!? ほら、とっとと着ろ。風邪ひくぞ?」
「…うん…、ありがと…」
彼女は嬉しくて堪らなくて、ほんの少しだけ涙ぐみながら、ブルゾンに袖を通した。
「ふふ、ぶかぶか、だけど暖かい…」
「これで風邪をひかねえだろ?」
「うん…。何だかアリオスに抱きしめられてるみたい」
愛しげに呟く彼女の仕草が、彼を魅了して止まない。
「だったら、ホントに抱きしめてやるぜ?」
飄々とした口調に、彼女はすっかり照れてしまって、俯いてしまった。
アリオスに手を引かれて、湖が一番美しく見える場所でありながら、人気のない、茂みに囲まれた場所にやってきた。
「ここが一番綺麗に見える場所だ」
「何が…、あっ!!」
言いかけて、アンジェリークは驚愕の声を上げた。
「どうした!?」
「----あのね・・・、レイチェルとエルンストさんが・・、あっ、こっちに来る!!」
親友とその恋人を見つけて、彼女はすっかりうろたえてる。
「しょうがねーな!! こっちだ}
彼に強引に手を引かれて、そのまま茂みの中へと連れ込まれ、身体を押し倒された格好になった。
「きゃっ!!」
連れこまれた茂みは、真の闇で何も見えず、彼女は小さな悲鳴を上げる。
丁度、狭い茂みの中で、彼に組み敷かれた格好になった。
彼の息、鼓動、暖かさ。
それら全てが近く感じる。
「おい、声を上げんなよ。見つかってしまうぜ?」
彼の声は焦りなど全くなく、楽しそうに響いている。
それが彼女には癪に障る。
「アリオス、見つかったら、あなたが困る…っ…ン…!!」
彼に深く唇をふさがれて、彼女は甘いと息を漏らす。
彼の唇は、彼女を宥めるように愛撫し、吸い上げ、舌が歯列を割ってゆく。
「…うん…」
甘い吐息と共に、彼の舌が彼女の口の中を愛でるように優しく動き回る。
彼女は、いつの間にか、彼の首に腕を回していた。
「ねえ、エルンスト、何か音がしなかった?」
「大丈夫ですよ、レイチェル。私がついていますから。さあ、行きましょう」
「うん!!」
補佐官とその恋人の声が遠ざかり、アリオスはようやく唇を離した。
「あ…」
それと同時に切なげな吐息がアンジェリークの口から漏れ、視線は彼の形のいい唇を追い求める。
「行ったぜ? おまえの親友とやらは」
彼は自分も起き上がりつつも、彼女をそっと抱き起こす。
「ありがと…」
今は恥ずかしくて、それ以上は言えない彼女だった。
彼に手を貸してもらって立ち上がると、再び手がつながれ、彼は彼女を導く。
「さっきの騒ぎで、いい時間になったみてーだ。茂みの前に腰を降ろすか」
「うん」
2人は仲良く腰を降ろして、夜空を見上げる。
アリオスはアンジェリークの華奢な肩を抱き、彼女は彼の胸に頭を凭れさせて、甘えた。
「もうすぐ、降りてくるから、しっかり見てろよ?」
「何が!?」
「秘密だ」
「もう!!」
甘いやり取りを続けながら、二人は夜空から目を離さなかった。
-----やがて。
星降る夜空に、七色のカーテンが下りてきた。
神聖にも神々しく輝くそれに、アンジェリークは魂の底から感動が込みあがるのが判る。
これを見に連れてきた彼が愛しくて、また嬉しくて、大きな紺碧の瞳からは大粒の涙が、幾筋にも流れた。
夜空に何よりも光り輝く存在はオーロラ。
彼との思い出が、大切な想い出が詰まった、彼女にとってはこの世で一番素晴らしい自然現象。
「…アリオス…」
感極まった彼女は、彼の名前を涙声で囁くことしか出来ない。
「アンジェ…」
そっと彼女の涙を唇で拭い、甘い口づけを何度も繰り返して、想いを伝える。
「女王陛下の計らいでオーロラが見れるお祭りがあると聞いて、おまえを誘ってやりたかった。"夜想祭”というらしいぜ。
オーロラは…、俺たちにとって思い出が詰まったものだからな。
----だから、見せてやりたかった…」
力強く彼女を抱きしめるアリオスは、彼女を離そうとしない。
彼女もまた、彼の思いに応えるべくその華奢な腕を彼の身体に回す。
「有難う…、大好きよ…」
「愛してる…」
心地いいテノールの甘い囁き。
アンジェリークはその声に酔いしれながら、何時までも彼の腕の中で、オーロラを見つめていた----
アンジェリークが帰宅したのは、もう深夜が近い時だった。
アリオスがちゃんと部屋まで送り届けてくれた。
レイチェルは幸いなことにまだ戻っていない。
きっと、今夜は帰ってこないだろう。
「じゃあな。アンジェ、また、"約束の地”に遊びに来い。仕事がヒマだったら、遊んでやるから」
「うん…、今日は有難う…」
そう云って、彼女はそっとアリオスに手招きをする。
「何だ?」
彼が屈んだところで、彼女はそっと彼に口づける。
「アンジェ…」
「今日のお礼…、ね?」
上目遣いではにかみながら、彼女は彼を捕えて離さない。
このままじゃ帰りたくなくなるじゃねえか…
彼は甘い微笑をフッと彼女に浮かべると、頬に軽い口づけを落した。
「----今度は、茂みの続きをしような」
耳元で囁かれて、アンジェリークは瞬間湯沸し器のように顔を真赤にさせる。
「…今度ね…」
何とか耳を凝らして聴こえるように囁く彼女に、彼は咽喉を鳴らして笑う。
「期待してるぜ?」
ウィンクして微笑む彼に、彼女はしっかりと頷いた。
「あの、ジャケットありがと…」
「ああ」
名残惜しそうに彼女は脱ぐと、彼にそっと差し出す。
「ああ」
受け取った彼は早速袖を通して、満足げに微笑んだ。
「おまえの匂いがするな…、いい匂いだ…」
「もう!!」
抗議しても、彼は飄々と笑うだけ。
「じゃあそろそろ行くぜ? 親友とやらに見つかったらヤバイだろ? またな?」
「うん…、またね…」
彼が部屋を出て、階段を下りてゆく音がする。
彼女はそれを聞きながら、幸せな気分に何時までも漂っていた。
アリオス…、今度…ね?
2人の願いがかなえられるのは、もう少しだけ先の未来。
オーロラだけが知っているのかもしれなかった----
NIGHT ESCAPE

コメント
4010番のキリ番を踏まれたれな様のリクエストで、「トロワな2人の夜のデート」です。
「Special2」風の暗闇にドッキリ編も少し入れてみましたが、いかがでしょうか?
久しぶりの、SWEETなSIDEにかいてて楽しかったです。
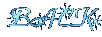
![]()
![]()