My Fair Lady X2 ぷらす
二人揃って疲れたような表情で、明後日方向へと視線を向ける。
周囲の人々はそんな二人の様子に気付いた風もなくわいわいと歓声を上げ、横を通り過ぎていった。
場所が場所なら二人は目立つ存在だった。
それも二人並んでいるとなおさらだ。
均整の取れた長身と、モデルにもなれそうな顔立ち。闇を集めたような黒髪と、月光を集めたような銀髪を持つ、二人の青年。
見る人が見れば、彼らが双子であることが判るだろう。
ただしこの二人、どうもこの場の雰囲気に馴染んでいない。
それは彼らも感じているらしい。
兄----レヴィアスが言った。
「遊園地だな」
弟、アリオスが頷く。
「遊園地だな」
全く感情が篭らない…というか、完璧に棒読み状態のセリフに近彼らの心中を察していただきたい。
いったい何が哀しくて、もうそろそろ三十路に近い(笑)というのに、男二人、しかも兄弟と遊園地なんぞに来なくてはならないのか。
いやいや、どちらか一人がいなければ、今の気持ちは全く違ったものになっていただろう。
しかし現実はそうはいかない。
ここが遊園地であるのは現実だし、横に双子の片割れがいるというのも現実だった。
「お兄ちゃんたち----! 早く早くっ!」
少しはなれた場所で、『妹』が嬉しそうに二人を呼んだ。
とりあえずは----行かなければいけないらしい。
ことの始まりはこうだ。
今を去ること数日前。(そんな大層な表現をするようなものでもないが)
ひょんなことから、CGデザイナーをしているアリオスに休暇がおりた。
無理に会社に行かなくていいという職業ではあるが、ぽっこと休みが取れるのは珍しい。
押し迫っている、仕事も別になかったので、アリオスはひとつの計画を練った。
それは幼馴染兼、想い人であるお隣の少女とデートをしよう、というものであった。
…別に計画を練るというほどのものでもないのだが、彼の場合、バレると拙い人間が居るのだ。
人の恋路を邪魔するような奴が少なくとも二人。
どこの誰とはいわないが、双子の兄とか、少女の親友とか(言ってるって)
というわけで、アリオスは少女を誘うのに細心の注意を払った。
もちろんどこの誰とはいわないが、兄に知られないように少女が通う学校の近くで待ち伏せて、二憎たらしい親友に見つからないように、親友が委員会で遅くなる日を選んだ。(…だから言ってるっつーに)
そしてそれらは功を奏し、アリオスはひとりきりの少女を捕まえることに成功したのだった。
「今度の日曜ヒマなんだが、どっか行かねぇか?」
「いいの?」
顔を綻ばせ、嬉しそうに声を上げる少女----アンジェリークを見やり、アリオスは唇を笑みの形に軽く持ち上げた。
「ああ。どこでも好きなとこ連れてってやるよ。どこがいい?」
「うーんと、ね、じゃあ…遊園地がいいな」
「…遊園地、ねェ…」
----色気のない場所である。
自分にそういう場所が似合うわけがないのだが、『どこでも』と言った手前いやだと言うことも出来ず、アリオスは僅かに眉を寄せる。
「…だめ…、かな?」
青年のためらいを敏感に感じ取ったのか、アンジェリークは少し肩を落した。
「いや」
彼は苦笑いしつつ首を振る。
似合わないのは事実だが、彼女と二人なら楽しいこともあるだろう。
「いいぜ。連れてってやるよ」
「わぁ、ほんと? じゃあ一緒に行こうね、アリオスお兄ちゃん!」
「クッ、はいはい、『一緒』に、な」
…これで大丈夫だと、彼は思っていた。
いや、実際のところ、兄や親友にばれないように色々根回しもしたのだが、どうやら考えが甘かったらしい。
それはもう、ぜんざいに団子の代わりにマシュマロを入れ、上から砂糖をまぶし、更にトッピングをしたハチミツの上にマロングラッセを飾り立てた(…まずそう)のではないかというぐらい甘すぎた。
とにもかくにも、いったいどういう理由で今日のことを知ったかは知らないが、双子の兄が自分の横の居るということはどうひっくり返っても事実だった。
…もっとも、例の親友がいなかっただけ少しはマシかもしれない。
「お兄ちゃーん」
明るい声が二人を呼ぶ。
ぱたぱたと嬉しそうに走ってきたアンジェリークは、あろうことかレヴィアスに抱きついた。
いや、彼女一人しか居ないのだから、抱きつくとなればどちらか一人になることは仕方ない。
アンジェリークには大した意味もなく、レヴィアスがアリオスより前にいた、という理由なのだろう。
その程度のことは分かっている。分かっているが…。
『ひくっ』などと可愛い表現などではなく、『ぴきっ』と言った感じでアリオスの顔が引き攣る。
理性が理解していたとしても、感情がそれについていかない。
手に持っているコーヒーの缶がカタカタと小刻みに揺れる。
そもそも今日誘ったのは自分であって、レヴィアスはただ単に付いて来ただけではないか?
言ってみれば『おジャマ虫』だ。
それがどうして、自分を差し置いてアンジェリークと笑い合ってなどいるのか。
ギシリと歯軋りをした時、ふとレヴィアスがこちらを振り向いた。
そして、勝ち誇ったようにフッと笑みを浮かべる。
ばきゃっ。
手の中の缶・・ちなみにスチール缶だ・・が音を立ててつぶれた。
背後で殺気立った視線を送ってくるアリオスを見やり、レヴィアスはふふんと鼻を鳴らした。
兄であるこの自分を差し置いてアンジェリークと二人っきりで出かけようなどと、片腹痛いというものだ。
第一誰がそんな事を許すものか。
まるで少女の父親のような気分でそんな事を思いつつ、彼はささやかな優越感に浸っていた。
周囲にある自分とは異質な世界・・主に親子連れだとか、高校生ぐらいのベタベタカップルだとか、あとはあまりにもファンシーすぎるアトラクションだとか・・はもはや完全にレヴィアスの思考からは除外されていた。
腕に絡み付いてくるぬくもりと、向けられる笑顔が今の彼の世界全てだ。
…背後に何かがつぶれるような音がしたような気もしたが…はっきり言ってどうでもうよかった。
----が。
天国というものは余り長く続くようなものではないらしい。
地獄はすぐにやってきた。
アンジェリークが指差したアトラクションに、レヴィアスとアリオスは動きを止めた。
真っ白な目でそのアトラクションを見やる。
視界の中で、子供が好きそうなおうまさんやらかぼちゃの馬車やらが上下に揺れながら回っている。
遊園地の定番。
子供の憬れ。
だが大の男には少々無縁なもの(…というか無縁にしたい)
それは。
----めっ、めりーごーらんど!
一瞬雷のような閃光が二人の脳裏に閃いた。
刹那、本当に僅かな間ではあったが、兄弟揃ってメリーゴーランドの馬に跨り、『あはは』 『うふふ』と笑う自分たちの姿を想像してしまった。
なぜそんなモノを想像したのか彼らも全く理解不能だが、混乱しているときの人間の思考などしょせんそんなものだ。
まさに少女漫画の世界。
バックに花が咲き乱れていても何らおかしくはない。
二人が気絶しなかったのは、ひとえにプライドのお蔭だった。
好きな女の前でぶっ倒れるなど、いくらなんでも恥ずかしすぎる。
しかし…、さすがに、さすがにこれだけはエンリョしたい。
だが、こともあろうにアンジェリークはこう言った。
「一緒に乗ろう、お兄ちゃん」
あまりにも無邪気にそう言う。
そしてだからこそタチが悪い。
いつもは愛らしいその無邪気さが、今はなんだか憎らしかった。
彼女にしてみればせっかく来たのだから、楽しい思い出を創りたいということなのだろう。
その気持ちはかなえてやりたいと思うし、そうしてやりたいのも山々だ。
だが、だからと言ってこれは…
「だめ…?」
少し悲しそうに蒼の瞳を翳らせ、アンジェリークが二人を見上げる。
「…いや、えーと…」
乗りたくはないっ! だがどうしてもいやだと言えないっ。
その時、無意識にジャケットのポケットに入れたアリオスの手が、何か硬い物に触れた。
「……!」
その正体に思い当たり、彼はニヤリと唇を歪める。
「アンジェリーク」
勤めて平静を装いながら少女に声をかける。
「俺はここにいるから、レヴィアスと一緒に行けよ」
「なっっ!」
「え…」
驚愕した兄の声と、戸惑った少女の声が重なる。
「どうして…、アリオスお兄ちゃん、そんなに嫌なの?」
…きっぱりと嫌だったが、そのことはおくびにも出さず、アリオスはポケットからそれを取り出した。
今やすっかり常識となったインスタントカメラだ。
一応持っておいたほうがいいだろうと言うことで、入場券を買う時についでに購入したのだが、まさかこんなところで役立つとは思ってもみなかった。
「記録係がいるだろ。な?」
それは単なる言い訳であることなど、一目瞭然である。
「っっ、アリオスッ、おまえっっ!」
「…何だ、レヴィアス」
クッと口の端を釣り上げ、目を細める。
「イヤなのか?
…イヤなワケがねぇよなぁ? なんつったってアンジェリークの頼みだもんなぁ?」
ククッと笑うその顔は悪魔そのもの。
ぐっと言葉に詰まるレヴィアスに、アンジェリークは期待でいっぱいの視線で追い討ちをかける。
----嫌だなどと、言える筈もなかった。
一体どんな写真が撮れたのか、とりあえずそれはレヴィアスとアリオスの秘密である。
黄昏時が迫り、園内に明りが灯される。
闇を知らないかのように、周囲が色とりどりの光に照らし出された。
観覧車に乗り、それを遥か上から見下ろしたアンジェリークが嬉しそうに声を上げる。
「見て、見て、すごくきれぇ…」
まるで幼い子供のように歓声を上げる少女に、二人は僅かに苦笑した。
少女の笑顔が好きだった。
真実、心の底から護りたいと思う。
無邪気で、言ってしまえば子供っぽくて、けれど日を追うごとに確実に成長している『妹』
それが嬉しくもあり、不安でもあり。
いつか時が来た時に、彼女の隣にいるのが自分であれば言いと願いながら、二人は少女に倣って夜景へと視線を移した。
不確かな未来を映し出すかのように、地上の光がゆらゆらと揺れていた。
「…ったく、今だけだからな」
帰宅途中の車内で、アリオスは僅かに不機嫌そうに呟いた。
後部座席ではレヴィアスに凭れかかり、アンジェリークがすやすやと寝息を立てている。
免許を持っているのが自分だけなどでなかったら許しはしないが、実際のところ自分しか持っていないのだから仕方ない。
レヴィアスは僅かに微笑を漏らす。
「そう怒るな。アンジェリークが起きる」
「…それもそうだな」
少女の寝顔をちらりと見やり、アリオスもまた小さく微笑んだ。
「おやすみ、アンジェリーク」
静かに囁かれた言葉はレヴィアスのものだったのか、アリオスのものだったのか。
眠りの淵に漂う彼女に判別できるはずもなく、ただ少女は、ほんの少しだけ嬉しそうに笑った。
THE END
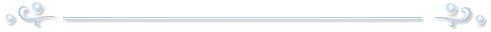
FROM tink WITH LOVE
空山樹様から頂いた、とっても素敵な『アリオス、レヴィアス双子話』です。
この二人の、アンジェリークを思う優しい気持ちがとてもすきです。
私にわがままを聞いてくださいまして有難うございました。
空山さんは現在「へのへのもへじ」というサークルをお持ちになっていらっしゃいます。
大阪のインテックスのイベントにご参加されていますので、もしお見かけになった方は、覗いてみてください。
とっても素敵な同人誌が購入できますよ!
また、今回のお話の同人誌も実は出されていて、私がこの本が大好きなので、お願いしました。
空山様、本当に有難うございました。

