初形について
詰将棋に初めて触れてから20年以上がたつ。最初は3手詰も解けなかったが、全盛時(?)には
20手くらいまでの詰将棋なら
多くは解くことが出来た。今もその気になれば一桁の手数ならば なんとかなるだろう。・・・・・たぶん。
解くことが出来る範囲はその時々でかなり変わってきたが、詰将棋に対する時に抱く違和感は20年前とあまり変わりない。
その違和感とは「初形におけるあたり駒の多さ」にある。どのような過程を経てその局面に至ったかがまるで分からないのである。
「実戦型」をうたっている詰将棋の本でも、どこが実戦形なのかと問い詰めたくなるような詰将棋が少なくない。
このような場合、他人の作品を用いるわけにいかないので、自作を例にとると・・・(図は「10=『3×3』+1」より)。
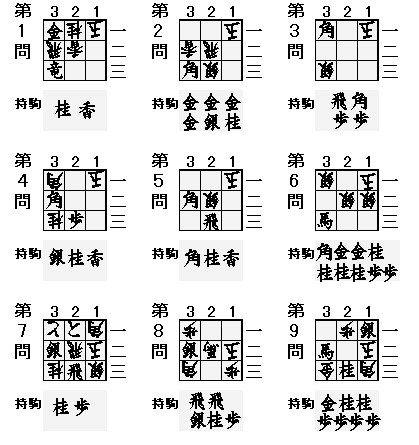 第2問から第6問までは攻方の駒に対してあたりになっている玉方の駒は
第2問から第6問までは攻方の駒に対してあたりになっている玉方の駒は
ゼロか1枚で無理がない。例えば、第6問は▲3三馬(角成)の王手に
△2二銀打と受けた局面と考えれば自然である。
そのほかの初形はあたりになっている駒が複数あり、ややこしい。第1問では
攻方の3三竜に対して、あたりになっている玉方の駒は2一桂と3二飛の二枚で、
さらにその3二飛に対し、攻方は3三竜と3一金の2枚の駒で取ることが出来る。
では、第1問の直前の玉方の一手は何か? この場合は攻方の3二の駒
(角・金など2一にきいている駒)を飛車で払ったところで、3三桂と竜をとると
▲1三香以下詰まされるのでやむをえず△3二飛とした、と一応説明はつく。
第8問は▲2二歩成△同馬、第9問は3三の攻方の駒を△3三金と取った局面と
することはできるが、それ以前の流れが分かりづらい。特に第9問の2三桂、1一銀
などは筋悪もいいところで自然な逆算が難しい。
きわめつきは第7問で、これはもう正気の沙汰ではない。
少し前に△3二と、△2三飛とすれば全然詰ましようがないし、そもそもこの初形に
なるには少なくとも、2一とが既にいる局面で1一角・2二飛を打ったか、攻方のと金が
2一に迫ってから玉方はと金を3一に動かしたか、のいずれかでなければならない。
(それ以前に3一とは何だ?という話は別として・・・)
第7問は実戦型ではないし、ちょっと極端すぎる例だが、実戦でこの玉方のような
危機感ゼロのおめでたい指し回しを見せる人、それに付き合って劇的な局面の演出に
協力してあげる人は残念ながら(?)いないだろう。
詰将棋は指将棋とはまったく違ったパズル、作り物であり、求められるのは解(「初形以後」の作意とされる手順)の一意性である。
初形も作品の総合的な評価には含まれるが、そこにどうやって至ったか、「初形以前」については当然のことながら、問題とされない。
しかし、詰将棋を始めた動機が「指将棋(終盤)に強くなるため」だったために、未だに別のものと割り切れないでいる。そんなわけで、
ごくたまに詰将棋を解こうと思い立っても、一目で解けない不自然な初形の詰将棋を見ると、駒を取って必至をかけること(第1問なら
▲3二竜)ばかり考え、見つかると一人満足してしまう今日この頃である。
「詰将棋で鍛えた終盤力を武器に一手違いのすれすれの将棋を勝ちきる」という理想にはなかなかたどり着けそうにない。