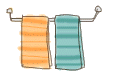例えば麻薬。
それは決して手を染めるべきでない代物だと私は知っているし、
身体や精神、そして心に毒だということも理解できている。
ましてや世間は、どんな理由があろうとそれに逃げ込んだ人間を許さない。
それは、小さな犯罪でも罪は罪だという観念以前に、
実は誰もがその人間の「弱さ」を責めているからだろうと思う。
それ故にその「弱さ」には、誘惑がつきものだったりする。
開けてはいけないパンドラの箱。
きっと恐ろしいものが存在するに違いないと私は震えてそれを見つめる。
そして得体の知れないものに怯えながら、いつしかそれから目が離せなくなる。
私は恐る恐る、その箱に手をかける。蓋の上で行ったり来たりと指を迷わせる。
この好奇心はどこから湧いてくるのだろう。この胸は何故こんなにときめいているのだろう。
そう思いながら私は自らの「弱さ」を初めて言葉にしてみた。 「少しだけなら」
でもやはり、そこには罪の意識などなかったのだ。
ずっと聞きたい事があった。
だけどそれを口にするには、私は少しばかり彼を愛し過ぎていたし
彼は少しばかり、私以上に守らなければならないものが多すぎた。
昔、恋に傷ついた友人が、フとこんなことを洩らした。
「私は惨めな女だ。でもどんなに惨めでも、私はあの人を諦められない」
確かに彼女の愛情は惨めに踏みにじられたものだったのかもしれない。
しかし心が自由だ。酷い現実とさえ同化してしまえる許容を、その心は既に手に入れている。
それに比べて惨めさを鼻から放棄している私のこれは一体何だろう。
不自由だ。自由な愛情が、私の心を不自由にしてしまう。
それはまるで排泄物を無理やり塞き止められてしまうような、そんな不快感にも似ていた。
彼は雨を好んだ。本降りになる一歩手前の、シャワーを道に浴びせるような雨。
私は雨が嫌いだった。そして窓の外に気を取られる彼のその横顔も。
私は耐えきれずボリュームを上げる。彼を雨に盗られてしまわないように。
雨の向こう側に浮かぶ存在に決して盗られてしまわないようにテレビのボリュームを上げ続ける。
「聞こえないの?」 少し心配げに彼は言う。
ううん、逆なの。全て私に聞こえてしまうから、聞こえてしまわないようにボリュームを上げただけ。
そう言いかけた唇を歯で噛んだ。堪えた言葉は今にも涙腺から漏れ出そうとしていた。
雨がノスタルジィを連れてくることを、子供の頃に知った。
彼が雨を好む理由。私はその答えさえ、もうそんな昔に理解してしまっている。
殺してしまってもいい?殺したいの?ううん、死なないで欲しい。だったら何で?
好きだから。好きだと死んで欲しくなるの?ううん、生きて欲しい。だったら何で?
例えばあなたが私を可愛がるでしょ?うん。それが私の首を絞めていることだとしたら?
俺が首を絞めてるの?そう、とても苦しい。可愛がっているつもりが首を絞めている、か。
それを知った時あなたはどうする?手を離すね。そういう風に別れたいの。つまり?
私の為だけに手を離して。苦しみを取る為に?そう、この苦しみをあなたも知るべきだもの。
嫌だと言ったら?やっぱり殺してしまうかも。俺を?ううん、私のことを。どうして自分を殺すの。
そんな苦しいことをする手まで許してしまいそうな気がするから、それがどうしても許せない。
それは空虚以外の何者でもなかった。
美味しいところだけをスプーンで穿りつくされ、残された部分。
彼と離れたこの世界は、まるでそんな乾いた殻のようにも思えた。
なのに季節は知らん顔で、こうして緑を芽吹かせ、生き物達の目を覚ます。
公園の隅に捨てられた空き缶。そこから流れ出したオレンジ色の濁ったジュース。
その甘い液体の中にプカリと浮かぶ溺死した黒い蟻が、風に押されて揺らめく。
とても美味しいその液体に窒息しながら死んだこの蟻は、幸せだったのだろうか。
私が彼を許してしまいそうだったように、これで死ぬなら本望だと思えたのだろうか。
この蟻は私だ。甘く大好きなものに苦しみながら殺される、満腹で幸せだった頃の私。
そうしてあの日を思い出すことを自分に許した瞬間、私は初めて泣いた。
恐れていたものの正体。それは生身の自分自身だったのだ。
「私は惨めな女だ。でもどんなに惨めでも、私はあの人を諦められない」
そういう風に彼を愛したかった。苦しさまで全て、愛情の糧にしてしまうぐらいに。
こんなに無我夢中で人を愛している自分を認めてしまうことを恐れた。
不様な自分を認めるなんて許せなかった。そして晒しきれない自分のまま、彼を手放した。
声を出して泣こうとしたのだけれど、呼吸はその悔しさに追いついてなどくれず
痙攣を繰り返す器官は、だらしなく私の息を乱し続けるだけ。
ずっと聞きたいことがあった。「私達に未来はあるの」 そう聞いてしまいたかった。
こんなにも世界が空虚なのは、彼を愛したからじゃない。
愛した事実さえも証明できずに逃げた、私の不自由な心こそが空虚なのだ。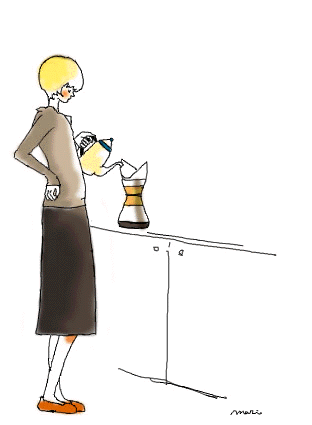
「どこか具合でも悪いんですか?」
しゃがみ込み嗚咽を殺す私を見つけた主婦が、心配そうに声をかける。
「心が」と私は口の中で呟き、そして静かに首を横に振った。
甘い水が欲しい。それが正しくないとわかっていてもそう思わずにはいられない。
私は溺死したその幸せな蟻を、流れる涙もかまわず、虚ろに眺め続けた。
長く、長く。まるで自分自身の死体を慈しむかのように。