須賀敦子さん
平成10年3月26日、69歳で癌のために静に旅立たれた須賀さん。
文壇にデビュー後わずか10年のことでした。
若い頃にフランス、イタリアに留学し、
イタリア人ペッピーノ氏と結婚しながらも結核で亡くし、
その結婚生活はわずか5年という短いものでした。
イタリア時代には日本の文豪、川端康成、谷崎潤一郎をイタリア語に翻訳し、
日本に帰国後はイタリアの詩人・ウンベルト・サバの詩や
ナタリア・ギンズブルグの文学を翻訳して日本に紹介なさった須賀さん。
きっとそういう素晴らしい作品を翻訳するなかで、
須賀さんは自らの文体を獲得なさったのだと思います。
20年以上の歳月を経た後にやっと語られた
彼女の家族、友人の思い出の数々。
彼女によって選ばれた詩的な言葉や文章は
読む者の乾いた心に清水のようにしみわたっていきます。
彼女が愛した人々と同様に霧の向こうの世界に行ってしまった須賀さんの
素敵な作品を少しでも紹介できたらと思います。
new 遠い朝の本たち (ちくま文庫)
「しげちゃんの昇天」
「父ゆずり」
「ベッドの中のベストセラー」
「本のそとの[物語]」
「[サフランの歌]のころ」
「まがり角の本」
「葦の中の声」
「星と地球のあいだで」
「ひとひらと七月の蝶」
「シエナの坂道」
「小さなファデット」
「父の鴎外」
「クレールという女」
「アルキビアデスの笛」
「ダフォディルがきんいろにはためいて・・・」
「赤い表紙の小さな本」
人は誰も 幼い頃に出逢った本がある。
親に隠れて布団の中で読んだ本、誰かからプレゼントされた本、
学校の図書館に足繁く通って題名に誘われて読みあさった本、
買い与えられた少年少女@@@全集より親の本棚に並んでいた本に興味を持ったり…
出逢いは様々で その時どれだけ内容を理解して読んでいたのかはわからない。
夢多き思春期のころに読み、知らぬ間に自分の血となり肉となっていた本もある。
須賀さんにも「壁につきあたって先が見えなくなるたびに、
羅針盤のようにして自分が今立っている地点を確かめた」本があった
『建築成った伽藍内の堂守や貸椅子係の職に就こうと考えるような人間は、
すでにその瞬間から敗北者であると。それに反して、何人にあれ、
その胸中に建造すべき伽藍を抱いている者は、すでに勝利者なのである。
勝利は愛情の結実だ。・・・・知能は愛情に奉仕する場合にだけ役立つのである。』
「星と地球のあいだで」から…サン・テグジュペリ「戦う操縦士」(堀口大学訳)
彼女は常に心の中に伽藍を建てるために闘っているかを自身に省みていたのだろう。
はたして私は心の中に伽藍を建てようとしているのか…
私は彼女の著書を読むたびに 必ず彼女の亡くなった夫君への想いを感じる時がある。
それは彼への想いを直接書いたものではない。
けれど、それはどうしてもぬぐい去ることのできない悲しみであったり
一方でその死を受け入れて生きていこうとする彼女の想いを感じる文章だったりする。
『さようなら、とこの国の人々が別れにさいして口にのぼせる言葉は、
もともと「そうならねばならぬのなら」という意味だとそのとき私は教えられた。
「そうならねばならぬのなら」。なんという美しいあきらめの言葉なのだろう。』
「葦の中の声」から…アン・モロウ・リンドバーグのエッセイより
彼女は中学生になったばかりのころにこの文章を読んで
「自国の言葉を外からみるというはじめての経験に誘い込んでくれた」といい、
またそれは、自分の中で「なにかが化学変化をおこしてしまうような
ひとつの<重大事件>にひとしいほどのめざましい文章だった」とも語っている。
これは私の全くの独りよがりの考えなのだが、おそらく須賀さんは夫君との突然の別れの後
その不条理な別れを受け入れられなくて、しばらく彷徨われたのではないか
その時に…そうだ、私の国には「さようなら」という言葉がある…
と想いだしたのではないか。そんな気がしてならない。
なお、本書は須賀さんが病床にあって最後まで推敲を重ねていらした一冊だとのこと。
よって刊行は彼女が亡くなった後となった。
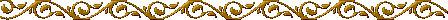
トリエステの坂道 (みすず書房 500円)
「トリエステの坂道」
「電車道」
「ヒヤシンスの記憶」
「雨のなかを走る男たち」
「キッチンが変わった日」
「ガードのむこう側」
「マリアの結婚」
「セレネッラの咲くころ」
「息子の入隊」
「重い山仕事のあとみたいに」
「あたらしい家」
「ふるえる手」
本書のほとんどは、須賀さんの夫、ジュゼッペ(ペッピーノ)・リッカとその家族、
親戚の人達を描いた回想的エッセイです。
しかしながら、いわゆる記憶を辿って私生活を書き綴ったエッセイではなく
20年以上たってもなお彼女の中に残る記憶の断片をモチーフにしつつ
彼女の詩的な表現力で小説のように描かれる不思議な作品です。
そんな彼女の文章は泣きたくなるほど悲しいのに、何故か温まる感じがして
渇いた心に水をやりたいとき聞きたくなる音楽のように、私を癒してくれます。
…トリエステ…
「ユーゴスラヴィア[クロアチア]の内部に、細い舌のように食い込んだ
盲腸のようなイタリア領土。そのまた先端に位置する」
夫ペッピーノと須賀さん自身が愛して止まなかった詩人、ウンベルト・サバの故郷。
この地を、11年間に及ぶイタリア生活を切り上げて日本に帰国したのち、
まるでペッピーノとの想い出を確かめるかのように、須賀さんは初めて訪ねます。
そんな「トリエステの坂道」を辿ることによって、ユダヤ人の母とイタリア人の父の間に生まれ、
また、フィレンツェとウィーンのふたつの文化が交錯する町に生きることによって
絶えずふたつの世界を意識しなければならなかったサバと須賀さん自身が重なっていきます。
そしてそれはまた、遙かむかし同じイタリアのミラノでの、夫の家族達との生活
次々と降りかかる不幸を運命づけられたかのような家族の貧しい生活を
「ながいこと使ってなかった時計をあわせるように」、しかし愛情をもってたぐりよせることにもなるのです。
最後におさめられた「ふるえる手」は、そんな彼女が道標とした作家のひとり
ナタリア・ギンズブルグとの思い出を語ることによって、またギンズブルグの文章から
彼女の文体の拠り所がプルーストだということに気づいた須賀さんによる
須賀さん自身の文体宣言でもあると思うのです。
「好きな作家の文体を、自分にもっとも近いところに引き寄せておいてから、
それに守られるようにして文体を練り上げる」
そしてギンズブルグを思い出すきっかけとなったローマのサン・ルイージ・デイ・フランチェージ教会にある
影で絵を描く画家・カラヴァッジョの「マッテオの召出し」に感動し
絵の中の<白い光をまともに受けた少年>と<みにくい手の男>の両方が見捨てられないように
<真っ直ぐなルネサンス時代の道>と <まがりくねった中世の道>の両方を
いつも心に求めていこうと決意した須賀さん。
このふたつの文化をいつも求め続けている心こそが
須賀さんの作品の底に流れている川なのだと思うのです。
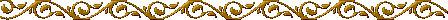
コルシア書店の仲間たち (文春文庫 450円)
「入口のそばの椅子」
「銀の夜」
「街」
「夜の会話」
「大通りの夢芝居」
「家族」
「小さい妹」
「女ともだち」
「オリーヴ林のなかの家」
「不運」
「ふつうの重荷」
「ダヴィデに・・・あとがきにかえて」
1930年代に起こった聖と俗の垣根を取り払おうとする
「新しい神学」に端を発した社会的運動の波は
1950年代の初頭、パリを中心にイタリア、ミラノにも及んだ。
「狭いキリスト教の殻に閉じこもらないで人間の言葉を話す<場>をつくろう」
という理想に燃え、コルシア・デイ・セルヴィ書店を開いたのである。
19世紀の文豪マンゾーニの歴史小説「いいなづけ」に出てくる通りの名でもある
セルヴィ修道院(今のサン・カルロ教会)の軒を借りた形のこの書店は
司祭で詩人でもあるダヴィデ・マリア・トゥロルド神父
イタリアでタイヤといえばすぐに思い浮かべる大企業の大株主のツィア・テレーサ
出版社の編集スタッフでもあったガッティ
翻訳や評論、序文を書き、出版社の編集顧問をやっていたカミッロ・デ・ピアツ
現代イタリアを代表する詩人ウンベルト・サバを熱愛し、後に須賀さんの夫となるペッピーノ
などなど、「それぞれクセが強くて神経質で救いがたく屈折したインテリ」を中心に、
詩人や小説家、評論家、政治家、宗教家、学生にまじって
書店の客達が議論を戦わすサロンとなっていた。
本書はそんな書店に集まる様々な人々、貴族の夫人から使い走りの少年まで
まさに「無名のひとりひとりが、小説ぶらないままで虚構化されて」
それでもなお愛情をもった眼差しで丁寧に描かれている。
1960年代末に過激化した学生運動の波をかぶり
思いがけない終焉を迎えたコルシア書店・・・
理想に燃えた仲間が夢みた共同体、コルシア書店を巡って
さまざまな人間模様が交錯し、一時代が風のように吹き抜けて行った。
けれども 須賀さんの胸の中で 彼らはいつまでも活き活きと生きているのである。
*****************
人生ほど
生きる疲れを癒してくれるものは ない
詩: ウンベルト・サバ
(須賀敦子訳)
*****************
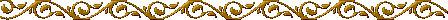
ユルスナールの靴(河出文庫 680円)
「フランドルの海」
「1929年」
「砂漠を行くものたち」
「皇帝のあとを追って」
「木立のなかの神殿」
「黒い廃墟」
「死んだ子供の肖像」
「小さな白い家」
「あとがきにかえて」
もし須賀さんの著書で1冊だけ勧めるとしたらどれかと問われれば
おそらく私は本書を挙げるでしょう。
そんなに沢山、彼女の著書を読んでいるわけでもないし、
2000年に出版された「須賀敦子全集」も手元にはあるだけで読破したわけではありません。
それでもこの「ユルスナールの靴」は彼女の人生を 彼女の魂の遍歴を
最もよく伺い知ることができる著書ではないかと思います。
本書は小説でもエッセイでもありません。
須賀さんが惚れ込んだフランス系ベルギー人の女流作家マルグリッド・ユルスナール。
彼女の半生と自分の人生を織り込みながら紡ぎあげた自伝のような作品。
人は自分と同じ匂いのする人に惹かれます。
須賀さんはフランスに留学していた時代に友人にこう言われました
・・・・「あなたは根本的にノマッド(nomade 放浪者)なのよ」・・・・・
故郷フランスを離れアメリカへ渡り
最後はマウント・デザート島で最後を迎えたユルスナールもノマッドであった。
私も自分が須賀さんに惹かれる理由がわかったような気がしました。
私も実はノマッドなのかもしれない。
本書を紹介するために読み直しているときに
須賀さんてこんな重い言葉を使う人だったかしら? っとふと思いました。
最初に読んだ時には気づかなかったのですが、
本書は須賀さんの生前最後の著書だったようです。
きっとご自分の病をご存知だったのではないでしょうか。
フランドルの海のように そしてフランドルの画家ルーベンスのように
暗く苦悩に満ちた言葉の数々
・・・・霊魂の闇、黒の過程、黒い廃墟、幻想の牢獄、死んだ子供の肖像・・・
それはユルスナールの、画家ピラネージの、
そして名も知らぬオランダの画家が使った言葉なのですが
須賀さんの歩んできた人生の足跡を彩った言葉でもあるような気がします。
最後まで晩年のユルスナールが履いていたような
「横でパチンととめる、小学生みたいな、柔らかい皮の靴」
を履きたいと思い、履けないままに逝ってしまわれた須賀さん。
ユルスナールに「ついて歩くような文章を書きたい」とおっしゃっていた須賀さん。
彼女がユルスナールの作風にふれた表現は
そのまま須賀さんの作風にも当てはまるような気がする私です。
・・・「強靱な知性にささえられ、抑えに抑えた古典的な香気を放つ文体と
それを縫って深い地下水のように流れる生への情念を織り込んだ繊細な作風」・・・
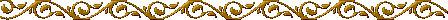
ミラノ 霧の風景 (白水社 870円)
「チェデルナのミラノ、私のミラノ」
「プロシュッティ先生のパスコリ」
「ナポリを見て死ね」
「セルジョ・モランドの友人たち」
「ガッティの背中」
「さくらんぼと運河とブリアンツァ」
「マリア・ボットーニの長い旅」
「きらめく海のトリエステ」
「鉄道員の家」
「舞台のうえのヴェネツィア」
「アントニオの大聖堂」
20年以上も経ってから語られるイタリア時代の友人ガッティやマリアの思い出。
彼女をイタリアへ、そして夫ペッピーノへと導くことになる
このちょっと風変わりな人達を愛情を込めて描いた作品や、
日本の文学作品(川端康成、谷崎潤一郎)のイタリア語訳の仕事を通じて知り合い、
彼女の精神を豊かにしてくれた編集者モランドとデベネデッティの思い出を綴った作品、
そして夫ペッピーノが愛した詩人サバの出身地トリエステ、
一緒に行く約束をして果たせなかったヴェネツィア、
この二つの町への想いは、
短いながらも充実した結婚生活を共にした
亡き夫ペッピーノへの想いにつながる作品など、
心に滲みるエッセイ集です。
私はミラノへは一度しか行ったことがありません。
空に向かってつき抜けるような沢山の尖塔を持つドゥオモの後ろには
眩しいばかりの青空が広がっていました。
そんなミラノの冬の風物詩が霧なのだそうです。
吸い込むと肺の奥までしみ込んでいくミラノの霧。
須賀さんがそんな霧の向こうに行ってしまった友人に捧げた本書。
今では須賀さんまでもがその霧の向こうへと旅だってしまわれました。
なお、このエッセイ集は須賀さんの文壇デビュー作であり、
その年の女流文学賞を受賞した作品でもあります。
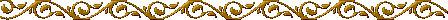
ヴェネツィアの宿 (文春文庫 560円)
「ヴェネツィアの宿」
「夏の終わりに」
「寄宿学校」
「カラが咲く庭」
「夜半のうた声」
「大聖堂まで」
「レーニ街の家」
「白い方丈」
「カティアが歩いた道」
「旅のむこう」
「アスフォデロの野をわたって」
「オリエント・エキスプレス」
本書の巻頭の「ヴェネツィアの宿」と巻末の「オリエント・エキスプレス」は
どちらも彼女の亡き父の思い出を綴ったエッセイ。
若き日にヨーロッパ各地で贅沢三昧の旅をした父、
二つの家庭を持っていた父、
ある日出ていったまま帰ってこなくなった父、
しかしヨーロッパのこととなると夢中になって語る父であった。
おみやげにオリエント・エキスプレスのコーヒーカップを所望し、
それを見届けるように亡くなった父に対する娘の思いがひそやかに伝わってきます。
「旅のむこう」は別府への新婚旅行の途中、
母の故郷豊後竹田を通過したとき思いをはせた母の思い出。
結婚当初の甘い思い出の中に生きていた母、
冗談のわからない人間を密かに軽蔑していた母
気弱で引っ込み思案だった母にも娘に見せた気丈な一面があった。
それでもついポロっと口から漏れる母の寂しい想い。
同性の母娘だからこそわかりあえる思いに自分を重ねてしまいます。
本書の中で特に印象に残った文章を「カラが咲く庭」から
・・・ヨーロッパにいることで、きっとあなたのなかの日本は育ち続けると思う。
あなたが自分のカードをごまかしさえしなければ・・・(修道女マリ・ノエル)
私は自分のカードをごまかしてはいないだろうか?
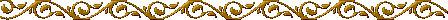
地図のない道 (新潮社 1400円)
「地図のない道」
・・・その一 「ゲットの広場」
・・・その二 「橋」
・・・その三 「島」
「ザッテレの河岸で」
工事中
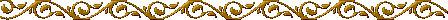
時のかけらたち (青土社)
「リヴィアの夢−パンテオン」
「ヴェネツィアの悲しみ」
「アラチェリの大階段」
「舗石を敷いた道」
「チェザレの家」
「図書館の記憶」
「スカッパ・ナポリ」
「ガールの水道橋」
「空の群青色」
「ファッツィーニのアトリエ」
「月と少女とアンドレア・ザンゾット」
「サンドロ・ペンナのひそやかな詩と人生」
工事中
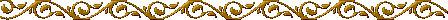

|