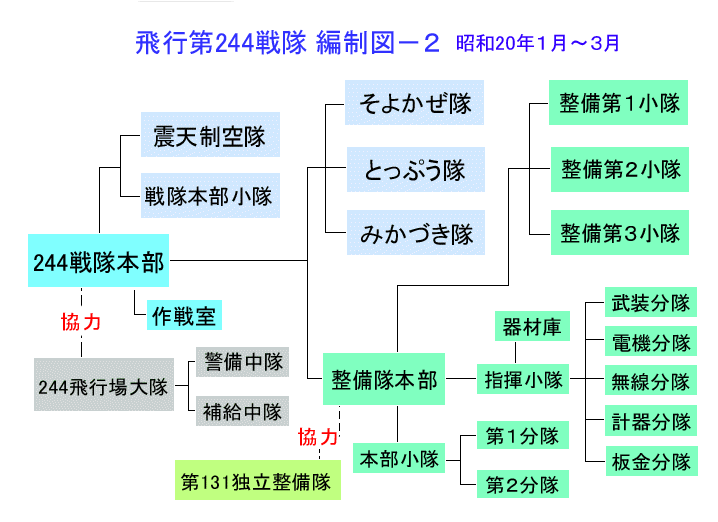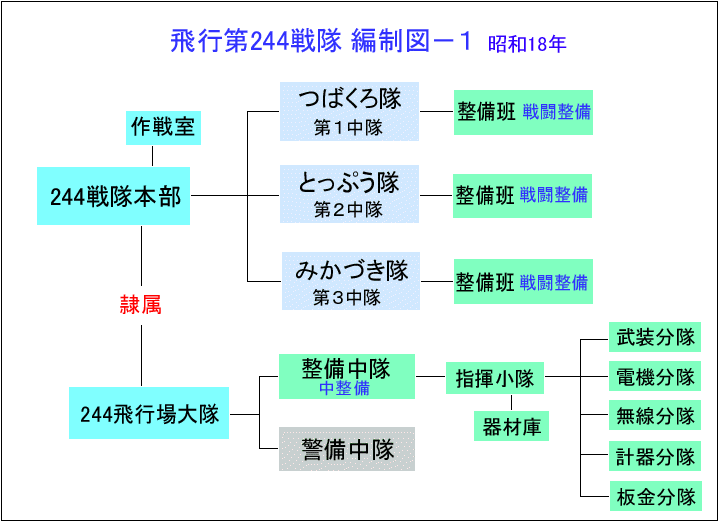
図−1 昭和18年当時の編制
この時期(19年初頭まで)の特徴は、中隊編制と飛行場大隊を編制内に抱えていたことである。空中勤務者である各中隊長は、飛行班(12機)と、それに付随する戦闘整備(注1)を担う整備班約50名、両者を指揮・監督していた。
飛行場大隊は整備中隊と警備中隊に分かれ、整備中隊は主に戦闘整備を上回る中整備(注2)を担当していた。整備中隊は約100名、警備中隊は約140名程度の陣容であり、戦隊の総人員は、500名弱であった。
整備中隊内の指揮小隊は大格に配置されて、発動機換装、事故原因探求、連絡・曳航機整備、外来機整備等を担当した。
注1 戦闘整備とは、今でいうライン整備。日常の保守、点検、試運転、燃弾補給等。
注2 中整備とは、時間点検および戦闘整備以上の作業でシリンダーヘッドの分解整備までを指す。それ以上の後方整備(オーバーホール等)は航空廠の担当。