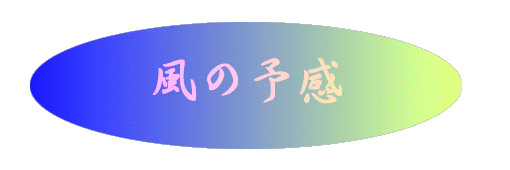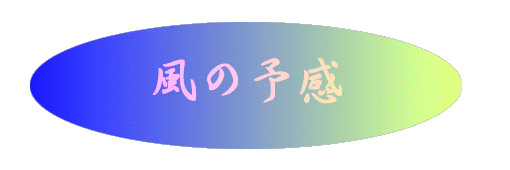
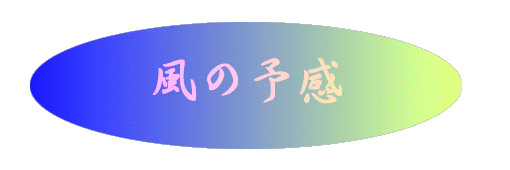
第1話 オフィス「風の予感」 =1=
|
運命が突然変わることがある。 ひとりの女性との出会いが僕を取り巻く状況を変化させたのだ。 彼女は春の太陽だった。ゆっくり訪れる夜明けのように彼女はそっと僕に寄り添い、昇りゆく朝日が急に輝きを増すごとく僕の心に照りつけた。夏の太陽ではない。春からイメージさせる優しさをも含んだ照射だった。 |
|
夜明け前。僕は昨日読み始めた本を読了した。熱中していたせいか眠気は全く感じない。 もう一冊未読の本がある。次は公園ででも読もう。そのうち眠くなるだろう。眠くなれば下宿に戻ればいい。 僕は大学に籍は置いていたけれど事実上フリーターであり、今日は一日何もするべき事がない。 僕は本を携えて原付に乗り公園に出かけた。途中で缶コーヒーを3本ほど買う。 決して広い公園ではなかったが、木々が茂り、その下にいくつかのベンチがある。すぐ側を幹線道路が通っていて環境がいいとは言えないが、それなりの市民の憩いの場になっていた。 早朝から散歩する老人や犬を連れた人たち。 時折ベンチに座る人もいたが、すぐに立ち去っていく。 10分ほどそういう光景を眺めてから、僕は缶コーヒーを開けて一口すすり、本を読み始めた。 |
|
「すいません、ここ、いいですか?」 女性の声がした。若い声だ。僕は活字を追いながら「どうぞ」と言った。 隣に座ったらしい若い女性には全く興味が無く、いつしか忘れていた。 読書をはじめると没頭するタイプなのだ。 ひとつの章を読み終えたとき、隣に人の気配を感じた。 (あれから、ずっといたのか?) ふと横を見る。おそらくまだ10代後半の少女だろう。苦しそうにハアハアと言っている。そして、流血。 ぼくはびっくりして「どうしたの?」と、叫んだ。 前頭部が割れているのだろうか。前髪で出血場所が不明確だが、額から唇の横へ血が伝っている。血はすっかり乾いてこびりついていた。 「どうしたの? 何があったの? 大丈夫?」 苦痛をこらえて無理に笑顔を作る。彼女はそんな感じで、「交通事故に遭っちゃいました」と、言った。 「病院は?」 聞くまでもない。彼女は病院になんか行っていない。 「大丈夫です。頭をちょっと打っただけだから。しばらくこうしてれば」 「大丈夫なもんか。」 「いえ、大丈夫です。病院とか、警察とか、まずいんです、ホントに。それに、服がちょっとひっかかって、そのせいで転んで、地面で頭を打っただけですから。痛みが収まれば、顔を洗って帰ります」 |
|
僕は一人暮らしだったので、彼女を家に連れ帰った。 傷口は確かにたいしたことないようだ。彼女はもう痛みに顔をしかめることもなくなった。 シャワーを浴びたいという彼女を、また傷口が開くといけないからと制し、洗面所で顔を洗うようにと新しいタオルを渡した。 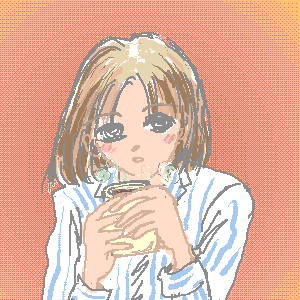 僕はパジャマを彼女に貸してあげた。破れたり血が付いたりしている服を「ごめんなさい。捨てていいですか?」と言ってから、彼女はゴミ箱に入れた。 僕はパジャマを彼女に貸してあげた。破れたり血が付いたりしている服を「ごめんなさい。捨てていいですか?」と言ってから、彼女はゴミ箱に入れた。コーヒーをいれて一緒に飲む。 僕の向かい側に座って、カップを抱きしめるようにして少しずつコーヒーを飲む彼女は、まばゆいほどに美しかった。 どこがどうというわけじゃない。存在そのものがまばゆいのだ。 左右対称ではない目、小さすぎる鼻、笑うとふくらむ頬、形はいいけれど少し薄い唇。ひとつひとつはなんだか欠点のように思える。でも全体としては美しく、可愛い。 ボサッとしていた髪は、洗面所にあった櫛を通したのだろう、綺麗にそろえたはずのボブがそのまま4〜5センチほど伸びた、という感じだった。 何で見知らぬ女の子が僕の部屋でお茶を飲んでいるんだろう? 本も公園も缶コーヒーも交通事故も何もなかったかのように、ちょんまりと彼女はこの部屋にマッチしていた。 当然という感じで。 さりげなく。 「ところで、君は誰?」 僕は問うてみた。 |
|
「わたしはこういう者です」 彼女は大事そうに抱えていたセカンドバックから、名刺入れを取りだした。 そして、堂々とした態度で、名刺入れから一枚引き抜いた名刺を差し出す。その所作はまったく慣れていた。まるでビジネスシーンに馴染んだOLのようだった。 僕は名刺を受け取る前に、もう一度彼女を見た。10代後半、その印象は変わらなかったが、顔を洗って血糊を落とした彼女はさらに若く見えた。女子高生と言っても通じるだろう。 名刺には、「(有)オフィス風の予感 主任調査員 立華清花」と記されていた。 「たち...か?」 「たちばな、さやか、と読みます。」 「たちばなさやか、さん」 「はい」 彼女は堂々と、そして爽やかに微笑んだ。名は体を表すというが、まさしくその通りだった。 オフィス風の予感、という会社名も爽やかだ。けれど、その社名にそぐわない肩書きだなあと思った。 主任「調査員」 いったい何を調査するのだろう。そして、この若さで「主任」とは。 「不躾なんですが」と、僕は言った。 いつの間にか丁寧な言葉遣いをしている自分に気づく。きちんとした職を持っていること、そして肩書きまであること。さらに、堂々とした名刺の出し方。これらに圧倒されたらしい。顔面に血糊を張り付けて他人の家に上がり込み(僕が誘ったんだけど)、服まで借用してしまう行動は主任らしくないけれど。 ただし、立華清花が僕より年下であるだろうという印象は変わっていない。それがまた僕にとってはプレッシャーだ。何しろこちらは「学生の身分を持った実質フリーター」なのだから。 「はい、何でしょう」 名刺を出したからだろう。彼女は営業スマイルで答えた。 「この『オフィス風の予感』は何をしてる会社なんでしょう? そして、差し支えなかったら、あなたの年齢を教えて欲しいんですが」 立華清花はふふっという感じで笑った。 「年齢ですか。じゃあ、プライベートモードで喋りましょ。少なくともあなたよりも年下だと思うから、変に丁寧な言葉遣いはやめてくれると嬉しいな。わたしも、生意気かも知れないけど、出来ればタメ口で話せると嬉しいな。仕事以外で人と会ってるのに、仕事みたいな感じがするの。ですます調で喋っていると。いいかな?」 いいかどうか返事を待たずにもうタメ口になっている。彼女の切り替えの早さは、頭の回転の速さなのだろうか? それとも僕が勝手に彼女に抱いた印象なのか? いずれにしても、自然に口をついた彼女に対する「ですます調」をやめるには、少し努力がいるようだった。 「はい、いいですよ...じゃなくて、ああ、いいよ、かな?」 「うんうん。わたしもそのほうが気楽でいいや」 立華清花はざっくばらんに笑った。営業スマイルとは異質な笑顔だ。無邪気さをめいっぱい含んだ笑顔。僕までほのぼのした気持ちにさせられる。 「で、仕事の方なんだけど、これはちょっと一言で説明するのは難しいな。」 「でも、何かを調査する仕事なんでしょ?」 「そうそう。調査する仕事。」 「それは、何を?」 「人の、心、かな?」 「ふうん。なんだかよくわからないや。」 僕はコーヒーをすすろうとして、カップの中が空っぽになっていることに気がついた。 「おかわりする? インスタントのようだし、それならわたしでも入れてあげられるよ」 「じゃあ」 なんなんだろうね、これは。今日初めて僕の部屋にやってきた結構イケてる女の子にコーヒーを入れてもらっているというシチュエイションは。ま、いいか。 彼女はキッチンに立ちながら、つまり僕に背中を向けながら、「ねえ、あなたは...なんて呼べばいい? 自己紹介してよ」と言った。 「僕は、橘和宣。偶然だけど、同じ『たちばな』。でも、漢字は違うよ。一文字の方。21歳。学籍だけ大学に置くフリーダーだよ」 学籍だけ大学に置くフリーター、というところを繰り返してから、けらけらと彼女は笑った。 「苗字が同じね。じゃあ、下の名前で呼んでいい?」 「いいよ」 「じゃあ、和宣君、ううん、ええと、呼び捨ての方がしっくりくるかな、和宣、うう〜ん。」 彼女は何度か、かずのりくん、かずのり、かずのりくん、かずのりとつぶやいた。 「やっぱ、呼び捨てでいいかな?」 下の名前で呼ばれることにも呼び捨てにされることにも違和感を感じた。でもたいしたことじゃない。 おそらく自己紹介を終えてコーヒーを飲み干したら、僕たちはそれっきりだ。通りすがりの出会いと別れ。その一瞬の共有した時間の中で、どう呼び合おうと関係ない。 「どっちでもいいよ」 「じゃあ、節約モードで、和宣。わたしのことも清花って呼んでくれたらいい」 「そうするよ」 「で、何の話だっけ? そうそう。わたしの会社の仕事だったよね。それはそうと、和宣はこれから暇? フリーターの人って、イメージ的には暇そうなんだけど、結構バイトで忙しかったりするのよね。で、もし暇だったら付き合ってくれないかな。助手、っていうのかな、ちょっと手伝ってくれると助かるんだけど。そうすれば、どんな仕事かも分かるだろうし」 実はこの後かくかくしかじかというわけで応じられない、などといえればかっこいいなと思ったけれど、残念ながら僕は暇だった。自ら望んで暇なわけじゃない。貧乏なのである。貧乏だからバイトのない日は用事を入れない。余計な出費を避けるためだ。家賃も払わないといけないし、学費も納めなくてはならない。生活費だってかかる。学生のくせにフリーターなのは、「小遣い稼ぎ程度のバイトでは生活できないくらい仕送りが少ないから」であり、バイトに精を出すうちに単位を落としたり留年したりで、ますます卒業が遠のき学費がかさむ。いつしか勤勉に講義に出席する意欲まで失せていた。悪循環を繰り返しているのだ。 本心としては早く卒業して就職したい。正社員になれば給料はじめ通勤手当に住宅手当と色々もらえるわけだから。曜日も時間も不安定なバイトに比べれば生活設計だって出来る。プライベートだって充実するだろう。 しかし現実を直視すれば、目の前のバイト料は魅力である。というか、それこそが大切なのだ。 「そりゃいいけど、その助手というか、手伝いというか、それはバイトだと思っていいのかな?」 「もちろん」 清花は名刺を取りだしたときと同じように、セカンドバックからお金を取りだした。 銀行の帯封がかかった一万円札の束。 帯封は少し緩んでいる。既に何枚かを引っぱり出した後のようだ。それでも90万円前後はあるだろう。 「そうね、とりあえず5日分の日当ということで、5万円」 いち、にい、さん、し、ご。 5枚を数えて僕に手渡す。 鮮やかに、さっそうと僕の目の前に差し出すものだから、僕も自然に受け取ってしまった。 受け取ってから、ちょっと焦った。 「こんなに?」 「多くはないわよ。日当計算だから。時給じゃないから残業もつかないし、いつ始まっていつ終わるかわからない。あ、必要経費は別に出すから。一緒に行動するときはわたしが払うけど、単独行動の時は立て替えといてね。領収書、忘れちゃダメよ。そうそう、日当の領収書も書いてもらわなきゃ。はんことか持ってる?」 はんこは持っているけれど、何だか一日一万円で買われたような気がした。 |
|
ディスカウントのジーンズショップで清花はGパンを買った。Tシャツは家を出るときに僕が貸したものをそのまま着ている。清花がコインロッカーからショルダーバックを取り出すのを待ち、僕は清花に促されるまま電車に乗った。 「とりあえず、これを読んどいて」 清花はセカンドバックの中からたたんだ紙切れを取りだした。 全く、何から何まで入ってるんだよな。そのセカンドバック。 通勤ラッシュは終えていたが、空席があるほどじゃない。僕たちは扉近くに立った。 天気が良く、のんびりとした陽射しが窓越しに僕の手元に届く。 広げた紙切れはA4サイズで、調査依頼書と書いてある。 まず依頼人の住所氏名電話番号などのプロフィールが記されている。依頼内容は、次のようになっていた。 調査対象人物:山本ふね(84)女性 死因:老衰 備考欄には、山本ふねの住所や、葬儀場、墓場などについて書かれている。 特記事項として、「特に、残されたお好み焼き屋について、思うところがあったかどうか。」と付記されていた。「なお、このお好み焼き屋は山本ふみの死後、息子の手によって不動産業者に売却を依頼しており、最近買い手が見つかった」とある。 「これは?」 「簡単に言うわ。オフィス風の予感は、死者の気持ちを調査する会社。故人がどんな気持ちで死んでいったか。それを調査して遺族に報告するのよ。」 「じゃあ、これは」 「和宣に渡したのは、山本さんのお孫さんからの依頼。息子さん、つまり依頼人のお父さんは宝石商でね。自分でお店を持っているからお好み焼き屋を継ぐことは出来ないし、お孫さんもサラリーマン。会社を辞めてお好み焼き屋を継ぐかどうか悩んだ末、おばあちゃんの気持ちを知りたい、とこうなったわけね。もっとも、お好み焼き屋はもう3年も営業していないから、いまさら再開させたところで常連さんが戻ってくるかどうかもわからない。つまり経営できるかどうかわからないわけよ。」 「なるほど」 「わかる? 大切なのは、死者の気持ちじゃなくて、それを知りたいという遺族の気持ち。これが私たちの仕事よ」 「でも、こんなの、どうやって調べれば」 「この案件は私達が抱える仕事の中では簡単な方よ。親しかった人を探して、晩年の山本さんが普段どんなことを言ったり行動してたりしたかを調査すればいい」 「出来るだけ詳しく?」 「詳しく調査する必要はないわ。報告書に書くレポートに矛盾がない程度の証言が得られればそれでいいの。わたしはもうひとつややこしいの抱えているから、出来れば全面的に任せたいんだけど」 手間のかかる仕事だとは思ったが、ひとつひとつの手順は難しくないだろう。しかし、どれほどの手間がかかるのか僕にはさっぱり想像つかない。 「5万円、つまり5日分の日当をもらったっていうことは、そのくらいで完了できそうだ、ということなのかな?」と、僕はおおよその感覚をつかむために質問してみた。 「ナイス! その通りよ。と、言いたいところだけど、3日もあれば出来るはずよ。それに、完了できそうだ、ではなくて、完了させて頂戴。依頼人は7日後に海外出張を控えてるの。遅くとも出発前日には調査報告する約束だから、5日間調査に費やしたら徹夜でレポートを書いて翌日渡す、なんて羽目になるわ。それに和宣は新人だから、早めにわたしに提出してチェックを受けること。うん、やっぱり今日を含めて3日間ね。4日目には提出して頂戴。オッケー?」 オッケーかどうかはやってみなくてはわからない。何しろ僕は清花の言うとおり「新人」なのだから。 「それから、ひとつ忠告。この仕事は、死人のためにやってるのではなくて、依頼人、つまり生きてる人のためにやってるんだからね。そこんとこ、忘れないで」 「ん。了解」 「じゃあ、この件、任せてもいい?」 死人の気持ちを調査する。そんなことが商売になることに若干の後ろめたさを感じないでもないが、要するに本人が死んでしまっている以上これが正解だなんてことは誰にもわからないはずだ。誰にもわからないはずのことを何とか調べる。そして生きている人のために報告する。 それはそれで興味深い仕事のように思えた。 少なくとも、マニュアルに忠実に作り笑いを浮かべながらファーストフードの店員をしたり、コンピューターのディスプレイを終日相手にしたり、あるいは工場のラインで単純作業を繰り返したり、そんなバイトに比べて、遙かに人間くさく、人の役に立ち、やりがいがあるような気がしたのだ。 「やれるだけ、やってみる」 「助かる。よろしく頼むね。困ったことや分からないことがあったら、携帯に電話して。」 清花が抱えているもうひとつの仕事も同じ町の人からの依頼だった。それでふたつまとめてこなすことになったらしい。僕たちは75分ほど電車に揺られ、すっかり牧歌的な風景に包まれたわびしい駅に降り立った。それでも駅前に4階建てのビジネスホテルがあり、僕たちはそこへチェックインをした。いうまでもないが部屋は別々である。 「このホテルが、この町に滞在中は私たちの本部ってことになるわね」 フロントのカウンターで宿帳に記入していると、フロントマンが「橘様ですね。お預かりものがございます」と言った。渡されたのはまっさらな名刺だった。きちんとプラスチックのケースに入っている。多分100枚入りだろう。 「お、早い。もう届いたのね。電車の中から携帯で注文しておいたのよ。社長がこの町の印刷屋に手配して大至急で届けさせたのね。」 「仕事が速いなあ。」 「あなたの名刺よ。受け取って。」 「うん」 そこには「(有)オフィス風の予感 主任調査員 橘和宣」と書かれていた。 「主、主任調査員? 俺があ? 臨時雇いじゃないのか?」 「いいじゃない、そんなこと。取締役じゃまずいけど、主任くらいなら構わないでしょ? そういう名刺の方が出された方も安心するし。まあ、この案件に関して主に任せた人、てなもんよ。私たちの会社は案件ごとの契約だから」 「じゃあ君も正社員じゃ、無いのか?」 「うち、正社員なんて、社長だけよ」 |