れんげ草への想い
れんげ草の会代表 宮野原 里子
父危篤の知らせに敬愛園に駆けつけた私を見るなり、父は、意識の遠のく中、振り絞るような声で、「帰れ、帰れ。」と言った。それきり後に続く言葉はなかった。20数年前、あっけない父の死であった。
父の遺体にすがって泣いたが、葬儀を終えるとその日のうちに、表面では何食わぬ顔をして嫁ぎ先へと戻った。家族に真実を話せない苦しみ中で一人布団にもぐり、幾晩も泣き続けた。
そんな折り、母から一冊の本が届いた。『らいの息子として』。林力氏の堂々たる宣言の手記であった。しかも、光田氏や国のらい予防法のあり方の間違いを厳しく非難している。この本に出合ってから、私は親に対する気持ちを変えた。これまで自分の出生を恨み、親から遠ざかろうとしていたことを恥じた。林力氏が苦しんできたことは、私が苦しんでいることと同じであった。それは、らい予防法が作りあげてきた偏見差別以外のなにものでもない。この苦しみから解き放たれるためには、病気に冒された者とその家族をこんなにも苦しめる法を正すことだと思った。そして、せめていつかは、この愛しい親を語りたい、それが親への罪の償いだと思うようになった。
しかし、その頃は、こうして裁判が行われるようになるなど、想像もつかぬことであった。

photo by ガラクタ箱さん
数年後、さまざまなことで離婚を迷っていた私は、15歳になった子供に親のことを話した。子供は私が自分の親を大切にしなかったことを怒り、私に離婚を決意させてくれた。その後は、敬愛園で老いていく母を我が家に連れて来たり、母の生家に正月のたびに連れて行ったりした。これが私のできる母への少しもの償いと、何よりも母との想い出となった。
あの時々見せる母の嬉しそうな表情が忘れられない。「寮の人たちが言うのよ、私たちの分も楽しんでおいで。」って、幾度も言った母の言葉には、娘のいることを何より誇らしく思ってることの表現であったと思う。未だ故郷に帰ることができない元患者さんが多い中で、その方々からすれば、母は羨まれる存在であったに違いない。
母の最期は、裁判の最中だった。父のような悲しい最期をさせまいと、執念のように片道4時間の道程を幾度も通った。離婚してて良かった、離婚していなければできないことだった。らいの子は、やはりこのような選択をするのが妥当なのかもしれないと、自分の生き方をしきりに自分に納得させた。もう二度と嘘いつわりの生活はしたくないと思った。
母の死後、私は大きな衝撃を受けた。私の出生について、幼い頃、母から聞かされていたことは、「両親ともこの病の子ではお前が不憫だから、あえて戸籍上、私生児にしておいた。でも真実お前のお父さんだからね。」。このことに、幼いながらも複雑な思いはしたものの、娘の幸福を考えてのことと受け止め、うなずいて涙をこらえたのを覚えている。私は、離婚してからは母とよく電話で話もし、最期も存分に看ることができたと思う。ただ一つ気掛かりに想っていたことに父のことがあった。敬愛園に収容されてからは、再び故郷の土を踏むことのなかった父の無念な生涯を想い、また、父への償いと思い、いつかは父の故郷を訪ねてみたいと思っていた。私は、母の葬儀の後、敬愛園の福祉課を訪ねた。
福祉課で見せられた父の戸籍謄本に、私は思わず、「それは私の父の戸籍ではありません。」と言った。
父の戸籍謄本の名前は、私が知っている父の名前ではなかったのだ。父の本名こそ、私に付けられた名前と同じだった。父は生涯において、そのことについて何も語らなかった。位牌も墓地も偽名のまま刻んで20数年の歳月が過ぎている。父の本戸籍を見た私は、身体が震えその場に泣き崩れてしまった。
涙を枯らし立ち上がった時、私の心に強く芽生えたものは、裁判に参加することの決意であった。娘の幸福だけを一途に願い、娘にさえも真実を語ることもせず、この世を去ってしまった父の無念さを国に訴えたい、裁判に参加する勇気を父が与えてくれた。
幸いに裁判は友人夫妻が支援の会で活躍してくれていたので、すんなりと入っていけた。しかし、支援の会の方の多いのに驚き、それでも今まで自分の本当の過去を偽り隠し続け、他人の真実を受け入れる心さえも小さくなってしまっていた私には、その光景がにわかには信じがたく怯えていた。しかし、元患者の、意見陳述を聴くたびに私は嗚咽した。断種や堕胎が容赦なく行われ、その苦しみの癒えないままに人生を送ってきた元患者の意見陳述に、敬愛園を逃げてまでも、一つの生命を守ってくれた両親を恨んだ日々が悔やまれてならなかったのである。
私の意見陳述は上記したことからわかっていただけると思うが、その後次の家族原告の意見陳述があるまでは、まだまだ怯えていたことは確かである。ようやく、二人目の家族原告の意見陳述を聴いた私は、法廷であることも忘れて泣き叫んでいた。その内容を自分の人生と重ね合わせ、偏見差別に苦しんだ日々が思い出されて仕方がなかった。
2001年5月11日、裁判は勝利したものの、家族原告には納得できない国の回答であり、特に20年を過ぎていた父の無念さが報われなかったのが未だ納得できない。このような立場にある家族の多くは納得できず、この裁判のあったことさえ虚しいものに思っておられるに違いない。最も社会的偏見差別の激しかった中を、どんなに苦しみ、悲しみ、悔しさに耐えて生きてきたか、そのことが鮮明な記憶であるだけに、裁判の勝利、そして、国の理解ある回答は、生涯を差別偏見に怯えながら生きた家族へのささやかな癒しとなるはずだったのに...(裁判の結果については、国が一定の理解を示し勝利したものの、それはあくまで「元患者」に対してのみであり、賠償も「元患者」及び「その遺族」が対象にすぎない。問題点は、「元患者」とともに同様に偏見差別を受けた「家族」の訴えに対して何ら解決がされていないこと、そして、「元患者の遺族」に対しても、「元患者」の死後20年を経過した場合、賠償の対象にされなかったことである。)。
判決の後も、私はずっと裁判に参加した。熊本まではかなり遠い道程であったが、裁判に行くことで、気持ちが落ち着くのを感じていた。偏見に怯えた歳月が長すぎただけに、すぐに心を開くことはできなかった。他人の真実を受け入れる心も小さくなってしまっていた。来る日も来る日もこの裁判のことが報道されるのを聴くのも怯えた日々、でも、ここでは弁護士の先生方と支援の会の方々が受け入れてくれる。かつて、自分の人生にこんな日々が訪れることを考えられただろうか。
らいの子にもこんな幸福が訪れたのか、これが、らいの子の幸福と言うものなのか、何と不思議な幸福感なんだろうか。手放しで喜べないのは心に壁を作ることが習慣づいているせいだろうか。それもあった。でも何よりも、ともに語ることのできる家族原告がいないことだった。いつも裁判に参加する家族原告は一人で、待ち時間は裁判所の木々を眺め、こんな想いにふけっていた。
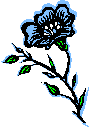
ある日のこと、国宗弁護士から一人の家族原告を紹介された。
K子さんは、幼い頃から自分の父は亡くなったと知らされていた。20歳になった時、彼女は突然父のことを教えられ、そして父に会った。その時彼女は、自分が親戚をたらい回しにされ言いようのない差別を受けたことは、このことだったのかと解った。それからの彼女は、自分のこれまでのやりきれなかった人生を父にぶつけ、父を恨んで生きてきたと話してくれた。
彼女の話は、かつての私自身の心の中を垣間見ているようであった。らいの家族となってしまった多くの人々は、偏見差別の谷間で同じような気持ちで生きてきたのかもしれない。その後、彼女は必ず裁判に参加するようになったが、彼女もまた他人には話せなかった過去を話せることで安らげる場所を得たのだと思う。
それから幾人かの家族原告の意見陳述がされた。その後はお互いを紹介し合うこともなく、私たちは心をさらけだして話すことができた。それはまるで、もっともっと以前より知り合いであったような気がしてならなかった。意見陳述の内容は少しずつ異なるけれど、社会からの偏見差別が原因であることに変わりないものであった。そして、年齢の高い家族ほど、受けた偏見差別が鮮明な記憶であるがゆえに、癒されない人生を長く送ってきたことも事実である。
未感染児童として龍田寮に入所の経験のあるH.Y.さんが意見陳述した。彼女自身は幼くて偏見差別を明確に覚えていないが、お父さんはあまりにも社会の不条理さに耐えかね、彼女を奄美大島の親戚に預けたのだと言う。
戦後の奄美大島に幼い子供を預けるという選択をしたこと自体、その偏見差別のすさまじさを物語っている。彼女もまた、親から離れることの悲しみの中にあっても、親が子供の幸福を願っての選択と受け止め、親と別れて奄美大島へ引き取られることに子供ながら納得したに違いない。戦後の奄美大島と熊本、気の遠くなるような距離に、しかも戦後復帰の貧しさのまっただ中に子供を送り離れて暮らした親子が、どれほど辛かったことだろうか。
父母に会いたい気持ちと同時に、何故か彼女の脳裏にはれんげ草畑が浮かんでくる。れんげ草畑...、何故奄美大島にない風景が脳裏から離れないのか不思議でならなかった。ある時、それはまぎれもなく龍田寮から見た風景であったことに気づいたと話してくれた。
偏見差別がなければ、親の側で暮らせたはずの彼女の人生の記憶である。
彼女からこの話を聞いたとき、即座に私たちの会は、『れんげ草の会』にしたいと思った。K子さんもすぐに同感して、三人が一致して命名したのである。
少女の目の高さに無限に広がるれんげ草畑
純粋で無垢な心のままに見つめていた
偏見とか差別とか知らないで、れんげの花を愛でていた
そして無限に広がるれんげ草畑のような夢を描いていた
そこに突然、偏見とか差別とかが襲って来て
少女から一番大切な大切な父と母という
宝物を奪ってしまった
それはずっと取り返すことはできなかった
今、やっと宝物を取り返すときがきたのだ
偏見とか差別とか追いはらって
そして伝えよう天国の父や母に
私たちの勇気で取り返す宝物
れんげ草畑のような天国で、きっと喜んでくれるだろう。
そしてこう言うだろう、偏見差別のない世の中に住みたかった...と
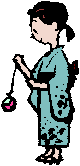
れんげ草の会を立ち上げた当初は数人だったが、国宗先生の呼びかけで会員も増えている。このことは家族原告の多くが、同じような想いで生きてきた証だと思う。
今後、私たちは、偏見差別の実態を明らかにし、国に対してその責任を問いただしていきたいと考えている。
れんげ草の会の立ち上げについては、弁護士の先生方の支援がなければとてもできなかった。でも、こうして会を立ち上げた以上、会をずっと存続していくようにしたいと思っているので、会員の積極的な協力をお願いしたい。
とりあえず、今回は、会の立ち上げに至るまでの想いを、私自身の親に対する回想や、裁判の中期からずっと参加した家族原告として報告を兼ねて述べてみたが、恐れることなくこの会に参加していただきたい。家族原告に会える日が楽しみである。
2003年5月