| 千町無田開拓とは
明治22年7月、筑後川流域は大洪水のために水浸しになり、田植えを終えたばかりの農民は途方に暮れた。特に自分の土地をもたない小作人や二男・三男坊は、生きていく術すら見出せずにいた。
そんな時、元久留米藩士の青木牛之助が、救済のために立ち上がった。彼は、藩士時代の人脈を生かして上京し、牛込の道林寺住職・東洲和尚を訪ねて、時の大物山岡鉄斎を紹介してもらう。被災農民のハワイ移住を嘆願するためであった。
600人の農民をハワイに送り出した後、牛之助は「年齢制限」で移住できなかった被災農民を救うべく、大分・東京・博多間を奔走し、九重高原の千町無田開拓を願い出る。
洪水から4年経過して、牛之助は40世帯を引き連れ、古代より火山灰が積もる湿原地帯の開拓に挑んだ。大分県知事との契約条件は「10年間で200町歩の開拓を成し遂げること」であった。移住農民は、牛之助の指導の下で、牛馬同然の生活に耐えながら、水田つくりに励んだ結果、11年後に見事な田畑をつくりあげる。
牛之助は、開拓成功を見届けると、久留米(津福)で留守を守る愛妻の元に帰っていった。
青木牛之助とはどんな人物だったか
青木牛之助は、弘化3年に久留米の京ノ隈(現京町)に生まれている。青木家は代々久留米藩の故実師範役の家柄で、父の代になって梅林寺(藩主有馬家の菩提寺)の寺侍を任じられている。
牛之助は13歳にして身長5尺5寸に達した大柄の体躯で、武術・芸術・などに長けていた。幕末には、藩兵として京都に出向き都の警護にも当っている。その際、他国の志士や公家との親交も深めた。
維新後は、特に目立った活躍はみられず、八百屋や煙草製造販売、久留米監獄の看守などで食い扶持をつないでいたようだ。
牛之助の趣味は広く、また器用であった。花簪の製造、表装、表具の技術をこなしたほか、絵や和歌にも才能があった。
そんな彼を、生涯をかける九重高原開拓に駆り立てた動機は何だったのか。
その一つは、もって生まれた正義感だったろう。才能を十分に生かせないでいた矢先の農民の難儀を、見てみぬふりができなかったのである。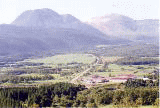
次は、彼が内心に秘める「野心」であった。人一倍プライドの高い牛之助は、明治維新以来周囲の知人・友人の活躍を黙ってみているのが辛かったのではないか。「このままでは俺の人生は終らない」との意思が、世の中の大転換期に一気に飛び出したといえる。
「歴史に残る大事業」を打ち立てることと、九重高原開拓の価値が、彼の中で完全に出来あがったのだ。写真は、千町無田全景
率いられた筑後の農民は
青木牛之助に率いられて、九重高原開拓に参加した筑後農民の真相はどこにあったのか。
江戸幕府以来の農民差別から解き放たれることを夢みた農民は、明治政府のより厳しい差別政策に落胆していた。
筑後地方においても、「士農工商」の階級差別はなくならず、町方と在方(田舎)の生活は天と地の違いに広がった。農民のなかでも、家を継ぐ長男と二男坊以下の立場は、経営者と使用人の関係以上であった。土地をもたない小作人の場合はもっと苦しく、牛馬以下であったと資料には記されている。
街が織物を中心とした景気に沸き、西南戦争が一部の商人を潤し、軍国主義化が一層進む筑後地区で、貧農民だけが取り残された状態だった。そこに、決定的な大洪水の襲来である。.gif)
家族が明日を生きるあてさえなくしたとき、青木牛之助がさし伸べた救いの手を、仏以上にありがたく感じたに違いない。開拓に参加するために家と家財の全てを処分し、1世帯3円を拠出し、生産の目途がたつまでの生活費を工面して、家族ぐるみで筑後川を遡って行った。10年後に自分の田んぼを持ち、ふるさとに凱旋する日を夢みて。写真は、千町無田の集落
だが、現実は想像を遥かに超える厳しいものであった。真冬に氷点下20度まで下がる気温、一面の湿地帯から水をぬく作業、何度挑戦しても目を出さない早苗、相継ぐ台風など、明日の兵糧すらおぼつかなくなった。そんな時、日清戦争の勃発で硫黄山の硫黄が重宝がられ、彼らは日銭稼ぎのため山から麓までの運搬に従事する。その分開拓の遅延を招くことを承知の上で。
地元住民とのトラブルも絶えず、祭りからも追放された彼らは、開拓地の中心に朝日神社を建立し、心の支えを確保して、次なる開拓へと進んでいった。
11年たって、農民は生まれて初めて「自分の土地」を手にした。だが、途中脱落者が相継いだため、喜びも分散されることになる。
歴史の証拠を見て欲しい
皆さんが千町無田を訪ねる折、目を瞑って110年前の入植当時にタイムスリップを試みて欲しい。延々と広がる美田の彼方に、荒涼とした湿原が広がる。牛馬でも嫌がりそうな掘立小屋で肩を寄せ合い寒さをしのぐ家族。青木牛之助の指導で、植えた杉の苗木は、今では大木となって天を突いている。朝日神社に祀られた年ノ神(朝日長者=五穀豊穣の神)と神格化された青木大明神は、辛い開拓を支え励ましたのである。
村では、ぜひたくさんの人と会話を交して欲しい。子孫である彼らから、青木牛之助や農民たちの生き様が伺えるかもしれない。
|



