福津市に「手光」という地名がある。「てびか」と読む。むかしは「てびかり」とも言われたそうな。珍しい地名につられて、村人の心の拠り所となっている長谷寺を訪ねた。JR福間駅を降りて北へ2キロ足らず歩いたところの山裾に、お寺の甍が見えてくる。正式には「施無畏山長谷禅寺」と称す。
境内に入るとまず目につくのが、時代を思わせる観音堂である。扉は頑丈に閉められていて、「この観音様は、秘仏で三十三年に一回行われる御開扉(本開扉)の日だけしか拝観
することができません」と注意書きがなされていた。そばには、秘仏の観音さまの謂れが記されてあった。
.gif)
鷹が飛び込んできた
手光村(てびかむら)の一軒家で、10歳になったばかりのお佳代が針仕事に勤しんでいた。母親と二人暮らしの可愛い盛りである。父親の五郎作は、彼女が生まれて間もなく、世を去っていて、残された母のトヨは、女手一つでお佳代を大切に育てていた。
「死んだ父ちゃんと母ちゃんは子供が欲しくてね、毎日観音さまにお祈りしたんだよ。そうしたら、お前が生まれたのさ。嬉しかったね。だから、観音さまには足向けて寝られないんだよ」とは、ことあるたびに母が娘に言って聞かせる言葉であった。
そんなある日、母が出かけている間、お佳代は針仕事をしながら留守番をしていた。その時である。バタバタと鋭い羽音をたてて大きな鳥が家の中に飛び込んできた。猛禽の鷹である。古びた梁にとまって、鋭い目でお佳代を睨みつけている。怖くて逃げだしたいが、後ろ向きになった途端に襲われてしまいそうで、身動きができない。鷹は、鍋の中の食べ物を狙って急降下してきた。「来るな!」、咄嗟にそばにあった鉈を鷹に向かって振り下ろした。
お慈悲にすがり
鷹は大きな羽をだらしなく広げたまま息絶えた。そこに、足音激しく侍が飛び込んできた。侍は土足で上がって来るなり、死んだ鷹を抱き上げた。
「何をするか、小娘」、怯えるお佳代の首筋を捕まえ、床に叩きつけた。「お許しください」と、額を床に着けて謝った。
「許せぬ。このお鷹さまをどなたと心得る?、殿さまが大切になさっているお狩場用の鳥さまなるぞ」
侍は、震えるお佳代の背中をめがけて刀を振り下ろした。お佳代はそのまま気を失った。侍は、鷹を宝物のように抱いて、さっさと外に出ていった。
それからなんどき経ったか、母のトヨが帰ってきた。「お腹すいたろう、すぐ用意するからね」と優しく声をかけたあとびっくり。お佳代がうつぶせの状態でぐったりしている。
.gif)
宗像地方の農村風景
「お佳代、お佳代」、いくら呼んでも、目は閉じられたままだ。お佳代の右肩から腹部にかけて、斜めに斬り裂かれた傷口から、血潮が噴き出している。トヨは、手拭いで傷口の血を拭き取ると、そのまま外に飛び出した。向かった先は長谷寺(ちょうこくじ)。行き慣れた急坂を駆け上ると、観音堂の前に倒れ込んだ。
「どうしたんじゃ、トヨさん」、出てきた住職が抱き上げてわけを訊いた。
住職は、血の気の失せたトヨを観音堂に引き入れて、観音菩薩の前の蝋燭に灯をつけた。
「南無大慈悲観世音」「「南無大慈悲観世音」…、住職とトヨは、息の続く限り観音像に向かって祈り続けた。
「どうぞお救いくだされ」と住職が唱えれば、トヨは「わたくしの命なぞ差し上げます故、どうぞ娘をお助け下さい」と祈った。
観音さまが身代わりに
トヨは、お佳代を介抱する傍ら、仏壇に灯をともして祈り続けた。
「父ちゃん、お前も一緒に拝んでおくれよ」と、仏壇の中の五郎作を呼び起こして、祈願の合唱を頼んだ。お佳代の具合は出血は止まったものの一進一退、両目は固く閉じられたままである。
そんな折、長谷寺の住職が訪ねてきた。
「漢音さんからお告げがあったぞ。おトヨの祈りとお佳代の親孝行が通じたらしく、間もなく回復するとな」、有難いお告げを聞くトヨは、更に仏壇ににじり寄って拝んだ。気が付けば、傍にいるはずの住職の姿は消えていた。
1.gif)
長谷寺の観音像
「お母ちゃん」、か細い声が聞こえた。振り向くと、布団の上にお佳代が正座している。信じられない思いで、お佳代の寝間着を脱がせて傷口を確かめた。ない、傷は跡形もなく消え去っている。お佳代の顔を覗き込んだ。
「どうしたと?、お母ちゃん」、怪訝な顔で見返すお佳代。
「行こう、お寺さんへ」、トヨは娘の手を引くと、寺への坂道を駆け上って行った。
「どうしたんじゃ、おトヨさん?」、落ち葉を掃いている住職が、妙な顔をして訊いた。
「お坊さんは、先ほどうちに来て、観音さまのお告げを知らせてくださいましたよね」
「いいや、わしは朝から掃除ばかりしていて、里には下りておらんぞ」と、こちらもキツネにつままれたように眉を寄せた。
「早く、お坊さん」
トヨは、住職の手を引くと、観音さまの前に倒れ込んだ。なんということか、目の前の千手観音像の右肩には、深い刀傷がつけられている。どす黒い塗料のようなものが傷口の周囲を汚していた。
「わしにも、お佳代の傷が観音さんに移ったとしか思えん。お前らの行いと仏に対する信心が、通じたのかもしれんな」
「お坊さんは、本当に観音さまのお告げを知らせにおいでじゃなったですか?」
「しつこいな、そんなことは知らないといっておるじゃろが」、住職とトヨのやり取りを、見比べながら、お佳代は、静かに右肩をさすっていた。(完)
|
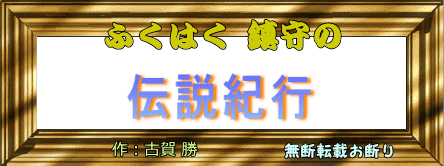
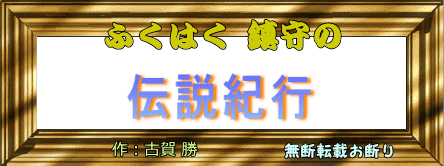
.gif)