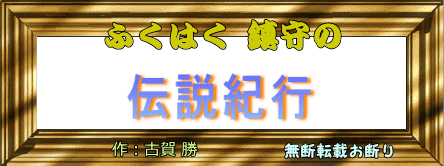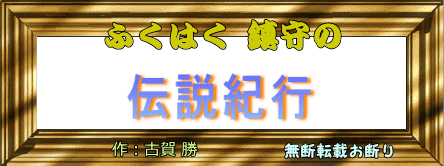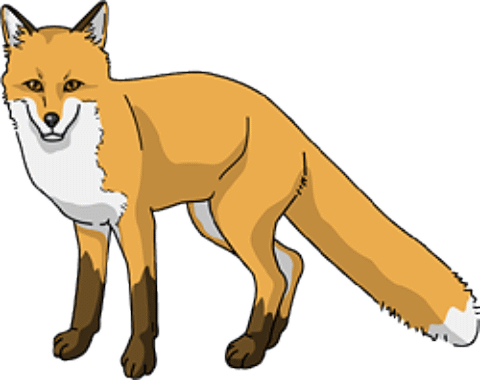| 福岡市中央区大名に、養巴通(ようはのとおり)と雁林通(がんりんのとおり)が並行して通っている。いずれも、本編に登場する鷹取養巴先生と鶴原雁斎(通称雁林)先生からいただいた通のお名前なのだ。雁斎さんの鶴原家は、代々「雁林」を名乗ってきたので、藩医になるとすぐに「雁林さん」と親しみを込めて呼ばれた。
1.gif)
雁林さんが住んだ城下町
今日も今日とて雁林さん。黒田の殿さまの身内のご病気を診たあとは、城下の“お客さん“のご心配ごとにも耳を傾けて、やっと帰宅する頃には陽もとっくに沈んでいた。先生のお屋敷は、今でいう福岡市中央区の国体道路脇の大名1丁目当たり。お城はすぐ向こうに聳えている。
現行犯逮捕のキツネ
「コンコン…」と悲しそうな泣き声で、雁林先生の足が止まった。泣き声はキツネだった。太い松の木に荒縄で縛られていて身動きがとれない状態でいる。キツネは、白っぽい毛に覆われた雌であった。捕まえたのは、高級役人の吉田三之助さん。わけを質すと、屋敷内の池で飼っている錦鯉を持ち去るところを現行犯逮捕したとのこと。
「それで、吉田殿はこのキツネをいかがなさるつもりですか?」と尋ねると、皮を剥いで襟巻にでもするつもりだと言う。そんなむごいことをと言いかけて、
「実はですね、キツネの生き肝は、我が家伝来の腹痛(はらいた)を治す薬をつくるのに欠かせない貴重なものでして…」、とかなんとか口から出まかせを言って、手持ちの小銭を差し出して譲り受けた。
.gif)
福岡城内堀
「腹が減っているお前の気持ちはわからないでもないが、池の鯉を食うってのは、人間社会では通用しないんだよ。今のうちに、あちらに見える油山に帰りなさい。あそこには、名の通りお前の好きな油揚げがいくらでもある」と諭して、お客さんからいただいた握り飯を与え、縛り縄を解き放してやった。命を助けてもらった雌ギツネは、何度も振り返りながら、ペコンと頭を下げて遠ざかって行った。
美女現れる
あれから何年たったかな。雁林さんは京の都にいた。家伝の飲み薬の研究結果を、日本国中の同業者に報告するためである。今日でいうお医者さんたちが集まる学会のこと。
ところが恥ずかしいことに、医者である雁林さん自身が、夜中に激しい腹痛に襲われてしまったのだ。旅籠の暗い部屋で七転八倒しているところに、障子を開けて女が入ってきた。自分の苦悶が漏れたのだろうと、目をつむったままでいた。
「大丈夫ですよ、私があなたの病気を治してあげますから」と、女はお盆に乗せた白湯と一緒に苦い薬を口移しで飲ませた。いつもとは真逆の立場の雁林さん、改めて女の顔を見てびっくり。博多の町ではついぞ見かけぬ色白で、仕草や話しぶりが上品な、絶世の美女であった。
「京の女子(おなごし)ちゃ、どうしてこげんきれいかとかいな」と、うっとり顔が元に戻らなくなってしまった。
「そないに言うてくれはるなら、あんたはんの腹痛が完全に治るまで、ここにいてあげましょう」と、美女は京言葉を駆使して座り直した。腹痛が治まりかけると、雁林さんはいつの間にか深い眠りに落ちてしまった。そして翌朝、目を覚ましたときには、夕べの美女の姿はどこにもなかった。

筆者が久住の山中で撮影した野生の狐(イメージ)
枕元にあるお盆を見たら、そこに白い毛が3本並べてある。「これは確かに獣の毛だ。それもキツネの毛に違いない。さては、夕べの女中は、殺されそうになるところを救ってやった、あの時のキツネだと雁林さんは確信した。
キツネに救われた
雁林さんは、急ぎ支度して帰路についた。山陽道を下りながら、人間でも恩義を感じる奴が少ないのに、「義理と人情」を持ち合わせた白い毛をしたキツネは大したものだ」と感心しきり。途中何度も転びかけたが、運よく助かり切り傷一つない。広島の山の中では、悪い奴に襲われても、落ちてきた岩石がゴマノハイを直撃して難を逃れた。あれもこれも、あの白狐が救ってくれたのか。
無事福岡の城下に戻った雁林さんは、早速屋敷の裏庭に祠と真っ赤な鳥居を建てた。小首を傾げる奥方には、あの絶世の美女を祀るなんてことを言わないで、「ちょっとした思い付きよ」と言葉を濁した。そして、毎朝の赤飯と油揚げ1枚を欠かさず供えるよう命じた。
1.gif)
雁林さんのお名前が今も
それから更に数年がたった宝暦3年(1753年)。浜町から出火した火事は城下から博多の町へと広がり、町中黒焦げになってしまった。世にいう「宝暦の大火」だ。雁林さんは、自分の屋敷に火の粉が飛んでくるのを、屋根に上って必死に防いだ。
「危ない!この家はあたいが守ってあげるからさ、あんたは安全なところにいな」と叫ぶ女がいた。女は、屋根から屋根に飛び移りながら、獣の尻尾のようなものを振りまわして、飛んでくる火の粉を片っ端からはねのけた。
一夜明けると、城下一帯は焼け野が原になっていた。吉田三之助の豪華な建物も、跡形もない。あの錦鯉が泳ぐ池は産業廃棄物の山になっていた。雁林さんは、痛む足を労わりながら我が屋敷にたどり着いた。家は大丈夫かと心配するより、奥方の命の方が心配だった。
不思議なこともあるものだ。雁林屋敷だけは類焼を免れて被害はほとんどなかった。「旦那さま!」、と叫びながら、子らの手を引く奥方と、後方から雇人などが雁林さん目掛けて飛びついてきた。
その時屋敷の裏手から、火消し男の大声が飛んだ。「白いキツネが、体中焼けて死んどる!」と。
すっかり陽が沈んだ大名の繁華街をを歩いた。狭くて、S字型で、カギ型の通路が行き交う窮屈な町だ。向こうの方からでっかい金属音が。天神ビックバンなる、町ぐるみ変形させる大工事の真っ最中だった。雁林さんが住んだ城下もすっかり様変わりしそうだ。
先生の住み家を探し回ったが見つからない。わずかに気配を感じたのは、「雁林町通り」の電柱掲示と、「雁林ビル」という名のビルの標識だけだった。
参考資料:佐々木滋覚著「九州伝説夜話・雁斎と狐」
|