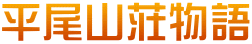

2024/02/04
11.gif) 
復元された平尾山荘&野村望東尼像
福岡市内に定住して40年。恥ずかしながら、すぐ近くにある貴重な「文化遺産」を見過ごしてきました。福岡市中央区平尾5丁目に建つ平尾山荘のことです。倒幕派と佐幕派が激突した江戸末期、ここ平尾山荘も重要な舞台となっていました。
当時平尾山荘の住人野村望東尼(のむらぼうとうに・旧姓野村モト)は、大田垣蓮月・中山三屋と並ぶ江戸時代を代表する女流歌人でした。特に、野村望東尼と中山三屋は、勤王女流歌人として討幕運動に貢献した人物として有名です。
執筆にあたり、改めて平尾山荘とその周辺を探索しました。復元された山荘は、西鉄平尾駅と動・植物園で賑わう南公園の丁度中間地点にあたります。山荘の周辺でまず気がつくのは、坂道だらけの住宅街であることです。一カ所たりとも、平らな道が見当たりません。
望東尼が過ごした頃の平尾村は、古木に覆われた丘陵地帯であり、山を伐り開いた典型的な農村地帯でした。手元の郷土史を紐解いてみます。当時の戸数は150戸、人口643人、田53町歩、畠17町余とあります。
江戸末期、そんなのんびりした丘陵地帯に、藁葺きの一軒家が建ちました。家の広さは、6畳・3畳・2畳の3間で、厨房と土間を合わせても10坪に満たないほどです。家の周りには雑木が密集していて、外からではそこに誰が住んでいるかも伺うことは出来ません。それが、野村望東尼が住処とした平尾山荘なのです。
ボクはこれまで、身近に隠れている歴史や民話を探し求めてきました。今回は、望東尼の女流歌人としての生き方を、彼女が歩いた足跡を追いかけながら深掘りして参ります。

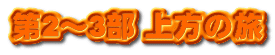

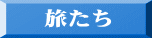
夫貞貫がこの世を去って2年が経過した。文久元年(1861年)の秋も深まった時期である。山荘での一人暮らしも、なかなか慣れないでいる。人恋しさが増すばかりである。
諦めきれない望東尼は、師の大隈言道に会えないのなら、こちらから出向いていこうと決意した。頭を丸めて初めての遠出である。野村家の当主となった貞一は猛反対した。義母の年齢は既に57歳に達している。60歳といえば、完全に老人の域に入る時代である。上方での遠出を、義理とはいえ息子として見ぬふりなどできるわけがない。それでも、望東尼は上方への長旅を譲らなかった。
この決断が、後の彼女の人生を決定づけることになる。

望東尼にとって、生まれて初めての上方旅行である。400石取りといえば、そのほかにも、手繰れば強力な縁故もたくさん居るはずである。それに、野村家に嫁いできて30年余りの実績が、不安を取り除かせる自信にもなっている。
親類や知人に見送られて福岡を発ったのが、文久元(1861)年11月24日の早朝であった。旅をともにしてくれるのは、大隈言道の高弟子で野坂常興と、所用で上方に向かう親類筋の藩士高谷弥太夫であった。
出立する時期、江戸では佐幕派と勤王攘夷派の対立がますます激しさを増していた。だが、それらの事件が、望東尼の足を止める枷(かせ)にはならなかった。
文久元(1861)年11月24日、望東尼の旅が始まった。明治維新から遡ること7年前である。旅の供をする野坂と高谷は結構気が合うらしく、終始賑やかな旅となった。福岡から門司の港までは、唐津街道を徒歩で行く。門司で渡し船に乗り馬関(関門)海峡を渡って下関へ。下関を出航したのが12月1日の朝であった。
途中、3人は気ままに船を降りながら名所旧跡に足を踏み入れた。これも望東尼の当初からの目当てであった。多度津港を降りて金比羅宮に詣でる。その日は参道沿いの大きな旅館に泊まり、船上での不安定な寝床からしばし解放される。
.gif)
金比羅宮参道
赤穂城を船上から望み、かつての赤穂浪士を偲んだ。6日目には、上陸して楠木正成の墓地を訪ねた。この墓には志士らが多数参拝していると聞いたことがある。後に望東尼に関係する人物だけでも、三条実美・西郷隆盛・高杉晋作・平野国臣らが名を連ねている。
大坂港に入ると、安治川を遡り中之島で下船した。7日間の船旅はここで終わった。
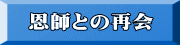
中之島で船を降りた望東尼らは、福岡藩の御用商人を努める津嶋屋藤蔵邸が宿泊所であった。翌日は、高谷と二人で今橋に住む大隈言道の住まいを尋ねた。二人とも、師との再会は4年ぶりである。
「よう来たな、高谷君もモトさんも。ご主人が亡くなられて、モト君もさぞ辛かったろう」
大隈は、夫婦ともに和歌の弟子であった望東尼に、貞貫の悔みを伝えた。改めて再会を喜ぶ間もなく、大隈は望東尼を連れだした。途中船場あたりを通る際、忙しそうにすれ違う人の多さに酔ってしまいそうになる。
a
大坂中之島の賑わい
連れて行かれたところは、大坂で四大呉服商の一人と言われる商人の屋敷であった。主人も大隈言道に和歌を習う弟子だと知らされた。屋敷内の庭や造りは贅を尽くしたものばかり。これまでに見たこともない置物が誇らしげに飾ってある。食事が出て、そのあとに雅な舞踊が囃子に乗せて座敷を華やかにする。時の経つのを忘れる思いであった。
次の日、大隈が連れ出したのは、鼈甲屋の邸宅である。剪定された黒松を配した庭園を散策のあとには、宴会が待っていた。接待する豪商の妻は、見た目も大名の奥方気取りであり、調子を合わせるのに苦労した。それにしても、大隈言道の顔の広さには、舌を巻くばかりである。
大隈言道に紹介される中には、福岡藩の大坂蔵屋敷に勤める者も多かった。全国から大坂に集う各藩は、堂島川・土佐堀川・江戸堀川の岸辺に大坂蔵屋敷を有している。蔵屋敷とは、各藩内で得た収穫物を売り捌くまでの間、所蔵する施設のことである。藩は、これらを中之島の取引所で売りに出し、藩の利益にする。現在、その福岡藩蔵屋敷の建物が、四天王寺の美術館敷地内に保存されている。
望東尼の宿泊所は、津嶋屋から本町の旅籠に替わった。そこへ、京都の呉服商大文字屋の番頭がやってきた。望東尼は番頭に連れられて、大隈とともに大文字屋の大坂支店を訪ねた。店には主人の比喜多五三郎が待っていた。
「ようこんな遠いとこまでおいでなさったな。わては京都の商売人だすが、たまたま大坂に来てましてな。大隈先生に知らせてもろうて、あんさんにお会いでけてほんまに嬉しいわ」
遠い九州から出て来た博多の女流歌人を、上機嫌な面持ちで迎える五三郎である。そろそろお暇しようと、大隈が目配せしたときだった。五三郎が膝を乗り出した。
「わて、あした京に帰るさかい、ご一緒しまへんか」と誘った。
「それはよかですな。モトさん。いや、望東尼さんでしたな。せっかく大坂まで来やはったんやさかい、ゆっくりみやこ見物でもしてきたらよろしいがな」
誘った五三郎より、大隈の方が熱心である。
「もっと、言道先生の傍にいたいから・・・」とも言えず、望東尼は京都行きを承知することにした。
「ほな、準備もありますやろから、ここらで・・・」
五三郎も、京都までの道中が楽しみだと言って別れた。
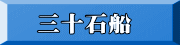
望東尼は、大坂を離れるのが辛かった。大坂というより、4年ぶりに会った師匠の言道と別れるのが切なかったのである。
翌朝、比喜多五三郎一行は、淀川を遡る三十石船(さんじっこくせん)に乗りこんだ。夕刻には京都の伏見港に着く上り船である。発着場に言道の使いの少年が現れた。師からの手紙を手渡すとすぐに走り去った。どうして、ご本人が来てくれないの。言道のつれなさに、心に重いものを感じずにはいられなかった。
.gif)
伏見の川港と復元された三十石船
生駒山あとに漕ぎゆく淀舟ののぼりたゆたふわが心かな
上流に向かって滑り出した三十石船では、五三郎が左右を指さしながら、得意げに名所旧跡を案内した。途中石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)を通過するときには、五三郎の声がますます勢いづいた。淀川は、石清水八幡宮あたりで大きく三つに分岐する。奈良に向かう木津川と嵐山への桂川、そして彼女らが向かう伏見方面への宇治川である。
伏見の船着き場は、その宇治川の途中に設けられていた。(現在は京阪本線中書島駅付近の宇治川公園あたり)
船着場が近づくと、やはり傍に言道の姿がないことが気になって仕方ない。三十石船は、江戸時代、淀川の京都―大坂間を往復する30人乗りの乗合船で、上りは岸からの曳き船、下りは流れを利用して運行する。


比喜多五三郎の邸宅は、上立売(かみだちうり)=(現上京区上立売町)の大文字屋本店と隣り合わせに建てられていた。伏見から上立売まで、距離にして3里余りである。陽が落ちているせいもあって、どこをどう進んだのか見当もつかなかった。
「御所はすぐそこです。反対方向に歩くと間もなく金閣寺…」
主人一行を出迎えた番頭が、客人の望東尼に説明した。上京翌日、大文字屋からの知らせを受けて、福岡藩京屋敷(筑前黒田屋敷)に勤める吉松言正がやってきた。大文字屋は、福岡藩御用達にふさわしく、福岡藩京屋敷の目と鼻の先で暖簾を張っていた。
※京屋敷:全国に散らばる藩が、藩主の参勤交代の際の宿泊所であったり、江戸-国元の連絡の場合の中継所として、京都に設けていた施設。
望東尼が生来尊敬してきたのは、藩主と天皇であった。そのせいもあって、京都名所を案内すると言う吉松に、淀みなく御所まで連れて行ってくれるよう頼んだ。大文字屋を出ると、すぐ今出川通である。番頭が言うように、京都御所は目と鼻の先にあった。

京都御所
この塀の向こうには、大君(天皇)や公卿さまなど、雲の上の方々が大勢お住まいになっておられると考えるだけで、身震いするほどの感動を覚える。遙か彼方まで続く玉砂利を踏みしめながら、手入れされた黒松の列を伝うようにして進んだ。
ふるさとを出立して1ヶ月経って大晦日。夜中になると、八方から除夜の鐘がもの悲しく伝わってくる。望東尼にとって、運命的な文久2年(1862)の夜明けであった。明治維新から遡ること6年前である。彼女にとっても57歳の新春であった。
せっかくの京都滞在である。この機会に、一カ所でも多くの名所を巡り、和歌つくりの糧にしなければと思う。まさしく田舎者の物見遊山であった。
元日には、散歩コースにもなった御所の前に出た。この日案内するのは五三郎夫妻である。途中往来する鳥帽子姿の従者を見れば、その仕草を観察して興奮を抑えきれないでいる。1月3日は下鴨神社へと足を向けた。この日から安相役は手代の馬場文英に替わった。4日は上賀茂神社へ。5日には福岡藩の手回しで、特別に御所に入ることを許された。 老舗呉服屋の持つ人脈が活きたのだと思った。
御所内では、新年を祝う千秋万歳(せんずまんざい)や猿楽(さるがく)などが華やかに催されていた。子供の頃からの願望であったみやこの貴人との触れ合いが現実となったのである。これも、福岡藩から御所へと通じたからであろう。
※千秋万歳:中世期に存在した民俗芸能。大道芸の一種である。
※猿楽:古くは「さるごう」とも呼ばれた、能と狂言で構成される能楽の一種。

望東尼は、京都に到着以来寸暇を惜しんでみやこ見物をしているうちに、自らの体力との相談を怠っていた。もともと身体は強い方ではなかったから、一度上がった熱はなかなか元に戻らない。
そんな折、気を遣ってくれるのが京屋敷(福岡藩邸)の藪幸三郎夫妻であった。忙しい商家では身体も休まるまいと、自分の家に移るよう誘った。言葉に甘えて藪家に転居したのは、御所の梅が咲き始めた頃であった。
ようやく体調も回復した4月15日。望東尼は十文字屋五三郎に誘われて伏見に出かけた。福岡藩主の黒田長溥(くろだながひろ)が、参勤交代の途中京都に立ち寄ると聞きつけたからである。五三郎は、この際藩主に対して、日頃の恩に感謝の念を述べるつもりであった。福岡藩士野村貞一(長男)の義母であり女流歌人の望東尼を、藩主に引き合わせる魂胆であった。
「大坂から上ってきたときは、陽が落ちていて暗かったさかいな。周囲がよう見えんじゃったから」
言われて眺めれば、宇治川からひかれた人工河川の周囲が華やかである。遊郭群であった。
「ここは酒造りの本場じゃ。酒のあるところに男の遊び場が集まってくるというわけよ」
現在の京阪電鉄中書島駅から歩いてすぐの、伏見の川港であった。
「あの看板は?」
望東尼が目を向けた先の建物には「船宿」の提灯が下がっている。
「寺田屋というてな、宿屋どすがな。聞くところによると、薩摩とか長州のお侍さんたちが、毎晩のようにお泊まりだそうな」
京都に着いて間もない望東尼には、それだけの説明では、この時代の政争の奥深さなどわかりようがない。世に知られる「寺田屋事件」は、望東尼が訪れた日から8日後に起こっている。
※寺田屋事件:幕末、京都伏見の船宿寺田屋で、尊攘派志士が殺傷された事件。
福岡藩主・黒田長溥の行列は、いくら待っても姿を見せない。
周囲にいた役人に様子を聞いた。返事は、播州大蔵谷で不穏な動きを察知したため、行列は西へ引き返したとのこと。この事件を、歴史家は「大蔵谷回駕(おおくらだにかいが)」と呼んでいる。
やむなく上立売の屋敷に引き返した五三郎は、藪幸三郎に頼んでことの成り行きを調べてもらった。わかったことは、「不穏な動き」の中心人物が、福岡藩士の平野国臣(ひらのくにおみ)だということ。当然望東尼は、平野という人物を知らない。だが、大蔵谷回駕事件は、比較的平穏に過ごしてきた福岡藩を、「明治維新の隠れた主役」に押し上げることになるのである。

望東尼の京都見物は、滞在期間が半年に迫ってもなお続いた。4月には上賀茂・下鴨神社で執り行われる葵祭へ。大人気(おとなげ)もなく、見物客の先頭に出てしまうほどに興奮した。その後も馬場は、嵐山や奈良・吉野方面など、遠方へも進んで案内した。
※葵祭:京都の三大祭り(葵祭・時代祭・祇園祭)の一つで、上賀茂・下鴨神社の例祭。日本最古の祭りと言われる。
4月も終わりの頃、望東尼は、公家の千種有文を訪ねた。公家の千種には、編纂中の歌集に序文を書いてもらうつもりであった。千種有文といえば、孝明天皇の妹和宮を徳川家茂に嫁がせる、所謂公武合体論に熱心な公家である。望東尼が尋ねた4ヶ月後には、千種有文は閉居の身となっていた。公武合体論を敵視する一派に、退けられたのだった。結局、依頼した序文は、望東尼の許に届くことはなかった。
望東尼は、嵐山見物の帰り道、頭から離れないことを馬場文英にぶっつけた。
「どうして、薩摩の島津さまは、身内のご家来衆までお斬りになったのでしょう?(寺田屋事件)」「千種有文さまが、糾弾されなければならないわけは?」
みやこ見物で心が浮つきがちだった望東尼が、目の前で見せつけられた「事件」の意味を理解したかったからである。馬場文英は、望東尼からの問いに、しばし目を閉じて考え込んだ。次に見開いた目は、みやこ案内時のにこやかさが一変していた。ギラギラ光る眼が彼女の表情をも固まらせたのである。
「貴女が考えているほど、今の世の中は平穏ではありませんよ」
「どういうことなの?平穏じゃないって」
望東尼もつい大きな声で聞き直した。
「いつ京都で戦いが始まるかわからないということです。これ即ち、幕府の力が日に日に落ちてきて、公武合体論が力を増してきたからです」
※公武合体論:幕末、公家(朝廷)と武家(幕府)が提携して、政局を安定させようとする主張。
馬場は、昨今の都の政情をこと細かに話し始めた。
「もう一つ、お尋ねしてもよろしいか?」
「どうぞ」
「先日比喜多さまと伏見にご一緒した際、福岡の黒田藩主さまを乗せた駕籠が上洛なさらなかった本当の理由(わけ)を教えてください。回駕の原因となったとされる平野国臣さまとはいったい…」
「どういう人物か知りたいのですね。皆さんの先頭に立って尊皇攘夷論を世の中に広げているお方です。黒田のお殿さまも、行列を妨害した者が誰かわかってらっしゃった。しかし藩内には、尊皇攘夷派のお方もたくさんおられるし…」
馬場が彼女に伝えた大蔵谷回駕の顛末は、次のようなものであった。
望東尼らが伏見で待った4月15日より2日前、福岡藩主の黒田長溥を乗せた行列が、播州大蔵谷宿に到着した。その後、本陣に2人の男が入ってきて、藩主への面会を申し出た。応対した者が面会を断ると、男は「京都滞在中の島津久光公からの書状でござる」と言って懐から取り出した書状を手渡すとすぐに立ち去った。
あとで書状を確かめた藩主長溥が驚いた。薩摩の島津久光からとは真っ赤な偽りであり、黒田長溥当ての「平野国臣」名義の建白書であった。
内容は、「我ら尊皇攘夷派の同士とともに、倒幕の戦いにご賛同いただきたい」というものであった。
黒田長溥は、平野国臣からの書状を見て驚き、急ぎ参勤の方向を福岡に逆転させた。これが、後の世まで伝わる「大蔵谷回駕」と呼ばれる事件である。
「それで、平野さまはどうなされたのですか、その後」
「帰国途中、福岡藩の役人に捕まったそうです。それ以上は私にもわかりません」
公武合体論を振りかざす一部の公家・武家と、270年の間、武家社会を死守してきた佐幕派との対立は、抜き差しならぬ所まで進んでいると馬場文英は言う。
「それでも、この国には天朝さま(天皇)がおいでです。かけがえのない崇拝すべきお方の…」
「わたしの考えも、貴女と同じです。武士の世は終わっても、天朝さまの立場は変わってはいけないのです」
それならば、公武合体を持論とする千種有文さまの立場はどうなるのか。望東尼の考えは、それ以上先に進めなくなった。馬場の話を聞いて望東尼は、京都で物見遊山に呆けている自分が情けなく思えてきた。

京都滞在も半年が過ぎた頃、心境を詠んだ。
ふるさとも菖蒲葺(あやめふ)くかと競馬見るうちさえも思いやられし
間もなく京都を後にしようとする5月、すっかり馴染みとなった上賀茂神社で、競馬(くらべうま)を観ての感想である。
※競馬(くらべうま):天下太平と五穀豊穣を祈って行われてきた神事。
半年の間福岡の地を離れて、すっかり都の風に酔いしれていた。もの珍しさと、我が身の400石取りの立場の有利さに甘えた旅でもあった。京都を離れる際には、馬場に大坂まで送ってもらった。馬場文英とは、福岡に戻った後も連絡を保ちたかった。滞在期間中動き回ったせいで、疲れもかなり積もっている。
浪速潟(なにわがた)なごりの波にこぎわかれ君のたよりをふるさとに待つ
馬場に対する惜別の念を詠めば、馬場文英も。
浪速潟なごりの海はへだつともよせくる波に音づれやせむ
と返して、将来の再会と今後の交流を誓った。
大坂に立寄った望東尼は、名残り惜しさも手伝って、再び大隈言道の家を訪ねた。だが、大隈は遠方に出かけているということで留守だった。わざわざ九州から出かけてきたのは、大隈言道に叱咤激励を受けるためだったのではなかったか。悔しさと切なさを重ね合わせながら、望東尼は船に乗り込んだ。帰りは、所用で大坂に滞在していた福岡藩士の岡部某と同じく藩士の腰元下枝(しずえ)が同行することになった。

|
11.gif)

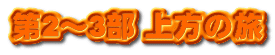

.gif)

.gif)

