|

福岡市内に定住して40年。お粗末ながら、すぐ近くに保存されている貴重な「文化遺産」を見過ごしてきました。福岡市中央区平尾5丁目に建つ平尾山荘のことです。倒幕派と佐幕派が激突した江戸末期、ここ平尾山荘も重要な舞台となっていたのです。
平尾山荘の住人野村望東尼(のむらぼうとうに)(旧姓野村モト)は、大田垣蓮月・中山三屋と並ぶ江戸時代を代表する女流歌人でした。特に、野村望東尼と中山三屋は、勤王女流歌人として討幕運動に貢献したことで有名な人物です。
執筆にあたり、改めて平尾山荘とその周辺を探索しました。復元された山荘は、西鉄電車の平尾駅と動・植物園で賑わう南公園の丁度中間地点にあたります。山荘の周辺でまず気がつくのは、坂道だらけの住宅街であることです。江戸時代まで城下に隣接した里山からなる農村でしたから、当然のことではあります。
望東尼が過ごした頃の平尾村を、手元の郷土史で紐解いてみます。当時の戸数は150戸、人口643人、田53町歩、畠17町余とあります。
そんなのんびりした丘陵地帯に、江戸末期藁葺きの一軒家が建ちました。家の広さは、6畳・3畳・2畳の3間で、厨房と土間を合わせても10坪に満たないほどです。家の周りには雑木が生い茂っていて、外から中を伺うことは出来ません。それが、野村望東尼の平尾山荘だったのです。
身近に隠れている歴史や民話を探し求めてきた筆者として、彼女の女流歌人としての生き様を深掘りしたくなりました。
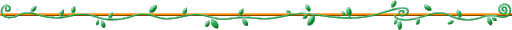


望東尼の前半生を、少しだけ振り返っておきたい。結婚する前の名前は浦野モト。文化3年(1806年)、300石とりの福岡藩士浦野重右衛門勝幸の三女として生を受けた。
産声を上げた場所は、福岡城の南門にあたる追廻橋(おいまわしばし)を出てすぐ近くの、南谷赤坂御厨後(おうまやのうしろ)である。今日の住所に置き換えれば、中央区赤坂3丁目で護国神社の東側一帯を指す。
近所には、御馬方や鷹匠など200石から500石取りの中級武士が多く住んでいた。モトの父親も御馬方に組み入れられていたようである。
.gif)
望東尼生誕の地(福岡市赤坂)
モトは生まれるとすぐから、父親が決めた道を進むことになった。幼くして習いごとや行儀見習いに追われ、17歳で20歳上の藩士と結婚させられることになる。だが、年齢の離れ過ぎた夫婦生活はうまくいかず、半年後には嫁入り先を出て実家に戻ってきた。
その後のモトは、幼い頃から習っていた和歌詠みに没頭することに。近所の仲良しと通う二川塾(ふたがわじゅく)は、その後の歌人としての人生を形成する大きな踏み台になった。
モトの2度目の結婚は、24歳を過ぎてからだった。双方とも再婚である。相手はやはり福岡藩士で、413石とりの野村新三郎貞貫(のむらしんざぶろうさだつら)。歳の差は11で、石高は実父や前夫よりかなり格上である。
モトが再婚を決意したきっかけは、野村貞貫が同じ和歌を教える二川相近(ふたかわすけちか)塾の熟生であったことだった。
モトの姓が、浦野から野村へと変わった。嫁いだ先は、城下の林毛橋袂にあった。現在の国体道路沿いである。後妻として嫁いだ先には、先妻の男の子が3人いた。長男は貞則、次男は貞一、三男は雄之助である。モトは、後妻として生きていくために、義理の子らに心遣いを惜しまなかった。時を経て、世の習いとして次男と三男は他家へ養子に出され、長男の貞則だけが野村家に残って嫁をもらうことになる。
夫貞貫は生来身体が弱く、その上藩内での出世争いを得意としない優しい性格の持ち主であった。結婚後15年が経過して、貞貫は成長した長男の貞則に早々と家督を譲り、隠棲することにした。藩士仲間から紹介された城下平尾村の土地を手に入れ、そこを晩年の住処と決めたのである。新しく建てる家は、野村家から半里(2㌔)ほど南方の丘陵地帯であった。
「ここなら、何かと気を使う武家屋敷からも離れられるゆえ、気持ちも落ち着くだろう。それに、子供や孫に会いたければ、気軽に行き来できる近さだし」
モトにも言い返したいことはあったが、黙って従うことになった。
「わしも、モトに負けないように、大隈先生のもとで和歌づくりに励みたい」
平尾山荘に家移りしてしばらく経って、貞貫が言い出した。「大隈先生」とは、望東尼の和歌の師匠である大隈言道(おおくまことみち)のこと。引っ越しが済むと、早速夫婦揃って今泉(現警固神社近く)に居を構える大隈言道の塾に通うようになった。その頃に望東尼が詠んだ句が残っている。
音もなき寛の水のしたたりもたりあまりたる谷の一つ家
師の大隈言道は、彼女の才能を見込んで歌集をつくるよう誘った。その後は、夫婦して大隈言道(おおくまことみち)の指導を受けながらの、「歌集向陵集」の編集に励んだ。「向陵」とは、彼女が住む丘陵地帯の風景から名付けたもの。

平尾村に転居してから10年が経つと、夫の身体が痩せ細っていった。医者に診てもらったが、はっきりしたことを言ってくれない。いよいよ、最悪の時がきた。夫は、山荘に駆けつけた長男の貞則や孫の助作などが、傍についていることさえわからなくなっていた。
貞貫が息を引き取ったのは、安政6(1859)年7月28日の早朝であった。夫が残していった子供や孫たちの行く末を、すべて後妻の自分が見なければならないことを考えると心配でならなかった。僧侶の読経の間、微笑んでいるようにさえ見える夫が恨めしくもあった。そのとき浮かんだ感情を詠んだ句である。
うち群れて庵(いお)はいづれど君ひとり帰らぬ旅となるぞ悲しき
貞貫、享年65歳であった。遺体は長男貞則が住む林毛町の本宅に運ばれた。山荘に一人取り残されたモトは、ありったけの声をあげて泣いた。山荘が雑木と畑で囲まれているため、誰一人彼女の叫びを気にかけるものはいなかった。
12.gif)
野村家墓所、左:望東尼生前墓
貞貫の初七日が過ぎて、モトは野村家の菩提寺である呉服町の明光寺(現在は吉塚に移転している)を訪ねた。住職に得度(出家すること)を願い出た。住職は、仏門に入る心得を承知することを条件に承知した。
「そなたの名はモトであったな」
住職は、一枚の和紙にモトに与える法名を書いた。「招月望東禅尼(しょうげつぼうとうぜんに)が、これからの名前である」
この世に生を受けて以来、慣れ親しんできた「モト」の名と決別するときであった。
「ご住職さま、もう一つお願いがございます」
モトは頂いた自分の名前にたじろぎながら、次なる願いを申し出た。
「野村家の墓の隣りにもう一つ、私の墓を建てることをお許しくださいませ」
聞いて驚いたのは、住職である。
「この墓は、亡くなられたお方が眠る場所ぞ。現にそなたはそこに生きておるではないか。ご遺体と同居できるわけはなかろう」
「わかっております」
生きている自分の墓を、夫のそばに建てると言う。「生前墓」のことである。「生前墓」なら、長生きを果たすためのおまじないとして、仏も許されるであろう。間もなくして、望東尼は夫が眠る墓の脇に小さな墓を建て、墓石には「望東尼墓」の碑銘を彫った。墓室には、住職に剃り落として貰った自らの頭髪を納めた。夫の遺骨さえ思うようにならない後妻の辛さである。新しい自分の墓の建立は、家族や一族に対するせめてもの意地であったのかもしれない。
庭の池で泳ぐ鯉にうつろな目を向けて、モトの目頭は濡れたままであった。これから残された人生を、女一人でどのようにして過ごせばよいのか。

師匠大隈言道に勧められて始めた歌集「向陵集」の編纂も、なかなか先に進まない。こんな折には、なによりも師匠からの叱咤激励が必要なのだが、その人は大坂に去っていて福岡にはいない。今でも師匠に会いたいと、胸が締め付けられる。
そんな折、林毛町の自宅から孫の助作が訪ねてきた。助作は長男貞則の継嗣(長男)で21歳。元服もとおに済ませていて、月代(さかやき)の青さがなんとも初々しい。
「おばば上、何をしているのですか」と近づいてくる。わざと知らぬふりをしていると、「ぼんやりしていると、池に落ちて鯉にかじられますよ」と孫が大きな声で注意した。縁側に座り直すと、助作もぬくもりが伝わる隣に座り込んだ。
「おばば上は、元気で歌を詠んでいるかと、みんな心配しております」
助作は、林毛町の実家との連絡役を担っているようだ。そこに瀬口三兵衛がやって来て会話に加わった。三兵衛は助作より7歳年上で、よき遊び相手であった。勤めの傍ら、山荘にきては望東尼に和歌づくりを習っている。お城の内情や城下のことなど、事細かに情報を伝えてくれるのも三兵衛であった。
望東尼は、丸めたばかりの自分の頭を撫でながら、助作と三兵衛の会話を嬉しそうに聞き入った。山荘にやって来る若き藩士は、三兵衛に限らず望東尼のことを「ハハウエ」と呼ぶ。
「おハハウエ、江戸では大変な騒ぎが続いておるそうですよ。長州の吉田松陰先生が、江戸伝馬町の獄舎で打ち首になられたとか。最近では、幕府の大老さま(井伊直弼)が、江戸城の桜田門を出られたところで襲われたそうです」(桜田門外の変)。
「それは大変だ。天皇さまや公卿さまたちが、無事であればよいが」
近い将来幕府による取り締まりが我が身に迫ることになろうとは、このとき考えも及ばないことであった。
夫貞貫が亡くなって2年が経過した。毎日やってくる瀬口三兵衛から、藩の事情や藩主の仕事ぶりなどを聞くのが唯一の山荘外との繋がりにもなっていた。
|

1.gif)

1.gif)
![]()