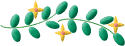
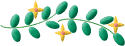
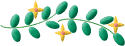
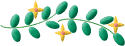
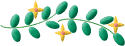
第12章
Kahdestoista runo
→前章からの続き。
…などと面白おかしく言ってみたものの、この章から後はとっても意訳しづらい状況です。それに、ジジイが出てこなくてちょっと寂しい。
悲しいかな、この章も若くてハンサムなレンミンカイネンが主人公。
故郷の村で、攫ってきた乙女、キュッリッキとの新婚生活を平和に続けていたレンミンカイネンですが、ある日のこと、妹アイニッキが彼に告げます。
「兄さん、義姉さんが約束を破って村へ遊びに出たわよ。」
それを聞くなり、レンミンカイネンは大激怒。妹…、あんた家庭をブチ壊す気かい。もーちょっと言い方はなかったんですかね。
結婚時の約束を妻に破られキレた彼は、そんなら自分も約束を破ってやる、とばかり、戦に行くと言い出します、この時代、略奪行為は当たり前。もっとも、カレワラに出てくるのは剣ふりかざすゲルマンの英雄達ではありません。この物語の世界では、あくまで知恵ある者、吟遊詩人や賢者が最強なのですから。
レンミンカイネンの目的は、戦に行ってどうこうっていうより、「ウサ晴らしに戦わせろ」程度のもの。ついでにキュッリッキに代わる、新しい妻を攫ってこようとか画策しています。
母と妻は必死に止めました。「ポホヤへ攻め込むだって? お止し! あそこには、強い呪術師たちが沢山するんだよ。」 「ふん、心配すんな、おふくろ。ラップ人(エスキモー)たちなんざ、大したモンじゃないね。」 「バカをお言いでないよ。お前、トゥリヤ・ラップの言葉(ラップ人が唱える特殊な呪文らしい)も使えないくせに!」
驕慢なレンミンカイネンは制止を聞かず、戦の準備を整え、さらに魔法の歌で自分に対し防御壁をつくりました。いわゆるマジック☆バリアってやつです。ポホヤの地は、呪術師たちが溢れているので、生身で行くとかなり危険。魔法攻撃は、盾で物理的に防ぐのは不可能ですからね。
それにしても、レンミンカイネン、単なるスケベな乱暴者かと思っていたら魔法も使えたんですねえ。うーん、やるな。
彼は、金の鬣を持つ愛馬に飛び乗り、北の地を目指します。やって来たのはポホヤの村、そう、前にワイナミョイネンやイルマリネンも来ていた、あの村です。
当然ながら、略奪に来た彼を好意的に迎える者はいませんが、レンミンカイネンは全く意に介せずもいちばん奥の立派な屋敷を目指します。
そここそが、ポホヨラの魔女、ロウヒの館。
庭番の犬を魔法で眠らせ、呪文で変身した彼は、やすやすと邸宅内に忍び込みました。厳重警戒の館に難なく入り込むとは、まるでルパ○3世です。
中には、ロウヒの手下の魔術師や吟遊詩人たちがぞろぞろと控えていました。普通に剣を持ってる人もいたようですが、軍のほとんどは魔法使い系のキャラです。これがシュミレーションRPGなら、ソッコーで全滅してもおかしくないメンツですが、なんせカレワラ世界は賢者が最強職ですからね。
臆することなく、レンミンカイネンはそこにいた面々に宣戦布告します。
「歌ってのは、短いほどに美しい。てめぇらの歌も、途中で終わっちまうより、自分たちで止めたほうが得策ってモンだぜ」 「な、なんだと?! 貴様は一体…う、ううっ?!」「なんだ、これは」
相手のセリフ最後まで聞かずに、レンミンカイネンはさっさと呪歌をはじめます。フイをつかれた魔法使いたち、防御するヒマもなく魔法にかかって戦闘不能。強い、強いぞレンミンカイネン。っていうか、本当にル○ン3世みたく眠りガスとか仕込んでたんじゃないの?
けれど、彼はただ1人、その中にいた盲目の門番、マルカハットゥにだけは呪文をかけませんでした。
哀れみではありません。侮辱です。「貴様、なぜ、わしを助けるのだ。」「ふん…助けたわけじゃないさ。お前のようなシスコン野郎(※原文では、もっとダイレクトな表現です。)に何も出来やしないと思ってな。」
門番、プチ切れた!
どうやら「シスコン」という言葉は、この世界では「お前なんか男じゃない」と同じくらい侮辱的な言葉のようです。しかし真っ向から戦っても負けるだけなので、恨みを抱いたマルカハットゥは、逃走を装って姿を隠して機を待つことにします。
自らの自信過剰が余計な災いの種を蒔いたとも知らぬレンミンカイネン(頭はいいんだけど、何か抜けてんだよなあ…)は、手勢を失った魔女ロウヒに対し、堂々と無茶な要求を始めるのでした…。
{この章での名文句☆}
大地より立て、剣士たちよ。泉より立て、剣客たちよ。
森よ、起きよ、部下とともに、
孤独な男を助けるため。
出陣前のレンミンカインが唱える呪文の一部。森の妖精や女神、土の勇士たちを呼び覚まし、
自らの保護を願う呪文。
この時代の人々が、自然にどのような姿を思い描き、また、臨んでいたかが見える幻想的な場面。
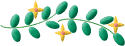
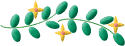
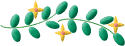
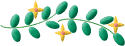
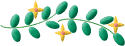
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()