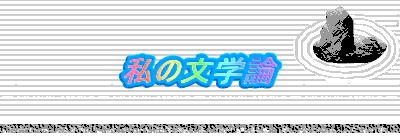
夏目漱石と「坊っちゃん」
1997.5.20記
| 高校生の頃初めて「坊っちゃん」を読んだ。 25才の時小学校の臨時教員になり、初めての土地でもある○○小学校に赴任した。その時「坊っちゃん」の事を思い出した。小説に描かれていた世界がそこにあると思ったからだ。自分が「坊っちゃん」で赤シャツや野太鼓に当たるような人々、イナゴを放り込んだ悪ガキなどもいたように思えたのだ。 こう書くと、当たり障りのある表現だが、新しい世界に入り、自分や周りをこのように感じる人も多いのではないだろうか。特にまだ世間知らずで純粋、正義感の「坊っちゃん」にはそう感じる事もあると思う。 この作品が約90年前の1906年に発表されたものでありながら、未だに若い人に支持され続けている事実はそこにあると思う。いや、43才になり、妻子もでき世間を十分に知ったはずの今の自分にとってもこの作品は共感できるものなのだ。そこに漱石の、純粋であるがゆえの普遍性を感じる。 この作品は漱石が39才の時のものであり、「我が輩は猫である」の後の作品である。そういう事を考えると、人間的にも作家としても漱石の充実期の作品と言っていいと自分は思う。その後の作品群と色合いが違うので、ちょっと突出した感じのある作品であるが、自分はすなおにこう思う。 作家としての自信を持った漱石が、およそ20年前の青春時代の体験を作品化したものがこれである。自身を「坊っちゃん」という形に姿を変えて、言いたい事を言い、やりたいことをやったのがこの作品なのではないかと思うのである。そうであれば、この作品は漱石にとって痛快である。読者である自分も痛快に感じ、爽快に思うのは、漱石のそういう思いが通じるからだろう。 教育の世界においても、偽善者や出世主義者のおべっか使いなどがいるものである。それはどこの世界においても同じだろう。 だが、教育という仮面をつけているだけにそれは余計に腹立たしいものである。生徒にしても同じである。みながみな純朴でかわいらしい存在としてあらわれるのではない。不当に逆らい、からかう、とんでもない輩もいるのである。教育の営みにおいても、くだらない形式ばった事がまかり通っている。 それらは、若者らしい純粋さや正義感にはがまんできぬものであるが、いかんせん若者には力がない、知恵がない、ずるさがない。よいようにあしらわれ、丸め込まれて迎合されるのが一般的だ。漱石にしてもそうだったのだろう。 その悔しさ、理不尽さは20年たった今も漱石に強く残っていたに違いない。それへの対決、戦を挑んだのが、この作品だろう。 しかし、この作品の結末は痛快さだけではない。むしろ孤独感だ。 この世界に「坊っちゃん」の理解者は清一人しかいない。その清も死んだ今、「坊っちゃん」は一人で生きて行かなければならないのだ。 自己の良心、正義感、自由を主張して生きるとは、結局孤独を選ぶ勇気を持つ事でもある。個人主義と孤立感とは共有するものだからである。 |
漱石が死んだ49才に今年自分もなるので、載せてみました。