|
�G�L�����j�J���W��ē�

�g�D�������N�w�i�D�r�D�o�b�n�@���U�ƍ�i
|
�g�D�������N�@�@�w�����̉��y�@�i�D�r�D�o�b�n�@���U�Ƌ���y��i�x |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����̉��y�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�����[�g�E�������N��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�o�u�Y��
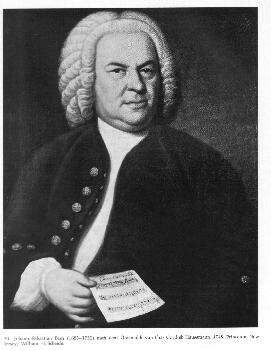
����ɂ��킽���ĉ��y�Ƃ����̐��ɑ���o�����ƌn�̂ЂƂ�Ƃ��āA���[�n���E�Z�o�X�e�B�@���E�o�b�n�́A��Z���ܔN�O����\����A�A�C�[�i�b�n�ɐ��܂ꂽ�B�ނ͏�������.�y�щ��y�̋�����A�g�߂Ȓn�����s�s�A����������B��w�ɂ͂䂩���A�ނ͂������m�����A���������Ƃ��������A�w�Ԃׂ���i�������ʂ��āA�Ɗw�ŏK�������̂ł������B
�u���[�n���E�Z�o�X�e�B�A���E�o�b�n�̏C�w���s�v
�Z�����Ԃł͂��������A�o�b�n�́A�n���u���N�w�̏C�w���s��������݂Ă���B�����Ŕ��͍���̃I���K�j�X�g�A�����E�A�[�_���X�E���C���P��(��Z��O�\�ꎵ���)��m��A�܂������[�x�b�N�ł́A�f�B�[�g���q�E�u�N�X�e�t�[�f(��Z�O�����\�ꎵ�Z��)�̑��ʂȊ��������������̂ł���B
�o�b�n�̉��y�ƂƂ��Ă̊����̓`���[�����Q���ƃU�N�Z���n���ł���B���Ȃ킿�A�A�����V���^�b�g(�ꎵ�Z�O-�ꎵ�Z��)�A�~���[���n�E�[��(�ꎵ�Z���[�ꎵ�Z��)�A���@�C�}��(�����Z��-�ꎵ�ꎵ)�A�P�[�e��(�ꎵ�ꎵ-�ꎵ��O)�ƃ��C�v�c�B�q(�ꎵ��O�\�ꎵ�܁Z)�ł���B
�o�b�n�́A�{�쉹�y�Ƃ����Ă����P�[�e��������̂����ẮA�قƂ�ǂ����A����y�ƂƂ��Ă̐E���ɂ��Ă����B
���̏C�w���s�̖ړI�́A�E���ɂ�����錈����A�o�b�n���g�ł������Ƃ���ɂ������A���݂邱�Ƃ��ł���B�Ⴂ���y�ƃo�b�n�́A�k�h�C�c�n���́A����ň̑�ȋ���y�Ƃ������瑽�����܂ȂB���C���P���ƃu�N�X�e�t�[�f�̓�l�̃I���K�j�X�g�����̐l�����ł���B
�v�N�X�e�t�[�f�́A����y�Ƃł���Ɠ����ɁA�����[�x�b�N�̃}���A����Œ���I�ɂ��炩�ꂽ�L���ȁu�[�ׂ̉��y�v�̎�Î҂ł��������B���̗[�ׂ̉��y�ŁA�u�N�X�e�t�[�f�͎����̍�i�����t�����̂ł���B
���̗[�ׂ̉��y����A�o�b�n�́A�~���[���n�E�[���ł̎��E��̂Ȃ��ɂ���A�ނ̃��C�t���[�N�̍j�̂Ƃ��݂��錾�t�ւ́A���ڂ̂Ȃ�����݂��������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��낤���B�ނ�
�u�����Â���ꂽ����y�v�̕K�v���ɂ��ďq�ׂĂ���̂ł���B
�A�����V���^�b�g����.�~���[���n�E�[���w�̓]���A�܂��A�Ȃɂ����~���[���n�E�[�V�������@�C�}���w�̓]���́A�o�b�n�̐V������Ȃ�����i�ɁA���t�̋@��Ƃ܂������������h���Ƃ�^�����B
�u���@�C�}������v
���@�C�}���ł́A�o�b�n�͍ŏ��A�ꎵ�Z���N����ꎵ��O�N�܂ŁA�{��I���K�j�X�g�ł������B���łɃI���K����i��A�܂��A�Ȃ��ł��ꎵ��l�N�ȗ��J�n���ꂽ�A����I�n������J���^�[�^��i�ɂ́A�C�^���A�̍�ȉƂ����̉e�����݂���B�Ƃ��ɁA�o�b�n���A������I���K���̂��߂ɕҋȂ��A�܂����̍\���́A�̓��^�[�^�̑����̊y�͂ɉe�������������A���g�j�I�E���B���A���f�B�[�̋��`�ȁA����ɓ����ō����̃C�^���A�̌��ƁA�̎��Ƌ����ɂނ��т����A�t�F�N�g ��@�́A�o�b�n���Ƃ炦�Ă͂Ȃ��Ȃ������̂ł���B
�C�^���A���y�ɑ���A���̂悤�Ȑ[���S�ɂ��S��炸�A�o�b�n���C�^���A�w�̏C�w���s����Ă��A�܂��A�ނ̃��@�B�}������ɁA�R���`�F���g�E�O���b�\�̃C�^���A�̉��y��̌��ɂ�������߂Ȃ������Ƃ���ɁA�l�̓o�b�n�̈�w�̋���y�ւ̐E�ƓI���f�̏����݂�ɂ������Ȃ��B���ׂẴC�^���A���y�̉e���́A�I���K���ƃJ���^�[�^��i�̂Ȃ����݂��������B
�u�P�[�e������v
�Z�N�Ԃ̃P�[�e������̃o�b�n�́A����y�ɂ��ẮA�Ȃ��̐ӔC���Ă͂����������B�����J���^�[�^���ق��ɂ���ƁA�n��̏d�_�́A�����ς��y�Ȃɂ�����Ă����B�e�X�̊y��̂��߂̍�i����A�����y�ȁA����ɂ͊nj��y�Ȃ܂ŁA�o�b�n�̍�ȗ���͍L���A�����ʂ�����߂��B�C�^���A���y�ɂ�������o�b�n�̊S�́A�������̊nj��y��i�A�Ȃ����u�u�����f���u���N���t�ȁv�ɂ����Č��������B�����́A�t�����X���x���y�̉e���́A�u�nj��y�g�ȁv�̍�i�ɂƂ��Ɍ����ł���B
�����Â���ꂽ����y��O�Ԗڂ̒��ڂ��ׂ��E�Ə�̌��f�́A�ꎵ��O�N�ɂȂ�����B�P�[�e���̋{�쉹�y�ēƂ��āA���y�E�̈ʂƂ��Ă͍ō��ʂɂ������o�b�n���A���C�v�c�B�q�́A����y�ē̐E�����������Ƃ������ƁA���������̐E���́A�e�[���}���ƃO���E�v�i�[�̎��ނ̂��ƂŃo�b�n�ɒ��ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃ́A����y����������o�b�n�̐M�O�̔��I�Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B

�u���C�v�c�b�q����v
���C�v�c�B�q�ɂ����Ă͂��߂āA�ꎵ�Z���N�ɏq�ׂ�ꂽ�u�����Â���ꂽ����y�v�Ƃ����j�̂��A���̊��S�Ȏ������݂邱�ƂƂȂ����̂ł���B�����ăo�b�n���g�̉��y�Ƃ��āA��������������ꂽ�����鉹�y�l���������݂Ɏg�����Ȃ����Ƃɂ���āA�J���^�[�^�ƃI���g���I���������邱�ƂɂȂ�B���@�C�}������u�I���K�����ȏW�v�̎��Ƃт�̂Ƃ���������ꂽ�A�u���ƍ����_�ɂ̂݉h�����A���A����ɂ���ėאl���P������v�Ƃ����A��d���ӏ��́A���j�����Ƃ̎��ۏ�̉ۑ�ł�����.
���[�n���E�[�o�X�e�B�A���E�o�b�n�̉��l�Ɠ��ɂ��̈Ӌ`�ɂ��Ă̖₢�́A���̐��a�O�Z�Z�N�̋L�O���ׂ��N�ɁA���R�̂��ƂȂ��牽�x�����x���Ƃ肠�����Ă���B'�Ӌ`���₢�ɂ��������ʓI�ȓ����Ƃ��āA�����Ȃ�O��Ȃ��ɁA�N�ł������ڌo���ł���o�b�n�̉��y�̂Ȃ��ɂ���u�������v.�����������B
�u�o�b�n���y�̎��������v
�o�b�n�̉��y���l�͒N�ł��A���̉��y�̍\���S�̂ɓ��݂���v�l�̖������ɖ��f�����B���������̒������Ƃ��������́A�����ĉ��y�n���ɕK�v�ȑz���͂�����������̂��͂Ȃ��A�J�낻�̑n���I�z���͂̂Ȃ��ĂȂ�ʕ����Ȃ̂ł���B
�u�����㉹�y�̏W�听�v
�o�b�n�̈Ӌ`�ɂ��Ă̑��Ԗڂ̓����́A�o�b�n���ق��̐l�X�Ƃ͈���āA�o�b�n���O�̉��y�l���̏��X�����߂����������̂Ƃ��A�܂��A�ނƓ�����̉��y���A�o�b�n�̉��y��i�̂Ȃ��ŏW�听���Ă���_�ł���B
�u�o�b�n��̉��y�ւ̐r��ȉe���v
��O�ԓ��̓����́A�o�b�n�́A���̍�i��ʂ��āA�o�b�n�̂��Ƃɐ������A�܂��n�����������y�ɂ������āA���{�I�ȉe����^���Ă��邱�Ƃł���B���y�̗��j�ɂ����č������ŁA�o�b�n���ł����ȉƁA���邢�͉��t�Ƃ͖������݂��Ȃ��B
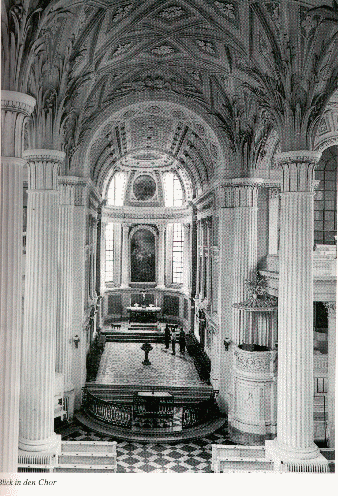
�u���U�̃e�[�}�ł�������q�v
�o�b�n�̈Ӌ`�ɂ��Ă̓��ʂȓ����́A�o�b�n�̃��C�t�E���[�N�̎��̂Ȃ��ɂ���Ǝ��͍l���Ă���B�����A�����̐l�X�ɂƂ��āA����Ƃ��̗�q�Ƃ́A�̂̐��オ�������悤�ȁA���S�I���S���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�������Ȃ��炱�̂��Ƃ́A�M�A��]�A�����Ĉ������ẮA�L���X�g���̎g�M�ɂ������āA�l�X�����{�I�ɗ`����r�����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���Ǝ��͎v��Ȃ��B��ÂɊώ@����A�����A�o�b�n�̉��y�́A���̃L���X�g�����g�M�𐳖ʂ����Ė��ɂ�����^���Ă���Ă���̂ł���B���̍ہA���̏�̖��S�����Ƃ��������́A���h�I�Ȕ����������N�����Ȃ��ł��ށB���������̃o�b�n�̃L���X�g���̍��{���Ƃ̘_�������A���ɋ�����������_�ł���A�����ō�������������邱�Ƃ��ł���Ɩ]��ł���B
�u�I���K���R���[���v
��Ȃ̏����̒i�K����A�p�d�n�͊��ɃI���K���R���[���Ƃ����`���Ǝ�肭��ł���B���̃I���K���R���[���Ƃ����l���ɂ���āA�o�b�n�͖L���ȓ`�������������Ƃ��ł����B
�I���K���R���[���Ƃ����`���́A�I�����_�́u�I���K�j�X�g�̋��t�v�����E�s�[�e���X�E�X���F�[�����N(��ܘZ��\��Z���)���͂��߂����̂ŁA���̒�q�����A�Ȃ��ł��T���G���E�V���C�g(��ܔ����\��Z�l)���p���A�����ăf�B�[�g���q�E�u�N�X�e�t�[�f(��Z�O���\���Z��)�ɂ�������̂ł���B���łɔ��ɑ��l�Ȕ��W���o�b�n�̎���Ɏ����Ă����̂́A�I���K���R���[���`�����̎�X�̌`���̖͔͂ł���B�o�b�n�́A���Ăɂ͐V������Ȍ`���W�������ɁA���̖L���ȓ`�����p�������̂ł���
�������Ȃ���o�b�n�A����Ӗ��ŃI���K���R���[���̐��҂����𗽉킵�Ă����̂ł������B�R���[�������Ɍ��т���ꂽ�̎��̈Ӗ��Ə�Ƃ́A�o�b�n�̃R���[���ҋȂƂ�����Ƃł́A����I�ȉe�����͂������B���̍ł������ȗ�́A�o�b�n�ɂ���Ċ�悳�ꂽ�I���K���R���[���W�ƃI���K���R���[���̘A��Ƃł���B�@
�u�I���K�����ȏW�v
���@�C�}������ɐ��������u�I���K�����ȏW�v�̎l�܋Ȃ́A�����ɂ��������Ă���B�����p���d�N�̏C����^�̍I�݂Ȏg�p�́A�̎��ɂӂ��܂�Ă���Ӗ��̒��ڂ̕`�ʁA�Ⴆ�Ώ㏸�≺�~�Ȃǂ̕`�ʂ��\�ɂ����̂ł��邪�A����A��ҁA�Q���A�ꂵ�݂Ȃǂ̂悤�ȁA�A�t�F�N�g(�)�̓`�B�����\�ɂ����̂ł���B�������Ȃ���o�b�n�́A�R���[���̉���������ɕ`�ʂ���݂̂Ȃ炸�A������͂邩�ɐi��ŁA�Ӗ����e��������A���y�ɂ���f����悤�ɂƂ߂Ă���̂ł���B�u�����l��A���̑傢�Ȃ�߂�߂��߁v(BWV622)�̏j�ՓI�ł������Â����������������ّ̖z�ł��A�܂��u�A�_���̑��ɂ�����ׂĂ͋����ʁv(BWV637)�̋����I�O�ꂳ�ɂ����Ă��A�����́u�傽��_��A�����V�̂��т��萂����܂��v(BWV6�P�V)�̃V���I���̕`�ʂ̐_�݂̂��Ƃւ̓���ɂ����Ă��A������̗g���ł��o�b�n�́A�M��ɂ������������e�����y�ɂ���ĕ\�����悤�ƁA�S���ӂ��Ă���̂ł���B
�u��R���[���ҋȂ̘A��v
�u�N�����B�[�A���K�ȏW��O���v�́A���̑傪����ȃR���[���ҋȂ̘A��̂��߁A�o�b�n�̍�ȔN�����ɂ�����A���@�C�}������́u�I���K�����ȏW�v�ɂ�������A��(��)���݂Ȃ����Ƃ��ł��悤�B����A���ɏ��Ȃ��Ȃ����̂́A�̎��̈Ӗ��̒��ږ͎ʂł���B�����ł́A������u�I���K���E�~�T�v�̗l���ŁA���傤�ǃ��^�[�̋����ԓ����s���Ă�������ɁA�L���X�g���M�̍��{�I�ȗ��ꂪ�\������Ă���̂ł���B�u�I���K�����ȏW�v�����摜�Ƃ͂������A�匚�z�ɂ���r�ł���悤�ȏC����^���A�傪����Ȏ��ݒ�ɑ������Ă���B���̌���̂ЂƂ́A�u�[�������A�����ɌĂ��v(BWV686-687)�Ƃ�����i�ȑ����y�Ȃł���B����́A�̑����Ղ��ӂ��ރI���K���E�v���m �̘Z�����y���ŁA��r��₷��悤�ȑ�z�����\���͂������āA�߂̍����Ƃ��Ƃ�`�ʂ��Ă�����ł���B
���ɂ������Ă���̂́A�u�V�ɂ܂��܂�����̕���v(BWV737�l�̕ҋȂł���B�������J�m���Ƃ��Ď�舵���Ă���̂́A�L���X�g�ɂ���Ă�������ꂽ��̋F�肪�A�L���X�g���M�̋����I���{�ł��邱�Ƃ�����킵�Ă���悤�ɂ݂���B�������Ȃ���J�m���̋F��̉��y���A�����ĂȂ��炩�ȗ���ł͂Ȃ��B���̕��G�����Y���ƁA�����Ƃ��悭�����Ă���悤�ɁA�o�b�n�́A�����Ŏ����̖��ƋF��̓��e�Ƃ̊i�������݂Ă���̂ł���B
�����̏j�Փ��̂��߂Ƀo�b�n�̃I���g���I�́A�قƂ�Ǘ�O�Ȃ��ɁA�ʏ�̓���������яj���̂��߂̃J���^�[�^�Ƃ���������������A���傪����ȏj�Փ��̗�q�̂��߂�����y�Ȃ̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ꎵ��l�N�A����шꎵ�N�̎��T�E�����j�����������ꂽ��̎��ȁA����шꎵ��ܔN�A���邢�͈ꎵ�O�ܔN�ɏ������ꂽ�������I���g���I�A�ꎵ�O�l�N���邢�͈ꎵ�O�ܔN�ɏ������ꂽ�N���X�}�X�E�I���g���I�A�����Ĉꎵ��ܔN�̏��V���I���g���I�͂�������A�����̏j�Փ��̓��ʂȈӖ���l�X�ɓ`�������A�Ƃ���l�����A���ꂼ��̏j�Փ��̕������L���̉��y���̏o���_�ƂȂ��Ă���B
�o�b�n�������ɓO�ꂵ�āA���̈Ӑ}�̎������͂��������Ƃ������Ƃ́A�I���g���I�������A��q������A�܂�����̗�q������藣���ꂽ�Ƃ��Ă��A������Ƃ��Ă��ꂼ�ꂪ�����Ă��鋳���̎��̎������Ђт����Ă���̂��A���������̌����Ă��邱�Ƃ�����킩��B
�o�b�n�́A�������̋L�����A���͂̂��鋭�����q�ŁA���Ȓ��̌��I�ɍ��������Ƃ����ŕ`�ʂ��悤�ƂƂ߂Ă��邪�A�܂������ł́A���R����R���[���̉̎��ɉ��y���������Ƃɂ���āA���ꂼ��̏o������P���ɒǂ��Ă䂭�̂ł͂Ȃ��ɁA���̏o�����̈Ӗ������߂��A�I���g���I�̒��S�I�ȓ��e�ƂȂ�悤�ɔz�����قǂ�����Ă���̂ł���B
�u�o�b�n�̎��ȁv
�I���g���I�̂��ꂼ��́A�܂�����Ȃ�����������킵�Ă���B���I�ȁu���n�l���ȁv�́A���T�̐����j�����畜�������͂�����Ƃ��������_�w�ɂ���āA�u�}�^�C���ȁv���͂܂�����������ڕW�ݒ�������Ȃ��Ă���B�u�}�^�C���ȁv�́A�L���X�g�̏\���˂̓��s���́A���ꂼ��̏ꏊ�Ɣ߂��݂ɂ݂����L���X�g�̖����ɂ�������A��ނ̂Ȃ��D�����ّz�����S���Ȃ��Ă���̂ł���B
�ق��̎O�̃I���g���I�̂�����ɂ����������āA�����̓��^�[�^�́A���܂�V�����@���I���̒��ɑg������Ă���B����������ʂ̉̎��̂��߂ɍ�Ȃ��ꂽ���y������.���x�g�p���邱�Ƃ́A���t�Ɖ��y�̊W��瑊�I�Ȃ��̂Ƃ��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����������V���̃I���g���I�́A�ŗL�̓����Ƃ��ꂼ��̏j�Փ��̎��ɑ��������m�ȓ��e�Ƃ����Ȃ��Ă���B���x����́A�L���X�g�~�a�̋L���ɂ���āA�݂��ɋٖ��ɂނ��҂�������u�N���X�}�X�E�I���g���I�v�̘Z�Ȃ̃J���^�[�^�̏ꍇ�Ɠ��l�ł���B
�u���Z���~�T�ȁv
�����ЂƂA�o�b�n�̎w���ʼn��t����邽�߂ɂ͏�����Ȃ������I���g���I�̍�i�́A�u���Z���~�T�v(BWV232)�ł���B�o�b�n�́A�ꎵ�O�O�N�A�L���G�ƃO�����A�Ƃ��h���X�f�����{��Ɍ��悵���B�ނ̔ӔN�ɂȂ��āA�o�b�n�͂��̃~�T�Ȃ����������B���̊y�Ȃ̑����́A�ȑO�ɍ�Ȃ��ꂽ�J���^�[�^�̓]�p�ŁA���̑��͐V�����������낵�����̂ł���B�o�b�n�͂��̃~�T�������Ď����ŕ������Ƃ͂Ȃ������B
�p����ꂽ�l���̂ЂȂ����̑��l�Ȃ��ƁA�܂��~�T�{���̉��߂̐[�����ɂ����āA�u���Z���~�T�v�́A�ނ̐��U�̎d���̑����Z�ł���B�o�b�n�̓L���X�g���M�̍��{���ɂ������āA��̗���ɂ����Ă���B�u���M���v�̋q�ϓI�ȉ��߂���A�v�Ă���T���Ői�ނ悤�ȁu���҂̂�݂������҂��̂��ށv�A�����āu����ƂƂ��Ɂv.�̂͂�����������ŁA�o�b�n�̗����̂Ђ낳�Ɛ[���Ƃ͊ѓO���Ă���̂ł���B���y�j�ɓo�ꂷ���i�̂����ŁA�L���X�g���M�Ƌ���Ƃ��A���̂悤�ɍL�����������{�I�ɂƂ炦�����̂��A��̑S�̂ق��ɂ���ł��낤���B
�u�o�b�n�̃J���^�[�^�v
�I���g���I�̍�ȂƉ��t�Ƃ́A�o�b�n�̖����̊����ɂƂ��ė�O�I�Ȃ��Ƃł������B������������ăJ���^�[�^�̍�ȂƉ��t�Ƃ́A�~���[���n�E�[���̍ŏ��̑n�쎞�����炠�Ƃ̃��C�v�c�B�q����ɂ�����܂ŁA�K�v���ł������B�̓��^�[�^�̍�Ȃ������Ƃ�������Ȃ����������́A�ꎵ��O�N�����.���N�ł���B�L���X�g�~�a����A�������̂܂��̋������y�����t����Ȃ��T�����O����A�o�b�n�͖����j�̗�q�ŁA���̓��̂��߂ɍ�����ꂽ�J���^�[�^�����t�����̂ł������B
���̗g��.�n�b�n�́A���ɍ�Ȃ����J���^�[�^�����t���邱�Ƃ��ł����͂��ł���B�������Ȃ���A���̎����ɉ��t���ꂽ��i�̖w�Ǒ啔���́A�V�����n��ꂽ���̂ł���B�����������Ƃ́A���̂悤�ȒZ�����Ԃɑn�삳�ꂽ�J���^�[�^�̐��̑����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�ނ���I���g���I�ɗD��Ƃ����Ȃ��A��i�̎��̍����ɂ���B
��O�Z�Z�̗̓��^�[�^��.�o�b�n�͑n���������A���̂����̓�Z�Z�Ȃ��������Ă���B���Ղ̃J���^�[�^��i�̑������A�����A�o�b�n�������A�܂����W��������l�X�́A��������ȍ�i�W�c�ɂƂ肭�܂��鍪���̈�ƂȂ��Ă���ɂ�����.�Ȃ��B
�o�b�n�̃J���^�[�^���A���܂܂Ŕ�r�I�ɂ��܂�m���Ă��Ȃ������̂́A�̎��̓��������Ƃ��낪���������B���̉̎��́A�����̎������ɂ́A�����Α傰�������āA�������ŁA�Ȃ��ɂ͋���ւ����Ȃ��l�Ɏv������̂����Ȃ��Ȃ��A�܂����̐_�w�͂��낢����Ӗ��œ��e�ɖR�����A�ނ��땽�}�ł���B�������o�b�n�̑z���͂́A���̂悤�ȉ̎��̂����ŔR�����������̂ł���B�̎��̌��t�̑I���́A���y�̓��@����̌`���ڂ���������_�@�ƂȂ�A���̎v�l�ߒ��͂������ȉ��y�\���̂��߂̊�b�ƂȂ����̂ł���B
��q�̈ꕔ�Ƃ��ė̓��^�[�^�́A���j������яj���̎��ƊW�������Ă����͓̂��R�Ȃ��Ƃł���B�Ƃ��ɖ��m�ɂ����߂�ꂽ�̂́A���̂悤�ɂ��č�Ȃ��ꂽ�O��j�Փ��A�L���X�g�~�a���A�������A����~�Փ��A�����Ă��̑��̋���j���A����юs�Q����������q�̂��߂̃J���^�[�^�ł���B�����̕��ʂ̓��j���̂��߂ɍ�Ȃ���A��q�̐������ۂ̎g�k���ƕ������ƂɊ֘A����J���^�[�^�̑傫�ȃO���[�v�ɁA�o�b�n�͂�������̎����������悤�Ƃ���S�����������Ƃ��킩���Ă��Ă���B
�u����̎��v
���̂悤�Ȏ��̑��́A�u�M�v�Ɓu�^���v�Ƃ������̐ݒ�ł���B�o�b�n�̑O�ɍ�����ꂽ����y�A���Ƃ��n�C�����q�E�V���b�c�̍�i�ȂǂƂ͈Ⴂ�A�o�b�n�̗���́A�����Ďn�߂���m��I�Ȃ��̂ł͂����B������J���^�[�^�u���M���A�������A�M�Ȃ���������������܂��v(BWV109)�ŁA���V�^�`�[���H�ƃe�m�[���̃A���A�̋^���ƕs�M�̕`�ʂ����Ɍ����I�Ȃ̂ŁA����ɂ������āA���̊y�͂ɂ�������ꂽ���̗���́A�����̗�����咣���邽�߂ɁA���ȓw�͂��K�v�ł������B
�o�b�n�����ʂɔz���������Ԗڂ̗̈�́A���Ԃ̐_�ɂ�������[���l�I�ȊW������B�C�G�X�́A�����̉�̂̎v�z����b�ɁA���̉Ԗ��Ƃ݂Ȃ���Ă���B���̗����Ԃ̑Θb�̂��߂ɁA�o�b�n�͈�A�̓�d���̓��^�[�^�����悵�Ă���B�����ł́A�\�v���m�����̖��������A�L���X�g�̐��͌Â�����y�̓`���ɂ��������āA�o�X����������ĉ̂���̂ł���B
��d���J���^�[�^�ABWV57�u�����ɑς���l�͍K������v�́A��l�̓Ə��҂����́A�Η����܂��������銴���I�ȑΘb�A�܂��o�b�n�����̍��ƍ��̉Ԗ��Ƃ̑Θb���A���傫�ȕҐ��̍�i�̂Ȃ��ł����������̂ł́A�Ⴆ�Ἠ��^�[�^BWV21�u�킪�����ɗJ���͖����ʁv�A�܂���BWV140�́u�߂��߂�A�Ƃ���ɌĂ�镨����̐��v�Ȃǂ�����B
��O�Ԗڂ̏d�v�Ȏ��́A�ق��Ȃ�ʃo�b�n�̗̓��^�[�^��i�S�̂�ʂ��Ă݂��������Ƃ̂ł�����A�l�Ԃ̂͂��Ȃ��A���ʂ��ƁA�����Ď����̂��̂����������Ăł���B���̍��{�I�ŁA���S�I�Ȗ��Ƃ��������K�R���́A�o�b�n�̓���A���邢�̓o�b�n�̎����̐����̂Ȃ��ɁA���x�����̎������Ɠ��l�ɁA�����ʂ葶�݂��Ă����B�o�b�n�̓�Z�l�̎q�������̂����A���l�̓o�b�n�̑������Ɏ��̂ł���B���Ǝ��ʂ��Ƃ�.�����l�����߂��炷�A���̂��Ƃ����ɑ����̃J���^�[�^�̎��ƂȂ��Ă���B
�܂��ق��̖����f���Ă���J���^�[�^��i�ł���A�X�̊y�͂̂Ȃ��ɂ��̎��̎���������Ă�����̂�����B
�u�o�b�n�̑S��i�Ɍ����鋤�ʂ̗���v
�o�b�n�̓�̗��ꂪ�A���ׂĂ̍�i�ɋ��ʂ��Ă��邱�Ƃ������炩�ɂȂ��Ă��Ă���B
���̈�́A�l�ԑ��݂̗L���������̑S�̂Ƃ��̂��ׂĂ̌������Ƃ������āA�`�ʂ��邱�Ƃł���B���������̍ہA�����a�炰��Η��̗����݂��邱�Ƃ����Ȃ��̂ł���B
�Ⴆ�A�̓��^�[�^BWV26�́u���������ɂ͂��Ȃ��A���������ɂނȂ������ȁv�̂悤�ȗg���ł���B
�o�b�n�̂�����̗���́A�L���X�g�̕�����ʂ��āA�������l�Ԃ̕������ۏႳ�������Ă���̂ł���B���[�Ԗ��̔�V����A���͂܂��Ȃ�����B���́A�炢�������v���������āA���̓�����҂���Ă���B�Ȃ��Ȃ玀�́A�L���X�g�Ƃ̈�v�𗈂��炷����ł���B����䂦�ɁA�����̃o�b�n�̑����J���^�[�^�ɂ����ẮA���ʂ̏������̃s�e�B�J�[�g�ɂ���āA�J���^�[�^BWV198�u������v�̂悤�ł͂Ȃ��A�ނ��뗦���Ɋ�����A�t�ł����̂ł���B���̂������Ȃ���z�����d���ŁA�o�b�n�͂��̎��ւ̓�����A�̓��^�[�^BWV95�u�L���X�g�����킪���v�̃e�m�[���̃A���A�u����̂Ƃ���A����������v�ŕ`�ʂ��Ă���B
����䂦�ɁA�o�b�n�̃J���^�[�^��i�́A����Ƀo�b�n���g����߂��u��������������y�v�Ƃ����w�͂̌��ʂȂ̂ł͂Ȃ��B�_�w�̗���̕`�ʂƂ������Ƃ�y���ɉz���āA�o�d�n�́A�l�Ԃ̍��{�I����c������悤�ɂƂ߂������ł͂Ȃ��A�������̂��߂́A�v�l�̏��^���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B
���̐��a�O�Z�Z�N����̎h���ƂȂ��āA�o�b�n�̃J���^�[�^��i�̍L�͂ȁA�����������J��Ă��Ȃ�����Ɉӗ~�������Ď��g�ނ��Ƃ��A�o�b�n�̗����A�܂����������g�������̂��߂ɂ��A�v����Ƃ��낪���������ƍl���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I
�ŋ߂̃o�b�n�����̓W�]�@
���R�o�u�Y�@�P�X�W�P�N�@
�x�����[���s�̃E���^�[�E�f���E�����f���ʂ�ƃV���v���[�͂̌�������Ƃ���A�h�C�c���j�����ق̗���ɁA�Ђ�����ƃ}�L�V���E�S�[���L�[���ꂪ����B�P�W�Q�X�N�R���P�P���A�������t�F�[���N�X�E�����f���X�]�[�����o���g���f�B�̎w���ŁAJ.S.�o�b�n�́��}�^�C���ȁ����ĉ����ꂽ���Ƃ͗L���ł���B
�������Ȃ���P�V�Q�X�N�S���P�R���́A���T�E�����j���ɁA���C�v�c�B�b�q�̃g�[�}�X��������t���ꂽ���}�^�C���ȁ����A�u�S���N��������ڂ��ꂸ�Ɂv(A�E�V�����@�C�b�@�[)�A�S�N��ɂȂ��Ă͂��߂āA�x�����[���E�W���O�A�J�f�~�[�ɂ���Đ��E�ɏЉ���悤�ɂȂ����w�i�ɂ́A���A�J�f�~�[�̎�ɎҁAC�EF�E�c�F���^�[�̋���y�A�Ƃ��Ƀo�b�n�̉��y���̔ނ̊S�̐[�������邱�ƂȂ���A���̍��{�ɁA�ނ̐₦����A���y��i�̕��͂Ɣᔻ�Ƃ����w�͂��A�����Ɏ����ނ����Ƃ����̂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�ނ̓����f���X�]�[���̎t�ł���A�܂��x�����[�����y��w�E����y�Ȃ̐ݗ�(�P�W�Q�W�N)�ɂ��v�����Ă���B
����ɔނ͓����́u��ʉ��y�V���v����ŁAF.���z���b�c�AJ.Fr.���C�q�����g�AC.M.�t�H���E���F�[�o�[�AE�DT�DA�D�z�t�}���AR�D�V���[�}����ƂƂ��ɁA�����Ƃ��Ă͍��x�ȉ��y��i�����͂Ɣᔻ�����M���Ă����B���̍�i���͂̋L���́A���ς��đS�̂̂R�P�p�[�Z���g����߂Ă����Ƃ����B��������́AR�D�V���[�}�����g����ɂ���u�V���y�V���v�ł��A��i���͂Ɣᔻ�́A���̓��e�̒��S���߂Ă����B
���y�̕��͂Ɣᔻ�ɂ��āA�V���[�}���̓x�����I�[�Y�̌����Ȃ̔�]�̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���̌����Ȃ��l�@�̂��߂ɒ���A��X�ȑf�ނ́A����킩���ɂ����Ȃ�₷���B����Ŏ��́A�f�ނ����ꂼ��̕����ɂ킯�`�����A�����̂��߂��́A���镔���𑼂���ؗp���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����[��������̂���Ԃ悢�Ǝv���B
���鉹�y��i���������邽�߂̊ϓ_�Ƃ́A �܂��`��(�S�́A�����A�y�i�A�y��)�Ə��@(�a���A�����A�y�ȍ�@�A���̐��ʁA�l��)�A��ȉƂ��\���������Ɗ肤���O�ƁA�`���E�f�ށE���O�����鐸�_�A���̎l�ł���v�B
�����ł́A���y���͂Ɣᔻ�ɂ��āA�V���[�}���Ƃ͂܂������ΏƓI�ȁAE�DT�DA�D�z�t�}���A���邢��H.�N���b�`���}�[�AH.���[�}���AH.�V�F���J�[�AH.�����X�}���Ȃǂ��A���j�I�����ꂽ�ǂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�������Ȃ���P�W���I�ȗ��A��ʉ����Ă������̍�i���͂���@�ƁA����Ɋ�Â����y�̌����Ƃ́A����ł͂���ɉ��y�w�̗̈悾���ł͂Ȃ��A���y�����̎�X�ȗ̈�ŁA�V���A�G���̉��y��]�A���y����ŁA�ȑO�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʂ��ǁA�d�v�ȈӖ��������̂ƂȂ����Ă���B
�u�����J.S.�o�b�n.�����v
W�E�u�����P���u���N�́A���̕Ғ��wJ.S.�o�b�n�x(�P�X�V�O�N)�̖`���ŁA�o�b�n�v���S�N���ɂ��������P�X�T�O�N�Ȍ�A��Q�O�N�Ԃɂ킽���ĂȂ��ꂽ�A��X�̃o�b�n�����̑�����������݂Ă���B�ނ͕������A
�@�o�b�n�̑S�̑��A�Ƃ��ɓ����̎v�z�I�A�܂����y�I���W�ƃo�b�n�Ƃ̊W�ɂ��āA
�A�o�b�n�̐��U�̊e�����ɂ��āA
�B�o�b�n�̎�X�ȍ�ȋZ�@�A����щ��y�l���ɂ��āA
�̎O�ɑ�ʂ��Ă���B
���̃u�����P���u���N�̕��ނ���z���ł���悤�ɁA����A�Ƃ��ɂP�X�T�O�N�Ȍ�̃o�b�n�����̎嗬�́A��i���͂���̂Ƃ������j�����ł���B�����Ă��̌����̖ړI�́A����������Ȃ���j��`��A�[�Î�`��A�܂��X�m�r�Y���̊댯�ɂ������邱�ƂȂ��ɁAJ.S.�o�b�n��i�́A�u����ɐӔC�̂�����߁v��ڎw���Ƃ���ɂ���_�ŁA����y�ɂƂ������A�d�v�ȈӋ`�������Ă���B
�u�������鋳��y�v
�O�q�����u�����P���u���N�̏����̒��ɂ���AM�E�Q�b�N�́u�o�b�n�|�p�̋��ɖړI�v(�|���́A�p�q��Y�ďC�E�o�b�n�p����P���E�P�X�V�U�N�ɂ���)�́A��L���ނ̇A(�o�b�n�̐��U�̊e�����ɂ���)�ɑ����A���Ɍ[������邱�Ƃ̑��������ł���B
�o�b�n�͂P�V�O�W�N�A���@�C�}���{��Ɏf�����]���āA�~���[���n�E�[���̎s�Q����ɑ��E���肢�ł�B
���̂Ƃ��o�b�n�́A�ނ̉��y�̋��ɖړI�́u�_�̉h�����]�����邽�߂̒������鋳�����y�v�ɂ��邱�Ƃ������炩�ɂ����BM�E�Q�b�N�̌����́A�]���́A���^�[�h������`�̗��ꂩ��́A����������ȉ��߂�ł��j���āA�o�b�n�̌��t���u�M�����Ƃ��āv�ł͂Ȃ��A�����ƌ����I�ȁA�o�b�n�́u���U�Ƒn�������̌����v�ł��邱�Ƃ��A���̐��U��ǂ��A�����炩�ɂ����Ƃ���ɓ��F������B
���Ƃ��A�o�b�n�͂P�V�P�S�N���@�C�}���ŁA�{��y�c�̊y���Ƃ��āA�J���^�[�^�����Ȃ���ہA�o�b�n�̉��y�̒����������A���́u�v�搫�v�́A�O�ʓI�Ȃ����߂����A���Ȃ������S�ȃJ���^�[�^�̈�N�ԕ��\�N�Ԍv��Ƃ����Ă悢�ł��낤���[���A���߂���l�����Ă����A�Ƃ����_���炠���炩�ł���B����������ɂ��܂��ďd�v�Ȃ̂́A���̊O�ʂɑ�����e�I�ȖʁA���Ȃ킿�o�b�n�́A���@�C�}���ł́A�V�^���̃}�h���K���E�J���^�[�^���l���Ă���B���Ȃ킿�A�]���́A�`�����d�����A�T��I�l�����`���Â�������J���^�[�^���A�̗w���ȁA����I�Ŏ��R�ȁA�������̂Ƃ��钲�ׂɂ��킹�A�V�����M��ȁA�h�i���`�̓��ʐ��ƒg���݂��A�C�^���A�̓Ə��J���^�[�^�̗D�����Əo��A���̂悤�ȐV�����J���^�[�^��ڕW�Ƃ��Ă��������̂ł������B
�����Ńo�b�n�����݂Ă��邱�Ƃ́A�ʂ������̖��ł���B�܂苳��y�Ƃ��ĈӋ`�̂���A�V�����̎��ւ̓w�͂ł���A�����Ă��̂悤�ȐV�����������Ȃ����V�������y�l�����m�����邽�߂ɁA���炩���ߒ�߂���{���ɂ����āA������\�����v��I�Ɏ��݁A�u��������܂��Ƃ���Ȃ��@��N�����v(�P�W�O�P�N�́u��ʉ��y�V���v)�A���̌��ʁA�u�ނ������ɂ͂ȂɁA�ЂƂ��r���[�Ȃ��̂��Ȃ��A���ׂĂ����S�ŁA�i���̎���̂��߂Ɂv(R�E�V���[�}��)�����ꂽ���̂ƂȂ����̂ł���B���̂��Ƃ̓P�[�e������́u�I���K�����ȏW�v(BWV599-644)���݂�A��w�����炩�ɂȂ邱�Ƃł���B
����M�E�Q�b�N�̋����[���_���̂ق��ɁA�u�����P���u���N���A�o�b�n�����̑���i��L�A�j�ɂ����Ă�����̂́AFr.�u���[���AH.T�E�f���B�b�h�AR. �G���[�AA.�f�����AG�E�t�H���E�_�[�f���Z���AF.�c�@���_�[������B�Ƃ��ɁAA�E�f������́A���C�v�c�B�b�q����̃J���^�[�^�̐����N��Ɋւ��錤���́A���E�̎��ڂ��Ђ��Z���Z�[�V���i���Ȃ��̂ł����āA���̌��ʂ́AW�E�m�C�}���́wJ.S.�o�b�n�̃J���^�[�^�̎�����x(�P�X�U�V�N)�̂Ȃ��ŁA�]����������܂������������炽�߂��邱�ƂɂȂ����B
�uJ.S.�o�b�n�̃p���f�B��@�v
�u�����P���u���N�̑�R����u�o�b�n�̍�ȋZ�@�Ɨl�����v�ł́A����̌����́A�o�b�n�̃p���f�B��@�ɏœ_��������Ă���BFr.�X�����g�́A�o�b�n�̌����J���^�[�^�u�������҂ɂ͌����v(�P�X�T��)�Ɓu�_�͂���̊v�V�Ȃ�v(�P�X�V��)�́A�Ƃ��ɂ��̑�Q���̉��y���A���łɍ�Ȃ��ꂽ��i�̓]�p�ł��邱�Ƃ������炩�ɂ��A�o�b�n�����̂悤�ȃp���f�B��@����������̂́A���ԂƘJ�͂̐ߖ�̂��߂����ł͂Ȃ��A����ɂ���ăo�b�n�͔���ɍ��x�Ȍ|�p���y�����肾�����̂ł���Ƃ��Ă���B
���̃X�����g�̌����̂ق��ɂ��A�u�����P���u���N�AA�D�f�����AW�D�m�C�}���AL�D�t�B�b�V���[�AM�D�Q�b�N�����l�ɁA�o�b�n�̃p���f�B��@�ɂ��ď����Ă���_������A���̖������ĊS���W�܂��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
���������A�p���f�B��@(���łɍ�Ȃ��ꂽ�����y�͂ɁA�V�����̎������邱��)�A���邢�̓R���g���E�t�@�N�g�D�[��(�P�����ɐV�����̎���t����)�́A�ҋȎ�@�̂ЂƂƂ��āA����y�ł́A�Ƃ��ɓ`���I�Ɉ��p����Ă������̂ł���B
�܂��o�b�n�̉��y�I�\���@�ɂ��ẮAA�D�V���~�b�c��H�DH.�G�b�O�u���q�g���A�܂�R�D�V���e�[�O���b�q���o�b�n���y�̗̉w���ȓ����AW�E�Q�[���X�e���x���q�̔��q�Ƃ��̑g�D�̌����AH.�c�F���N�́u���ϗ��N�����B�[�A�v(�|�O�q�A�o�b�n�p����X���ɂ���)�AE�D�V�F���N�́u���y�̂��������́v�ȂǁA����������j�I�����y���͓I�����ł���Ȃ���A����̃o�b�n���t�̉��߂ɁA�d�v�Ȏ�����^������̂ł���B
�u�o�n�̑S�̏ہE���̗��j�I�ʒu�v
H.�x�b�Z���c�́u�J��҂Ƃ��Ẵo�b�n�v(�o�b�n�p����P��)�́A�u�����P���u���N�̑O�q�������ނ̇@�ɓ�����̂ŁA���̌����͗L����A�D�V�����@�C�c�@�[�́u�o�b�n�͂ЂƂ��I��ł���B�ނ�艽�����o�ł��A��͂����o�b�n�ɏW�܂�̂݁v�ɔ����������A�o�b�n���A�t�B�[���b�v�E�G�}�[�k�G���E�o�b�n���o�āA�ÓT�h�ɂ�Ȃ���̂ł��邱�Ƃ������炩�ɂ����B�܂��u�����P���u���N�́u�o�b�n�ƌ[�֎�`�v(�o�b�n�p����9���j�ŁA�u�o�b�n�̗L���Ȍ��t�\���ׂẲ��y�Ɠ��l�ɁA�ʑt�ቹ�̖ړI�Ƌ��Ɍ����v�́u�_�̉h�����^�����邱�Ɓv�Ɓu�l�Ԃ̐S����y���܂��邱�Ɓv�[�́A�m���Ƀo�b�n�ɋA���ׂ����t�ł͂����A���̈ꕔ���A�P�U�X�O�N�̃��H���t�K���N�E�J�X�p���E�v�����c�̏����̂Ȃ��ɂ݂������A�܂��A���̃o�b�n�̌��t�́A���Ƃ����^�[������`�̗��ꂩ��ł��邱�Ƃ͂܂������Ȃ��ɂ��Ă��A�����̗�����M�ƑΗ��������A���҂������\���Ƃ���[�֎�`�̉e�����ɂ��邱�Ƃ��w�E���Ă���B
���̂悤�Ɍ���̍�i���͂���̂Ƃ������j�����́A���p�I�ł͂��邪�A��̓I�ŁA����������̐l�X�ɐg�߂ȃo�b�n�����A���悤�Ƃ��Ă���B�o�b�n�̉��߂Ƃ����ϓ_����݂āA����̐l�Ԏ����ɂӂ�A�o�b�n�̈Ӌ`�������炩�ɂ��邱�Ƃ́A�o�b�n�̔�_�b���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��\��������Ȃ��B����������ɂ���Ď���ɂ����炩�ƂȂ��Ă���o�b�n���́A����y�ɂƂ��Ă��A�]���̂悤�ȍd�������A���������Ȃ���Ƃ͂������āA���i�Ɩ��͂�����̂Ƃ��āA�����Ă���悤�Ɏv���Ă��������Ȃ��B�@�@�@�@�@�ȏ�
�i�G���w�V���x��40���@1981�N�t�G�����]�ځA�ꕔ�C���j
|
|
|

|