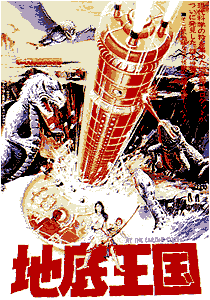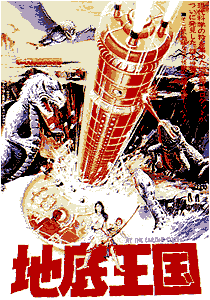|
「ターザン」シリーズの作者としてもお馴染みのエドガー・ライス・バローズによる「ペルシダー」シリーズの映画化である。
今見ると、レトロなメカ造型が心地よい「ファンタジー映画」の佳作であるが、初見の当時はダメダメだった。怪獣があまりにもあからさまな着ぐるみだったのだ。
「私、ウレタン製です」
と自己主張するが如きデブデブとした「ドラム缶体形=B200・W200・H200」が実にどうもカッコ悪く、
「やっぱり毛唐は東宝にはかなわないよな!」
と、「独占!女の60分」での予告編を注視しながら、ブラウン管の前で毒づく当時小学5年生の私がいた。
カラス天狗みたいな怪獣が空を飛ぶシーンなどワイヤー・ロープで吊っているのがミエミエで、しかも、実際にワイヤー・ロープが見えていた。その時点で、
「この映画はダメ!」
との烙印が押されてしまったわけだが、私を含めた周りの連中は、みんなこの映画を映画館まで観に行った。
何故、観に行ったのだろうか?。
その答えは、チラシの裏に掲載の「ボインのおねえちゃん」にあった。みんな、このおねえちゃんが見たくて観に行ったのだ。そのおねえちゃんとは、後に『007私を愛したスパイ』で我らの「夜のおかず」となることになるキャロライン・マンローであった。
さて、本作を久しぶりに再見して感心したことは、ピーター・カッシングの演技の幅の広さである。フランケンシュタイン伯爵役でお馴染みの彼は、どちらかというと冷酷無比な知的悪漢を演じることが多かったが、本作ではドジで間抜けな老いぼれ博士を好演している。怪奇映画のヒーローは、優れたコメディアンでもあったのだ。
それから、主役のダグ・マクルーアは「どこかで見た顔だなあ」と思っていたら、『ゴースト・イン・京都』で最後に首チョンパされている人だった。監督は同じケヴィン・コナーだからね。
|