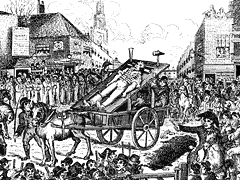第2の犯行の想像図
ラトクリフ街道は帝都ロンドンの貧民窟イーストエンドを通って東へと抜ける幹線道路である。ここで1811年、過去に類を見ない残虐な殺人事件が連続した。その残虐さゆえに、後に同じ土地に出没する「切り裂きジャック」と共に、今なお語り草になっている。
1811年12月7日深夜、メリヤス商を営んでいるティモシー・マーの一家が全滅した。助かったのは主人に頼まれて牡蠣を買いに出掛けていた女中だけだった。彼女が帰るとドアには鍵がかかっている。あらら。締め出しを喰っちゃったわ。おかみさ〜ん、開けてくださ〜い。然れど返事がない。あれえ。どうしちゃったんだろ? 仕方がないので隣人に助けを求めた。なんだい、こんなに夜遅くに。なになに? そりゃ変だな。おれが見て来てあげよう。隣人が裏の塀をよじ上って店に入ると、まず丁稚につまずいた。頭蓋骨は陥没し、飛び散った脳が天井から滴っている。その近くに倒れていたおかみさんも同じ有り様。カウンターの後ろには、頭を打ち砕かれた上に、御丁寧にも喉を掻き切られた主人の遺体があった。ゆりかごの中の坊やの頭も潰されている。物盗りにしては凶悪に過ぎる犯行だ。
帝都ロンドンは恐怖で震え上った。新聞各紙はこぞってその残虐さを報じ、犯人の迅速な逮捕を強く望んだ。ところが、当時のロンドンには満足な警察組織が存在しなかった。夜回り程度のお粗末な治安対策しか講じられていなかったのだ。故に捜査は杜撰そのもの。裏口に残されていた2組の足跡は保存もされず、現場に残されていた血まみれの木槌に「JP」のイニシャルがあることに気づいたのは12月19日になってからだ。次の惨劇が起きたのはその晩のことである。
12月19日深夜、ティモシー・マーの店から歩いて2分ほどの場所にある酒場『キングズ・アームズ』の2階の窓から、寝巻き姿の男が「人殺しだあ」と叫びながら、裂いて結んだシーツを伝わって降りてきた。中では主人のジョン・ウィリアムソンとその妻、まだ少女の女中の3人が頭を叩き割られ、喉を掻き切られて息絶えていた。このたびの凶器は鉄梃である。
2階から降りてきたのは下宿人のジョン・ターナーだった。女中の悲鳴を聞いた彼が何事ぞと1階に降りて覗き込むと、羅紗のコートを着た身長180cmほどの背の高い男が夫人の遺体を物色していた。その男は片足を引きずっていたという。
杜撰な捜査により数十人が連行されたが、そのほとんどが宿なしか飲んべえか外国人だった。オリヴァー・サイリャックは『世界犯罪百科全書』の「外国人嫌い」の項で、当時の風潮として「こんな惨いことをするのは外国人に違いない」との偏見があったことを指摘している。特に疑われたのがアイルランド人で、だからこそ容疑者のジョン・ウィリアムスの調書には「びっこのアイルランド人」と記されていた。しかし、彼はびっこでもなければアイルランド人でもない。生っ粋のスコットランド人である。