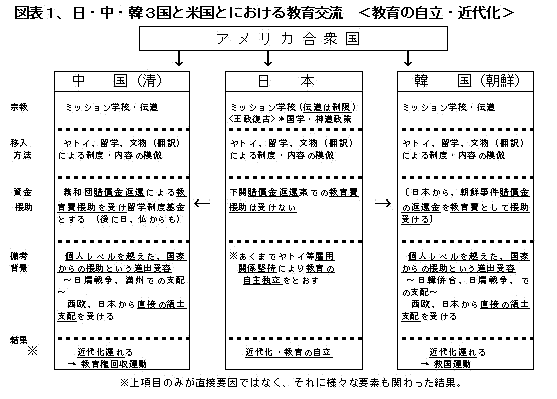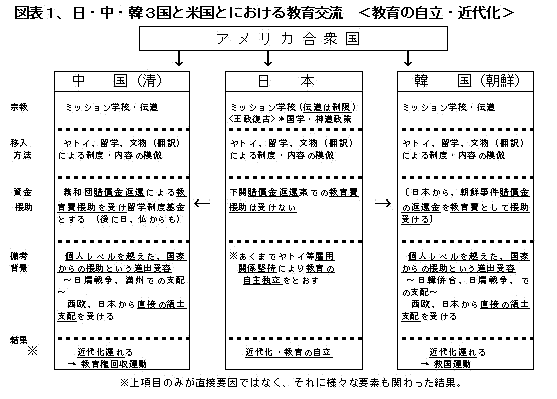第12回 (7月4日)
前回まで、「比較」の手法で教育の歴史を考察してきました。単純な日本の全体を並べてその前後関係をみることと、近代と現代との制度比較をしてみたのがまず最初。次にこまかく日米関係の並行比較を試みた。そこで近代教育の歴史的位置づけをしてみたのですね。すべて「固定観念」をふきとばして、本質を明らかにするために「比較」の研究方法を行なってきたのでした。
最後に関係比較をすすめるというか、複合的な「関係」と「作用」から教育の本質・性質を明らかにしてみたいと考えます。それで、予告どおり、日米関係のみならず、日本と同じく米国から影響を受けて「近代化」の枠組みに組み込まれていった東アジアの国・中国と韓国・・・・、清王朝と朝鮮と表記すべきかもしれませんが、この二つの国における近代教育の状況も踏まえて考えてみたいと思います。
さて、また閑話休題的に話がズレると思うのですが、皆さんは女性です。私は女子教育史の研究もやってみたいテーマの一つであったのですね。ずっと資料も集めて、文献にもあたっているのですが、10年ぐらいそう思っていてまだ動きだせていない。・・・しかし、私が考察する時には、タイトルは「近代化された、教育された女性の歴史」にしようと考えています。
実は私は皆さん「女性」「女子」は「近代化された」のだと考えているのです。こういう言い方は差別的だとかジェンダーにひっかかる表現だと仰る方もいるかもしれません。ただ、事実をいったのみです。私は「近代化」というのは「近代化」された国によって、そうでない周辺の国が「近代化」されていった結果だと思うのです。国対国ではそういう一面があった。東アジアやアフリカなどは半ば強制的に、植民地・反植民地・同盟国・開国といった様々な形態で「近代」の枠組みに取り込まれていったと考えます。近代化されていない国は「野蛮」といわれた。だから「啓蒙」してあげる必要があるのだと考えるのですね。いまも米国が世界の警察であるかのように様々な地域に介入する。それを快く思わない人もいる。そういう意識が、近代化当初にもあったのではないでしょうか。
いや、女子も最初に娘さんに教育を受けさせようと考えた人はどんな人だったのでしょうね。「うちの娘も隣家の息子と同じく教育を」と考えたのでしょうか。女子教育は小学校での共学から始まりましたが、やがて別学・別科目もあらわれる。高等教育への進学だって達成・実現はかかったのですね。そこでも女子学校とそうでない少数の女子とでは意味が違うのですが、・・・とにかくそういう中で「教育された」中から女性の自立を説く、すすめる人材も育って来たというのも事実です。これは米国の黒人の歴史とも重なります。差別・選別から、例えばバス通学等の黒人学校の問題や特別枠のアファーマティブ・アクションなどの逆差別的制度もあった。しかし、その中から中心的人物も登場してきたのですね。その意味で教育の効果はたしかにある。「近代化された」という面もあるけど、そのなかでさらなる「近代性」を求める運動も出てくるわけです。
なぜ、こんなことを言いだしたのかというと、いつも間にかこのキャンパス内にエレベーターがつくられていますね。バリアフリー的な考えもあるのでしょう。それはたいせつなことです。しかし、「ノーマライぜーション」が語られる時、多くは制度だけを準備して、それで終わるとか、あるいは「ここまでノーマルにしてあげる」という態度というか、ラインをひいていて、それ以上が構想されていないという一面があるときというのがあるのじゃないかとも思うのです。人間、すぐに「カタチ」にこだわってはまってしまうのですね。それも一つの「固定観念」です。
例えば「不登校」というコトバ。あれはたしかに認めさせる段階までは「行きたくても行けない状態で広いもの」という意味があったのでしょうが、その後、認められてからはどんどん「人権」的に主張するための「名辞」になっていったという面はないでしょうか。はじめは「学校恐怖症・病phablar」であった。病院にいきますからね。でもこのコトバは「ある個人」特定に原因があるという考えが反映されていますね。少ない症例なんだと。続いて「登校拒否School Refusal」となる。少し広くなったけれど、やはり権利的面もみられるけれどその拒否する主体や家庭に原因があると考えが出ていないでしょうか。英文ではRefusalは、「いすくみ状態」ですね。つまり心身症的なこともあるとされていた。ところが学校を考えようという「不登校non attendance」のコトバになった。当時の文部省も「誰にも起こりうる問題」と認めた。すると・・・、ここから「不登校」の意味は変わると思うのです。いや「変わった」と思うのです。
たしかに最初にフリースクールをつくった当初は悲壮感も使命感もあったのでしょう。しかし経営を続けていく時にそれは使命感が増すというか変容しないでしょうか。いつまでも意識が変わらないのでしょうか、次の代に引き継いでも大丈夫でしょうか。例えば学校の解決策も単に「カウンセラー」を加配すればそれで免罪符みたいになっていかないでしょうか。そういうカタチにこだわる方向・・・。そういうのはないでしょうか。
それで、ノーマライぜーションなりのコトバもそういう性格をもつのではないかとも思うのです。ここまではいいというそういうトップダウン的考え方。いや勘違いしないでいただきたいのは、「いい人」に思われたい私としては当然バリアフリーは必要ですよ。あたりまえです。そうじゃなくて、その後がその後こそが問題になるということです。意識が大切。・・・難しいですかね。考え続けていきましょう。
国家間でもそういう考えが、つまり「教育してやる」「授けてあげる」「近代化してあげる」という方向があったと、今日、みていきます。近代化とはなんであったかということについてみていきます。
1、日米教育交流と近代化
予告したとおりに日本と中国と韓国とを、米国(あるいは西欧諸国)との関係において比較してみたいと思います。まず、単純に図示すると次のようになる。
日本は過去において中国の属国的に扱われていた歴史もあったのではないでしょうか。朝貢外交なども行なわれていたし、なにより文化的に影響を受けていたのですね。漢字(語)文化圏、儒教文化圏とも考えられます。例えばハンチントンなんかもそう位置づけしている。
実際に大陸である中国への領土的あるいは市場としての関心は欧米諸国には高く、その方向性があったからこそ日本はそんなに領土的野心の対象にならなかったともいえます。中国へ向かうルートの途中というか、周辺にあり、薪や水・食料を補給できればいいともとらえられていたのではないでしょうか。つまり本命ではなかった・・・。
そう考えると複雑ですね。比較する上で、さきに「開国」したのは中国です。でも日本の方がさきに近代化&自立をとげて、帝国主義国家の一員ともなって支配する側にさえなった。なぜかといえば一つは「近代化の枠組みに加えられた」とはいっても形態が違ったのですね。領土支配を受けたかどうかの違いがあった。
でも、それだけでしょうか。もちろんそれは大きかったとは思います。
しかし、私は「教育」が国家の自立や近代化に果たす役割に注目したいのですね。例えば「近代教育はナショナリズムの教育である」なんてことばもある。あるいは「近代社会は学校教育そのものである」とか「学校化」ということばもある。近代以降に国民教育システムが導入されて、それによって「近代国家」と認められた、そういうこともあるのではないでしょうか。いままで見て来た歴史考察ではそうでしたね。そのために日本は直訳的輸入による移入をした。いや、公教育の制度がない国などは「前近代的」であるとされるのではないでしょうか。人権が認められていない、野蛮な国といった見方があるのも事実でしょう。実際に阿片戦争においてどう考えても人道上ひどいことをした英国は「かわりにGodをあげる」という驕った考えでキリスト教が侵出したりもしたのです。そういう親切ごかしな、一見道義的な、そういう外交というのもあるのですね。
話がズレますが、基本的に近代以前の歴史ではアジアがヨーロッパに勝って勢力をもったときもありましたね。オスマン・トルコ帝国、モンゴル元朝、インダスや黄河の文明だって大きく影響を与えたわけです。だから有史以来欧米が勝っているということではないのですが、「近代化」というのは西欧から波及した世界システムであったのも事実です。
まぁ、話が戻ると同じく「近代化された」東アジアでも、その後の時間は差があったのですね。そこにある「教育」関係に注目してみます。
さて、江戸時代の、つまり前近代の日本も発展していたのだといい、日本の「独自性」といいますかその後への「連続性」を強調する声があります。それは事実あったとも考えます。しかし、多くは直訳導入した時への「反応」だと思うのですね。「断絶」か「連続」かというのも単純な二分論になる可能性があります。
しかし、ここまで、日本「教育」のアメリカ化=近代化を論じてきましたので、今回は日本「教育」の独自性形成=日本型近代化のメカニズムというものにも着目したいのですね。
図で見るとわかるように、「西欧化」導入の方法は日・中・韓三国でほぼ同様でした。欧米の書物の翻訳をし、またお雇い外国人教師によって授業を実現し、あるいは留学生を現地に送ったりした。そういう方法は共通しているわけです。でも、同様の方法で導入したのに三国では近代化に差がでた。領土割譲はおいておいて、私は「教育」のイニシアチブというか独立だできなかったことと、そして「キリスト教布教」が禁止されたかどうかが大きな違いとなったのではないかと思います。
そして次に、その「教育」に対する「援助」を受けたかどうかですね。それも大きくあったのではないか。「対外教育交流によるイデオロギー統制」と記しましたが、説明しますが、戦争に関する返還賠償金による教育費充当(教育費援助)と教育の自立・近代化との関係に注目したいのです。
2、近代教育の移入様式と独立・・・日本「教育」のアメリカ化=近代化
日本(やアジア諸国ら)の「近代化」は西洋化の一面もあったのですね。「植民地化」「半植民地化」、という様々なカタチでそのシステム内に組み込まれていったわけです。そんななかでナショナリズムの自覚が起こり、そしていずれ自立・独立していったのですね。そのスピードの違いを「教育」から観るのですが、「外交」と「教育」がどう関連するのか、それをまずみていきます。
返還賠償金による教育費充当(教育費援助)と教育の自立(近代化)
1863年6月25日(文久3年5月10日)、長州藩の米商船ペンブローク号砲撃に始まる下関事件(下関戦争)は、翌年に英・米・仏・蘭4ヵ国と幕府との交渉で、幕府が300 万ドルの賠償金を四国に支払うこととなり解決した。この支払いは明治時代にもちこし、1874(明治7)年にようやく全額を払い終えた。しかし米国内では1868(明治元)年頃から「償金返還論」が出て、数年の論議を経て、1883(明治16)年にほぼ支払い総額分の785'000ドル87セントが日本へ返還された。この返還論の中で「日本の教育費用に役立てる目的で返還する」との論があり、この論には対日関係の有力アメリカ人やお雇い外国人の助力があった。また、他の東アジアの国家に対しても同様の外交事例がみられることから、これは米国の対アジア政策の「文化進出」方法ともいうべき独特の方策であると考えられる。
上の文章は私がかつてまとめた研究の一部なのですが、ようするに「米国」は他の西欧諸国と違って「教育」援助という外交をしていたと思うのです。それは実は米国には武断的外交をする十分な軍事力がなかったというのがあります。
もちろん日本を「黒船」の威力で開国させたのは米国です。軍事力がないわけではない。しかし米国は植民地獲得には遅れたのですね。アメリカ大陸内だけで精一杯であったともいえる。いや、国内に南北戦争という難題を抱えていました。そういう戦争と、そして人権意識ですね、そういうものが強くあった。「奴隷」や「戦争」に関する嫌悪感があったわけで、英国や仏国とは違って「強制的侵出」をすると国内での反発もありえたのだと思います。
それで、国民(国内)をも納得させ、そして外交としても好印象を与えられる、さらに効果的な(武力不用の)方法として「道義的外交」がすすめられたのでしょう。そういう一面がみられるのでみてみましょう。簡単にいうと相手の出費の一部を返して「恩」も売る、さらには親米派に育てられるという「洗脳」的方法でもあったと考えます。
ちなみに、日本の下関戦争賠償金を返却しようという動きは次の三つの時期に分けられます。
下関償金返還運動の3つの時期区分
『償金返還問題提言期』(~明治5年頃まで)
『教育費充当論期』(明治5~11年頃まで)
『上下両院における返還決議期』(明治11年以降)
明治元年頃から「返すべき」との意見が出て来た時期。無条件でした。キリスト教関係者等から多くは出て来た意見です。人道的だったのですね。「略奪金」だなんていっていた。続いて明治5年頃から「教育の基金として」という意見が出されたのですね。ちなみに明治5年から11年頃というのは「学制」期そのものですね。日本が米国のカリキュラムを取り入れていったその時期、多くの米国人関係者がお雇い教師としていた時期でした。しかし、結局日本が条件を受け入れず、また米国内でも無条件でと世論が高まって、そのとおりに無条件で返されました。なお、返されたお金は横浜の波止場つくりに使用されました。それがメリケン波止場です。誰も言っていない事実です。
米国の対アジア政策・教育的外交
下関戦争直前(1864年7月22日)英米仏蘭4ヵ国の下関砲撃に関する共同覚書協定第4条には、土地の割譲、利権、占拠は一時的にのみで、あとは禁止、と規定された。すなわち、わが国を彼らの海軍基地として長期間占領すること、日本領土の割譲等を互いに警戒・牽制しあっていたのである。欧米列強の対日政策は、(開国要求への)『日本の封建制度打破』、(各国間牽制の)『漸進的変革の助長』、(及び)『領土割譲、軍事基地化の警戒』等、を主な基本政策とした。
対アジア及び対日外交において米国の特徴ともいえるのが、この教育交流(文化交流)支援政策であったのですね。他国とは違った。それが米国独自であると考える理由は、他にもそういう例があったのです。
同様の事例・・・中国への義和団賠償金返還による留学生教育。
その賠償金返還による留学生教育基金充当は米人宣教師アーサー・スミス(Arthur Henderson Smith 1845-1932)の建議によるもので、スミスは中国人を米国に留学生として送り出すことに熱心で、痛烈に日本留学の速成教育中心、金儲け主義を批判し、「義和団事件の賠償金としてアメリカが中国から受け取る金額の一部ないし全額を中国に返還し、これをもって中国人青年を教育するための費用とするべきだと主張した。そしてルーズベルト大統領に対し、『現在中国の青年を教育することに成功する国は、将来その捧げた努力に対し、道徳的、知的、ならびに経済的影響において最大の報酬を得る国となるだろう・・・』と力説して、それを政策として取り上げるよう提言」(阿部洋『中国の近代教育と明治日本』1990年 福村出版 227 頁)し、「合衆国上下両院は1908年5月、他国に先んじてこの義和団事件賠償金の一部を中国に返還する権限をルーズベルト大統領に付与することを決定、両国政府の数次にわたる交渉の結果、これを基金にして中国人のアメリカへの官費留学生派遣事業を発足させた」(同上『中国の近代教育と明治日本』230 頁) のである。
以上のように対中国政策(対華,大陸政策)においても同様の外交事例がみられたのです。これにより米国の対日政策は対アジア外交の一環であることがわかる。以上の二つの事例(対日、対中国)は、その実現には違いがあるものの、計画としては、ほぼ同様である。教育による人的交流対外政策、特に金銭援助による人材育成。その基金には賠償金という特殊な金(ある意味では略奪金)があてられることとなった。そして、そのアプローチ(建議)には、在外公使やお雇い米国人教師らの寄与するところが大きかった。彼らにとって、日本(中国)の教育の貧困、特に教育財政の貧しさが実感できることと、その援助によって自国(或いは自分)の立場・影響力を強めることが望めること、或いは自作の教育計画の実施費用として必要であると考えられた(もちろん純粋に対象国への愛着・親愛をもっての考えかもしれないが)。そのために公正さ、誠実さ、正義とを自国民に訴え、また直接の利益と、親米国家をつくりあげられるという間接的利益をも説いたのであった。
また受領側日本への予想外の影響事例もあったのです。対朝鮮,対義和団問題での,日本の模倣とその立ち遅れです。1882(明治15) 年7月、朝鮮事件勃発、同年8月30日、済物浦条約調印により日本は賠償金55万円を5年賦で得ることとなったが、1884(明治17) 年11月9日の「償金一部還付に関する文書」によれば「教育費に充つる条件」つきで40万円を返還することとしたのです。
P.J.Treat,“Diplomatic Relations Between The United States And Japan",1963. によれば、 Following the example of the United States, Japan returned, on November 11, 1883, about 400000 yen of the indemnity of 550000 yen payable by Korea under the Convention of July 27, 1882 . This sum was to be used for educational purposes in Korea. とある。(P.559)
また1924(大正13) 年3月、特別会計法制定により義和団事件償金に基づいて「対支文化事業」を発足することとなったのです。このように、すぐ国際的視野での長期的展望は行われなかったが、その根底には遅れはしたものの大陸政策に米国流『道義』が採用されたことは興味深いといえましょう。そもそも、朝鮮を開国に追い込んだ時の手法も米国の黒船が日本に開国をせまったときと同じであったわけですが・・・。後の「同化」政策、「皇民化」政策と同じ「文化進出」の一面があってつながるものだと思います。
○次に、「キリスト教布教」と「教育の自立」との関係を考えてみます。あまり時間もないようですから、サッと資料をながめてもらいながらすすめていきます。
宣教師が教育事業に果たした役割
まずは日本に渡って来た外国人、最初に「教師」になった外国人についてです。
先程、「野蛮」な国を「近代化する」という方向があったといいました。その「近代化する」ための方法の一つが来日したお雇い外国人教師でした。
さて、渡って来たのはいいのですが、「近代化」されるまでは「野蛮」なわけですね。「危険」な「異文化」の「遠方」地域へ「最初」に渡ってくる。すごいリスクがあったのではないでしょうか。コトバも文化も違う。食料も天候も違う。帰れるかどうかもわからない。そういう「危険」な土地だったのではないでしょうか。
では、最初にどういった人物がどういった想いで来日したのか。
サッカーや野球でもいいのですが、本当の一流外国人が果たして日本にどれぐらい来ていますかね。日本と米国では違うから「あう・あわない」があるなんていわれます。しかしあうかどうかも試してないでしょう。実際に両チーム対決で大きな差がみられることだってある。なぜ、来ないのか。お金もそうかもしれないけれど、そこまでして来る理由を向こうの選手が感じないと来ないですね。だって来る必要がないのですから。リスクがありますし。
すると明治初頭前後に来日して教師になったのはどういう人物か・・・。これは最初は船乗りとか荒くれ者とか、たまたま日本に来ていた人物が教師に採用されることがあったのです。とりあえず外国語はしゃべれるのだし。しかし、質に問題があるのは明らかだった。それでクビになって、その時に「質」がいいものとして雇われた(貢献した)のがキリスト教宣教師だったのです。
彼らは「危険」な「未開」の土地へ「布教」のために覚悟して渡ってきていたのですね。そして荒くれ者ではないし、基本的に聖書を読み説くなどの知識や教育技術的なものもあったわけです。穏やかな人物も多かったのでしょう。いきなり鞭や暴力をつかわないという意味においてです。だから適任者となったのですね。その例を明治学院やフェリス女学院あるいはヘボン式ローマ字でしられる宣教師ヘボンの書簡からみてもらいます。
① ヘボン1859年8月31日付の書簡(上海から、スレーター宛)「日本についてのわたしの予想は決して明るくありません-外国人が人民と接触することは禁じられており、キリスト教は、特に人間の邪悪なものとして排撃されねばならぬと考えられています。人民にキリスト教を教えることは許されておりません。日本文や漢文で書かれたキリスト教の書物は注意深く排除されております。現在、長崎には二人の監督教会の宣教師がおりますが、いずれも邪魔されております。わたしは医者として静かに行き、その職業をいとなみ、漸次、わたしの途をきり拓いてゆきましょう。--しばらくは語学の習得につとめます--辞典を編さんし--他の人々に有用な働きをいたしましょう。」(高谷道男『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 42頁)
ヘボンは来日前、中国布教から流れてくるのですが、日本への布教に希望と不安をいだいていた。しかし、強い布教の意志をもってそのために「はたらく」というのですね。
② 1860年5月5日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「幕府はわたしどもが、日本語を学び、日本の国情を知ろうとしていることを恐れています。わたしどもが日本人のことを知りたがっているのを、幕府が猜疑心と不安の念を抱いているとは妙なことです--お互の言語に関する知識をもって、自由に意思の疎通がてきることは、それがないために生ずる多くの困難な問題を除くことができるのに、それを彼らは悟らないようです。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 62頁)
来日後もその布教の困難を語っています。
③ また「福音がこの国に入る門戸の開かれる前に、大きな変革がこの国に達成されなければならぬ」と述べ、「住民の間に医療事業は何もやれません。施療所の開設に家か部屋を借りるため、わたしは奉行に願い出なければなりません。それで奉行は江戸の閣議にそれを計るまでは何ら回答を与えることはできません。でもわたしは、だんだん、何か施療めいたことをやってゆくつもりです。わたしが日本語を話せるまでは待っています。しばらく日本語の修得に専念します。」と布教のための準備として、日本語学習(翻訳)と施療をすることを語った。(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 63頁)
④ 1861年4月15日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「ネビウスが引き払ったあとの寺で施療所を開いています。患者はまだ少数です。しかし、わたしはためしてみるつもりです。おだやかな方法で、宣教の糸口をつけようと思います。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 76頁)
⑤1874年9月25日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「わたしは一週間二回、善良で熱心な聴衆に説教します。そして日曜日には朝九時半から十時半まで五十人から七十五人ほどのいつも来ている聴衆に説教します。午後は二十名ほどの青年の大きいバイブル・クラスをおこないます。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 117頁)「聴衆の大部分は、わたしどもの学校の青年と子供たちです。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 118頁)
以上、布教のための教育、翻訳事業、施療であったことがわかります。キリスト教布教が警戒され制限された国で布教を広めるには語学の学習と、近代的技術、科学で人心を引きつけて感化することが最良の策であった。特に日本において国家間の条約によって先兵としての来日外国人が制限されるというジレンマもあったのですね。
⑥ 1863年11月27日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「この政府に大きい変革が起こらない限り、福音を伝えることはできないということです。わたしども宣教師は、日本人のきびしい法律とわれわれの条約と二つで、あらゆる方面で締め出されているのです。わたしどもは役人たちによく知られており、警戒されているのです。現在締結されている条約によって、もし宣教師が福音を伝え始めたら、日本政府は、その宣教師について、われわれの公使または領事に抗議をするのです。したがってわたしどもも追放されるのです。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 84頁)
また、あくまでも先兵としての役割であって、外国人の来日が増加すると、しだいに自分の役割が減少するということもあった。布教目的の他宗派も増えて、競合することになるし、またお雇い教師も「専門的」な教師が招聘されるようになると、初期の外人教師の多くが仕事を失っていった。またお雇い外国人自体、いずれは自らが教え育てた日本人によって、そのポストをとってかわられる運命にあった。
⑦ 1886年6月2日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「フィラデルフィアのクエカー派は、この国に伝道を開始しました。あわれな日本。欧米のあらゆる教派がこの国にごたごたと入りこんできます。いつ終わるかわかりません。なぜ合衆国の良識ある人々は、その自国の政治的、社会的無秩序をおさえるために立ちあがらないのでしょう。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 204~205頁)
⑧ 1872年8月5日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「この国に展開しつつある変革はほんとうに驚嘆すべきものです。彼らは実際に風俗習慣その他外国文化のあらゆる道具だてを一括して採用しつつあるのです。日本人がキリスト教を受けいれるのも遠い先のことではありますまい。彼らはすでに古来の宗教制度を破壊し、その偶像を捨てました。わたしの言う意味は政府自身がこれをおこなっているというのです。一つの驚くべき進展が達成された後、次に何が来るかを知らずに、国民一般はぼう然として見ているばかりです。彼らは笑うべきか、泣くべきかを知らない。けれど全般的には不思議なほどこの変革を受け容れています。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 112頁)
⑨ 1884年11月1日付の書簡(ヘボン→スレーター宛)「日本人はまことに不思議な人々で、わたしがかつて知った、また書物によって知っている他の民族とちがって、古い習慣や制度をさらりと脱ぎ捨てて、偏見から解き放たれ、西洋諸国が長い間の戦いと労力によって、やっとかち得た進歩の同じ段階に、その習慣と方法とを理知的に採用し、熱狂的に人々を信じさせるのです。」(前掲『ヘボンの手紙』<増補版>有隣新書 1976年 196頁)
ここでヘボンが希望を失っていないのは「日本」が「廃仏毀釈」などで仏教排斥に出て、その結果「神道」に変えたという事実ですね。そういう激変があった。ということはクリスチャン化もありえるということです。そういう期待があったと思います。しかし、実際にはこの「神道」への転換が国内であったことから、それが政権に利用されたことから、キリスト教を受け入れないということが可能になったのだと思います。
さらに前述のように、条約による規制もあったが、近代国家の公教育では「宗教教育」を行なわないというジレンマにもぶつかったのですね。例えばフランスの社会学の成果では「キリスト教」にまかされていた国民育成を解いて「学校」にしぼってからが近代だというコトバもあります。
次に、文部省最初の外国人顧問であったモルレーの活動を分析して、キリスト教と学校教育との近代化における位置について考察していきます。
文部省顧問モルレーの教育活動と、彼の考える近代化
ダビッド・モルレー(David Murray 1830~1905年)は、1873(明治6)年6月に来日し1879(明治12)年1月に離日するまでの約5年半の間、わが国において文部省最高顧問として活躍したアメリカ人です。日本最初の文部省顧問です。ちなみに彼が在籍した時期が下関償金返還における「教育費充当論」の時期でもありました。前には博物館設立や女子教育設立にも貢献したんだといった人物です。彼はヘボンらと違って、「専門」のお雇い外国人(顧問)として契約して招かれた人物です。そのモルレーはキリスト教と無関係ではなかったのです。
A,モルレーとキリスト教との関係
⑩ 来日以前に奉職していたラトガース大学(Rutgers College)・・・ニュージャージー州のニューブランズウィックに設立され州内(植民地)に2番目の大学として開校。植民地大学特有の宗派的性格を強くもっていた。古くはニューヨークとともに同州はNew Netherland(新オランダ領)であったため、オランダ改革派教会(Dutch Reformed Church)系。
〔Queen's College → Rutgers College → Rutgers University → the State Univ.〕
日本との接点も、この宗派的性格によりました。日米関係はキリスト教からはじまったともいえる。日本に宣教師として来日し御雇外国人として様々な功績をもつフルベッキによって、日本人留学生たちが米国のミッション伝導本部に紹介され、NYのジョン・フェリス主事の好意によって彼らがラトガース(のグラマースクール)に受け入れられた。ここで語学を学び、その後目的に応じて各地へ送られた。この時に留学生たちに接して、世話をしたのがモルレーであり、有名なグリフィスらであったのです。当時、米国の同地に留学していた学生リストです。後に外交で活躍する人物や勝や岩倉の息子など次代のエリートが同地で学んでいるのですね。
⑪ 海外留学者リスト (ニュージャージー州ニューブランズウィック地区)
〔幕末〕 17 船越 慶次
1 井上良一(六三郎) 9 谷川 猛 18 町田 清次郎(啓次郎)
2 筧 庄三郎 10 田村 初太郎 19 松村 淳蔵(市来和彦)
3 勝 小鹿 11 柘植 善吾 20 丸岡 竹之丞
4 木庭 栄次郎 12 堤 勉 21 横井 左平太
5 日下部太郎(八木八十八) 13 手賀 儀三郎 22 横井 大平
6 児玉 章吉(章介) 14 富田 鉄之助 23 吉田 清成
7 鈴木 知雄(六之助) 15 畠山 良之助(義成) 24 吉田 伴七郎(太)
8 高木 三郎 16 樋口 宗儀 25 吉原 重俊
〔明治元~7年頃〕 29 南部(大隈)英麿
1 岩倉 具定(旭小太郎) 15 木村 熊二 30 長谷川 雉郎
2 岩倉 具経 16 工藤 精一 31 服部 一三
3 大儀見 元一郎 17 国友 次郎 32 原 保太郎
4 大久保 三郎 18 駒井 重格 33 平賀 義質
5 大沢 良雄 19 斉藤 金平 34 船越 慶次(同人物)
6 大塚 綏次郎 20 白峯 駿馬 35 松方 幸次郎
7 小川 鋪吉 21 杉浦弘蔵(畠山義成) 36 松方 蘇介
8 奥平 昌邁 22 多久 乾一郎 37 松平 定教
9 小幡 甚三郎 23 竹村 謹吾 38 松平 忠礼
10 折田 彦市 24 田尻 稲次郎 39 三井 弥之助(養之助)
11 筧 庄三郎〔2度目〕 25 津川 顕蔵(良蔵) 40 三井 三郎助(弁蔵)
12 華頂宮 博経 26 土倉 正彦 41 ミナミ K
13 香月 経五郎 27 名倉 納 42 山田 稈養(稲安)
14 川村 清雄 28 奈良 真志 43 山本 重輔(重助) <石附実『近代日本の海外留学史』の付録をもとに作成>
同じく明治初期に来日・活躍した外国人にも同校卒業生が多かった。これもプロテスタントの影響ですね。
⑫日本で活動した主なラトガース大学卒業生
◇Robert H. Pruyn , ◇James H. Ballagh ,◇ Robert M. Brown , ◇Henry Stout ,
◇William E. Griffis , ◇Edward Warren Clark , ◇Martin N. Wyckoff ,
◇Eugene S. Booth , ◇N. H. Demerest , ◇Howard Harris , そして関係者Murray
モルレー自身、来日以前には積極的なキリスト教活動があった。彼の両親はスコットランドからの移民でありプロテスタント教会・長老派の教会員であった。また生家のある地域がスコットランドからの入植者が多かったことから、必然的にモルレーも地縁で長老派教会に加わっていた。オーバニー・アカデミー時代にはthe State Street Presbyterian教会の設立に関与し、日曜学校の仕事にも関わった。
⑬<“In Memoriam , David Murray," 『追想録』から>
While in Albany he was active in religious and public affairs as well as in
the duties of the Academy. He was concerned in the establishment of the State Street Presbyterian Church. He interested himself in Sunday School work as wellas in literary societies.
In Rutgers College he attained a distinguished reputation as a successfull
organizer and administrator. Here also he became interested in ways outside thesphere of his professorship. He and the late Dr.Jacob Coooer were the founders of the Alpha Beta Kappa Society in New Jersey, Professor Murray being its firstpresident. He was instrumental in establishing the Historical Society and the Young Men's Christian Association, to which also he was elected first president. He united with the Second(Dutch) Reform Church, in which he served as elder from time to time, and as Superintendent of the Sunday School for many years until he left for Japan.
ラトガース大学に移ってからは同大学の教派でもある改革派教会員として活動した。改革派と長老派は教義及び実践で多くの共通点をもつが、彼は改革派教会の長老(elder)を務め、また日曜学校主事を来日前まで務めていた。さらに同大ではY.M.C.A.(Young Men's Christian Association)の設立も援助し、自ら初代会長(first president)となったのである。
また同大学が総合大学・州立大学へと発展していくのに大きく貢献したのが、キャンベル学長(William Henry Campbell 1808~90)、モルレーの先輩であるクック教授(George Hammell Cook 1818~89)、その2人に招かれて同大学へ来たモルレーの3人であった。この3人はオーバニー校長からラトガースへと同じコースを歩んでいて、また3人とも改革派教会員であった。大学の発展は一面で宗派的性格からの脱却でもありこれは自らの教義・信仰・教会活動と抵触していたともとれるが、宗教と大学教育は別と考えていたのであり、キリスト教を軽んじていたのではなかった。
また離日後もNew Brunswick神学校の特別委員会会長を13年間つとめ、1895年には米国改革派教会の議長にも選出されていた。
以上のように来日前後のモルレーには積極的なクリスチャンとしての活動があった。
でも、彼は布教には加わらなかった。「教育」にだけ貢献したのです。
B,モルレーの考える近代化とキリスト教
ところが、ここまで見てきたように、来日前までは宣教師ではないものの積極的な活動のあったモルレーが、来日後は発言力・影響力のあるポストに就いていたにもかかわらずキリスト教活動が見られないのです。
実際に開国後の日本にキリスト教を布教させようという意見は多くの欧米人が持っていた。例えばモルレーは、在米中の森有礼の“EDUCATION IN JAPAN"(日本の教育の進路についてアメリカ人有識者にアドバイスを求めた)に回答を送っているが、他の回答のうちいくつかは日本をキリスト教国化すべきとの意見であった。回答したのは13人であり、そのうちの6人は牧師の資格を得ていることから、当時の牧師がいかにエリートであったかがわかる。
⑭<森有礼“EDUCATION IN JAPAN">
●教育の効果についての森の質問1. Upon the material prosperty of a country.
2.Upon its commerce. 3.Upon its agricultural and industrial interests. 4.Uponthe social, moral, and physical condition of the people; and 5. Its influencesupon the laws and government.
●回答者Theodore D.Woolsey, William A.Stearns, Peter Cooper, Mark Hopkins
Octavius Perinchief, J.H.Seelye, James McCosh, Joseph Henry, David Murray, B.G.Northrop, Charles W.Eliot, George S.Boutwell, John A.Garfield,
以上のうち「日本におけるキリスト教採用」を提言しているのは、スターンズ、ホプキンス、シーリー、マコッシュ、ヘンリーの5人である。モルレーは「日本の立場に立って日本の教育のあり方を考え、そのためには指導者階級も育たなければならない」と指摘。
Every nation must create a system of education suited to its own wants.
There are national characteristics which ought properly to modify the sceme of education which would be deemed the most suitable. The culture required in one nation is not precisely what is required in another. (以下略)
以上のようにみると、モルレーは来日以前までは、積極的なキリスト教活動をおこなったが、それ以降は活動がないようにもみえる。しかしモルレーは「安息日を守る人 (great Sabbatarians)で、日曜日には一切娯楽や招待に応じなかった」(“In Memoriam , David Murray," op.cit., p.6)ことや、離日後も例えば木村熊二との書簡(妻マルサの筆)に「私達の救主、イエス・キリスト」(東京女子大学所蔵資料)とあることなどから、その信仰の深さをみることができる。また田中不二麿に「道徳心」(teaching the students morality)のためには何が重要かと問われ「バイブル(聖書)」と答えていたのである(“In Memoriam , David Murray,"op.cit., p.5-6)。
また離日後の“Education and Religion in Japan"(「日本の宗教と教育」)という演説で、「宣教師の活動によって日本の宗教的な気風が変わっていく」とキリスト教の影響を述べている。しかし同演説で神道と仏教が日本人の道徳的役割を果たしているとも指摘していた。つまり「日本には日本に適したもの」が必要という、穏やかな、そして現実的・漸進的な考え方であった。これは悲観的であったというよりも、「キリスト教に対する偏見がなくなり日本において信仰の自由が確立するならば、キリスト教はその信者を獲得することができるという希望的観測に示されるように、むしろ彼は楽観的だった」(明石紀雄「米国からの教育使節~デビッド・マレー~」筑波大学『地域研究』1 1983年、116頁)といえよう。ちなみにモルレー夫人(マーサ Martha)から木村宛書簡には「いつか日本がキリスト教化されるように(Christianized)」(木村にとってのキリスト教伝道がうまくいくように、あるいは日本にも救い主キリストの加護があるように、との意味であろうが)と述べられていたのである(東京女子大学所蔵資料 1880年3月6日付書簡)。
⑮またモルレーの著述“An Outline History of Japanese Education" で、日本人が「西洋諸国」に追いつくことを記している箇所の記述は“Western nations "となっている(“An Outline History of Japanese Education" p.26)が、その草稿段階でのモルレー直筆文では“Christian nations"となっていた( Japanese Education -- Ancient and Modern p.44)。さらに“Education in Japan -- With special reference to Missionary Education"では、海外伝道、宣教師たちによって日本の教育が進歩したと述べるが、「公立学校では宗教教育を除外すべき」との立場にあった(“Education in Japan -- With special reference to Missionary Education" p.12)。そして「近代化推進、達成のためには政府主体で国民教育制度を確立することが第一」(ibid., p.12)と考えていたのだと考えられます。
⑯ただアジア諸国へのキリスト教伝道については次のように述べている。
They have always in the providence of God found a work to do and on influence to exert. Let their continue to do this work. But our first duty, as in India, in Chine, and in Japan, is to depend on the school. (ibid., p.29)
モルレーのキリスト教観は、近代化して西洋の制度・学校制度が普及すれば、必然とChristianizedされるとみていたのではないか。 そういう人物への「シフト」があって、それで「学校化」というシステム転換が可能になったのだと思います。
ちなみにモルレーは「プロテスタント・改革派」でした。中国の賠償金返還に尽くしたスミスは「プロテスタント・組合派」ですね。ヘボンは「プロテスタント・長老派」でモルレーももとはそうだった。実はこの三派はカルバン派の合同的・協調的立場で結びつくもので、まさにフェリス代表の「伝道ボード」でいっしょのものなのですね。すると東アジアへの外交・教育・宣教にはこの伝道協会が大きなチカラを尽くしたことがわかる。そういうように伝わったものです。
はじめ、「教会」からやがて「学校」へ。そして「キリスト教宣教師」から「専門お雇い外国人教師」へと。そういうシフトチェンジができて、それではじめて「近代化」が成立するのではないかと思います。
3、「日本」化とナショナリズム形成
最後に、受け入れ側日本がなぜキリスト教を廃し、その上で近代文化だけを取捨選択できたのか、その時に語られる「独自性」や「連続性」はなんなのかをみてみます。文部省設立以前の明治3年の学校構想のうち「大学規則」をみていただきましょう。
(1)1870 (明治3)年 「大学規則」「中小学規則」公布
〔大学規則〕 学 科
教科神教学 修身学
法科国法 民法 商法 刑法 詞訟法 万国公法
利用厚生学 典礼学 政治学〔施政学〕 国勢学
理科格致学 星学 地質学 金石学 動物学 植物学
化学 重学 数学 器械学 度量学 築造学
医科 予 科数学(度量) 格致学 化学(鉱土 植物学)〔金石動植学〕
本 科解剖学 薬物学 原病学 病屍剖験学(医科断訟法)
〔解剖学 「原生学」 原病学 薬物学 「毒物学」 病屍剖験学〕 内科外科及雑科治療学兼摂生法
文科紀伝学 文章学 性理学
※〔 〕は語の置き換え、「 」は新たに加わった部分
「教科」は「教育学部」みたいなものです。「宗教」あるいは「哲学」の方が近いかもしれません。「法科」は「法学部」。「理科」は「理学部」、「医科」は「医学部」ですね。それまでの日本にはなかったもので、たしかに西欧的です。これも直訳的ともいえる。しかし、次のをみてください。
●「三科必読書目」(「教科」「法科」「文科」で使用する「教科書名」)
例:「教科」・・・「古事記」「日本紀」「万葉集」「宣命」「祝詞」「論語」「大學」「中庸」「禮記」
「法科」・・・「令」「残律」「延喜式」「三代格」など
「文科」・・・「五國史」「大日本史」「枕草子」「源氏物語」「史記」「前後漢書」など
教科目は西洋に範をとり、内容は「復古精神」の書物を用いることとしたのですね。これはまさに「和魂洋才」ですね。そういう精神というか、ナショナリズム的風潮があった。これが日本のキリスト教排除での近代化を可能とした「独自性」ではないでしょうか。
最後に閑話休題・・・「舎中条規」という宿舎の規則(校則)。午前8時から午後2時までが授業であり、授業中はみだりに「他席ニ行へカラス」と学級崩壊のようなことが書かれていたことから、一斉教授というものが定着しないことが現実としてあったとみてとれる。門限は夕方6時までであり、また休日は「一六休暇」であった。日曜が休日で2002年から学校五日制実施になるも、この当時は月のうち「一」と「六」がつく日が休日になったので「1日、6日、11日、16日、21日、26日」と月に6日間も休みがあったのであり、実態は隔週5日制でもあった。ただ曜日による時間数定着にも問題があるし、教え込み不足という問題もあり、さらに外人教師の礼拝日としての日曜日を受け入れざるをえない状況でもあった。ちなみに一般的にも定休概念が定着したのは最近のことであり、戦後の60年代以降になって社会的に定着したと思う。官庁や大企業とともに学校がこの定着をリードする役目を演じた。このことからもいわゆる社会の「学校化」ということがいえるのではないか。
次回は最終回なので教育基本法と教育改革国民会議という、「現在」の教育の変容・構想・理念を考えてみます。