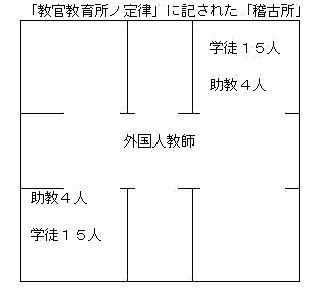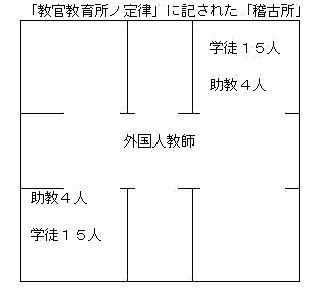第7回(5月30日)
近代と現代との比較(西洋教育史概観)
今回は前回までと違って、外国の教育について概観します。前回までみてきたように、日本の「近代教育」が海外から移入されたものであった。「近代化」されたのですね。その中で「国際性」と「独自性」との間を揺れ動いていく、と。それが近代教育の性質とも思えます。近代化されていない国に「近代教育」が伝わる。そこでは同じような状況、変化がおこるのではないか。例えば東アジアにおいては、やはりキリスト教系学校や海外からの情報が入ってきて、その中で時間的なズレはあってもやがて「教育のナショナリズム」が高揚するのですね。自国らしい教育の必要が指摘されるようになる。そして自主独立を勝ち得ていくという歴史的展開がある。
そして、前回までみたように、これは「近代」「現代」ともに同じ反応がある。「どこまでが近代か」といえば、お話ししましたが明治以降、戦時期までが「近代」で、戦後の教育改革(教育基本法体制)からが「現代」と考えていますが、そこに同じような反応があったことをみていただきました。
これまでは「近代」の教育理念の性質をみていただくように、まず歴史的に全体を比較し、特に「現代」とも比較してみていただきました。前からいっていますが、様々な「比較」の方法によって、通史の誤解や固定観念を打破できると思います。
今回は、「近代」より前の「教育」を考えてみたい。私は「教育」は「近代以降」普及して、さらに日本の教育史はまだ150年以下の歴史的に新しいものなどといってきましたが、もちろん「教育の歴史」はそれ以前からありました。「公教育制度」の歴史が新しいのですが、とにかく「近代以前」もみておきたいと。前提になっているのじゃないかと思います。
例えば、以前調べたことがあるのですが、「スポーツsport」という言葉は近代以降に「つくられた」ものです。すると「スポーツ」は近代以降しかないということになる。いや「古代オリンピック」とか「アゴニーズ」とか儀式・祭典はあったわけですし、マラソンは「人類最古のスポーツ」などといわれる。「スポーツ」の用語が定義されていなくても、ほぼ同じ意義をもつ、あるいは似た形式の行ないはあったのですね。「前身」というやつです。それと同じく「教育」も学校教育の「システム」化は新しい概念かもしれませんが、もちろん古代の人間社会においても同様の「モノ」があったのです。そこで、どう理念や目標が違うのか、あるいは形式や内容が違うのか、概観しておきます。教育の前史的なものです。
① 近代以前の教育
・・・一部の個人、少人数→多数を相手に授業が行なわれるようになるまで。
|
*学校の歴史(公立学校制度ができるまで)を概観する
①古代→ギリシア古代都市の哲学スクール、アカデミア等。プラトンやアリストテレスらの哲学者・教養人。一部の政治的指導者=「知識人の教養」のためのものという限定。
②中世→ヨーロッパ・キリスト教の宗教思想。僧職が特権階級。僧職のための学校。
③ルネサンス期→科学の発達。宗教改革、世界観変革。実学が流行。私塾。学問熱が高まる。
④絶対主義国家確立→支配階級の教育。国民統一、軍事力をつけるための教育。国民支配。
⑤産業革命期→資本主義化、貿易等で経済力を増す国、工業化によって国力を富強した国が「近代化」。工場労働問題との関わりで国民に知識を与える必要、子どもへの教育の必要性が説かれる。
⑥公教育制度の確立→19世紀後半に初等教育の義務化という形式で達成。義務・無償・中立性の3原則が公教育の特徴。
|
| |
国民の、人間に共通する基本的な権利として把握される以前から、古くから、一部の人のために教育はありました。徒弟制度とか技術の教育・伝承もありました。
古代のギリシアには、シューレとかヒムナシオ、ギムナジウム、アカデミアなどの施設がありました。シューレは「余暇」の意味ですね。お金や生活やまさに長寿健康の意味でも「余暇・余裕」のある人が受けることができたのですね。
ちなみに『ギリシア人の教育』という本は、おすすめですが、次のようなことが書いてあります。古代ギリシャにおいてプラトン、イソクラテス、古くはアイスキュロスらがPaideia(一般教養)というものを提起して、これが教育論のはじまりだ、と。しかしその内容は「子どもは人前で口をモグモグしない」「座り方は膝を前に置く」「食事は年長者から」等が書かれていて、これはむしろ子どもの養育、躾け、作法ともいうべきものですね。そして、プラトンは数学を教育課程として重んじていて、17、18歳まで自由に数学・幾何・天文学らを学び、これに20歳までは強制的な体育訓練を加えて、30歳ぐらいまでに全体的に結びつけさせるのだと。その後35歳ぐらいまで哲学問答を経て、50歳まで公務につき、それ以降は国政につき、哲学を説くとしました。イソクラテスの場合は弁論、言葉、文学、修辞学を重んじて教育課程としてふりわけているわけですが・・・。
こうみると、何才から「国政に就く」などとしているのは権威的とも思えます。秩序と順序を年齢で定めている年功序列主義ともみえる。哲学という思考と弁論を一部の年齢層でかこいこむような、そういう性格もあったとも思えます。・・・もちろん実際には、いまの政治家の方々とは違って、プラトンの時代では国政は「責任」は重くその分もつ権限というか権威もあったのでしょうが、彼らの考えとして不正をなくすためか正義のためか、お金にならないものだったのですね。つまり二世議員とか地盤・看板ではなく、やる気がないとやってもしかたないしんどいものであったということが根本的には違います。そういう責任感は違った。でも、教育(的なもの)は「社会秩序」のためにと考えられていた。
中世キリスト教の時代だって、宗教がある程度、社会的秩序維持の装置にはなっていましたよね。ちなみに「カトリック」とは本来「公会」という意味をもちます。まさに公の集まり(会衆)のための教義なのですね。神父が司式し、そして「説教」をするわけです。いや、仏教の説法も同質ですね。してはいけないことを輪廻転生で説明したり地獄絵図というビジュアルでみせたり・・・、そして生まれ変わりや天国を説くことで現世での我慢や服従・従属といいましょうか、不満を解消する。不安に対応するのが宗教ともいえますから・・・。そして仏教もキリスト教も教義を解したり読めるのは宣教師や僧職であり特権化された文字というかそういう理解でした。当時の知識というか「人心」を集める最高峰がまさに一部の人たちに占められていたというのも事実の一面です。
これが長く続いて、ガリレオ・ガリレイやコペルニクスらによって宗教観を変えるような発明・発見がされたのが次の時代ですね。ルネッサンスによって学問熱・科学熱があがった。「地球は丸い」という地動説の証明によって、宗教の権威はゆらぎますし、それに国際感覚と異文化の流入・摂取によって新しいものが生み出されていく、シンクロされる時代になりました。蒸気機関、羅針盤、火薬、いろんなものが発明されて富裕の国と支配される国、いろんな文化によって発展する国とゆらぐ国がでてきたのですね。日本にもザビエルや鉄砲が伝来して、それで城下町や戦争の形態も、権力の形もかわっていきますから、世界的に「流れ」が大きくうねって伝わったと・・・。
そして王権の国や絶対主義という国際性とうらはらに帝国主義的な強大な国家がでてきます。強兵づくりのためのイデオロギーや体育訓練、そういう強権的な国家も出てくる。他国を知ることから「自国」というナショナリズムや「国体(国家体制)」という考え方も出てくるのですね。これは反する、矛盾するようでセットになる。一方で理解をといって、一方で優越性や差異を説き、そして国内へは一致団結という服従従属を説く。そういう極端に走る国もありました。
そこで時代がすすむと市民革命等もでてくる。権力・圧政への反感がいいだせるタイミングというのはありますね。他国へ強かったものが弱くなった時、あるいはあまりにも国内圧政を理不尽なまでに進めた時、・・・革命の時期はやはり世界史的に共通しているともいえる。まぁ、次に述べるルソーの時代のような本当の流血革命もありましたが、技術革新の革命もあったのですね。それが産業革命です。ちょうどルネッサンスと時代をはさむ形です。そういうものが流れとしてある。「工場法」というやつが成立して、イギリスでも日本でも同じくありましたが、それで児童の労働に規制をかける・・・、「子どもは働かせるより学んだ方が後のためになる」という「学校教育の必要性」がある種、経済的にとらえられた。まさに経済的に授業が行なわれたり(助教法)、急速に教育が普及していくんですね。市民の時代到来か、となる。そういった経緯があって、近代教育が成立したわけです。公教育がある時代になった。
②教育の思想・・・代表的な教育思想家から考える「近代教育」
教育学をつくりあげた教育思想家を概観することから考えていきます。近代教育のキーパーソンと呼ばれる人々を古い順にあげてみることで全体の流れを説明してみましょう。
なお、基本的に「人名」や「事柄」を記憶しろとはいいません。「知識」として学ぶのはいいのですが、とりあえずまずは発展の経緯・歴史・雰囲気をみてもらって、そのキーワードたりえる人物を紹介してほんの一部の活動を話すぐらいに限定します。各自で興味をもった人物について調べてみてください。また、各人物の著作もあげますので、具体的にその人物の思想を知るにはそういうものにも目を通すといいと思います。難しい本もありますが、新書版のものもあります。教養のためにはいいのではないでしょうか。
まずはコメニウスです。
①コメニウス(Comenius, J.A. 1592-1670)
教授学を構想した人物でラテン語を教える教科書として『大教授学』(1632年)を著し、また世界初の絵入り本『世界図絵』(1658年)を著した。「近代教育学の父」と称される人物。幼児の自発的な発達に注目し、ようするに家庭で児童を教育するということを重視して指摘した。特に知識というか言葉の教え方にウェイトを置いた。やさしいものから難しいものへと学ぶ(理解の)順序を考えた。とにかく人間にとって「教育」の必要性を説いた人。授業の進め方として自然界でいうところの「太陽」のように全生徒に同時に教授することを説いた。ベルやランカスターによって助教法として各国に広まったものもこの影響を受けている。
「助教法」というのは後で紹介します。学校というか「工場」のように教えるといいますか、そういう一斉教育の必要をいっていた。図示テキストといいますか知識伝達の効率性・教材をつくった人物でもあった。
続いてはルソーです。世界史の授業等にも出てきた重要人物です。この中には専門的に勉強されている方もいらっしゃるでしょうが、あくまでも簡単にとりあげます。
②ルソー(Rousseau, J.J. 1712-1778)
ルソーは『社会契約論』を著してフランス革命に影響を与えた人物で、教育論としても『エミール』(1762年)を著して近代教育史上に大きな足跡を残している。自然主義、子どもの自発性、内発性、主体性を尊重するという「児童中心主義」の教育観を展開していた。「消極的教育」といって、教え込まない教育、自然な教育を標榜していたが、革命論と同じく、当時の教育に対する反発から出たものでもあった。当時、フランスでは暗記重視の教育だった。それを批判して自然主義的な教育を主張した。『エミール』の内容は家庭教師による個人教育と発達・成長について書かれている。小説で教育論を展開し、大きく影響を及ぼした人物である。
『エミール』は今でも教育界で聖書的(福音書)に扱われるベストセラーです。個人的には複雑な人物でしたが、当時思想家として影響力があり、「画一的で詰め込み的な教育」を批判したという点がひじょうに印象的です。しかし、そのルソーをあげて「教育は必要」としている現代の教育(あるいは教員養成)は、やっていることは「画一的な現実ももつ集団教育」という現実(矛盾)があります。教育とはそういうものなのかもしれません。その二面性については、またさらっと説明します。「不平等起源論」「社会契約論」「エミール」の記述内容からその複雑さがわかります。簡単にひとことでいいきるべき人物ではないのですが、あえてここではこのぐらいにとどめます。
次に、実際に「学校での授業方法」を実践して考案した人物です。
③ペスタロッチ(Pestalozzi, J.H. 1746-1827)
ペスタロッチは実際に学校を経営して教育の方法を研究した人物である。直観主義の教育方法(メトーデ)を確立した。「直観」とは直接モノを観て教えるという実物主義の考えで、「数・形・語」を教えた。例えば果実でその数、形体、名称や性質を教える。基礎陶冶を重視して、その上で開発主義の問答法で認識をすすめていくのであった。
ペスタロッチの教授法は以前に資料でみたものです。明治期の日本にもこれが最新のものとして導入されました。実物で「数・形・語」を教えるというのは、例えば「りんご」をもってきて、その名前を教え、性質を教えます。丸い、赤い、青い、大きい、小さい、硬い・・・、いろいろありますね。綴りも教え発声発音も教えます。そして比較して数概念も教えられます。洋数字を教えて、その書き方、概念を理解してから、応用して増やしたり減らしたり・・・、足し算にも引き算にもなりますね。半分にカットすれば分数も可能ですか。・・・とにかくそういう教え方が可能である。これは物でなく絵図に省略されることが多かったですね。「実物主義」ではあったが形式的ではありました。前回のインターナショナルスクールの算数の教え方がまさにこれですね。この基礎を言っていた人とも考えられますか。世界中に広まって行きました。
その方法を応用してその前段階で試みたのがフレーベルです。
④フレーベル(Frobel, F.W.A. 1782-1852)
上のペスタロッチの学校で学んで幼児教育で実践した人物。幼稚園(Kindergarten)の創始者であり、英語圏でもキンダーガーテンというように、彼がつくった名称がのこっている。子どもの自己活動を重視して、児童の遊戯の教育的意義を指摘した。遊具(恩物)を考案して幼児期の教育のあり方を提唱した人物。『人間の教育』(1826年)を著した。
「遊戯」や「遊具・玩具」、とくに「恩物」というもので様々な形や数を体得させるように考えました。いまの幼稚園の教育の基礎もここにありますね。
そして「教授学」といいますか「教育学」を大系化するのに尽くしたのがヘルバルトでして、ペスタロッチに並び称される人物として知られます。
⑤ヘルバルト(Herbart, J.F. 1776-1841)
ヘルバルトもペスタロッチに接しているが、科学としての教育学の確立を目指して活躍した人である。学校教育の基礎を構築したともいえる。四段階の理論として「明瞭」(個別の知覚)・「連合」(表象の連合)・「系統」(多数のものの関係・秩序)・「方法」(応用)を掲げた。のちに弟子たちによるヘルバルト学派によって五段階(予備・提示・比較・総括・応用)に変えられ世界中に伝わるが形式的な段階説となってしまったという点もある。
明治期に日本の学校制度が確立した時に最も影響力をもっていたのがこのヘルバルト主義の教育でした。助教法を乗りこえたペスタロッチ主義をさらに乗りこえたものともいえます。ここで教科教授法の大枠は完成した(ここまででいちおうの完成をみた)とも考えられます。
その後、ヘルバルト主義等の集団教授を画一的で教師中心であると批判し、新しい教授法といいますかあるべき教育観を説いたのがデューイという人物です。
⑥ジョン・デューイ(Dewey, John 1859-1952)
アメリカのシカゴ大学における実験学校で自らの哲学思想(実用主義・プラグマティズム)に基づく経験主義的授業研究(実験主義)を行ない、「社会」と人間の成長・学校との関係を説いた。著書『学校と社会』『民主主義と教育』等とその基礎理論「経験主義」「問題解決学習」「児童中心主義」等が20世紀新教育運動の中心的理論となった。「子どもが中心・太陽」であり、学習者の経験・周囲のことから出発・組織していくのが授業ということになる。作業等をとりいれたのも特長。
デューイによって、根本的に教育観はくつがえされたともいえます。もちろんルソーもなにも「児童中心主義」をうたってもいますが、その「授業」を具体化して普及させたのはこのデューイ等です。例えば次のように世界中に「新教育」として広まりました。
→→キルパトリック(Kilpatrick, William H. 1871-1965)
デューイから指導を受け、「プロジェクト・メソッド」を開発。子どもに発見・計画させ、その解決作業を通して知識・経験を得させようとするもの。
→→1920年代以降、「能力別学習」「個別学習」(生徒の能力・個性差、自主性を尊重するシステム)が流行。ウォッシュバーン(Washburne,Carleton W. 1889-1968)の「ウィネトカ・システム」、パーカースト(Parkhurst, Helen 1887-1973)の「ダルトン・プラン」、モンテッソーリ(Montessori, Maria 1870-1952)の「モンテッソーリ・メソッド」。日本でも大正自由教育として沢柳政太郎の成城小学校での実験(1917年)、及川平治(明石女子師範附属小学校)の各科分断の方法、木下竹次(奈良女子高等師範附属小学校)の合科教授、小原国芳の玉川学園の教育、羽仁もと子の自由学園などがあった。
以上のように、「知識の教授(教師による教授)→→学習者主体の学習」へと転換したのですね。ちなみに「近代教育」という場合の「近代」とは日本の場合は「明治期から第二次世界大戦敗戦まで」といいました。それでいうと、このコメニウスからデューイまでが近代ともいえます。
コメニウスは「近代教育学の父」とも称されますし、「世界図絵」とかのテキスト等を著すことによって教育方法と内容ということを保障したというか準備した。そして彼によって「太陽の光のように一斉に生徒を照らす」とされて、一斉教授の重要性がひろまったのですね。それは助教法へ影響を与えた。ルソーによって画一的な教え込みが批判され、消極的な「自然な」教育がすすめられた。著書『エミール』の影響が大きく「教育の福音書」ともいわれたベストセラーになった。ペスタロッチによってメトーデ(教育方法)の一つとして「直観主義教育」がつくられ、教室で実物や掛け図をつかった効率的な授業が可能になったし、そのペスタロッチに学んだフレーベルによって幼稚園での幼児教育が、そして同じく影響を受けたヘルバルトによって教授学(教育学)が構築された。いまの学校教育の原型はこうやってできてきたんだともいえますね。
そのかたちと違って、学習者中心の「児童中心主義」の教育を提唱したのがデューイでした。、シカゴの実験学校(大学の附属学校)での成果をもとにすすめたのですが、経験カリキュラムともいわれるもので、生活体験主義にもとづくものですね。まぁ、あくまでも単純に比較すればコメニウスらの一斉教授が「教師が太陽」という教師中心主義なのに対して、ここで「児童・生徒が太陽」の児童・学習者中心にと変わったともいえる。生徒の「自主性」という点ではかなり変わったのだと思われます。
日本でもほぼ同じ流れです。ヘルバルト主義の教育が主潮のころは教科書検定や国定化への間でもあり、全体を重んじる風潮があった。授業集団としての「学級」が重んじられその「管理」が重視されたんですね。いずれ「学校批判」はでてくるわけですが。
大正デモクラシーのころの「新教育運動」もあり、例えば1920年代末から30年代頃に「生活綴方運動」があったと。
③ 一斉教授における初期の形態・教育方法=助教法(モニトリアルシステム)→ペスタロッチ式教授法
コメニウスの提示した「一斉教育」の必要性は、とにかく実現するにしても「学校」も「教員」も不足していたのですね。あたりまえですが、最初の導入なわけで、ゼロからはじめるのにそんなにうまく条件があうわけがなかった。それまでの少数や一部の人への教育、あるいは家庭教育と違って、学校的な場所で生徒を多数集めて、それを対象に「一斉授業」をするのには準備がたりないわけです。そういうシステムがなかったのですから。
ですから、教員が急速に養成される必要があった。テキストや生徒がいても、教師がいなければ授業はできないですね。それで、その不足を補うように考案されたのが「助教法」です。資料で配布したように、ベルとランカスターの広めた方法です。経済的な方法でした。モニトリアル・システムmonitorial systemといいますが、日本語では「助教法」と称されます。
教員を雇うにはお金がかかるでしょうし、しかも少人数の教師で多人数の生徒に教えられるという効率性から考えても、たしかに経済的ではあったと思います。ただし、内容的にはお粗末になりかねない、そういう限界がありました。
下の図は日本での助教法が示されたものです。教室の真ん中に「教師」が位置して、そして教師がまず朝の時間に助教数人に教授するのですね。次の時間に助教がそのまま各担当スペースの生徒に伝える。ちなみに「助教」は「生徒」の一員です。首席であったり優秀であったり、上級生であったり、そういう生徒の代表でした。例えば日本のこの資料とした文書が「学制」草案に付された師範学校計画案ともいえる「教官教育所ノ定律」という文書ですが、時間割では次のようになります。
自九字至十字・・・教師二十五人ノ助教ヲ教授ス
自十字至十一字・・・助教生徒ヲ教授ス
自十一字至十二字・・・助教朝朝教授ヲ受タル所ノ者ヲ筆記ス
(以下、繰り返し)
つまり、こういうことですね。朝9時から10時の時間に、教師が25人の助教に対して今日教えるところを授業するわけです。
次の時間に、10時から11時まで、助教は教わったとおりの授業を生徒に対してする。
そしてその後、助教は今日の内容を筆記記録するのですね。それを午後も繰り返す。
この方法ならば、たしかにわずかな経費で多数の児童に同時に教育内容を伝えることができるわけです。しかし、きわめて形式的ですね。画一的で注入的とも指摘されるでしょう。内容的に例えば生徒の発問に答えうるシステムとはいえないですね。そういう質的な限界がありました。あくまでも導入時期に有効な、そういう限定的なものであったと思います。
各地に「教育」を普及させるに際して役にたったとはいえます。質より量という本質があったのではないでしょうか。
そういうものを批判して、乗り越えようとしたのがペスタロッチ主義の教育ともいえます。「直観」教授という、あるいは「実物」教授という、ものを提示してそれで事物の効用等を教えるという方式で、いちおう開発的な、問答を通して児童の内面から理解させていこうという目的をもったものではありました。
例えば「数・形・語」というのを教えるのですね。リンゴをつかってなら、その名称、スペル(綴り)、特徴とか、ですね。丸い、赤い、青い、大きいのと小さいの、硬いなど。それと数ですね。お買い物計算みたいにも発展させられるわけです。今でも初歩的教育の教科書はそういう例えで教えられているはずです。そういうもとをつくったわけだし、児童の興味をひくというか、実際的な実学的なものでもあった。
その具体的な教え方が世界へ広がって行ったし、その応用で各教科や教員養成が行なわれるようになったのですね。その点で、助教法の画一的なものや注入的なものを批判したともいえます。実際には、これも形式的になって、また初期にはやはり助教方式が行なわれたりもしたのです。その区分けは微妙だと私は思います。
④教師中心の授業から、児童中心の授業へ
デューイの構想した経験的学習では、この授業スタイルがガラッと変わった。生徒の生活体験にねざすとして教科指導というか協同作業的なものが重視される一面もあった。そこで教室内でのスタイルも、例えば「調べ学習」などでは一斉に教壇の方を向くのではない座席の配置になったのですね。カタチだけの違いでもありますが、児童観・教育観が少し違っているといえます。
もちろんデューイ自身がどう考えていたかは、やはり運動の中心となって他国へ拡がっていくときには変えられて伝えられた部分もあるかとは思います。しっかりと規制をいっていたとか、米国の教育も多くは教師中心であるとかの現実はあります。しかしそういうシンボルとしてとらえられているということも事実ですので、ここでは「児童中心主義」といっておきます。ルソーも例えば本質的には複雑だったり・・・、そういうものです。