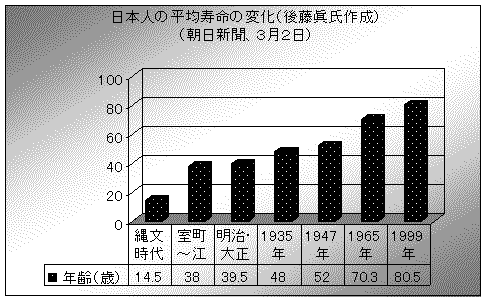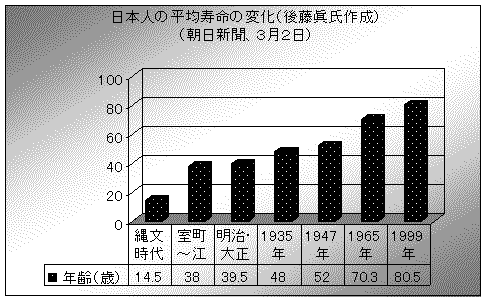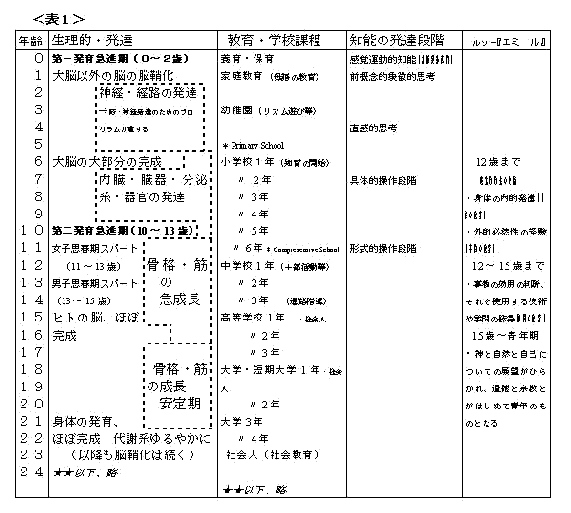第二回(4月25日)
2)教育の本質・目的,教育の行なわれる場所
3)発見された子ども,近代の子ども観と教育原理
第二回目の授業ですが、まず前回のアンケートでお答(応)えしておきたいことがあります。この中の、受講者の中の半分ぐらいの方が「教職」のためにとっていて、他の半分が「社会教育主事」か「博物館学芸員」の資格のためにこの授業を履修しているわけです。その「教職」以外の方々からのご意見として、「学校教育の話しよりも社会教育とかについてやってほしい」「なぜ教育原論が必要なのか」という要望・疑問がありました。お気持ちはわかります。
シラバスにも明らかなように、この授業の内容は「学校教育」中心でして、たしかに「どこが関係あるのか」という疑問はあるでしょう。お応えになるかわかりませんが、あえてお答えすると「この世に無駄なもの」「無関係のもの」「学んで意味のないもの」はないと考えます。ちょっと説明しますと・・・。それは今回からの内容にも関わります。
「社会教育主事」は公務員になって教育委員会などで仕事する際にいきるものでして、地域(地方)の「社会教育」の事業・行事に際して「指導的」な立場から助言等を与え、または関わっていくというものです。社会教育の行事とは例えばその地域での教育フェスティバルとか社会体育のレクリエーションなどもそうですが、生涯学習の集いや講座なども含まれますかね。そういうものに関わっていくとき、この「学校教育」の理念について知っておくことは必要です。なぜなら、教育の行なわれる場は普通「家庭」・「学校」・「社会(地域)」だなどと言われ、特に「家庭と学校、地域との連繋を」ということばが課題としてピックアップされます。たしかに正しいとは思います。しかし、これは実はいまは同時に存在しますが、時代的には発展してあとから付け加えられてきたものだと考えます。具体的にいえば最初は「家庭」しかなかった。長生きするようになって、また社会の変化もあってそれで「学校」という一律の公の教育の場がつくられた。これは小学校だけから中学・高校と・・・(義務教育が延長されて、いまでは90%以上の子が高校に進学しますね)、しだいに拡充拡大してきた。
長生き、長寿化ですね・・・。原人の平均寿命、鎌倉時代のもの、江戸時代のもの、昭和初期(戦前)のもの、戦後、平成の現在と比べれば・・・、60歳以上まで平均寿命が延びたのは戦後以降なんですね。全体が長寿化・高齢化していく社会・・・、それによって大衆社会が実現した。ここで細かいデータはあげませんが、しかし考えかたとして、人生20歳までで、小学校11歳ぐらいまで、あるいは大学22歳まで教育を受けれません。教育で人生完うしてしまう。寿命40年だってそのうちの半分が教育を受ける期間だとしたら、その後は子育てで人生終わりますね。しかし60歳なら、20年教育を受け、その後子育てをし、子どもが20年教育を受けたらその後の20年を自分の人生としておくることは可能です。それでもまだかなり短い。ところが現在のように80〜90歳まで生きるのならば、これはかなり充実した教育期間をもたせることができますね。結局教育はそういう「可能」という現実の反映として充実してきたという一面もあります。
で、話が長く、さらにそれていきますが、戻れば「社会教育」という話しは「学校」教育後の充実というか不満の裏返しというか、例えば充実感を求めるママさんバレーのような集合として、欲求があってでてきたものといえます。「人間は生涯学ぶもの」という考えがユネスコなどの国際的会合で出てくるようになった。その反映ですね。
ここまでで乱暴にいえば、「家庭」だけで足りないので「学校」がつくられ、それでも足りないとなって「社会教育」がつくられた・・・、そういう面もあります。そして今では「社会教育」は「学校後」ではなく、家庭も学校も含んだ全体のこととなっています。地域の教育機関・施設、地域の教育力などといえるのではないでしょうか。
もう一つは「家庭」で教育されるのは順番的に一番最初ですね。言葉なんかを習ったり、その後、幼稚園とか学校に行くわけです。で学校にいる年齢がそれに続きます。それで学校後の教育が社会教育であるのなら、まさに「学ぶ場」としての年齢順序でもあります。
さて、そんなわけでして、「社会教育」を学ぶ方、「学校教育」が関係ないなんてことはありません。もしも「批判」から社会教育が構想されたのなら、その批判の対象の学校の限界を知っておく必要があります。さらに年齢だとしても、自らの施設に来る前に彼らが受けていた「教育」について、つまり「学校」について知っておく必要があります。
どうでしょうか? 無関係ではないと思います。
そして「博物館」の方も同じです。博物館は「社会教育の施設」です。教育を目標としてつくられたものです。今回、学ぶコメニウスとかもそうですが、最初の教育は「百科事典」のようなテキストで事物を学ぶことであった。いや、例えば王の墳墓の埋葬品などに特徴が表れていると思いますが、「物を集める」それを「保存する」というのは、「宝物殿」などもそうですが、そういうものも栄華を極めるというのとともに、いろんな情報の保存というか教育的効果もあったんですね。後に博物館がつくられますが、例えば世界規模の博覧会などがあって、そういうものに参加して、そういうものが「必要だ」となって世界中にそういう「施設」がつくられていく。例えば日本の「東京教育博物館」というのは明治初期に文部省最初の外国人顧問であったDavid Murrayという人の意見があってつくられたものですが、・・・博物館は「教育」のためのものであった。「知識(情報)」を得るのに重要な機関だったのですね。ちなみに Murrayという人物について研究もしているのですが、彼の建言によってこのお茶の水女子大学もできたといえるかもしれません。「女子教育・女子師範学校」の必要を説いたのがこのアメリカ人でした。
だから、博物館も学校も教育機関として一緒でして、「教育」の理論・理念を知っていなくてはならないとされたんですね。それでこの授業が充てられたわけです。
どうでしょうか。無理に納得などしないでください。とりあえず無意味ではないように授業をすすめますし、それに関連することもやっていこうと思います。
(他に「生理曲線」「人生の関数曲線」等によって「教育」のありかたについて説明をした。その時の図は省略する。)
さて、それではシラバスの2と3の部分について入っていきます。
まず、「教育がなぜ必要とされるのか」ということからはじめましょう。
教育学の「前提」は教育の必要さを説き、それによって人間が「善く」なるということであるが、これはある種の神話づくりともとらえることができる。まさに教育の逸話、必要性を説くための、その根拠となる伝説が教材となって語られるのである。
「教育」の必要さは自明のことだとも思えるのだが、あえて「教育学」の基礎として、次の3つの事項・ことばが三点セット的に語られることが多いと思う。テキスト等で確認してみていただきたい。
●カント(Kant,I.)→→「人間は教育されなくてはならない唯一の被造物である」
・・・哲学者カントのことばですね。そういう言葉があることが示される。
●教育学の「逸話」→→「アヴェロンの野性児」や「狼に育てられた子」の物語
・・・密林で保護された子ども(アマラやカマラなど)の成長の記録が教材となる。しかしこれは事実なのでしょうか。「アヴェロンの野性児」は約200年前の記録で「野性児」というか孤独に屋外で生活する人間の子の物語です。「狼に育てられた子」とされるアマラやカマラはしかし疑わしいのではないかと私は考える。まず実証不可能で、再現しようとすればそれは人権侵害になる。言葉が獲得できなかったとか、人間としての生活規範が身につかなかったという示唆的なものと読むべきもので、しかし「事実」かどうか疑わしいものを「教育学」の前提にあげているのはおかしい。生物学的に納得がいかない。いえることはただ一つ、事実かどうかではなく、その記述で示された状況は発達・発育障害であるということだけです。生理的に機能障害があるとはいえる。(実はもっと前にコメニウスとか「近代教育学の始祖」的存在の人のテキストにもこういう例が書いてあるのです。そういうものが「語られる」不思議さがある。)
●ポルトマン(動物学者)→→医学的・生物学的「生理的早産」
・・・ポルトマンは人間を「生理的早産」であるとした。これによって人間には幼児期の養育が必要だし、社会(への依存)が必要だから社会性を育てるためにも「教育」が重要だというのはわかる。いちばん科学的で納得はいく。哺乳類のうち高等なものは妊娠期間が長く、少産で離巣性という性質がみられる。下等なものほど多産で就巣性、妊娠期間も短い。これは危険性というか弱さを示しています。で、人間は高等なはずなのにこれにはあてはまらない。なぜなら少産ではあるけど、就巣性です。赤ちゃんがすぐに立てないし、しかも成人とはかなり異なる形態で生まれてくる。
テレビで放映されるシーンによくあるように動物(馬や牛)はかなり親に近い形態で生まれてくるし、すぐに親について歩きまわります。例えば今朝のテレビで出ていたのですが、2歳の馬で額だけ白いのがいて、それが子どもなのですが、成長すると全身が白くなる。そのときいっしょに映った白い馬は親馬なのですが、体格体高は同じぐらいでした。差がない。人間の大人と2歳の子どもで、同じということがありえますでしょうか。
そう考えると人間は急激に成長するというか、激変する生物ですね。急激にというよりも長い時間をかけて成長していって、それでかなり変わる生物です。それで能力が高くなっていくし、高等な哺乳類となる。だから生まれた時は貧弱脆弱です。ですからある種、恒常的な「未熟児」として生まれてくるわけですね。これを「生理的早産」という。
二足で立つ生物であるし、脳が発達しているから、これ以上胎内で成長しちゃうと出て来れないということもあるのでしょう。それで「恒常的に未熟」な時点で体外に出され、そこで本来なら胎内で発達させるべき諸器官の発達がすすむわけです。だから大人による養育が必須なわけです。
また人間の幼児期には「可塑性」が大きくみられます。これも他の動物とは違った特長です。大きく変わっていく可能性がある。だから幼児期から関わってあげる必要がある。
次の図をみてください。
私がいいたいのは、「教育」の必要性には「伝説」を語る必要はないのではないかということです。そもそも、医学の発達、解剖学の発達、生理学理解の発達があって、長寿もあるし、「子どもの発見」というのが可能になった。それで「教育」がでてきたというか、意味をもつようになった。どこの国でも産業革命以降「工場法」とかがつくられて、子どもが(子どもの時に)働くよりもその時期に教育を受けることでのちに益をなす人材に育つことが説かれていた。日本でも明治中期にそういう運動がおこった。
そして図表に示したように、「生理学的」に裏付けられるというか、そういった発育・成長段階に従って、「教える内容・方法」や必要な「教育」のありかた(目標)、あるいは精神・心理的変化がありえるし理解されてきたと考えられます。いや、何がいいたいかというと「加齢変化」ですね。教育学や心理学でいろんな前提とされるもの。これは「生理学」的知見として裏付けられているものなのだと・・・。だから曖昧なことはいらないで、正しく堂々と科学的にいくべきではないかなと・・・。ルソーの『エミール』は教育学にとってバイブル的存在ですが、そこで説かれる発達過程に「ふさわしい」教育も見事なまでにあてはまるわけですね。(絵は省略しますが)また、乳幼児から幼児期までに神経系が発達するとして、中枢から末梢へと神経が通ってくることによって「掴む」とか「歩く」とかが可能になりますが、そのときには「神経」系のための教育が必要になってくる。だから幼稚園とかの教育内容は「手遊び」などなんですね。幼児教育の内容や、幼稚園はフレーベルという人物によってつくられた面が大きいのですが、その内容はまさに「生理学」的にもふさわしいものです。あたりまえですが簡単なものから入ってじょじょに難しい高度なものにすすんでいく・・・、これらを段階にわりふる時に、そう分けられたものの前提は「観察」的なものであったにしても「生理学」的、「医学」的に正しいのであればもっとこれらを強調していいのではないかと考えます。
今日は時間となりましたので、ここで終わります。
以下のアンケートに協力をお願いします。
① 専門的か、あるいは教養的であるかにかかわらず、大学で受講しているなかで、面白い講義というのを教えてくれますか。
② 本日の講義内容について質問・疑問・ご意見等はありますでしょうか?
自由にどうぞ。
* なお、用意したけれども内容にふれることができなかったレジュメ・資料も付す。
「家庭と学校、地域との連繋を」ということば
教育学をつくりあげた教育思想家を概観することから考えてみる。近代教育のキーパーソンと呼ばれる人々を古い順にあげてみることで全体の流れを説明してみよう。
①コメニウス(Comenius, J.A. 1592-1670)
教授学を構想した人物でラテン語を教える教科書として『大教授学』(1632年)を著し、また世界初の絵入り本『世界図絵』(1658年)を著した。「近代教育学の父」と称される人物。幼児の自発的な発達に注目し、ようするに家庭で児童を教育するということを重視して指摘した。特に知識というか言葉の教え方にウェイトを置いた。やさしいものから難しいものへと学ぶ(理解の)順序を考えた。とにかく人間にとって「教育」の必要性を説いた人。
②ルソー(Rousseau, J.J. 1712-1778)
ルソーは『社会契約論』を著してフランス革命に影響を与えた人物で、教育論としても『エミール』(1762年)を著して近代教育史上に大きな足跡を残している。自然主義、子どもの自発性、内発性、主体性を尊重するという「児童中心主義」の教育観を展開していた。「消極的教育」といって、教え込まない教育、自然な教育を標榜していたが、革命論と同じく、当時の教育に対する反発から出たものでもあった。当時、フランスでは暗記重視の教育だった。それを批判して自然主義的な教育を主張した。『エミール』の内容は家庭教師による個人教育と発達・成長について書かれている。小説で教育論を展開し、大きく影響を及ぼした人物である。
③ペスタロッチ(Pestalozzi, J.H. 1746-1827)
ペスタロッチは実際に学校を経営して教育の方法を研究した人物である。直観主義の教育方法(メトーデ)を確立した。「直観」とは直接モノを観て教えるという実物主義の考えで、「数・形・語」を教えた。例えば果実でその数、形体、名称や性質を教える。基礎陶冶を重視して、その上で開発主義の問答法で認識をすすめていくのであった。
④フレーベル(Frobel, F.W.A. 1782-1852)
上のペスタロッチの学校で学んで幼児教育で実践した人物。幼稚園(Kindergarten)の創始者であり、英語圏でもキンダーガーテンというように、彼がつくった名称がのこっている。子どもの自己活動を重視して、児童の遊戯の教育的意義を指摘した。遊具(恩物)を考案して幼児期の教育のあり方を提唱した人物。『人間の教育』(1826年)を著した。
⑤ヘルバルト(Herbart, J.F. 1776-1841)
ヘルバルトもペスタロッチに接しているが、科学としての教育学の確立を目指して活躍した人である。学校教育の基礎を構築したともいえる。四段階の理論として「明瞭」(個別の知覚)・「連合」(表象の連合)・「系統」(多数のものの関係・秩序)・「方法」(応用)を掲げた。のちに弟子たちによるヘルバルト学派によって五段階(予備・提示・比較・総括・応用)に変えられ世界中に伝わるが形式的な段階説となってしまったという点もある。
⑥ラングラン(Paul Lengrand )
上に述べた5人と違ってグッと最近の人。ユネスコの成人教育推進国際委員会として「世界に生涯教育を」と提案(1965年12月:パリ)した。学校教育後の教育というか、人間は生涯学ぶものとの宣言であり、生涯教育時代を提示するものであった。1985年にはユネスコで「学習権」宣言が採決され「生涯学習」時代到来となった。
<参考となる書籍>
広川洋一『ギリシア人の教育』岩波新書 1990年
苅谷剛彦『知的複眼思考法』講談社 1996年