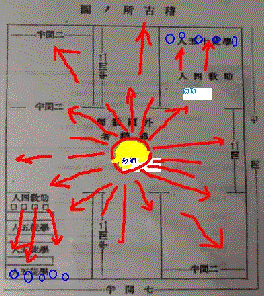教育の歴史 ④ 2002年10月18日
|
* 「どうしてこのような形で『教育』は変わってきたのか?」ということから「歴史」的に考えていく |
<前回の復習>
(3)教育のおおまかな流れ(世界史) <教え方の歴史的変遷 1
当時の学習観の違い>
|
流れ |
細かく |
日本 |
展 開 |
学習観 |
|
古代 |
古代 |
古代 |
①古代→ギリシア古代都市の哲学スクール |
哲学者 |
|
中世 |
初期 |
中世 |
②中世→ヨーロッパ・キリスト教の宗教思想 |
宗教者 |
|
後期 |
③ルネサンス期→科学の発達。実学が流行。 |
科 学 |
||
|
近世 |
④絶対主義国家確立→支配階級の教育。国民支配。(身分差があった) |
統 合 |
||
|
近代 |
初期 |
近代 |
⑤産業革命期→資本主義化、工業化により国力を富強した国が「近代化」 |
市 民 |
|
|
⑥公教育制度の確立→19世紀後半に初等教育の義務化という形式で達成 |
公教育 |
「古代」→「中世」→「近代」と移り変わってくる中で、基本的に「一部の人間のための教育(伝達)」というものが、「国民(大衆一般)のための教育」へと発展してきたことがわかる。その時の「学習内容」が「学習観」を形成したし(つまり価値あるものとされた)、その知識を限られた者に継承していくことがその時代の「教育」行為(機関)であった。中世後期までは「身分差」があり、限られた階層のための教育であったが、そうではなくなって広く一般大衆へと教育が拡大されていったのが「近代」とされる時代であった。私たちの「現代の教育」はここを直接の出発点とするものである。
(4)学校によって大衆教育が可能になった <教え方の歴史的変遷 2 一斉教授のはじまり>
・・・ 「教室」の構造、及び教育ツール・教材・教具(教科書)の発明
「近代の教育」が「大衆教育」だとしたら、それが可能になったのは何によってであろうか。「時代が変わったから」として受け止めるのは簡単だが、それでは「考えた」ことにはならない(初回の授業で説明している)。
これまでの講義で、教育の形態(授業)が歴史的には「一斉教授→児童中心主義の学習」と発展してきたことをみて、また「授業の形態」は「人数」によって規定されるということについても考えてきた。
|
|
|
|
|
|
そして前回の考察によれば、その時代の「価値観」としてあった「学習観」がなんらかの理由で「限界」になって「変わる」ということで教育は現在のような形式にまで発展してきたのではないかということである。つまり「その時代」に不都合が生じるというのは、例えば「奴隷制」であったり「王政」であったものが権威を消失し、その時に力をもったのがキリスト教思想であったり、普遍的な思想としてとりいれられていったのであった。そのキリスト教も拡大していく中で科学的思想の前に限界が生じ、「世界」に関係性というものが実感されるようになって(拡大して)いく。そのような様々なインパクトもあって国家の再編成なども起こるが「世界」に情報・知識・文化が広まり、普遍化していく中で「普遍化」や「一般化」という反応もあったのではないか。世界中に「近代国家」観、あるいは「平等」「自由」などの社会のモデルが広まっていったと考えられる。民主主義、社会主義などの運動の拡大も基本的には同様であろうと考えている。かくして「人的投資」ともいえる(人間の権利としての)「教育」のシステムも世界に拡大していき、現在においては少年・児童への義務就学が世界中で実現しているのである。こう考えれば「個人指導」で事足りた技術の伝承や家庭教育や、「少人数指導」でよかった一部の階層(身分)の者だけを対象とした特別な教育だけでは「方法的」に無理があり、その形のまま「大衆教育」(一斉教授)を実現するのには無理が生じたと思われる。
するとその「移行過程」においては、やはり何らかの試行や実験、開発、工夫がいくつかあり、それを経て「いまの授業方法による教育」におちついたのだと考えられる。これは歴史の断絶や大きい変化のみ見るのではなく、その連続性や細かな変容にまで注目するべきということでもある。今回は「大衆教育(一斉教授)」がどのようにして可能になったのかというのを「教授法の開発」及び「教室」「教材」「教具」の発明ということから考えていきたい。
●「大衆教育」(一斉教授)のための方法の発明
「国民全体」を対象とする公教育制度は「近代」以降のことではあったが、「人数」として比較的に「多数」を対象とする「教育」(つまり一斉教授)の実践はそれ以前の時代にもあった。古くはコメニウス(Johann Amos Comenius,1592-1670)が一斉教授の必要を唱え、今日の「教師中心主義」ともいえるような授業方法(「教師が太陽として均等に生徒を照らす」というもの)を提唱しているが彼が「近代教育の父」と呼ばれる所以であろう。このコメニウスの方法論は後に「助教法」として実現される。少し遅れてラ・サール(Jean
Baptiste de La sall,1651-1719)によるフランス「キリスト教学校同胞団」における貧民対象のキリスト教信仰を目的とする教育などもあり、等級編成という考え方も工夫された。教育の目的も、また対象も国民全体ではないことから違いはあるが、しかし「多数」を対象とする一斉教授の方法が考案され試行されたとはいえる。もちろん「宗教」、ことに「キリスト教」の礼拝は、牧師(司祭・神父)と信徒(教会員)という<教師-生徒>関係に近い関係が成り立ち、また「教会」という場所で教えを説くという性質も似通ったものではある。もちろん時間は短いが、教える構成や順序もあり、聖書講読や解説、訓話や音楽(讃美歌)もあり、祈祷などによる始まりと終わりという明確さももっていた。教会という場所が「教師」が位置するのが「前」であり、基本的に前方(祭壇)を向かって聴衆が座っているというのも「構造」として共通点がある。おそらくキリスト教や宗教はもっとも「大衆」のために「教える方法」として近代の「学校教育」に影響を及ぼしていると考えている。
それでも、実際に「学校」で一斉教授をする必要が出てきた時、ある程度の長さの時間を、またある程度の「教科内容」を教えるとなった時に、そのはじめの時には問題が生じたと思われる。いまなら「子どもに興味をもたせる」「知的好奇心を刺激」する授業や、「個性を尊重」する授業が課題となるであろうが、「最初」の問題はそのようなものではなかったと考える。もちろん「まず学校へ就学させる」ということも現実的問題ではあったろうが、しかしそれ以前に「学校」を成立させることが必要であったと考える。全国一斉に国民教育を開始などというのは現実的には難しかったはずで、おそらく授業のために人の集まった所とそうでない所とがあったと思う。しかし、現実的に「教育」を必要と考えるエネルギー(要求や受け入れられる状況)があったから、そのようにニーズが生じて実現をせまられたということも考えると、「教育内容」をかなりの多数を相手に一斉教授するということがせまられたことであろう。つまり、「やらなければならない」状況にあったと思われるが、それには「学校」が必要であったと思うのである。「学校」という場所や「教室」というスペースもそうであるが、とりあえずは「教師」が絶対的に必要だったのではないか。いや「不足」していたのではないか。「司祭」による教化や、あるいは宗教教育という「多人数教育」については実践はあったであろうが、しかし何らかの「教科内容」、つまり「読み、書き、算数」程度からであろうともそれを専門に、大衆を相手に教えてきたという「教師」が当時においてどのくらいいたのであろうか(「学校」を現在のようなものとみるのではなく、当初は「読み書きの延長」を大衆に教えるものというレベルから始まったと考える方がいいのではないか)。それまで達成(実現)されていなかった「大衆教育」を専門とする人間はいなかったのではないか。もちろん「宗派学校」や「私塾」の教師はいたとしても、彼ら自身「学校教育」を受けてきた経験があったであろうか。あるいは比較的「多数の授業」を受講してきた経験者が「教師」になった例があるにしても、それがどのくらいいたのであろうか。少なくとも「学校」なり「私塾」なりが隆盛にならねば職業としてのニーズが生じないわけで、すると計画的に「教師」を養成する必要もなければプログラムもなかったのではないか。「教師」が専門的に養成されなかった。したがって「教師」は絶対的に不足していたというのが実状ではなかったろうか。
ある日突然に「学校での一斉教授」が実現したのではなく、それには試行錯誤の段階があったのである。まず、最初の問題である「教師の不足」をどのように補ったのかを考えてみよう。
コメニウスの示唆にもあったが、一斉教授を「教師不足」でありながらも可能にしたのが「助教法」(monitorial system)という方法である。「通史」でいえばまさにニーズの生じた「産業革命期」に考案された方法である。イギリスのベル(Andrew
Bell,1753-1838)とランカスター(Joseph Lancaster,1778-1838)により同時期に考案されたため「ベル・ランカスター法」とも称される。少数の教師で多数の生徒に教授する方法として工夫されていて、生徒の中の優秀な者数名を「助教」(monitor)として選出し、彼らに他の生徒を教授させるという方法である。「教師」は数人の「助教」を相手に授業をし、「助教」が各集団の「生徒」を対象にしてその内容を伝えていく。これならば例えば教師一人が10人の助教に教えたとして、その助教が各10人ずつにその内容を伝えていけば教師1人で110人の生徒を相手に授業をしたということにも計算上なるのである。「産業革命」期という「教育需要」の拡大の時期に象徴的であり、ある種、機能的で経済的でもあった。「工場生産」にも似た性質の、効率が重視されたものともいえる。もちろん問題は多くある。「質」「内容」が最大の課題であったろう。「教師」養成が強く実感され、訴えられたという。しかし、その「評価」は別として、この「方法」が過渡的なものとして存在したために、その「教師養成」の必然性もわかり、かつ養成期間をつなぐことができたとはいえないだろうか。これをもって「近代教授法」と称賛するのでもなく、また不十分であったと評価するだけではなく、実はこの「転換期」に必要とされた工夫であったと考えてみたい。
この方法は世界的規模で行なわれている。一般に学校制度化にも多少の「時差」があるにもかかわらず、例えばこの「イギリス」に遅れて米国でも、そして日本でも「初期」において行なわれているのである。例えば日本では1872年、最初の「教員養成機関」の計画書にこの「助教法」の採用が示されている。当時の英米ではこの方法はすでに終わり、近代教授法というものが導入されていた時期であり「時差」がある。なぜその「最先端」の「近代教授法」が導入されなかったのであろうか。それは「教師の不足」という現実的問題ではなかったか。その時に「近代教授法」を実践可能であったのは、その実践を積んだ英米人のみであり、日本人ではない。しかし、そういう「日本人の教師」を養成するまで「学校」を凍結するわけにはいかないし、外国人を招聘して学校を教えさせるにも限度がある。「学校」がつくられるということは「小学校」から行き始めると考えられないか。もちろん大学からつくられる例もある。しかし「国民教育」の機関が準備されたのである。英米から招聘された外国人教師は大学のような機関の教師となり、あるいは日本人教師の養成を担当した。「国民教育」は国民の「教師」でなければならないし、まずは「実践しながら養成」というのが現実的であったろう。そのためには「自らが生徒であり、そして教師でもある」というこの方法は都合がよかったのではないか。
この「助教法」を一斉教授試行段階の初期型の方法ととらえておきたい。
<一斉教授初期型=「助教法」>
|
|
|
|
|
|||||||||||||
「教官教育所ノ定律」に記された「稽古所」
「助教法」はある意味では「生徒」間での学習を促す部分ももち、また「複数」の教師が空間に存在する「集団内」での「個別対応」を可能とするものと考えれば、「グループ学習」や「ティーム・ティーチング」とも共通するものである。しかし「一斉教授」の開始された当初であるこの時期に、「学習」や「個別」を考えるには限界もあった。実際に行なわれたのは「形式的」な暗唱を中心としる授業であった。しかし当時の欧米の初等教育自体が「暗記(レシテーション)」と考えられてきたという面もある。
いずれにせよ、この「助教法」を経て、それが批判されて「計画的に養成された有資格の教師」による待望の格調高い「授業」が行なわれるようになっていく。
|
|
一斉教授(教師中心) |
右の画像のような構造が現在も中心的に行なわれている「一斉教授」の形式であるが、「教師」が養成されてはじめて全国で行なわれることが可能となった。「助教法」と同じ点は「教師が太陽」であるという点である。「教師中心主義」という点では同様のものといえよう。
また、そのような方法が可能になったのは、「教室」の前で「教師」が「太陽」となっても均質に教育内容が伝わるということが可能になったからである(もちろん「位置」によって差はあると思うが)。「助教法」が「ティーム・ティーチング」的要素を持つというのは「多数」を相手に授業が行なわれるが基本的に直接に接するという点ではそれぞれ「少数教育」という点においてである。そのためアシスタント抜きの「教師」単独による「一斉教授」は現在でも批判されるように困難なものであった。それが可能になったのは「教師」が養成されたのと同様に、均質な教育を可能とする「媒介」が工夫・開発されたためである。
左の画像のように「教科書」「教材」が開発されたことが重要な意味をもつ。何を学ぶのかが明確に示され、またドリルなども行なうことができる。初期は「掛け図」を指し示したりして文字や意味を教えていたが、やがて教科書とノートというセットが普及することで、はじめて条件が揃った-あるいはそのような一斉教授が可能になったのではなかったか。
●教材・教具の開発-教育の物資的条件-
意識して相手に情報を「伝える方法」(知識を教える方法)には「話す」ことと「読み書き(文字)」とかがある。「教育」における「授業」でも基本的にはこれで情報が伝えられていく。教師は教育の内容について「話し」、そして「読み書き」をする。「話す」という方法としては、昔から、直接の対話、講話、講義、説法、説教、講演などがあった。口述の方法であり、間接的には口伝、あるいは民間伝承、物語等で伝わっていくというものもある。しかし「話す」ことはコミュニケーションの基本ではあるが伝わりにくいという限界もある。少数の技術の伝承ならばかなり充実するであろうが、それは少数で、実習もあるからである。「話す」だけだと「記録」されなくて忘却されやすいし、対象が多数であればあるほど伝わりにくいのだ。「共通」に物事を考えることも困難である。そこで、「文字(読み書き)」を組み合わせることで効果が出てくる。教科書、掛け図、黒板等、授業用にテキストを示すことで共通に問題に取り組むことが可能となる。また「記録」も可能となる。図絵(写真)や図鑑、百科事典・動植物図鑑、写真集等の視覚的に理解を深めていく教材も同様の効果を示す。これらの物資的条件によって「大衆教育」が可能になったのではないか。
例えばこの時期に大量印刷技術の発達、鉛筆、ペン、ノート等の発明・普及というものが著しく進んだことが指摘されている(佐藤秀夫の研究)。
佐藤氏は、「書きつけられるモノ」について歴史的に考察されている。古代から近代にかけて、世界中で「文字」を書きつけて記録するものとして様々な物が使用されてきた。メソポタミア文明では粘土板にテキストが記され、エジプト・地中海圏では葦のパピルスに記された。ローマ時代にはパピルスはなくなりパーチメント(羊の腹皮)やヴェラム(子牛)が使用された。インド、チベットでは貝多羅葉(バイタラヨウ)、中国では甲骨、石板、竹筒、木簡などに文字が記された。日本の場合、もちろん古代には石碑などもあったが、かな文学などが書き記されたものはなんであったか。あるいは掛軸、障子紙、書状・書簡などがあるように「紙」が使用されていた。「紙」技術は朝鮮から日本へと伝わり発達したが、こうぞ、みつまた、がんぴ等の材料・原料が豊富であったことが大きい。これが「和紙」のもとである。とりあえず動物の皮や骨よりは限りがない。またヨーロッパにはこれらは植生しない。後に針葉樹から「洋紙」がつくられるようになった。比較的に強く耐久性があり、持ち運べて大量に生産可能という点において「和紙」があったというのが日本の「教育」文化においても大きく影響しているのではないか(他に万年筆やペン、鉛筆の技術や、溶ける紙の技術・スキについても話したが略する)。出版・刊行のための「印刷技術」というものの発展も考えれば、「教育」における「教具」「教科書」等の開発という物資的条件は小さくないと考えられる。
●<伝承の形式>は「文化」のカタチを決定づける?
物資的条件を追求すると、次のような問いも出てくる。「国、地域で教育の方法が違っているとしたらそれは物資的条件に関係するのか?」という問いである。もちろんそのような差異の要因は複雑な問題であろうし、物資的といってもいまではどこに国でも印刷技術・製紙技術とも大差があるとは考えられない。もしも伝統的にそのような影響がみられたとしても、年月を経るごとに普遍化されてくるはずである。教育の差異、教育観の差異が「文化・慣習」による違いという意味ではこのような物資的条件(伝統)や技術も関係しているともいえなくもない。一般に「文化圏」ということでは次のように区分されてとらえられていることも多い。
|
|
|
なるほど、日本人は対話やスピーチで表現するのが下手だと言われるし、ディベートや討論も欧米の学生のようには活発には行なわれていないようである。それはこれまでの教育において重視されなかったという事実でもあろう。そのような大きい意味では「文字文化が発達している」ことで読み書き重視の教育となったという考え方もできよう。その分「文書学」や「書」が発達しているともいわれる。しかし、難しい問題である。例えば米国では大学の卒業論文以外にその口述発表などが広く行なわれているし、小学校段階からでも「授業中に発言・参加する態度が好ましい」というような考え方というものがある。「そのような教育をされている」と言った方が当てはまるのではないか。
つまり物資的条件は教育の可能性を広めていったが、「文化」の形まで形作っていったかはわからない。文化伝承や形成に寄与することになったとはいえるだろう。そして「教育」は(「そのような教育」という意味において)その地域・文化圏の価値観や慣習をつくり維持しうる。
「いま」を生きる私たちの考え方では、「教育は経済発展の附属的なもの」「時代により変わる」とされるが、この「ことば」だけでは「本当」には考えたことにならない(わかったようでわかっていない)。今後も多角的な視点で、歴史的に考察していきたい。
(リアクションペーパー配布→回収)