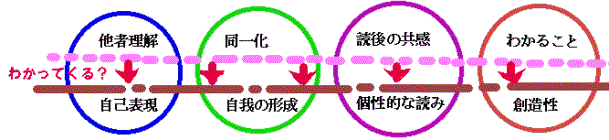教育の方法・技術論⑤(10月26日)
|
前回の復習・・・「わかる」ということを「心理学モデル」で頭の中の役割演技によって理解度が増していくという<「わかる」仕組み>を説明した。哲学のヘーゲルの論も紹介して「自己同一性」というもので「理解していく」ということも説明してみた。「心理学モデル」では「仮想の体験」によって実感にまで深まっていく過程で、その置き換えや統合が行なわれていって「自分の知識としてわかる」のだと考えたいということ。それを<言語化→構造化(おきかえ)→身体化>ととりあえず整理しておく。繰り返し説明してくれたり、例えてくれたことによって、また教材の提示や図示で置き換えてわかっていくそういうもの。視聴覚教材やテレビがわかりやすいというのはこれで、「身体化」して受け取りやすい。しかし、それを文字や言葉に置き換えられるだろうか。その「言語化」できるというまでわかることも、また、言語化から身体化まで深めていくのと同じで大切である。それで、苅谷剛彦氏の著書の「マジックワード」の「おきかえ」というのにも注目してもらった。「わかったようで、わかっていない」というところから一段アップするには、この作業が必要になるかと思う。 |
もう一度、確認・・・
|
|
・・・「わかってくる」というのは、「他者理解」が増したり、「同一化」の部分が増すことであり、「共感」が増すことでもある。しかし、上の図では「わかればわかる」ほど「自分」の部分がなくなるともみることができる。しかし、これはある「枠組み」の範囲内である。もともと「自我」「自己」「自分」という部分はちゃんと「主体」としてはあって、その中の「理解の枠組み」の中も「自分だけ」に凝り固まっていると「固定観念」として他の知識をうけつけないということになるわけである。もちろんある意味で洗脳ではないが、逆転移とか、あるいは本当に自我すら失うほどの共感というか影響の受け方もあるとは思う。そう考えれば「理解の枠組み」の中も完全に「自己」がなくなるかのような図示はすべきではないし、もちろん言ったように「完全な理解」はありえないというか、自分の役割演技にも似たものだからそれはないのだともいえる。「キュウリ」を食べても「キュウリにならない」といったのはそういうことも含んでいる。そして「役割演技」でいえば、まず全てに事前に「先入観」があるわけである。その見方もパターン化はされるけれども差異はある。しかし、会話をするシーンにしても、「彼は日本人だから」とか「いくつぐらいだろう」とか「どこどこであったから何が好きそうだ」とかの予想をもって話していくわけである。だから「話したり」、「話題を決めたり」、あるいは「日本語で語りかけたり」、「丁寧語にしたり」つかいわけるのですね。そこから情報を収集していきながら、だんだんと「相手」の部分が「枠組み」内で大きくなっていくことだということを説明しました。
教え方の歴史的変遷
1 コメニウスからデューイまで(学習観の違い)
2 一斉教授のはじまり
3 「教育」から「学習」へ
1、コメニウスからデューイまで(学習観の違い)
①コメニウス(Comenius, J.A. 1592-1670)
教授学を構想した人物でラテン語を教える教科書として『大教授学』(1632年)を著し、また世界初の絵入り本『世界図絵』(1658年)を著した。「近代教育学の父」と称される人物。幼児の自発的な発達に注目し、ようするに家庭で児童を教育するということを重視して指摘した。特に知識というか言葉の教え方にウェイトを置いた。やさしいものから難しいものへと学ぶ(理解の)順序を考えた。とにかく人間にとって「教育」の必要性を説いた人。授業の進め方として自然界でいうところの「太陽」のように全生徒に同時に教授することを説いた。ベルやランカスターによって助教法として各国に広まったものもこの影響を受けている。
②ルソー(Rousseau, J.J. 1712-1778)
ルソーは『社会契約論』を著してフランス革命に影響を与えた人物で、教育論としても『エミール』(1762年)を著して近代教育史上に大きな足跡を残している。自然主義、子どもの自発性、内発性、主体性を尊重するという「児童中心主義」の教育観を展開していた。「消極的教育」といって、教え込まない教育、自然な教育を標榜していたが、革命論と同じく、当時の教育に対する反発から出たものでもあった。当時、フランスでは暗記重視の教育だった。それを批判して自然主義的な教育を主張した。『エミール』の内容は家庭教師による個人教育と発達・成長について書かれている。小説で教育論を展開し、大きく影響を及ぼした人物である。
③ペスタロッチ(Pestalozzi, J.H. 1746-1827)
ペスタロッチは実際に学校を経営して教育の方法を研究した人物である。直観主義の教育方法(メトーデ)を確立した。「直観」とは直接モノを観て教えるという実物主義の考えで、「数・形・語」を教えた。例えば果実でその数、形体、名称や性質を教える。基礎陶冶を重視して、その上で開発主義の問答法で認識をすすめていくのであった。
|
|
|
|
④フレーベル(Fröbel, F.W.A. 1782-1852)
上のペスタロッチの学校で学んで幼児教育で実践した人物。幼稚園(Kindergarten)の創始者であり、英語圏でもキンダーガーテンというように、彼がつくった名称がのこっている。子どもの自己活動を重視して、児童の遊戯の教育的意義を指摘した。遊具(恩物)を考案して幼児期の教育のあり方を提唱した人物。『人間の教育』(1826年)を著した。
⑤ヘルバルト(Herbart, J.F. 1776-1841)
ヘルバルトもペスタロッチに接しているが、科学としての教育学の確立を目指して活躍した人である。学校教育の基礎を構築したともいえる。四段階の理論として「明瞭」(個別の知覚)・「連合」(表象の連合)・「系統」(多数のものの関係・秩序)・「方法」(応用)を掲げた。のちに弟子たちによるヘルバルト学派によって五段階(予備・提示・比較・総括・応用)に変えられ世界中に伝わるが形式的な段階説となってしまったという点もある。
⑥ジョン・デューイ(Dewey, John 1859-1952)
アメリカのシカゴ大学における実験学校で自らの哲学思想(実用主義・プラグマティズム)に基づく経験主義的授業研究(実験主義)を行ない、「社会」と人間の成長・学校との関係を説いた。著書『学校と社会』『民主主義と教育』等とその基礎理論「経験主義」「問題解決学習」「児童中心主義」等が20世紀新教育運動の中心的理論となった。「子どもが中心・太陽」であり、学習者の経験・周囲のことから出発・組織していくのが授業ということになる。作業等をとりいれたのも特長。
→→キルパトリック(Kilpatrick, William H. 1871-1965)
デューイから指導を受け、「プロジェクト・メソッド」を開発。子どもに発見・計画させ、その解決作業を通して知識・経験を得させようとするもの。
→→1920年代以降、「能力別学習」「個別学習」(生徒の能力・個性差、自主性を尊重するシステム)が流行。ウォッシュバーン(Washburne,Carleton W. 1889-1968)の「ウィネトカ・システム」、パーカースト(Parkhurst, Helen 1887-1973)の「ダルトン・プラン」、モンテッソーリ(Montessori, Maria 1870-1952)の「モンテッソーリ・メソッド」。日本でも大正自由教育として沢柳政太郎の成城小学校での実験(1917年)、及川平治(明石女子師範附属小学校)の各科分断の方法、木下竹次(奈良女子高等師範附属小学校)の合科教授、小原国芳の玉川学園の教育、羽仁もと子の自由学園などがあった。
2、一斉教授のはじまり(日本での教育の実際)
・・・日本の初期の(最初の)授業はどのようなものであったのか?
(1) 坪井の回想...「学科授業法は勿論、何でも洋風に机と腰掛で授業をするのでなければいけないといふので、わざわざ昌平校の畳を剥がして、穴だらけになった板の間を教場に用ゐた(略)」(坪井玄道「創業時代の師範教育」国民教育奨励会編纂『教育五十年史』民友社 1923年 p.18 )
(2) 辻の回想...「先づ教場は総て板の間にして机と腰掛を置いて、それからスコットの命ずる通りの黒板をこしらへ、それから教師が教鞭を持...(中略).此方の流儀でなく、彼の国の事をそっくり取ってやる...」 また掛図については「製へ方でも又大きさでも文字の大きさに至るまで彼の式の通り」にする。
(辻 新次「師範学校の創立」茗渓会『教育』第344 号 p.28-29)
(3) スコット自身「“Yet the manner and matter were all changed. Text books were either made , or translated by competent men into Japanese.
These books were made into a graded series, as with us; also chart and forms of all kinds for primary schools. They have substituted our system of figures for theirs in all their schools." 」と語っている。 (Scott,M.M. “Education in Japan," The Hawaiian Monthly, Nov.1884,)
(4) 高嶺秀夫も、「学力優等のものを選びて助教(後に上等生と云ふ)とし、其の餘を 師範学校付小学生徒とし(後に下等生と云ふ)、教師は先上等生を以て仮に小学生徒と見做し、一切外国の小学科を授けて其の授業法を会得せしめ」て,上級生はこれを下級生に試みるという方法であったと述べている。(高嶺秀夫先生記念事業会『高嶺秀夫先生伝』培風館 p.66 )
(5) 一斉教授における初期の形態・教育方法=助教法(モニトリアルシステム)
「助教法」・・・ベルとランカスターの広めた方法。モニトリアル・システムmonitorial system。
自九字至十字・・・教師二十五人ノ助教ヲ教授ス
自十字至十一字・・・助教生徒ヲ教授ス
自十一字至十二字・・・助教朝朝教授ヲ受タル所ノ者ヲ筆記ス (以下、繰り返し)
「教官教育所ノ定律」に記された「稽古所」
|
|
||||||||||
3、「教育」から「学習」へ
あくまでも単純にいえば、コメニウスからデューイへの流れは、<「教育」の達成>から、生徒主体の<「学習」の主張>へともみてとれる。
|
|
左はコメニウスでも示唆された「助教法」の教室の授業。右はデューイの方法でもあった児童中心主義の授業方法。 |
|
|
*資料・・・『小学授業必携』『小学教師必携』『小学読本』巻ノ五、なども
※参考資料・図書・・・(略)