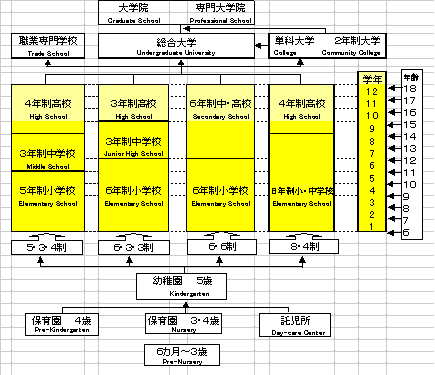教育学概論⑦(2002年11月25日) -日本と米国との比較-
アメリカ合衆国の教育システム
|
|
米国の学校教育制度
|
|
(1)教育行政、制度、システム
〇義務教育と就学制度(学校制度)
(※概略のみ記す)米国では義務教育期間を学年ではなく年齢で定めている。州により期間は異なるが、多くは6~7歳から始まる。日本では一律に<小学校-中学校-高等学校>と続くが(6・3.3制)、米国では高校までの12年間を分割する様々なパターンの就学制度がある。6・6制、8・4制等があり、各学校の呼称も様々である。そのため、「学年」は小学校1年から高校3年にあたる12年間を通しで「1年生(First
Grade)、2年生(Second Grade)」と数えていく。日本のように年齢による学年規定がないのも特徴であり、能力や成熟度を考慮して学年を決めることもある。ちなみに高校は「準義務教育」ととらえられている。
(2)教育精神
〇歴史的背景
1600年代、アメリカ東海岸に移り住んで来た人々は、「聖書を読むことはキリスト教徒の義務である」と、教育の必要性を唱えた。この考えに基づき、47年マサチューセッツ州では公教育を法律に定めた。しかしながら、依然として一般的には子どもの教育は重要視されず、裕福な家庭の子どものみが私塾に通ったり、家庭教師をつけるなどして教育が施されていた。
1800年代に入り、産業革命が起り始めると、経済を推進させる、より生産的で創造力豊かな労働人口を生み出すための教育を要求する動きが活発になる。南北戦争後には民主主義の発展とともに、教育は社会に欠くことのできない要素と人々が認識し始めた。
〇教育信条
自力で生活を築き上げてきた移民の国、米国では、教育の向上はコミュニティーによるという考えが根底にある。-「公教育は無料でなければならない」「公教育はすべての人に平等で万人に開かれていなければならない」「公教育はいかなる宗教、信条からも自由でなければならない」「公立学校の運営は、学校の所在する州政府、及び地方政府に委ねられなければならない」「保護者は学齢期の子どもに義務教育をうけさせなければならない」「学校教育は単に基礎教育にとどまらず、子どもたちの心身の成長を助け、1人ひとりの能力を最大限に伸ばせる場でなければならない」-
〇教育改革
■1960年代・・・ベトナム戦争や人種問題などの社会背景のもと、国内では校内暴力や非行、生徒の学力低下が問題視された。そこで従来の学問中心の効率重視教育から、人間的な教育を取り戻そうとする「Humanizing Schools / Education」という動きが起り始めた。生徒の適性・能力・関心を最大限に生かすことを強調し、生徒が自由に選べる選択科目を増加する等の対策をとった。しかし、現実には多くの科目が知識の修得に重点を置かないものとなり、カリキュラムは均質化され、目的がはっきりしなくなった。この運動は中退(Drop Out)を減少させることはできたが、学力低下を食い止めることはできなかった。
■1970年代・・・70年代中頃には、60年代の運動の反省として、新たな動き「Back to the Basics」が起こった。読・書・算を基本とする基礎学力の修得が学校教育に必要不可欠であると強調され、また規律重視の伝統的かつ厳格な教育が見直されてきた。
■1980年代・・・1980年4月4日、「国家をあげて教育の機会平等を確実にし、優れた教育を促進すること」を使命に、アメリカ教育省(U.S.Department of Education)が設立された。2000年までに達成したい10の教育目標(National Education Goals)には、高校卒業率を少なくとも90%に増加すること、数学・科学の教育を強化すること、学校への薬物・暴力・銃・アルコール類の所持をなくし、学習指導のしやすい規律ある環境を提供すること、等が含まれている。
■1990年代・・・政府の教育に対する動きとして、基礎学力の向上、中退率の減少、教育環境の良質化などの他、具体的には、経済的に恵まれない家庭の幼児を対象とする補償教育を目的とした「ヘッドスタート計画」(Head Start Plan)があった。高校レベル重視から幼児教育-就学準備教育の改善にシフトするものであった。1989年「教育サミット」開催や、91年に21世紀の全国的共通教育目標を掲げるなどをした。クリントン政権下、教育機関へのインターネット普及が進められたのも、居住区に左右されない均等レベルの教育の提供、教育対象児童の拡大等の促進をめざしたものである。
■現在・・・実際にはリーディング能力に問題をもつ児童も多い。ブッシュの教育改革「No Child Left Behind」には、教育者のレベル向上、英語を母国語としない生徒の英語力の強化、教育現場の安全性の確立、両親に対する情報提供の推進等が含まれている。政府が定める教育方針達成に貢献した所は評価し、報酬を与え、そうでない所には何らかの処置をとるなどの政策もあげられている。
(3)授業、学校生活
〇授業形態
各教師がそれぞれ教室を持ち、生徒がそこへ移動して授業を受ける(日本と反対)。1クラスの生徒数が40名の日本に比べ、米国では20~30名。生徒たちの授業を受けるスタイルも異なり、米国では授業中に率先して自分の意見を述べることが大切とされている。発表や床に座ってのアクティビティーなどの光景もよく目にする。参加(Class
Participation)という積極的姿勢を大切にしている。なお出席は男女混合のアルファベット順に呼ばれる。
通常「1時間」(One Period)は50分。授業間の休み時間はたいてい5分間。また生徒が教室の掃除をすることはない。さらに「始業式」などはなく、初日から授業がスタートする。
〇クラス編成
多くの学校で能力別のクラス編成が行なわれている。他人との比較によって評価するのでなく、各個人の進歩に重点が置かれているため、一斉授業の他に「英才教育」や「障害児のためのクラス」のような特別クラスが設けられている。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇学期
9月に始まり、6月中頃に終了する。始まりの日や休暇などは学校区が定める。連邦法定休日や各学校の方針による祝日の他、クリスマス・ホリデーの冬休み、イースターの時期の春休みがそれぞれ1週間から10日間ほどある。学年終了後に2カ月半の夏休みとなり、生徒が学校で過ごす日数は年間平均180日である(日本は243日)。
〇教科書
日本のように簡潔に要点のみをまとめた教科書と違い、大きく、厚く、重い。これらすべての教科書は学校から貸し出されるものであり、公共備品扱いとして制約がある。各教科書には生徒の氏名や賃貸年月日等が記録できるようになっており、破損、紛失の場合、罰金や代金支払いの対象となる。学校によっては古い教科書を販売している所もある。
公立学校では、学校区(School District)内に居住する学齢期(School Age:1~12年生)児童に対する教育を無料で施し、教科書、スクールバス、ヘルス、ソーシャルサービスも無料で提供している。通常、高校まで無試験で進学できるが、能力別クラス編成を多くの学校でとりいれている。もちろん地域によっては学校区と無関係に試験選抜を行なう特殊な学校もある。
中央政府が絶対的権利をもつ日本の教育システムと異なり、米国では地方行政(州や学校区)による運営であるため(連邦政府が教育政策を統括する権限をもたない)、教育水準、プログラムの種類、内容、施設などに大きな格差がある。連邦政府の教育庁は、基本的な教育方針を決定したり、財政援助を行なう機関である。その方針をもとに、州教育委員会(Board of Education)がガイドラインを設定し、さらに教育局(大都市を統括)や郡教育庁(中・小都市を管轄)によって基本指針が定められる。学校区はそれらをもとに、発展させ、実施する役割をもつ。「学校区」は「教育委員会」(住民から選出、政策を担当する-法規や教育長の任命、教職員の採用など)と「学校局」(区内の教育活動実際に運営する-予算、人事、教育計画、総務など)からなる。
(米国の校長先生の書簡-略=9.11テロ事件当日の学校側の対応が示されている)