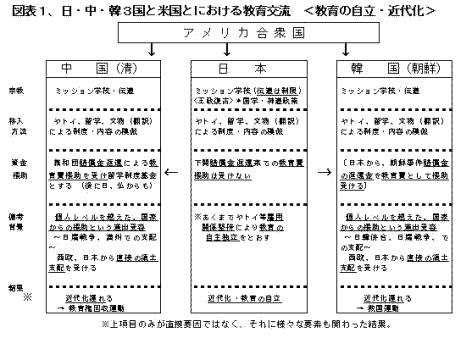教育学概論Ⅱ⑥(11月18日) <世界システム>としての「教育」(続)
|
<前回>・・・<世界システム>としての「教育」 ★-しかし、システムが安定させている社会が誰かにとって不平等なものだったらどうだろう? それを「安定させている」のも「システム」なのだとしたら? ★★-英国は身分・階級社会を再生産するようなシステムであった。日本も教育改革によって家系などにより不満をもたない子どもが育つということが数値に表れている。階層が分化され不平等にさえ気づかない。米国内でも学力差は大問題となっている。 ★★★-「世界」もこのような仕組みになっていることはないか? 天野郁夫によれば、日本は<世界システム>内の「辺境」という位置から「中心」という位置へ、上昇したという。米国やドイツという新興国家をモデルにしてかけあがった。・・・しかし、それでも米国が中心であり、日本は実際には二番手以下なのではないか? 初等教育や中等教育での学力や国家の経済力でたしかに日本は向上したが、「教育」ではまだ米国らには及ばないのではないか? いや、学力や国家の産業で並んでいることの評価すら、<世界システム>という枠組みにおいては考慮されないのではないか。留学生の志向をみれば明確である。そして米国に「知」が集中し、「中心」を占め続ける。このような「関係」を--<世界システム>的関係という。 |
1、日本の近代化は米国化であったという一面?(初期の教育交流)
|
|
★視点として、次のことに注目してほしい。「世界システム」という関係性があり、序列なり国際関係・国家間の関係があるのだとして、前回のように「日本が『中核』国家の仲間入りをした」のだとすると、なぜ日本がシステム内の「中心」国家に入れたのか? もちろん「先進国になった」「近代化された」などということと「世界システムの『中核・中心』」とは別に考えるべきかもしれないが、とりあえず前回の天野氏の考察に従うならば日本は「中心」になったと。ではその「中心」とは何か? これを考える必要があるだろう。もしも「周辺」に対して「進んでいる状況」、つまり「従属する国家をもつこと」をその本質だとするのなら、日本は「従属すること」から逃れて「従属させる立場」になったともいえるのだろうか? そういう国家間の関係をいままで授業で扱ってきた方法をつかって、例えば比較してみていきたい。「自立」して従属から逃れ、他国を従属させるというのを「発展」過程とするのならば、日本はどうであったのか。ここで「比較」の対象として、同じく東アジアに位置し、同じ時期に「中心」国によって「世界システム」内にとりこまれていった「清(中国)」「朝鮮(韓国)」「日本」の三国を比べていきたい。当然この授業では「教育」について比較していく。従来は「法律」「政治」「経済」「外交」といったもので論じられるべきものとも思えるが、実は「教育」が重要な役割を果たしていたと思っている。特に「宗教」「援助」のもつ意味に注目してもらいたい。なぜほぼ同じ時期に開国した日本のみが比較して急速に「近代化」なり「中核化」なりが可能であったのか。
(以下、内容は概説する-ホームページ上では概略のみとする)
●米国との関係での、海外からの影響の受け方、情報の入り方
→「宣教師」が先兵的に入ってきた。彼らは伝道のために海外に出る。宣教師の持ち込む情報や近代科学にニーズが集まり、学校・塾が建てられた。しかし日本のみ「伝道」に制限があった。高札は撤廃したが、事実上の制限があった。廃仏毀釈までおこす当時の王政復古・国学の興隆と無関係ではないだろう。
●移入の方法
→「ヤトイ(お雇い外国人教師)」「海外留学」「翻訳」という三つの方法は三国に共通している。すると、ここまでの比較だと単純に「キリスト教」布教に関係するということになるが、事態はもう少し複雑にとらえていくべきである。
●「資金援助」への注目
→1900年義和団事件の賠償金返還による対中国への米国留学受け入れ政策の資料を読むと、他の先進国と米国との違いがみえる。日本へも1863年下関戦争の賠償金返還による同様の政策を考えもちかけたが、これは日本により却下された。この「賠償金」というものを「資金」にして「該当地」の教育を援助する(というよりも米国に受け入れる)というのは、次代のエリートを親米家として養成するという策ではなかったか(ルーズベルトの資料に書いてある)。なお、日本も1882年朝鮮事件の際に得た賠償金を返還して同様の策を朝鮮にもちかけている。これは「日本」が米国に学び、そしてその本質を理解していたからこそ自らは断り、そして他国に応用したのではないか。(資料略)
●結果
→日本は急速に「強国」化した。まず国家として独立を保つことができた。国家の政治・経済・法律を自主のものとして保つことができた。「国民」をもつことができた。このことは大きい。例えば「中国」のナショナリズムの興隆として「教育権回収運動」があるが、これは排日運動とか以上に海外の宗派立学校を中国のものとしていくという運動でもあった。韓国の「救国運動」も同様の面をもつ。つまり「国家」主体による「国民」づくりができるかどうかが、実は「近代」にとっては重要な問題なのである。また、例えば、中国の最初の近代学校制度は日本の「学制」の翻訳版であった。朝鮮の近代教育令も日本の「教育令」の移入でもあった。このように初期の国家指導者が日本へ留学した経験は無視できない。日本が「教育者」であった一面である。前回の天野氏の説でいうと、あのころ「米国」が日本にとって「教育者」であったというのを学んだがそれと同じことである。また、日本の最初の近代学校制度「学制」はそもそも西洋諸国の教育制度の翻訳版であった。教育内容は米国中心というのも学んだ。すると、「西洋・米国(世界システム)→日本→中国・朝鮮」という情報の伝達と発展の順序がみえてくる。「位階」は教育によってつくられるということも国家的にもあてはまるのではないか。
2、日本が独自性を保持できた理由
次に、その「独自性」を大事だとしても、結果論ではなくて本当に当時の「日本」が考えて意識していたのかというのを資料から考えておきたい。これは「日本人」が偉大であったということを単純に言いたいのではなくて、「どういう受け取り方をしたのか」というのを冷静にみておくというのが目的である。従来の歴史研究の記述では、多くは「日本には近世に先見性があった」と称賛されることが多いが、そういう日本人が具体的にどのように外交なり教育なりを考えていたのかを比較的に詳しい資料からみておきたい。
通説の概略のみホームページには載せる。
(通説1)「近世」社会における教育の充実があった?
●幕臣の教育・・・昌平坂学問所(最高学府)、蕃書調所、和学講談所
●各藩の教育・・・藩校(藩士の育成)--儒学・習字から実学へ、郷学(地方)
●庶民の教育機関・・・寺子屋(丁稚奉公、弟子、女中奉公)、郷学
(仮説1)最初から独立を意識していた? 近代化当初、「維新」期の教育の性質(文部省設置以前の学校構想)
●(概略のみ)1870 (明治3)年 「大学規則」は文部省設置以前の大学構想であるが、5つの学科が構想されていた。「教科」「法科」「理科」「医科」「文科」。一見して洋風だとわかる。「教科」に神教学などがあるからミッション学校の影響であろう。理系の「理科」「医科」は南・東校の領域で外国情報中心。他の「教科」「法科」「文科」には「教科書」という教育内容が示されていた。略述すると「古事記」「日本紀」「万葉集」や「宣命」「祝詞」、「論語」「大學」などや「令」「残律」「延喜式」「三代格」、「大日本史」「枕草子」「源氏物語」「史記」「前後漢書」などで、つまりはぜんぜん「洋風」でも「国際的な法律」でもなかった。「国学」系の古典、「復古精神」のつまったものであった。「器は洋風で、中身は復古」「外見は西洋を模しても、内実の精神は天皇制(王制)復古」というのはまさに「和魂洋才」と称されるものであり、維新期の特徴であろう。これが日本の受け入れ方の特徴として効果を及ぼしたのではないか。
(仮説2)日本は「拝外」から「排外」を意識していたか?
●本当に「自立」を意識して外国と対峙していたのか。次の資料をみてほしい。
|
『公文録』「大学伺(庚午9月~閏10月)」 |
→いわゆる「外国学問」とされ教科書もなかった「医学」でも下線部のように「独立」のためには外国人の
教授に頼ることないシステムが必要と「このとき」には意識されていたのである。次の資料は「理科」である。
|
「南校専門生徒留学并教官為質問洋行之儀申立」(文書、三十六)の一つめの文書 |
(仮説3)「学制」(明治5年)にもあらわれている?
●「学制」の原案に付された文書「後来ノ目的ヲ期シ当今着手之順序」には、「小学に力を注ぐこと」、「その小学の教師を養成すること」、「小学では男女共学」というように小学教育が重要とされていたが、その最後に「反譯ノ事業ヲ急ニスル事」として「人ヲ率ヒテ學ニ就カシム悉ク洋語ヲ以テ之ヲ教ユヘカラス反譯ノ業亦尤急ナルモノトス」とあった。翻訳して自国の文字や言葉で教えられるということを政策過程で意識していたことがあらわれている。
3 世界システム?
<世界システム>の手段
|
|
→「自国らしさ」の保持=「他国」の抑制でもある?
※「教育」は「社会生産装置」-国内でも、国際社会においても・・・。
・・・「拝外」「排外」というのはいささか誇張した表現ではあるが、私は「日米教育史」を研究してきて、その中でいわゆる「米国の影響が強い時期」といわれる時期の存在理由について興味をもっている。そもそも通史では例えば明治初期の「学制」制定前後にはオランダの影響であるとか、あるいはフランスの影響が強くみられるとかの研究成果が公表されてきていて、それは個々の研究者が何らかの資料を発見・紹介したり、比較したりしながらそう論じているのだが、私は「小学教則」というカリキュラムの普及や「授業」の方法・形態については「アメリカ合衆国」の影響が大きくみられると考えている。もちろん翻訳書や輸入元など幕末よりのつきあいならオランダ、あるいは民法ならフランスというように、セクショナリズム的ではあるがそういう影響はみられたであろうし、さらには後に「ドイツ」の影響が強くなるなどと分析される時期もあるわけである。私は日本と米国との「関係」に興味をもっているのだが、明治期の教育は「米国オンリー」とは思ってはいないし発言してきたこともない。ただし、なぜ米国ではなくドイツ優勢になったのか、あるいはその時に背景や教育は変わっていったのか、またあるいはその後いつまで「欧米」の影響を受けて、それが変わることがなかったのかそれとも変わったのかということには興味をもっている。どこかの国だけでなく、そういう「拝外」ともいうべきものからもしも日本独自の「排外」というものにシフトしていったのだとしたら、それはどういう流れでいかなる性格のものなのかというのに興味をもっている。
結論を簡単にいうと、ただ日本のみならず相手側の思惑や対応の距離感も関係すると考える。その点で米国は実質的な距離も近く、さらに軍事的にも物資的にも限界があり、またプロテスタント伝道の活動もあって「教育」や「文化」的交渉が尊重されやすかったのである。もちろん米国内の世論などの問題もある。そして受け入れ側日本は中国(清)や韓国(朝鮮)と違ってキリスト教を排除してなるべく「自治・自立」というものを意識していた(流れではなく当初からその意識があった)と考えているのである。それは「富国強兵」なりのスローガンにも表れてはいるのだろうが、そういうレベルではなくて、もっと具体的に「教育の体外交渉」の中に表れているのではないかと仮説をもっている。
さて、本日の資料の一つのこの文書はもちろん「医学校」の留学生の話しであり、日本の教育政策すべてに言及しているのではないが、それでも当時の学問(洋学普及の実態)の状況を考えれば、この「お雇い教師」から「留学生帰国」へのシフトチェンジを「自前(独立)」と考えていたというのは注目されていいのではないかと思う。もちろん従来も「翻訳」から「お雇い外国人」、そして「留学生」という点での導入の過程については指摘されてはいるが、この対外関係においてその当初からわりと明確な「意図」(意志)があったというのはその後の「近代化」過程とあわせて、そして他国と比較しながらとらえなおしてみる価値があるのではないだろうか。
他にもいくつかの応答・伺の文書が収録されているが「留学」が「専門教師」の雇い入れに比べても有効なもの(現地で学ぶ)ということであったことがいくつか記載されている。もちろん「直接に学んだ方が雇い教師に勝る」とか「外国からの影響を最小限に抑える(干渉を防ぐ)」などとは書いていないのだが、日本の対外教育交渉の態度が表れているのではないかと考えている。(この問題についてもまた考えていきたい)