教育学概論Ⅱ⑤(2002年11月11日)
<世界システム>としての「教育」
|
本日の講義の内容 |
(5)「世界システム」論という考え方
「社会」には何らかの取り決めやルールがあるわけで、それにより「安定」していると考えられますし、これまで「教育」がそういうものを身につけさせる、あるいは再生産するという「役割」を果たしていたということをいくつかみてきました。あるいはそういう「仕組み」になっていたということですね。日本には日本の教育が、「イギリス(いわゆる「イギリス」)」には「イギリス」の教育があって、そこで日本人なりイギリス人が育成され、それによって国家が形成され安定させられていく。これはたいしたことをいっているのではないごく普通のことなのかもしれません。そういう「仕組み」を「システム」といってきたのですが、今日は「世界」にも(「各国家」ではなく「国家間」において)そういう「システム」関係があるという考え方を試してみます。「世界」も安定しているし、共存がいちおう保障されているし、各国間での行き来、例えば教育ならば「留学」がある。そして私たちは「比較」して物事を考えたように、あるいは「教育改革」の時に他国での実践や方法論が参考にされるように「世界」を意識しないで「国内」で教育が行なわれているというわけではないのです。むしろ「制約」というのであれば教科書記述の問題でもなんでも「国際的」な問題ともなっている。例えば欧州諸国では「ヨーロッパの歴史」などの新しい枠組みも出てきているし、これはアジアでも必要ではないかとの意見が出ることもある。何がいいたいかといえば「世界」や「他国」の影響というのは「教育」についてもみられるということです。するとそれは「世界システム」とでもいうべき、一つの大きいシステム(秩序維持、あるいは権威的位階)があるのではないか、その中で一国のシステムは影響を受けて変わることもあるのではないかとも考えられるわけです。例えば以前に「教育改革」についてみたときに、1980年代に欧米諸国・日本で共通して改革が起きている。これは明らかに「世界」規模の影響関係にあるといえないでしょうか。
このような「広い」範囲でシステムという考え方をしていくものを「世界システム論」といいます。経済学や社会学、歴史学の方法・理論であって「教育学」のためにつくられたものではないのですが、そういうものも「社会」を理解するためにとりいれていきたいと思っています。後半に紹介するように日本でも採用している教育学の研究者はいます。なお、「一般システム理論」「スクールシステム論」など、他の「システム」論もあって、それぞれ現代思想や学校制度化を理解するためのものですが、そういう「システム」という「関係」は注目されていると思います。注目すべきものとも思っています。「グローバル化された世界」などという時代ですから、今後「世界システム」が重要な視点となるでしょうし、実際には米国の比較教育学の研究紀要・雑誌類をみるともう1980年代ぐらいからとりいれられているのですね。その意味では日本の研究レベルが遅れているのだと反省しています。
●導入-<世界システム>論という考え方-
まずは「教育」には関係しない部分から説明していきます。前回の最後に皆さんに「日本独特の料理とは何か?」ということをきいたところ、寿司、刺身、煮物、納豆、天ぷら、豆腐、そば、味噌汁、などの意見が多くありました。普通、こういうものがイメージされますね。しかし、買い物で店に行って表示されているラベルシールをみればわかるのですが、「それら日本文化と思われる料理の食材」はほとんどが「輸入品」であることがわかります。小・中学校などでの「総合的な学習の時間」などでも「料理」という体験から「国際理解」へと広めていくという点でこういうネタが使われていることが多いのですが、例えばマグロは日本近海のものが多いのでしょうか? 水揚げ漁港名がシールに示される例もありますが、オーストラリアや地中海などで漁獲されるものが多いのですね。天ぷらのエビもほとんどが外国からの養殖エビの輸入。ころもの小麦粉も同じく輸入されているものが多いのです。そば粉も同じです。そうではないものがテレビで放送されますが、それは「価値がある」つまり「少ない」ということの証明でしょう。限定品ですね。特選素材とか「幻」などという野菜や魚、肉も同じです。少なくて高級である。だから輸入品にたよるのですね。焼き魚としてサケを食べようと思ったらチリ産もあるし、煮物の野菜はいまは中国野菜が多く輸入されているのをみれます。納豆、豆腐、味噌汁は「大豆」からつくられるものです。湯葉、豆乳、油揚げもそうなのですが、「大豆」も加工品はほとんど輸入ですよ。もちろん「国産大豆100%」ということわりの表示もある。逆にそうでないものが存在するという証拠ですね。ちなみに「枝豆」も大豆ですが、国内で生産しているのはほとんどがその形態だと思います。加工品なら輸入にして多量に買った方が安価です。「安価」「コスト」というのは「経済学」の考え方ですね。
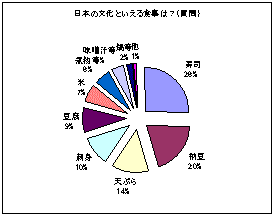 ここでいいたかったことは、日本の中にも「世界」中のものが入ってきているし、日本は世界との依存関係なしにはいられないということです。世界と無関係ではないのです。
ここでいいたかったことは、日本の中にも「世界」中のものが入ってきているし、日本は世界との依存関係なしにはいられないということです。世界と無関係ではないのです。
次のグラフは「自給率」、つまり国民全員一年間分の食料を国家が何%満たしているのかというものを示していますが、日本は低いですね。ほとんど中国からの輸入というのが多いのですが、もし中国と仲が悪くなって輸入できなくなったらどうなるのでしょうか。もちろん飢えるというより、他国から買うことになります。でも安いし輸入しやすいから中国から買っているのだとしたら、それよりも不利な条件で買うことになることもありますかね。すると財政・経済の負担が増すことにもなるのでしょう。北米大陸はすごく自給率が高いですね。フランス、ドイツの欧州もかなり高い数値です。日本は1997年に41%、さらにグラフ内に「*」を付しましたが1998年には39%と落ち込んでいるのです。もちろん食料以外も輸出入の関係は世界中であります。「買ってることの何が悪い」という考え方もあるでしょうか。ここでは「依存関係」を示したのみです。
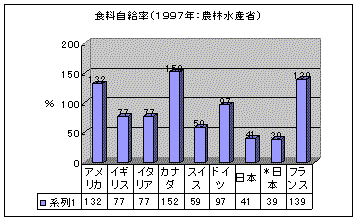 しかし次のように考えていったらどうでしょうか。日本人が何かを食べるために輸入する。安く買ってくる。これはたしかに「自由」です。なにしろ「自由貿易」という名があります。しかし「資源」は有限という考え方もある。「環境破壊」というものと同じレベルで考えてもいい。よくいわれるように日本では食料や残飯などを捨ててしまっているけど、世界には飢餓に苦しんでいる人々もいる。そこを「日本人が悪い」などと直結はしません。しかし、そういう「持てる国と持たざる国」とがある。例えば熱エネルギー資源も買っていますね。料理のため、暖房のためなど。石油、天然ガス。それらも有限です。それを大量に消費することが危惧されてもいます。減らす手段も考えられてはいますが、しかし暖房をつかえる人とそうではない世界の人々もいる。そういう「持てる国と持たざる国」とがある。日本の出版業界は落ち込んでいるといわれていますが、例えば「印刷」して本をつくるときに、昔なら東京の北区や長野県、あるいは関西の印刷工場に持っていって、大量印刷していましたが、例えば今なら国外に運んでつくった方が安いという考え方もありえますね。ある国に持っていって、それで印刷・製本させて、それを搬入する。その国でやった方が人件費を安くできたりします。例えば日本人に20万円支払うべきところを2万円ですませられる。コスト削減です。これも「何が悪いのだ」「それで相手は生活できるのだろう」という考え方もありますね。そのとおりです。しかし、同じ仕事なのに賃金は10分の1です。「良心」の問題を言っているのではないです。そうではなくて、彼らは「そこ」にいるかぎり、おそらくずっと10分の1の賃金で仕事を与えられるのだといいたかったのです。「地域格差」と簡単に言ってもいいのですが、「使ってやってる」なんて思うのでしょうか。国費で現地の人を安くたくさん使用人として雇って「貴族的」暮らしに満足してしまっている「外国つとめ」の人々のように・・・。それが「外交」だとしたら見下しているように判断力が鈍らないように期待したいですね。また難しいでしょうけど、ようするにそういう「持てる国と持たざる国」とがあるのですね。「持たざる国」はそのまま「待たざる国」の方がお互いに幸せなんでしょうかねぇ。彼らが「持てる国」になるチャンスってどのくらいあって、またそれを周囲は「援助」でもしているのでしょうかねぇ。
しかし次のように考えていったらどうでしょうか。日本人が何かを食べるために輸入する。安く買ってくる。これはたしかに「自由」です。なにしろ「自由貿易」という名があります。しかし「資源」は有限という考え方もある。「環境破壊」というものと同じレベルで考えてもいい。よくいわれるように日本では食料や残飯などを捨ててしまっているけど、世界には飢餓に苦しんでいる人々もいる。そこを「日本人が悪い」などと直結はしません。しかし、そういう「持てる国と持たざる国」とがある。例えば熱エネルギー資源も買っていますね。料理のため、暖房のためなど。石油、天然ガス。それらも有限です。それを大量に消費することが危惧されてもいます。減らす手段も考えられてはいますが、しかし暖房をつかえる人とそうではない世界の人々もいる。そういう「持てる国と持たざる国」とがある。日本の出版業界は落ち込んでいるといわれていますが、例えば「印刷」して本をつくるときに、昔なら東京の北区や長野県、あるいは関西の印刷工場に持っていって、大量印刷していましたが、例えば今なら国外に運んでつくった方が安いという考え方もありえますね。ある国に持っていって、それで印刷・製本させて、それを搬入する。その国でやった方が人件費を安くできたりします。例えば日本人に20万円支払うべきところを2万円ですませられる。コスト削減です。これも「何が悪いのだ」「それで相手は生活できるのだろう」という考え方もありますね。そのとおりです。しかし、同じ仕事なのに賃金は10分の1です。「良心」の問題を言っているのではないです。そうではなくて、彼らは「そこ」にいるかぎり、おそらくずっと10分の1の賃金で仕事を与えられるのだといいたかったのです。「地域格差」と簡単に言ってもいいのですが、「使ってやってる」なんて思うのでしょうか。国費で現地の人を安くたくさん使用人として雇って「貴族的」暮らしに満足してしまっている「外国つとめ」の人々のように・・・。それが「外交」だとしたら見下しているように判断力が鈍らないように期待したいですね。また難しいでしょうけど、ようするにそういう「持てる国と持たざる国」とがあるのですね。「持たざる国」はそのまま「待たざる国」の方がお互いに幸せなんでしょうかねぇ。彼らが「持てる国」になるチャンスってどのくらいあって、またそれを周囲は「援助」でもしているのでしょうかねぇ。
この「持てる国と持たざる国」というのは、実は「世界システム」とでもいうものではないか。あるいは「世界システム」でそういうような序列や関係が「安定」(再生産)させられているのではないか。そういうことを考えたのが、ウォーラーステインの<世界システム>論です。私たちはどうしてもそういうことを「進んでいる国」と「遅れている国」というように考える。あるいは「先進国」と「後進国」という考え方ですね。「低開発」「未開発」などともいうわけです。昨今の外交関係の税金迂回システムの不正疑惑(アフリカ・ソンドミリュウダムなど)なども「後発展国」の「開発援助」という考えのものでしたね。「南北問題」という貧困の格差の問題もある。
ウォーラーステインは、こういうものの認識が正しくないと言っているのです。こういう「関係」が「世界システム」としてつくられてしまったと指摘しています。まず「後進国」といういいかたは、それだけで「その国が遅れている」から悪い、だから援助してやるという考え方が表れています。そうではなくて、実は「先進国」とよばれる国によって、「後進国」という国がつくられてしまった、あるいは「後進国」として発展させられたといえるという考え方です。「先進国」「後進国」とよばずに彼は「中心(中核)」と「辺境(周辺)」というよびかたをしていますが、「中心」が栄えるためには(「中心」として位置するためには)「周辺」がその必要な作業を請け負ってくれることが必要なのです。
難しいですかね。では、考え方をかえて、例えば「イギリス」は先進国だといって、「進んでいる国」なんだというわけです。何が進んでいるのかといえば、オートメーション化された工業化の進んだ社会(科学技術の発達)で、経済も発達しているし、文化も発達しているというのです。「われわれはジェントルマンだ」(文化が発展している)というのですかね。しかし、その「工業化」はどうして進んだのでしょう。近代化の過程で「産業革命」というのがあって、工場生産が進展したのがきっかけですが、そこで「綿製品」がつくられた。それにより「いま」の発展がある。しかし、その「綿」の原材料は自国内にはなかったのです。インド地方にあったからムガール帝国を植民地化して、「綿花」を得る、さらにプランテーションの労働力やインドでの工場の労働力として現地の人間を「はたらかせる」。もちろん「雇う」といいかえてもいいのです。しかし「農奴」や「奴隷」ともいわれたのですね。さらに進んでアフリカ大陸からも「奴隷」を確保して、働かせ、またはそれすらも(奴隷売買をも)商売にした。・・・こう考えればけっこう大きな帝国で、進んで(栄えて)いた「インド地方」を「後進国」や従属国にしたのは誰なんでしょうか。少なくともそういうところからの原料と労働力があって「世界」規模の生産力を得て、それで「先進国」化したのではないでしょうか。もちろん「野蛮人にはアヘンとキリスト教の愛をくれてやる」などといった悪意はそう持っている人はいなかったとは思いますが、少なくとも「自国」だけでは「工業化」発展は不可能だったのではないでしょうか。「ジェントルマン」的生活文化もそういうものの発展・基盤の上にある。あるいは具体的な嗜好品として「茶」ですが、原料はインド地方や中国のものでしょう。それらを栽培して輸入する。そこに同じような「構造」がある。原料と労働力ですね。それを「門戸開放」で「自由な貿易」というのでしょうかね。そしてこれは日本が安く外国の人間をつかっていることとものすごく大きい差なのでしょうかね。私がいいたかったのは、「国際的な序列」はつくられてしまったものだから、グローバルや共生をいうのならばそういうことも意識しておくべきだということです。「環境を大切にしよう」というのと同じレベルのあたりまえのこと言っているだけなんですね。
以上は「教育」に直接関係しないのですが、ウォーラーステインのテキストで「教育」について書かれた部分を読んでみます。
★「教育」という「システム」を広めた「資本主義社会」(西洋文明社会)という考え方。
|
「資本主義文明がもたらした純粋に恩恵といえるものとして、教育組織を生み出し、これを世界中に広めたという事実があると。この事実は、すべての個人に自己の潜在能力をよりよく認識させ、なかには、自己の能力を顕示することで、階級の障壁を越えることのできる人もあったのだ、ともいう。普遍的な公教育という概念自体は、「資本主義的世界経済」の産物-それも、比較的最近の産物-である。在学年数の延長という意味でも、世界中の多様な集団にとって、学校教育を受ける機会がどれくらい増えたかという点からみても、教育制度は着実に発展してきた。」 |
★しかし、一方で、「教育」は人間を「平等」にしたのだろうか? という疑問もある。
|
「教育手段が増加すれば、人びとが、より高い水準のフル・タイムの仕事に就ける機会が増すといわれている。もちろん、このことは、相対的な問題としては正しい。つまり、教育年限と勤労所得のあいだには高い相関関係がある。しかし絶対水準としては、それはきわめてあやしい。教育制度の発展は、ただちに、特定の雇用に要求される教育水準をエスカレートさせる。したがって、一九九〇年には、小学校教育を受けた人物であっても、一八九〇年になら公式の教育をまったく受けたことのない人にも得られた仕事からさえ、排除されるようになったかもしれないのである。」(以上 177ページ) |
また、教育制度の発展の重要な結果として、 自分の家庭のために所得を稼がず、逆に授業料無料であっても家計にかなりの出費をかけるようになった-「人的資本」への投資-という考え方が普及していったということも、その影響として述べられています。そういう影響を次のようにまとめています(板書)。
|
(1)学齢期にあたる年齢集団全体が、家庭からも、家庭外からの職場からも、完全に奪い去られた |
|
(2)「人生の諸段階」という概念が開発され、個人の生活の現実として定着していった |
<「幼児依存」→「社会参加・労働」→「終末依存」>から、長期間を依存的な「子ども」として労働力からはずれるという、そういうライフサイクルが成立したのもこの資本主義による<世界システム>のもとでだと考えられているのですね。どこの国でも原則的に同じ=平等な一面(人間の成長が保障されている)が実現されるようになった。このようにして<世界システム>は普及していき、その中で「教育システム」も整備されていった。そしてその「教育システム」によって<世界システム>が補完されていくという関係もあったと思うのです。以上のような簡単な記述しかないのですが、そこからも、「教育」も「世界的なシステム」の一部として伝わってきたということがわかる。そして、「社会再生産」機能などをどのように考えればいけばいいのかということも、「世界システム」としてとらえなおしていくという考え方もありえると思うのです。つまりこのような「教育」が常識的で共通するものになるということは、「世界」の共通水準がつくられるということでもあり、それにより「客観的数値」という名のもとに測られていくという面もあるのではということです。そういうことを考えるのも「システム」という考え方だと思います。
前提としての話しが長くなりました。簡単に<世界システム>内の関係を記してみます(板書)。
|
|
|
|
「中心」国家側は「自由」を主張して、「門戸開放」政策のもと、あるいは「条約」を結んだり、脱退する自由というのもあるのですが、そのような「自由主義」かのような理想的な社会であると人々が感じられる生活を送っていきます。余裕もあるし、「競争」を勝ち抜いていくのだというエネルギーもあるのでしょうね。「国内世論」も支持率が安定して、理想的な国家のような気がします。そのような状態が「世界システム」内の中心という状態ではないでしょうか。他国より有利で強い立場にあって、自由で公正にみえる。しかし、「周辺」国家側は「世界システム」の中で特定の役割を強いられてしまっています。もちろん抜けるのは自由でしょうが抜けて自立するのには「国家」としての力がなくては困難です。しかし「世界システム」の中で不利な状況のままでは「国力」を充電しきれないのです。単純にいえば賃金格差があって、外国資本と競争していけません。お金がないから争えないのです。「資金源」をもっている地域は例えば「自立(独立)」をめざします。かってのグルジアやバルト三国がそうですし、チェチェンも油田埋蔵量など資源があるから、それを商売にしていく希望もあって独立をめざしている。僕はロシア系三世ですから悪口ではないのですが、ロシア側としては独立を許すと自分の「国力」が減るので絶対にさけたい。「紛争」になります。チェチェニアン(チェチェン人)はイスラム教徒が多いのです。かってのソ連時代からイスラム教徒とタタール人という民族は差別され、国内でも違う仕事・役割を押しつけられるということもありました。実は五輪王者にチェチェン系が多いというのも米国の黒人(アフリカ系)と同じような傾向をもちます。少数であったイスラム教系は特定の役割を押しつけられ、その共和国内は貧困になります。資源は豊富なのに、それが国内の特に中央(モスクワ等大都市圏)のために消費される。実際の潜在的「力」は無視されるこの構造(そういう「差別」は慣習や教育でつくられます。例えば「カリンカ」という有名な歌はある民族のためのものという限定があります)。貧困ゆえにその共和国内では規制的です。耐えしのび、秩序を保って存続しようとする。基本的に取り込まれているのですから「対外」としては(チェチェンはソ連邦に)従属的でした。しかし、それが開放され、より広い世界システムを知り、そして可能性を知った時、その時にさらに変わらぬ圧力をかけられるとやがて我慢の限界が来ます。当然、反動的になるのではないでしょうか。それが今の「紛争」です。ロシアからみれば「テロ」ですし、チェチェンからすれば「開放」(「解放」ですけどオープンという意味でそうもいえます)のための戦いとなる。・・・これはそのままアメリカ合衆国のテロ事件前後(以降、現在まで)の問題と同じではないでしょうか。北朝鮮の場合はどうでしょうか。フセイン政権も金政権も国内支持率は高く、規制的ともイメージされます。私はどこかの国をいいイメージ、悪いイメージをもってほしいとは思っていません。「考え方」を考えて欲しいというだけです。この<世界システム論>からは「世界」がこのようにも読みとれるのです。
●日本の教育システム-<世界システム>内での位置変動-
天野郁夫先生の『日本の教育システム-構造と変動』(東京大学出版会、1996年)をテキストとして、「日本の教育」を世界システムとの関わりにおいて考えてみます。天野先生は『学歴の社会史』『試験の社会史』などの面白い、かつ話題になった著書のある「教育社会学」の分野の代表的な研究者の一人でして、著書もたくさんありますので読んでおくと勉強になると思います。さっきまで述べた<世界システム論>は直接「教育」に関わるものではないので、まだ日本ではこの考え方を発表されている例が少ないのですが、この本はその中の一つです。「話の筋」としては、日本は世界システムの中に組み込まれた時に「辺境」の位置からスタートすることになったが、今では「中心」の位置にまで発展したのだと。首尾よく近代化できたということでしょうか。しかし、その中でも様々な変容があって、様々な国を手本として教育制度を模倣していったのだと。最初は米国、次にドイツ、それで戦後に米国の占領下に影響を受けて、いまでは肩を並べるまでになった、というものです。この「世界システム」「中心」「辺境」というものがとりいれられていることは注目すべきものです。少し読んでみましょう。
|
1 教育の日米関係 |
はじめは「アメリカ」をモデルにしたという部分でした。しかし政府からの反対にあい、自由民権運動に対する中央集権的国家体制づくりに矛盾するものとして批判を受けるようになります。これは前期に「歴史的考察」としてやったことと一致しますね。「中央集権的教育体制」へと進んでいくことになるのです。1880年代になると、法律、政治、行政、軍事など、国家体制の基本になる諸制度のモデルをヨーロッパ諸国のなかの新興国家であるドイツに、集中的に求めるようになると続けて述べられています。
|
「辺境」にあって急速な近代化を目指す日本にとって、ならうべき具体的な「中心」として選び取られたのは、民主主義的なイギリスやアメリカでも、また革命を経たフランスでもなく、絶対主義的なドイツの諸制度だった(中略) |
ドイツ「絶対主義」は日本の国家体制にあうと考えられ、受け止められたのですね。もちろん米国からの影響は完全に断絶したのではなく、ミッション系学校や私学で少し残されていましたが、1900年代以降は国家による統制が強化され、その独自性を奪われていったと説明が続けられます。そして戦争に突入し、敗戦し、米国の占領下において「戦後の教育改革」が行なわれた。
|
三 占領下における教育の「アメリカ化」 |
再び「アメリカ」の影響がはじまったというわけですね。学校制度の「六・三制」の導入や、ハイスクールをモデルにして高等学校がつくられるなどをした。「いま」の形式がここでつくられたのですね。米国は「教師」であり日本は「生徒」であった。これはつまり「教育をされた」ということではないでしょうか。ちなみに「小学区制」には地域独立(分権化)などの構想が表れているわけです。その後の実態はともかく、まさに米国的システムが導入されようということになった。ドイツと扱いが違ったというのは注目すべき点ですが、ここでは除外しておきます。日本は実際に戦後に「フルブライト奨学金」などの援助によって優れた人材が米国に招かれ学んで帰国し、その後に日本で活躍していったということもありました。米国での「教育」がいろんな面に影響を及ぼすようになってくるともいえないでしょうか。しかし、次の4節には反動があったと語られます。
|
四 アメリカ化への「反動」 |
1952年の占領終了後、「反動」へと向かうというのですね。これも前期の授業で指摘済みのことですが、すぐに「自国・土着」化という反動反応が出てくるものと考えています。「学習指導要領」にそのような反動が表れてくるということをすでにみておきました。天野先生は、「我が国の国力と国情に合し、真に教育効果をあげることができるような合理的な教育制度に改善する必要がある」とされたと記しています。文部省の管理・統制権限の強化というものが起り、教育の地方分権化から中央集権化へと移行したのですね。しかし以前の反動時との違いがあると続きます。
|
第二次世界大戦によってヨーロッパが経済的に、また学術研究の面でも著しい地盤沈下を経験するなかで、アメリカの地位は相対的にもまた絶対的にも上昇し、新しい世界の「中心」としての地位を確立した。(中略)・・・日本はアメリカに、戦前期のドイツに代わる新しい「中心」を見出したのである。留学生の流れは大きくアメリカに向かい、また学問の諸分野はアメリカの強い影響下におかれることになった。 |
以前と違って米国(「アメリカ」)は絶対的な中心になっていたので、前回のようにドイツなど他のものに傾倒するということはなくなったのだというわけです。米国が「世界」において「ヘゲモニー(超大国)」の地位にいたという考え方ができるのではないでしょうか。
しかし、次節の「五 新しい段階」になり、アメリカとの関係は、教育、政治、経済とも複雑なものになり始めているといいます。
|
それは明らかにこれまでのような「中央」と「辺境」の関係でもなければ、「教師」と「生徒」との関係でもない、それは相互依存的、相互影響的な関係に変わりつつあるといってよいだろう。日本の教育の「アメリカナイゼーション」をいう一方で、アメリカの教育の「ジャパナイゼーション」が問題にされねばならない段階がやってきたのである。 |
たしかに「日本」の教育システムの成果や方法はある程度注目を集めていると思います。マスコミ用語的には「ジャパナイゼーション」という表現もある。「日本」が「中心」入りしたのも事実かもしれません。なるほど、以上のように考えれば「世界システムとしての教育」というものもわかっていただけるでしょうか。
この天野先生の記述は、忠実に「世界システム論」の文脈に「近代教育」「日本の教育の近代化」をあてはめているものと思います。本当にそのような視点の先行研究が少ないので参考になります。例えば次の表「世界システムの展開」にぴったりとあうともいえる(この表はAERA Mook10『歴史学がわかる』所収の川北稔「『中核』と『周辺』が単一の時間を共有していた」<世界システム論の考え方>を参考にした)。
◆世界システムの展開
|
時期 |
特徴 |
世界商品 |
|
1450-1620 |
成立期・ブームの局面 |
農産物と銀など |
|
1620-1750 |
収縮の局面・重商主義による中核諸国の生存競争オランダのヘゲモニーの成立と崩壊 |
茶・砂糖・奴隷など |
|
1750-1840 |
拡大の局面・アジアの大半が組み込まれる英仏のヘゲモニー争い、イギリスの勝利となる |
綿織物など工業製品が重要性を増す |
|
1840-1917 |
イギリスのヘゲモニーの盛衰。合衆国とドイツの中核化 |
鉄・石炭・ゴムなどが加わる |
|
1917-1967 |
ロシア革命以後の社会主義政府の成立・反システム運動(社会主義的労働運動とナショナリズム)展開。アメリカのヘゲモニーの成立 |
石油・自動車などが加わる |
|
1967- |
ポスト・アメリカの時代 |
電子製品など |
しかし、「私」はこの結論についてだけは少し違う考えをもっています。厳密には<アメリカ→ドイツ→アメリカ>という部分も、もう少し細かく「教育内容と教育観」及び「対外交渉」の視点から考えていますが、それは前期にお話ししたのでホームページに更新してあるものを読んでもらえればいい。それよりも「私」は<世界システム論>をもう少し複雑にとらえています。いや、後期にこれまで述べてきたことからもそうですが、「システム」がある状態を維持・安定をさせるものだとしたら、そんな簡単に日本が「アメリカ」に並ぶことがありえるのでしょうか。いや「並んでいるじゃないか」とか「疑いすぎだ」というご意見もあるかもしれませんが、今日の講義の最初に述べたように「世界システム」とは何か理不尽なまでに序列化されているものではなかったでしょうか。「私」の思う<世界システム論>では、日本は「中心」の仲間に入るまではいきましたが、しかし「ヘゲモニー」としての米国には並んでいない。いや「並んでいるようにみえる位置」と「されている」と考えているのです。もちろん「アメリカ」をヘゲモニー(超大国)としてみなければ並んだといういいかたができるのかもしれません。今の米国は「孤立」や「強引さ」すら感じることもありますが、「超大国」はいいすぎでしょうか。しかし、私は逆に「教育」の<世界システム>においては米国にヘゲモニーがあるのではないかと思っています。
なぜなら天野先生のいう「ジャパナイゼーション」も一面としては事実でしょうが、これは高等教育を除外してのことではないでしょうか。でもそうならば、国際的な学力調査ではとっくに米国は他国より順位が低いわけです。日本や韓国、インドだってそうとうに高い。では日本以外も並んだのかとなるでしょうが、そうではなくてそういう状況の米国でも「高等教育」になると評価が高いままで他の追随をなかなかゆるさないものではないでしょうか。もちろん他国にもすぐれた有名な大学・高等教育機関はあります。しかし米国のものは評価が高く、それは留学の傾向にもあらわれていないでしょうか。いや、少なくとも、日本は「高等教育」で並んでいるのでしょうか。「日本の大学教育はひどい」などと言われることはよくあります。私自身は「ひどい」とは思っていません。しかし、「入りにくくて、出やすい」日本の大学よりも欧米の「入ってから難しく、学問を追究しないと出れない厳しさ」をもつ方が優れていると考えられている。わりと一般的にそうとらえられていないでしょうか。だとすると初等・中等教育では並んでも、高等教育では並んではいないのではないでしょうか。いや、ここで「システム」を考えてもらうと、なぜ「初等・中等教育では並んで」、あるいは追い抜かした(ジャパナイゼーションまでさせている)のに「高等教育」で追いつけないのでしょうか。それは大学の制度が悪いのか、あるいは教員が悪いのか、何が理由なのでしょうか。おかしくないですか、急に逆転されて大幅に差をつけられているのだとしたら。これは「価値観」が狂ってしまうようなことではないでしょうか。その理由もわからないで「そうなってしまっている」状態を私たちはこれまで「システム」内で「システムを知らない状態」としてみてきたのではないでしょうか。少し別の視点からみていきましょう。
●「留学生」のニーズ-<世界システム>としての序列・位階-
本当に「私」が危惧するような米国志向というべきものがあるのか。そしてそれが<世界システム>の位置づけになっているのか。「世界」のニーズをみてみればいいのではないでしょうか。「世界」の教育といえば、「留学」をみていくとその一つの特徴を示しているはずです。「留学生のニーズ」をみていけば参考になるかと思います。
まずは「日本へのニーズ」です。文部科学省の調査によれば次の図表のようになっています。
日本に来ている留学生地域別一覧
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )内は平成12年5月1日現在の数
あくまでも単純にいえば、「留学」してくるのには目的や理由があるはずです。少なくとも「日本から何かを学べる」とは思ってはいるでしょうか。そう思っている国のうち欧米はどのくらいでしょうか。国別のデータもあるのですがあまりにも少ないのです。いうまでもなく「北米」はアメリカ合衆国だけではありません。ほとんどが「アジア地域」からのニーズがあるのだといえます。距離や治安や学びやすいとかはあるのでしょうが、しかし物の値段(物価)が高いような暮らしにくさもあるとも思います。様々なそういう現実の中で以上のような傾向が出ているのですね。もちろん数年にわたって並べるとまた様々な見方が可能ですが、ここでは「日本が米国に並んでいるか」ということ一点を見ていくために、この資料に限定しておきます。ちなみに国別にベスト5をあげると次のとおりです。出身国の上位5ヶ国においては中国が多数を占めていて、タイが5番目に浮上している。これらは上の「アジア」地域の中のもので占められていますし、その5位のタイ一国よりも「北米」地域全体からの留学生は少ないのです。
|
|
次に「日本人留学生」がどこに向かうのかということです。次のグラフを見てください。北米に57%強が行っている。北米では語学留学としてカナダが注目されてもいます。しかし米国にもやはり多いのでしょう。ヨーロッパの23%強を加えると実に8割以上になります。もちろん専門分野などで他の地域にも留学生は向かっていますが、それにしても圧倒的というまでに傾向に格差が出ているわけです。
日本人海外留学生の留学先
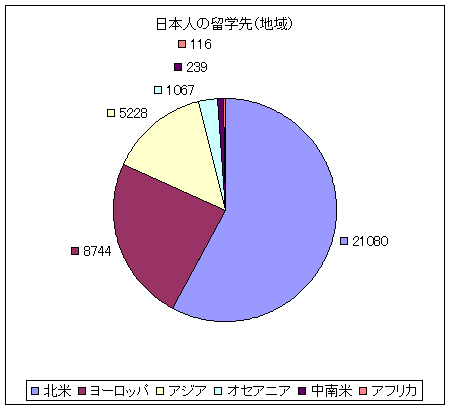 世界の留学傾向の図表もあげておくべきでした。しかし例えばマレイシアでもほとんどが米国へ向かい、次の次というレベルで日本へということになっています。中国でも日本に来る留学生が多いのですが、しかしより多く、いやより高いレベルの留学先として米国の大学があるというのが現実です。「米国では学位がとれる」が日本の大学にはそのシステムが未発達であるなどともいわれます。簡単にいえば「米国」留学帰りの方が権威があるということになります。これは「日本」がめざしているというだけではなく、「世界」も米国を高く評価しているといえないでしょうか。単純に「留学先」も<世界システム>で価値づけられているのではないかとして、日本にはどこから来ていて(どのように価値が認められていて)、日本からはどこに行っているのか(どこに価値を認めているのか)をみてみました。それはどうやら世界的傾向でもある。
世界の留学傾向の図表もあげておくべきでした。しかし例えばマレイシアでもほとんどが米国へ向かい、次の次というレベルで日本へということになっています。中国でも日本に来る留学生が多いのですが、しかしより多く、いやより高いレベルの留学先として米国の大学があるというのが現実です。「米国では学位がとれる」が日本の大学にはそのシステムが未発達であるなどともいわれます。簡単にいえば「米国」留学帰りの方が権威があるということになります。これは「日本」がめざしているというだけではなく、「世界」も米国を高く評価しているといえないでしょうか。単純に「留学先」も<世界システム>で価値づけられているのではないかとして、日本にはどこから来ていて(どのように価値が認められていて)、日本からはどこに行っているのか(どこに価値を認めているのか)をみてみました。それはどうやら世界的傾向でもある。
ここで話を戻すと、「日本は並んだ」のでしょうか? 米国が基礎教育の部分でジャパナイゼーションを目指そうと、つまり日本が事実上目標とされるまでの高位に上がったのだとしても、なぜか「高等教育」では評価に格差がついたままです。いつ、抜かれたのでしょうか? いや、日本が勝ったという順位がつくのなら韓国もインドも勝っているのですね。米国はそうとうに負けているはずです。
ここではわざと「勝った、負けた」としました。勝ち負けのスポーツに例えるということをおそれながらゆるしてもらえれば、「巨人」は今年は優勝しましたが、毎年強いですか? いや「勝ち、負け」ならば何故、優勝したヤクルト、広島、中日、阪神、パ・リーグなどから選手が「巨人」に向かって移籍していくのでしょうか。お金、知名度、テレビ放送、媒体、その後に解説者になれるなどの保障などいろいろあるのでしょうけど、ただただ「単純な勝敗」を超えたところでブランドとして価値観の頂点に君臨しつづけているのですよね。ただ伝統があるというだけにもみえるのに。そこに偉大な選手が集まりやすいという構造が再生産されている。なにやら理不尽なまでに強引なときもあって批判されてもその構図はそうは変わらない。どうでしょう。日本は「アメリカ」に、その座に並んだといえるでしょうか。私はこのように複雑なものまでを含んでシステムが維持されている状態を<世界システム>と考えています。
もちろん誤解をおそれずいえば、実際に米国の大学はすぐれています。やはり優秀な人材が集中していきますし、日本の研究者も米国に向かうということも多い。これは私を含めて日本にいる研究者がしょうもないということではありません。しかし世界の頭脳といわれるような研究者も米国の大学に勤務したり、授業もするのでレベルは高いです。米国の教育について授業で話す時に(数回後に)説明しますが実際に奨学金制度の充実やデイ・ケア・センターなどの環境の整備、あるいはやる気のある学生ならばそうとうにケアを受けて学習に専念できるという点からみても日本の大学より優れている点は多くみられます。その一方で留学生であろうとなんでも厳しい課題が課され、論文やゼミの進め方も非常に高いものを要求されるという厳しい面もあります。あくまでも単純にいえば、それだけでもレベルは高い。環境・機器整備も充実しているところが多くあります。もちろん全ての大学がではありません。しかし、実際に私の知っているかぎりではかなり学習環境としては高レベルだと思います。
さて、私がいいたいことは矛盾してはいません。ただ、もし初等・中等教育でいくら国家カリキュラム規制などで学力を上げるよう努力しようとも、逆にいうと米国ではいくら到達度評価が低くても、そういうように「アメリカ」を目指して「知的」な権威が集まり、実際に高水準の環境が再生産されるということなのです。それを知った上で留学するのはいいだろうし、それに権威的であろうとなかろうとそれは個人の自由です。ただ、いいたいのは「日本ではなぜそうならないのか」ということなのです。日本にも知的刺激にあふれた研究や授業が集まって来てもいいとは思いませんか。そこまで考えないと、追いついたように満足してしまって結局はよくはならないこともあるのではないでしょうか。この大東文化大学は私が見て来た大学の中でハワイ大学マノア・キャンパスに似ています。すごく環境がいい。ここは国際関係学部ですから留学生も多いですよね。私は先生方で存じあげる人がいないので、おそらくいい先生方がたくさんいらっしゃると思います。それに加えてより知的刺激が集まって来たら、皆さんがもっといろいろとつねに考えていく機会が増えたら、それは学ぼうと思う時には幸せな状態なのではないでしょうか。そういうふうにより高い状況をめざす。それがもし<世界システム>なるもので制限されているのだとしたら、その中で満足している場合ではないですね。でもその「システム」を知れば、自ら主体的に学んでいけるし、またより多くの人間が知っていけば、いずれは<世界システム>内でどのようにしてその構造を変えてよいものにしていくかがわかってくるのではないでしょうか。
このような「教育」の<世界システム>ということをまた次回に考えていきます。「世界」という「社会」をも「安定させる機能」としての「教育システム」というものを明らかにしていくために、多国家間の教育比較(交流史研究)という視点が必要になりますので、次回はそういうお話しにしていきます。
(リアクションペーパー配布→回収)