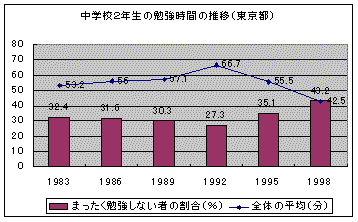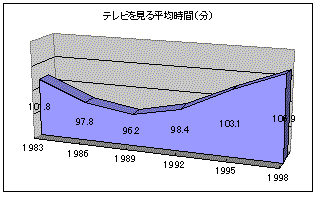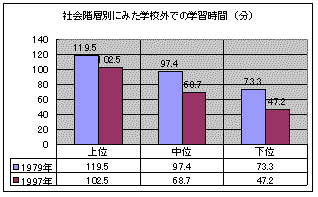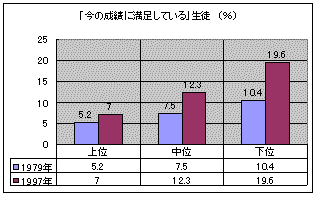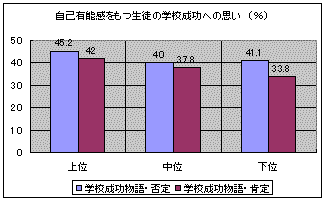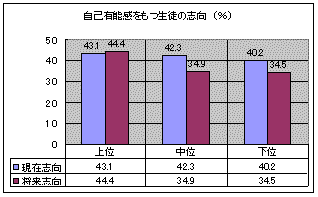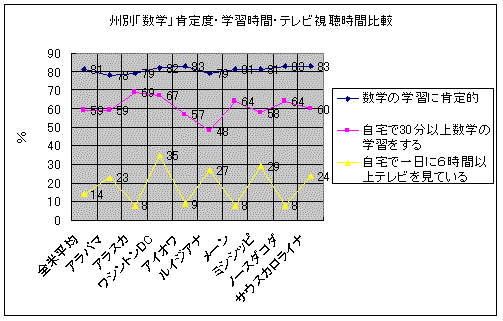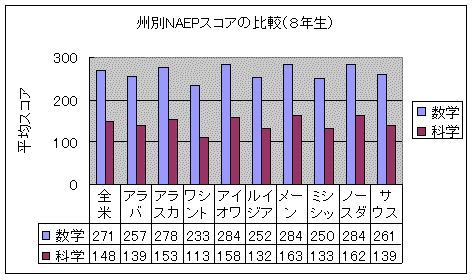教育学概論Ⅱ(社会と教育)④ (2002年10月28日)
|
今回の講義内容 |
前回の授業で「イギリス」の教育制度と、教育改革について考えてみたのですが、実にダイナミックな動きがみられたわけですね。「(いわゆる)イギリス」という国家にとって「教育」は社会の重要な課題でもあったし、また「社会」を安定させ、秩序や序列(関係)を再生産するものでもあった。それは、ある階級・階層からみれば「安定」「保障」でもあったし、別の側からみれば理不尽な「不平等」でもあった。まさにこの授業のタイトルでもある「社会と教育」というものの重要な結びつきを示す一例ではなかったかなと考えています。
前回まで、「比較教育学」の視点から、そこから「イギリス」に注目していったのですが、その「イギリス」を考察したことで学んだことをいかして今度は別の問題を考えていくことで、本当に、「比較教育学」が学問として意味をもつのだと思います。今後もしばらく数ヶ国をあげて、その国・地域の教育をみていくことで、その「社会」における「教育」の役割や意味というのを考えていくことをシリーズのようにして続けていこうと思います。ですから「比較」の視点は続けていきます。それで、今回は前回の最後にもいいましたが(あるいはクラスによっては次の資料を概説しているが)、「教育改革の成果」というものを「日本」の場合についてみていきたいと思っています。
すでに予告済みで資料を配布済みでしたが(見ておいていただきましたが)、今日は「社会学」という考え方から「教育改革の成果」を分析・判断することを試みていきます。前期の講義でも「人間と教育」を理解するために、様々な学問分野の研究方法・視点をかりてみました。生物学、生理学、医学、脳神経学、哲学、心理学、歴史学、考古学などを参考にして、「教育」と「人間」の関係を考えてみたのですが、後期の「社会と教育」でも様々な分野の優れた方法を参考にしていきます。「比較」の方法もその一つですが、今後、社会学、文化人類学、経済学などの理論を借りて考えていきたいと思っています。今回は「社会学」、「教育社会学」という考え方の中から、統計分析を通した実証的な分析方法というものを紹介して、その有効性を学んでもらうというのが目的の一つでもあります。もちろん「社会と教育」の意味を確認していくことも大事ですが、今後の考察の方法論の勉強にもなればいいと思っています。
(3)「教育改革」の成果を予測する(社会学の方法)
参考書籍としてあげた苅谷剛彦先生の本は、前期にも何冊か紹介しましたがすごく面白く読めて楽しめるのではないかと思います。おそらく大学生時代に読んでおくとためになる本のうちの一冊ではないかとも思うのですが、今回はその中から資料分析の部分を紹介します。苅谷先生はここ数年、すごく研究が評価されるようになってきた方でして、実は私は研究というものは10年ぐらいたたないと認められにくいという性質があるのではないかと思っています。これは研究そのものというか、学界(学会)のシステムだと思うのですが、ある研究が認められるのには時間がかかると思うのですね。「その研究」に価値が承認されて与えられるのに10年ぐらいかかるのではないかと思っています。ようするに、苅谷先生も昔の論文を読ませていただいてもブレとかはなくある意味で一貫して調べて主張してきたことが--ここにきてさらに分析がすすんだというのもあるのでしょうが--認められてきたのだと思うのですね。いまの「教育改革」論議をリードしている論客だと思いますし、また「学力低下論」の火付け役とも言われますが、すごく誠実に実証を積み重ねてこられた説得力のある研究(方法)だと思います。いろいろな参考になると思いますので紹介します。
さきに結論めいたことをいいますと、この今日紹介する研究はすごく影響力があると思うのです。いま、文部科学省の教育改革の方針は揺れているようにも思われています。「ゆとりを」といっておいて(あるいは「いきる力」など)、例えば「必要最低限の基礎部分を徹底して教えればいい」といって内容の精選・厳選を行ないながら(計算機の使用や円周率の教え方の変更に象徴されていますが)、いろいろな不安な要素が出てくるやいなや、「学習指導要領は最低限度を示しただけだから、それ以上を教えていいのだ」とガラリと方針転換かのようなことをいう。いくつも例はありますが、あのブレはこの苅谷先生らによる実証の影響もあるのではないかと思います。いや、つまり、苅谷先生が今日みていく分析結果で「警鐘」を鳴らしたのですが、実はこのような「調査」をおそらく文部科学省側はしていなかったのではないかと思うのですね。もちろんデータはあったのだけれど、それを読みとって(意識して)いなかったのではないかとも思います。今日の後半でもいいますが、実は米国などではこのような調査はわりあいに普通に行なわれていて、その結果は重要視されていると思っているのですが(もちろん地方分権のためになかなか全国的な政策化はできないが)、日本では過去においても実施してから「結果」が出て、それに対して対応をしていくということのみで、実はさきに「結果を予想して政策を決定する」という視点が弱かったのではないかと思うのです。それは「歴史」から学んでいないということでもありますし、データをいかしていないということでもあります。これではなんのための「調査」かというのがわからないのですね。
ですから、今回紹介する考え方は三つの意味で注目してほしいのです。一つは単純に「教育改革の結果はどうなるのか」という部分。もう一つは「こういった統計分析という方法の可能性」です。最後に「こういった調査資料をいかしてその上で考えていくべきではなかったのか」という改革推進の手順論です。苅谷先生の視点はもうそういう方向に行っていると思いますし、すでに次の段階として「文部科学省」側が「意図したことは違う」というのならば(「いいわけ」というだけではないのでしょうが)、その「意図」が現場に伝わる際の経路は充分に意識されているのかという点にまで考えが進んでいるようです。これはいいわけをゆるさない、いや実はそういう構造を修正していこうということまで考えられているのだと思います。実際に私も何度か前期に言ってきましたが、「伝わる」というのはそう簡単なものじゃない。簡単なら「教育」なんて楽なものです。でも何故か人は「自分が意図したことはふつうに伝わるものだ」と思ってしまうのでしょうね。それで失敗したならば「(受取側が)意図したとおりにしていないからだ」ということになる。「意図した」のならば「それをしっかりと伝える努力」をしないとせっかくの努力も水の泡と消えます。「教育」というのはそういう難しくて重要なものなのに、その「教育」を改革する(つまり指針を決定する)時に「そういう根本的なこと」が取り違えられているというのがすごく残念なことです。さて、あまりさきに結論じみたことをいってもしかたないですし、それにあまりにも「困難」「失敗なのか?」などと不安視させるのもよくはないですね。少し安心していいと思うのは、こうして「ブレ」という認識違いや準備不足はあったけれども、しかし今回調査や実証の重要性を知ったということは、今後の推進やあるいは次回の改革の時にはそれを教訓としていかしていくのではないかと期待できます(そういう期待をしたいと思っています)。それでは、苅谷先生の著書から資料をみて考えていきましょう。
●「社会階層」による学力差
東京都内の中学2年生を対象としたアンケート調査結果を分析したものです。1970年代後半から1998年までの結果を図表化してわかりやすく説明していきます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上の資料・分析から何が読みとれたでしょうか。中学2年生を対象として、その勉強に対する意識や取り組みを調べてみると、全体的に昔より今も方が意欲や学習時間が減少の傾向にある。それで学校においては「内容」「時間」ともに減らされているのですから知識・情報に触れて吸収する機会が少なくなっているというのは事実でしょう。もちろん「ゆとり」も大切ですし、「生きる力」という意図もわからなくはないのです。しかし、それがどういうものなのかが明確じゃないために信頼が得られていないというのはあるのでしょうね。その「信頼度」がこの資料分析の結果に勝てるような説得力がないといういいかたもできます。だから推進するならばちゃんと説明なりがされていけばいいのです。それがもう一つはっきりしないのではないのでしょうか。
「ゆとり」がめざすものは自宅でテレビをみる時間ということではないわけですね。もちろんテレビを見ること自体が悪いのではなく、その「ゆとり」によって最終的に学校などで「学ぶ」ことによい効果が出ればいいわけです。極端にいえば「学力」の規定の問題でもあるのでしょうが、あえて点数でないというのならばそうはっきりいえばいいわけです。「学校で、ゆとりある中で何かをつかむのだ」と。ところがそれがイメージしきれていないのか、少なくともこの資料の説得力に押されてはいないでしょうか。
そして実際の問題として、「階層」分化というものがみられるのではないかということです。これは「皆さん」にも意識してもらいたいことです。いまも(大学でも)そうですが、講義を受けながら、「こんなものは適当でいい」「成績が合格ならばそれで(高くなくても)いい」「自分は自分、大学・学校から学ぶことなんてない」などと思い、そして「いまがよければいいのだ」と考えていることはないでしょうか。「自己肯定」や自身をもつことは必要です。しかし、自分にいいわけをしたり、あるいはかってにあきらめたり、あるいは刹那的にいきたりなんてことになるとどうでしょうか。「自分にいいわけ」して納得している場合には、それは意識しないと気づかないでいるということになりませんか。僕の好きなニーチェならそういう状態を「奴隷の道徳」あるいは「荷物を運ぶだけのラクダだ」なんて言うかと思います。こういう状態になっていることは意外に多いのではないでしょうか。だから私は何度か言っていますよね。出席とか代返とか、あるいは私語とかすることについて、「何が大切なのか」というのを考えていくべきだと。同じ学生として同時に講義に出ている。ある人にとってはわかる講義だけど、別の人にはわかりづらい。「わからない」ままにしておくことが問題なのです。もちろんわかったつもりで、それがわかっているかはまた別です。だから「わかっていく」「確認する」「考えていく」ことが何よりも重要なのではないでしょうか。「いいんだ、こんなの適当にやって単位さえとれれば」と考えることももちろん「自由」です。それが「逃避」だったとしても自由です。しかし、その「本質」や「逃避」の可能性もあるのだとこの「資料」で読んだ以上は、皆さんはそうならないように考えていくようになるのじゃないでしょうか。もちろん規制でも強制でもないのですが、とにかく「わからないままにしておいて、かってに納得している」というのはあまりいいこととも思えませんね。ニーチェ流の「奴隷」はいいすぎにしても、実際に同じく税金を払って生活する上での権利として教育を受けながら、ある層(上位)はちゃんとそれを生かして、教育システムの恩恵を受けていくことができて、・・・そうでない層は満足感はもっているけれどもけっきょくは恩恵をあまりいただけないということになる。「俺は俺」「自分は優れている」という気持ちは本来大切でもあるだけに微妙な問題ですね。それによって社会に階層をつくりあげ、おまけに不満すらもたないし、行動もしない。挑発的な言葉をゆるしてほしいのですがそういう人間はすごく「操りやすい」「都合のいい」人間だと思います。皆さんがそうでない人間であることを祈ります。それには世の中の「仕組み・システム」を考えて、相対化、客観化していく思考法を意識していくべきと思います。
以上、苅谷先生の資料分析の紹介からお説教じみた私の考え方のお話しになってしまいましたが、実際にこの「資料」をみてどうだったでしょうか。「説得力がある」と思われた人が多いのではないでしょうか。次に、同じような指標の調査をみてみます。米国の例です。
(4)社会学の方法を点検・確認する(米国の場合)
下のグラフ・表類は、米国での「学力」調査といえるでしょうか、NAEP(National Assessment of Educational Progress)というテスト(数学・科学)の州ごとの平均点数と(下側の棒グラフ)、それとの関係・諸条件を考察するための視点として、「数学を肯定的にとらえているか」「自宅で数学を1日に30分以上勉強するか」「テレビを1日に6時間以上見るか」(以上、上の折れ線グラフ)というものの割合を表示したものです。NAEPは全米統一テストという正確のものではなく、大学入学のために要求されているテストでもありません。数学の満点が500点、科学が300点になっています。ちなみに「数学」「科学」というのは国際到達度テスト(世界の学力評価)でも基準とされるものです。主要科目ですが、「国語」が各国によって違うので数値で客観性をもって比較することが難しいわけです。社会科の知識も世界史、世界地理なら共通するもののそこにも配慮が必要となる。その点、自然科学については「比較」が可能なわけです。それでこの調査でもその2科目があげられています。また「対象」が「8年生」ということで、日本の「中学2年生」に相当するので上の苅谷先生の調査とも符合するものです。
|
|
「学力(点数)」と「勉強時間」及び「テレビをみる時間」、さらに「学習を肯定しているか」ということが影響関係にあることがわかります。もちろん「あたりまえ」でもあります。その勉強を好きで、必要と感じて勉強して、それでテレビも見ないで打ち込んでいるのなら、点数が高くなるのはあたりまえだろうとも思えます。その意味で日本での調査と米国での調査は同一性をもちます。もちろん調査の目的は異なっているのかもしれません。しかし、その分析から大きい問題が形としてみえるからとして、改革が行なわれていくのですね。全米でもこの「指標」は優良な教育が行なわれている「州」という評価になりますし、実際に留学のガイドとしてもとりいれられている客観的数値です。「自由」とイメージされる米国でも「学力」の問題は教育改革の重要な柱となっています。しかし、日本ではこういった調査は行なわれ、そしていかされてきたのでしょうか。苅谷先生らによる提言で、文部科学省にブレがみられるのだとしたら、そういった調査・分析から改革を誘導していくということは行なわれてこなかったのでしょうか。だとすると米国とは「逆」のアプローチからの改革となってしまいます(何にもしていなかったという意味です)。いったい「国家の教育の改革」とはどのようなものなのでしょうか。
しかし、ここで問題にしておきたいのは「点数」ではなくて、それを通してはかられ、そして形づくられる「階層」というものです。英国→日本という順序でこれまでみてきました。米国にも深刻な人種・多民族の問題があります。しかし、これまでみてきたことからいうと、「システム」というものは「そういうもの(階層)」をすら安定させていく一面があるわけです。「学校システム」「教育システム」といいかえても同じです。不平等や、序列づけ、階級化、あるいは関係性でもいいのですが、そういうものを再生産して、また保障していく。だから、「社会」を考えていくことが重要なのですね。システムへの関わり方、社会の形成の方法。そういうことを意識して学んでいきたいものです。次回はもう少し広げて「世界レベル」(国際社会)でのシステム関係というのをみていきます。<世界システム論>という考え方を紹介する予定です。
(リアクションペーパー配布→回収)