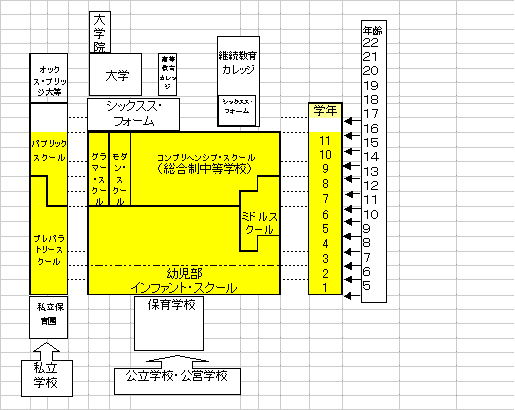教育学概論Ⅱ(社会と教育)③ (2002年10月21日)
|
今回の講義内容 |
●前回のまとめから・・・
前回は「比較教育学」研究の方法について説明し、日本とイギリスの学校教育制度を単純に比較することを試みました。教育と「社会」との関わりを考えていくために、まず「他の社会」(他国)における教育がどのようなものなのかをみていくことが有効ではないかと思うのですね。単純に「違う」部分はすぐにイメージできるとも思いますが、あまり意識されないでも一致したり共通する部分というものもあるのではないでしょうか。形が違っても、果たしている意味が共通していたり、お互いの国同士(国家間)での影響はなくとも、なぜか同じような役割を果たしていたり、またはその制度が決められる土壌や過程は異なっていても、どこか共通する部分があったりということを仮定してみたらどうでしょうか。もしもそういうものがあったならば、それが「社会と教育」を考える上でのなんらかの答えの一つにもなりえるのではないでしょうか。どこの社会でも共通するものが見出せたならば・・・。ですから「比較」することが有効で意味があるのです。比較をしないと相違点が見つかりませんし、そもそも違いがあるからこそ「本質」的な共通する「意味」の部分がわかってくるのではないでしょうか。
もちろんただ闇雲にどこかとどこかを比較するというよりは、できればある程度ターゲットは絞れていた方がいいとは思います。さらに調査した結果わかったことが一般的な概念になって、それをつかってさらに他の対象を調べていけるようになっていけばもう立派な学問ですね(それが比較教育学です)。
前回は日英両国を比較したのですが、そこには「比較」する理由がありました。1979年のサッチャー(保守党)政権以降の政策(「教育の民営化」「学校選択制」「教師の成果賃金制度」等)を現在の日本でも導入しているので、参考になるし比較しやすいということです。例えば「学校の選択」は東京都では公立高校は次年度から学区を撤廃するとも報じられていますし、義務教育段階でも区や地域によってはすでに「学区制」を廃止したところもあります(あるいは「特区」や港区の新しい情報について話したクラスもある)。もちろんこういった「教育改革」は世界的潮流でもあります。1980年代以降に顕著にみられるものでして、イギリスだけのものではありません。1983年にアメリカ合衆国が『危機に立つ国家』という観点から大幅な改革をはじめた(つまり教育改革が必要だと認識された)のに始まり、続いて英国が1988年に前回にもみたサッチャー改革法とも称される改革を断行した。続いてフランスはミッテラン大統領当時の1989年に「新教育基本法」(いわゆる「ジョスパン法」)を出し、ロシアも続いたのですね。日本も中曾根総理大臣のイニシアチブで臨時教育審議会が招集され、教育改革が試みられた。これが1990年代に皆さんが受けてきた「教育」のもとになっています。文部省中心ではなく内閣総理大臣がリーダーシップを発揮したという点でも時代の波に乗ったものともいえるのではないでしょうか。現在の「教育改革」も基本的にはその路線の延長線上にあって、1998年前後に議論されたことが施行(試行)され、また新たに大学の統合・改革やバウチャー制やコミュニティースクール構想などが加わってきているのですね。基本的には「ゆとり」でもあるし「民営化・自由化」でもあり、また情報化や国際化を意識したものです。そのような改革の一部は、すでに英国等で実行されているものなので、これから導入されるに際して、その実態や効果・課題などを知っておくことには意味があるでしょう。そしてそれを通して両国を比較していけば、そこから何らかの発見があるかもしれません。前回はそういう意味で比較をしたのですが、まず単純な部分比較をしたところ、イギリスでは学校課程が「二系統」に分けられていて、そこには身分差・階級差の社会であるという特徴が表れていた。いや、もっと正確には、「教育」によってその格差すら安定させられて維持されているのではないかというのがみれたかと思います。「受験」の持つ意味(重要度)が大きいのではないか、と。そういう日本と比べての違和感があったけれど、それをもう少し詳しく並行比較の視点でみていくと、この「機会の不平等(格差)」を巡って「政治」問題となり、それが政権ごとの重要な課題となるというダイナミズムがあった。エリート層を代表する保守党と、労働階層を代表する労働党との争いですね。少なくとも「教育制度」が「社会的再生産」の機能を果たすという一面はみえたかと思います。重要な問題であった。
しかし、どうなんでしょうか。いろいろ考え方もあります。「11歳」で決まるシステムが重視されれば実質上それは「エリート重視」かもしれない。しかし、おそらくサッチャー側にいわせれば「何の問題があるのだ」となると思います。逆に「透明性があるだろう」と。「そこが選択肢・岐路だと明確にしているじゃないか」と。こちらが「できない不利という現実」を訴えようと、あちらからは「誰にでもチャンスが明確になっている」ともいわれる。ですから単純に評価はできません。しかし、実際には、前回の表には「私立学校」が入っていないのです。ほとんど上流階級・貴族と呼ばれる層は子どもを私立学校(パブリック・スクール)へ入れていて、これはもうまるっきり違う学校系統ともいえます。オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった、通常の公教育路線の延長上にあるのとは別の試験を行なう「大学」(特別な大学)なのですが、世界的にも有名なこのような大学にほぼ進学するのです。つまりさらなる「階層」があるのです。さらに「上」がある。具体的にはパブリック・スクールのカリキュラムにはラテン語とギリシア語があるというのが公立学校と異なるのですが、その言語がオックスフォードやケンブリッジの入試に出るのですね。すると事実上、これらの私立校に行かないと進学はかなり困難になるということです。このように別のシステムもある。するとそれで公教育を比べたらまだましなのか、それとも、そこでまでわけられてしまうと考えるのか。それで大きく変わってきます。
今回も、もう少し詳しく「イギリス」の教育システムについてみていきます。最終的にはそこから学んだことで「日本の教育改革がどうなるのか?」ということに発展していきたいですし、そしてさらに他の国まで含んだ多様な比較へと発展できるような「関係比較」をしていくなんらかの視点を得れればいいと考えています。なお、前回の考察と今回の配布資料にある引用から、次のようなことが特徴としてあげられるでしょう(資料は略する)。
◆イギリスの教育システムから読みとれる特徴
|
★「制度」のもつ意味、果たす役割、作用(教育と社会的再生産) |
●イギリスの学校教育制度
まず、今回は新しい学校制度の図表をあげておきます。前回の日本と「イギリス」とを対照した図表はわかりにくいと私は考えています。あれはどんな「教育学」関係の本や資料集にも載っている代表的なものなのですが、ああいうものは「ダイジェスト」にしたもので、わかる人がみればわかりやすかったり、あるいは「わかる説明が伴ってはじめてあの図でわかる」といったものなのです。前回、説明を試みましたが、まだそれでも不十分でしょうし、(しかし説明したからこそ)今回の表をみれば前回以上にはわかりやすいのではないかと思っています。パソコンのエクセルというソフトでつくってみましたが、皆さんも何かの図表なりを「自分なり」に置き換えたり、つくりかえたりすると、よりわかりやすくなっていくことがありますので試してみてください。
|
|
●イギリスの教育制度 -政治的ダイナミズム-
前回もみた「教育制度・改革」の流れを確認しておきます(詳細は略する)。
イギリス教育制度
|
年 |
法規・提言・政権等 |
事 項 |
|
1880 |
教育法 |
5~10才(小学校段階)での義務教育制度 |
|
1944 |
|
●5~15才(後16才に延長)まで無償義務教育の保障(中等教育を全ての者に保障)。●「教会立学校」をボランタリースクールとして公営化し統制し、LEAのカウンティスクールと合わせて公営学校として義務教育を担わせる。●18才青年までの多様な延長教育の準備(ファーザーエデュケーション) |
|
1965 |
教育・科学省(労働党政権) |
11才テストの廃止と、中等教育による差別化廃止の方針を提起。 |
|
1970 |
教育・科学省(保守党政権) |
上記通達を廃棄する。 |
|
1974 |
教育・科学省(労働党政権) |
上記(廃棄した)通達を復活する。 |
|
1976 |
教育法(労働党政権) |
グラマースクールの廃止決定 |
|
1979 |
(保守党政権) |
1976年教育法の廃止(*サッチャー政権) |
|
1983 |
提言(労働党) |
私立学校を「無償で公正な教育制度への大きな障害」と批判。 |
|
1988 |
教育法(保守党政権) |
サッチャー公約後1年で法律化。●ナショナル・カリキュラムとナショナル・テストの設定。●ガバナー制度。●地方財政経営による財政権限の学校への委譲。●グラント・メインテインド・スクールの創設。●シティ・テクノロジー・カレッジの設立。●オープン・エンロールメント・システム導入。●大学制度改革。●ILEAの廃止。 |
|
1995 |
ブランケット氏(後の教育・雇用大臣/労働党) |
「試験による選別」と「グラマースクール」への反対の立場を強調。 |
|
1996 |
教育法(保守党政権) |
幼児教育へのバウチャー制度導入 |
|
1997 |
(労働党政権) |
上記制度を廃止 |
|
1999 |
(労働党政権) |
●サッチャー政権下の目玉であるGMスクール制度を廃止(すでにつくられたものはファウンデーション・スクールとする)。●グラマースクール存廃をめぐる地方投票の法律制定。 |
|
2000 |
|
3月。グラマースクール存廃をめぐる地方投票第一回実施。 |
争点の重要なものの一つとして、「グラマースクール」の存続について、つまり「2系統」に分かれるという「階層分化」に関する争いがみられるわけですが、それを取り出してみます(板書→次の図)。
グラマースクール等の推進か否か?
|
|
●1988年の教育改革で何がおきたのか?
次にサッチャー時代の教育改革で何が構想されたのか、どのようになったのか、どのような意味をもつのかをみていきましょう。配布した年表の1988年の改革の内容をもう少し詳しく記述したものが次の資料です。
※1988年、教育改革法の内容(主要な8項目)
|
改革された事項 |
概 要 |
日本との違い |
|
●ナショナル・カリキュラムとナショナル・テストの設定 |
「到達度」で拘束力が設定。教育の国家管理。 |
主要科目以外の時間制限なし。教育委員会による指導案点検などない。 |
|
●ガバナー制度 (学校理事会制度) |
学校・教育の独立・自治 |
コミュニティスクール構想があげられつつある |
|
●地方財政経営による財政権限の学校への委譲 |
財政上の自由→生存競争 |
各地の教育行政柔軟政策の検討中 |
|
●グラント・メインテインド・スクールの創設 |
国家による直接財政保障 |
-エリート教育をめざしているが--- |
|
●シティ・テクノロジー・カレッジの設立 |
学校民営化の実験(産業界) |
科学技術系の大学が促進中 |
|
●オープン・エンロールメント・システム導入 |
親の学校選択の促進 |
学区撤廃自由化が試みられつつある |
|
●大学制度改革(大学基金委員会管轄下とする) |
大学民営化へのステップ |
今後、急ピッチで進む |
|
●ILEAの廃止 |
ロンドン市政廃止に続く |
政治とのつながりはない(日本) |
まず、あくまでも簡単にコメントすることからはじめますが、先頭の「ナショナル・カリキュラム」というのは日本の「学習指導要領」をイメージしていただけますでしょうか。それまで国家が統一したカリキュラムを設定していなかったので、全体の「基礎学力」向上のために必要としたのですね。日本の制度はこういうときによく成果をあげている例として模範にされます。「影響」というのは相互の関係でもあります。しかし日本と違う部分もあります。いわゆる「主要科目」(教科)以外の時間などは制限をしていないですし、また現場の教育への影響力行使にしても実際には教育委員会による指導案の点検などまでは規定していないのですね。日本ほど徹底していないともいえますし、日本が管理が強すぎるという意見もありえるでしょうか。ちなみにもう一つこの「国家による関与」として特徴であったのは「宗教教育」の強化が指摘され、また「全体の集会」というものを義務づけたというものがありましたが、これらは事実上無視されています。宗教や押しつけは排除されていたのにこの時にサッチャーらがそれを求めた。これは現在における「公」心を強く求めたり、あるいは教育基本法を変えようとする日本の政府と同じ方針ですね。愛国心や道徳心、そして奉仕や「公」ということを重視する。前期の授業でもそのような反応(反動)について扱ったのですが、このような同じ問題が表れるということは、まさに世界的というより「人間」の社会的性質なのではないでしょうか。
次の「ガバナー」というのは「ガバーメント(統制)するもの」という意味で、つまり学校の「理事会」なりで独立・自治をしていくことを推奨するということです。日本でもいま「コミュニティー・スクール」構想があげられていて、これは米国のチャータースクールの考え方の影響も受けていますが、学校や教育の独立・自治という点では近似する。しかし「自由」というのは反面もあって、バウチャー制度や評価による厳しい生存競争が待っていることにもなるのですね。
三つめの「地方財政・・・」は配分される予算内で財政上の自由が認められたということです。公教育予算配当は日本でも厳しく決められていて(「公」という性質ゆえに)、それゆえに独自性などが制限されることもあったのですね。それをゆるすというのですから、上のガバナーと並んで非常に学校の裁量を認めた制度ともいえる。しかし生存競争という現実があると思います。日本でも各地の教育行政において柔軟な政策が検討されています。学校へその特色(アイデンティティ)が求められるようになってきた。その一方で少子化や学区撤廃による廃校・統廃合という結果もありえるわけです。
四つめは「グラント・メインテインド・スクール」。Grant Maintainedというのは、「政府による直接の資金が支給される」という意味です。「GMスクール」と略されますが、ようするに国家による直接財政保障がされる学校ということです。たんなる国立大学附属小中学校というものではなく、むしろ地方から離れた教育をする機関をイメージしています。「地方」というのは「労働党」勢力が強くあるので、そこから切り離すことを構想したのではないでしょうか。日本でもエリート教育は課題としてあげられますが、政策上の対立はあまりみられない事実だと思います。
次の「シティ・テクノロジー・カレッジ」はある意味では上の「国家直轄管理」とは逆に民間にまかせて運営させるカレッジです。産業界にその科学技術系のカレッジを運営させて、その分野を推し進めていくことをめざしています。これを単純に「ものつくり大学」と同じとは言い切れませんが、性質的に似ている部分もあります。実際に中曾根総理時代の臨時教育審議会の教育改革案でも「民間活力導入」が大きな課題になっていたので、きわめて時代性のあるものでした。
六つめの「オープン・エンロールメント」というのは学校選択のオープン化ということでして、親が自由に学校を選べるようにするというものです。1980年法で一部実施となっていたのですが、それを断行していくと。日本でも学区撤廃自由化が試みられつつあります。そういう意味で似ている。しかしすでに述べたようにこれは熾烈な競争もありえますね。
続いて七つめ。「大学改革」ですが、大学基金委員会の管轄にとすることで、大学民営化へのステップとしていくものです。内容はいくつもあるのですが、例えば新規採用の教員のテニュア(終身雇用)を廃止するなど人事面の改革も考えられています。それまでは誰もが終身雇用が保障されていたということで、そのことによる弊害があったのでしょうか。日本でも遠山プランやトップ30構想など、様々な大学改革構想が進められています。私や皆さんはその波をかぶる存在ですね。まぁ、本質的に各自が学ぶことを大切にしていければいいのですけれど。学生による授業評価などもここに入りますかね。
最後の「ILEAの廃止」は少し特殊とも思えます。ロンドン市政廃止に続いてと書きましたが、「インナー・ロンドン教育当局」という機関を廃止したのです。さっき「労働党の影響から切り離す」といいましたが、これも伝統的に強かった労働党の影響をカットするためであるといわれています。国家的に教育を管理する上で「あまりにも独自なもの」を排除したといえます。日本では政治上ではあまりみられないことではないでしょうか。もちろん地方選挙区の組み換えなどの策略がそれにあたるかもしれませんが、例えば政令指定都市の教育委員会を排除したりというのはおそらくみられにくいだろう。ちなみに、LEAと評されるのはLocal
Education Authorityで「地方教育当局」というもので別のものです。
以上のように、日本の教育政策にその影響を受けたと思われるものや、同質性をもつものがみられるわけです。ここに「イギリス」を考察する意味があるし、また「比較する」ということ自体の意義がわかっていただけるでしょうか。
次にその改革の結果(効果・影響)を考えていきます。
●教育改革の成果
1988年の改革のもっとも大きい変革として、「ナショナル・カリキュラム」と「ナショナル・テスト」の設定があげられます。次の資料(図)をみてください。
※「試験」で分配されるシステム
|
年齢 |
88年改革以前 |
88年改革以降 |
目的 |
|
7才 |
|
統一テスト |
学力到達度調査 |
|
11才 |
11才テスト |
統一テスト |
中等教育への配分/到達度調査 |
|
14才 |
|
統一テスト |
学力到達度調査 |
|
16才 |
GCSE |
|
一般中等教育資格試験 |
|
18才 |
Aレベル試験 |
|
大学入学資格のため受験 |
あくまでも単純にいえば、イギリスでは大学へ行くまでにこのように4~5回の全国一斉テストを受けることになるのです。私たちは日本を「受験熱の高い国」とイメージしていましたが、このイギリスの状況をみたらどうでしょうか。これは単に「階層差」を超えたレベルではないでしょうか。7才で学力到達度を調査するために全国で「統一テスト」を受ける。これは11才、14才でも同様に受験します。そして11才には志願する者はグラマースクール等へ行くためにと「11才試験」を受けることもできる。それと高校入学程度をはかる(資格)ために16才で「GCSE」試験を、また18才で大学入学資格のための「Aレベル試験」がある。
ちなみに「統一テスト」はSATともいいます(Standard Assesment Taskの略)。GCSEは、General Certificate of
Secondary Educationの略で、Aレベル試験はAdvanced Level Examinationと記す。このAレベル試験はシックス・フォーム・カレッジ2年めに大学入学資格を目的として受験するものです。
「ナショナル・カリキュラム設定」とは、<国家的な教育内容規定>から<国家的な学力試験>を課すということがセットになっていて、それによる「学力の向上」が目指されていますが、それ以上の意味や弊害がみられるとも思います。実は「学力向上」のためにかなり個人を管理し、教育を管理する力を強めているのではないかとみています。これだけ試験がある。たしかに他の改革で学校の自由裁量は増しているが、しかしそれは熾烈な生き残り競争でもあった。そこにこれだけ「到達基準」とクリアされたかをはかる「統一テスト」がある。まさに「日本」で(実態の分析は別にして)批判されたような画一性が出てくるのではないか。実際には「11才試験」、「GCSE」、「Aレベル試験」の結果は新聞紙上に講評されるのです(「リーグテーブル」という)。合格・不合格の割合が学校単位・地域で明確になる。到達基準をどう達成したかの責任が「上」からだけでなく、「周囲」からも問われるというシステムになっています。前にもいいましたが、「学校」の評価は「地価」の評価にまで及びます。いい学校がある地域に住みたいとは思うのですね。学区を自由化しても通えるかどうかの問題もある。大きい効果があります。
もちろん「弊害」と批判もあります。このサッチャー改革以降の「競争原理」は問題視されることもある。例えば実際の「授業」ですね。参考書によれば(略)この試験の重圧のために学期間の授業数に大きな弊害が出ているという。36週間のうち約10週が試験かその準備としてドリルをしたり、講義のない時期になっているというのですね。ただ日本と異なるのは「塾」という学外のシステムがないというかWスクールというシステムにはなっていないのです。まだ学校での学習評価を中心としているという違いがあります。「指導案の点検まではない」ともいいましたが、その意味では日本とは異なるのです。
以上のことについての評価には、二面性があります。
①一つは、この国家によるカリキュラムとテストというものは、いちおう、「達成度として客観化された数値」ではないかという考え方です。授業の最初にいいましたが、ある意味では公明正大で、教育成果の「透明性」を保障しているともいえるわけです。人によっては歓迎すべきものでもある。たしかにこれまでは「階層差」によって機会が与えられなかったものに「指標」がつくられた。そのような意味では「自由度」もあるかもしれません。
②もう一つは、中央による「教育の管理と統制」という面が指摘されます。透明性や自由とはいっても、現実的には「エリート育成」の機能を果たしているのではないかと。いやむしろそれを強化して不平等を再生産しているのではないかという指摘です。
しかし、実際には「評価、競争で管理される」ことで「自由」は事実上「制限」されていると私は考えています。
以上のように賛否の意見がある。なお、この1988年の改革は「いま」も問題なのです。皆さんは「サッチャー時代」は「保守党」だから、それはその後の「労働党」政権で変えられたと思われるかもしれない。さっきみた年譜だと「労働党」にかわり「グラマースクール投票」が行なわれ、「GMスクール制度を廃止」とある。たしかに変えられたものはある。・・・しかし、大きく変わっていないのですね。
ここに違和感を感じられるでしょうか。それとも「学力問題」は全世界の共通の課題だからといって納得されるでしょうか。たしかにそういう面もあります。しかしそれを「時代」のひとことですますのではなくもう少し考えていくことも必要です。①の面は、労働党の中も新しくなってきているというのもあって、新労働党が中産階級にシフトしようとしているのではないでしょうか。つまりさらに「階級・階層」内での分割という面です。「大学」を希望するというニーズはあるわけで、それをいかせる立場・位置にあるものは、批判・否定ではなくて肯定していくこともありえる。新自由主義のたちあがりなどがそれを示していないでしょうか。新局面ともいえる。もう一つは「世界」との関係にしても少し詳しくいえば(簡単にですけど)、「ヨーロッパ統合」という課題を抱えて、優秀な人材、あるいは労働力にしても形成していくということは切実なことであった。だからサッチャー保守党の遺物であっても、その「国家的管理システム」はブレアー政権(保守党)以後も継続されているのではないかということです。そのような意味で「時代」や「世界」との関わりで規定されているといえるわけです。
さて、(いわゆる)「イギリス」の教育については専門書も多くありますし、すぐれた研究者もたくさんいますので、今後も興味があったら学んでいくことをおすすめします。本当ならば「イギリス」のことでさえ1年ぐらいかけてみっちりと授業をやっていくべきでしょうが、この講義ではあくまでも「一つの資料」として分析対象にさせてもらうのみです。次回からアメリカ合衆国や、他の国を少しとりあげていきますがそれらも同様の「資料」です。この講義では「教育」と「社会」との関わりや、「社会」の奏で「教育」が果たす役割をとらえていくことと、いくつかの「考え方(方法)」を学ぶということが目的となっています。そのために簡単な、うすっぺらいものになることもありえますので、こちらも努力はしますが皆さんも興味をもったら自分で調べて深めていってください。
さて、次にいまみた「教育改革の成果」というものを「日本」の場合で考えていこうと思っています。弊害や多様な評価もあったし、それに国家の状態も周囲(外部)との関わりで変わっている部分もある。それならば、同じような「改革」を導入している日本ではどうなのかと、そしてそういうものを考えていく有効な方法はあるのかをみていきます。すでに配布資料にあるようなグラフを中心に、「教育社会学」(苅谷剛彦先生という有名な方の研究)の方法を紹介して考えていきます。
(※リアクション・ペーパー配布→回収)