|
諺と格言の社会学

| 人間はみんな自分の頭の中へ飛び込んで死んでし
まうんです。(椎名麟三)
|
|
1.落語「頭山」(1773)
山村浩二作のアニメーション『頭山(あたまやま)』は、2003
年の75回アカデミー賞短編アニメーション部門で、日本人として
初めてノミネートされ、また、国際アニメーション映画祭の短編
部門で最高賞のクリスタル賞を含む、6つの映画祭でのグラン
プリ受賞そのほか世界各国の映画祭で16入賞と70以上の映画
祭コンベンション作品に選ばれた大傑作である。
この作品は1773年に演じられたという落語『頭山』(別名、
「あたま山の花見」、「さくらんぼ」)をアニメ化したものである。
私の手元に「頭山」を収録したCD『正蔵改め林家彦六名演集』がある。それは正
味3分足らずの小噺である。この受賞が切っ掛けとなって、この落語が子供のた
めの絵本や童話本に取りあげられるようになった。
その内容を要約すると以下のようになろう
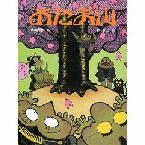 けちな男が、さくらんぼを食べたとき、もったいないということで種まで飲み込んでしまった。その種が体温の暖かさで腹
の中で芽を出し、だんだん成長し、頭を突き抜けて立派な木
となり、春になると見事な桜の花を咲かせた。すると、多くの
人が花見にやってきて、男の頭の上で、飲めや歌えのドン
ちゃん騒ぎをする。うるさくてたまらない。とうとう怒った男は
この桜の木を引き抜いてしまった。頭の真ん中に大きな窪
みができた。用足しに行ったときに夕立にあい、雨水が溜ま
った。けちってそれを捨てないでいたら、池となった。その内、その池に、鮒だの鯉
だのダボハゼだの泥鰌だの海老だの、魚が湧き始めた。すると、今度は子供たち
が釣りに来て、わめいたり、喜んだり、泣いたり…と頭の上で朝から晩まで大騒
ぎ。夜になると舟遊びとしゃれ込む大人がいて、これまた大変な騒ぎ。 その男は、
「こうるさくちゃあ…とてもたまらないと、頭の池に自分で身を投げた」。 けちな男が、さくらんぼを食べたとき、もったいないということで種まで飲み込んでしまった。その種が体温の暖かさで腹
の中で芽を出し、だんだん成長し、頭を突き抜けて立派な木
となり、春になると見事な桜の花を咲かせた。すると、多くの
人が花見にやってきて、男の頭の上で、飲めや歌えのドン
ちゃん騒ぎをする。うるさくてたまらない。とうとう怒った男は
この桜の木を引き抜いてしまった。頭の真ん中に大きな窪
みができた。用足しに行ったときに夕立にあい、雨水が溜ま
った。けちってそれを捨てないでいたら、池となった。その内、その池に、鮒だの鯉
だのダボハゼだの泥鰌だの海老だの、魚が湧き始めた。すると、今度は子供たち
が釣りに来て、わめいたり、喜んだり、泣いたり…と頭の上で朝から晩まで大騒
ぎ。夜になると舟遊びとしゃれ込む大人がいて、これまた大変な騒ぎ。 その男は、
「こうるさくちゃあ…とてもたまらないと、頭の池に自分で身を投げた」。
この落語に対し、いろいろな芸能評論家が、「民衆の健康な笑いを土台としたシ
ュールリアリズムの小品である」(尾崎秀樹)とか、「江戸の『SF短編』である」(小
島貞二)とか、「荒唐無稽のうちに哲理」があり、「無条件に傑作中のピカイチ」(飯
島友治)であるとか、「落語の演目の中でも最も非現実的な内容でありながら、強
いリアリティが感じられる傑作」(フリー百科事典『ウィペディア』)であるなど、と批
評している。
いったい、この「荒唐無稽」な小噺に宿る「哲理」とは何であろうか、また、「非現
実的な内容」が持つ「強いリアリティ」とは何であろうか。
2.『邂逅』(1952)と「頭山」
私が初めてこの落語「頭山」を知ったのは、椎名麟三の小説を通してであっ
た。
 「実子さん! 落語にこんな話があるの、知っていますか。ある男がさくらんぼを食べているとき、種子を一緒に
飲み込んでしまったんです。その種子は、体の中で芽を
出し、だんだん生長して、頭を突き抜けて大木に育った
んです。木の周りに池もでき、春になると人々が桜の下
で集まって、花見の宴を張る騒ぎなんです。しかしその男
は、とどのつまり、いろいろな理由から世をはかなんで、
自分の頭の中にできている池に飛び込んで自殺してしまったのですが、どういう風
にして自殺したと思いますか」 「実子さん! 落語にこんな話があるの、知っていますか。ある男がさくらんぼを食べているとき、種子を一緒に
飲み込んでしまったんです。その種子は、体の中で芽を
出し、だんだん生長して、頭を突き抜けて大木に育った
んです。木の周りに池もでき、春になると人々が桜の下
で集まって、花見の宴を張る騒ぎなんです。しかしその男
は、とどのつまり、いろいろな理由から世をはかなんで、
自分の頭の中にできている池に飛び込んで自殺してしまったのですが、どういう風
にして自殺したと思いますか」
実子は、オーバーのポケットに手を硬く突っ込んで、寒い風に耐えながら、黙って
安志を見た。この男は漫才や落語しか知らないのかしら。安志はいった。
「紐を縫ったときに裏返しにするでしょう。そのような仕方で自殺したのです。面
白いじゃありませんか。僕は、人間はみんなそうなんだ、と思うんですよ。めいめ
い自分の頭の中へ飛び込んで死んでしまうんです。それ が人間の不幸の原因じゃ
ないかと思いますよ。こんばんは兄さんの家にお帰りになった方
がいいのじゃありませんか」 が人間の不幸の原因じゃ
ないかと思いますよ。こんばんは兄さんの家にお帰りになった方
がいいのじゃありませんか」
実子は、肘掛け椅子の中にぐったりしていた兄を思い浮かべ
た。しかし、彼女は、真っ直ぐに安志を見ながら笑った。
「わたしが、自分の頭の中へ投身自殺しているように見えまし
て?」
「先刻、先に帰ってくれとおっしゃったとき、そう思っただけで
す」
「落語ですね」
「落語にだって真理はあります」
この引用文は1952年に発表された小説『邂逅』の一節である。この小説「邂逅」
は椎名麟三の行き詰まりを解決する転機となり、絶望からようやく自由になり、生
きてゆける自信を得させた記念碑とも言うべき作品であったと言われている。その
執筆の動機について、彼は遠藤周作との対談で次のように語っている。
「ただ、生きたかった。世の中のやつがどう言おうが知っちゃいないよ。(洗礼を
受けてから)一生懸命(聖書を)読んで一年もかかちゃった。 復活のところで、ル
カ伝の復活、バカン、バカン、ときたんだよ。自分の絶対と考えているものが全部
ひっくり返っちゃった。 キリストと出会うことができたことがうれしくてしようがないか
らさ、その事柄を喜びとして(『邂逅』を)書いたわけだ。」と(『三田文学』1966年
10月号)
真っ暗闇の中を、助けを求めてもがく椎名麟三は、愛読するドストエフスキーの
作品の持つ不可思議な魅力に引かれて、洗礼を受け、キリスト教に入信した。そ
して、彼は真剣に繰り返し聖書を読んだ。しかし、キリスト・イエスの十字架での死
は彼の絶望をさらに深めた。椎名麟三にとって、死は生を虚妄とする以外の何も
のでもなかった。死とは人間性の喪失であり、人間でなくなることであり、しかも、
絶対的なものであり、「いつまでも」続くものである。「いつもでも死んでいるというこ
とはニヒリズムの根底である。…いつまでも死んでいなければならないこととなる
と、死はどんなに重い意味を持っているのか。《いつまでも》が怖いのだ」。死の絶
対性と無限性の前に、彼は凝固し、精神的に死んでいた。イエスに助けを求めた
にもかかわらず、そのイエスが死を避けることができなかったのである。
聖書にはイエスは十字架で死んだが、「三日目に」よみがえったと書かれてい
る。しかし、「復活というのは、誰もがナンセンスと思う。この世の人は信じない。ぼ
くだって、信じない方に味方する」と、いつも読み飛ばしてきた。ところが、ある日、
その復活が「ドカン、ドカン」と大きな意味を持って彼を襲ってきたのである。その
時、彼にとって復活はどのような意味を持ったのか。イエスは十字架で死んだ。確
かに死んだが、しかし、「いつまで」ではなく、「三日間」であった。彼が絶対である
と思っていた死の絶対性を、イエスの復活は否定したのである。椎名麟三を凝固
させ、精神的に死なせていた、その死の絶対性と無限性を否定したのである。イ
エスの復活が意味しているように、死が絶対でないとすれば、今までの彼はなん
だったのか。彼が死を勝手に絶対化し、その意味付けによって、自己疎外を起こ
し、自由を失っていたのでである。復活のイエスとの実存的な出会いは、「自分の
絶対と考えているものが全部ひっくり返っちゃった」のである。
自己の考えを絶対化することによって自由を失い、生き生きと生きることができ
なくなった人間を、その自己絶対化から解放し、自由にし、生き生きと生かすため
に、イエス・キリストは十字架にかかり、そして復活して見せたのである。椎名麟三
はその「キリストと出会うことができたことがうれしくてしようがない」ので、『邂逅』を
書いたのである。
作家椎名麟三は、小説『邂逅』で、復活のイエスとの出会いで、「自分の絶対と
考えているものが全部ひっくり返」えり、自由にされた主人公安志を通して、いろい
ろなものに囚われて自由を失った人間の諸相を描いている。思想を絶対化するこ
とで動きが取れなくなった人間、自分を取り巻く困難な状況を絶対化することで無
力となった人間、、死を絶対化することで虚無に陥った人間。これらの人間は、復
活のイエスと出会うことによって自由にされた主人公から見れば、「自分の頭の中
に投身自殺」をしようとしている人々である。これらの人々は、多分、信仰を得る
前の椎名麟三の姿であったであろう。主人公の安志は、そのような人々のあり方
に同意を見せながらも、微笑をもって、彼らのこわばりを緩め、もっと自由に生き
生きと生きるようにと、側に立ち、手を差しのべる
3.『自由の彼方で』(1954)…椎名麟三の自殺未遂
『自由の彼方』にあった彼の半生記で、彼は彼自身の自殺未遂について次の
ように記している。
 「清作は、縄の一方の端を首に巻きつけて、他の一方に結ぶ。荒縄の、ぷんと甘い、かぐわしい、健康そうなにおいがす
る。その彼には、店頭に縄でつるした歳暮の新巻の鮭の格好
が思い浮かんでいる。しかしそれだけなのだ。何故なら彼に、
ほとんど毎夜のような、涙ぐましい戦いが始められているから
である。首に縄を巻きつけている彼は、片足を土間の方につ
き出し、もう一方の足も同じように上がりかまちから土間の方
へ離そうとする。だが、その片足は、一方のそれとは違って、
とりもちで上がりかまちにくっついてしまったようになかなか離
れないのだ。しかもその時になって、必ず便意を催してくるのである。……勇気を
搾り出そうとする。彼は、百度決心し、そしてさらに百度決心し、あらゆる種類の掛
け声を掛ける。だが、やがてこの滑稽な芝居は、諦められる。そして彼は、首から
縄をといて、いとも悲しそうな溜息をつく。」 「清作は、縄の一方の端を首に巻きつけて、他の一方に結ぶ。荒縄の、ぷんと甘い、かぐわしい、健康そうなにおいがす
る。その彼には、店頭に縄でつるした歳暮の新巻の鮭の格好
が思い浮かんでいる。しかしそれだけなのだ。何故なら彼に、
ほとんど毎夜のような、涙ぐましい戦いが始められているから
である。首に縄を巻きつけている彼は、片足を土間の方につ
き出し、もう一方の足も同じように上がりかまちから土間の方
へ離そうとする。だが、その片足は、一方のそれとは違って、
とりもちで上がりかまちにくっついてしまったようになかなか離
れないのだ。しかもその時になって、必ず便意を催してくるのである。……勇気を
搾り出そうとする。彼は、百度決心し、そしてさらに百度決心し、あらゆる種類の掛
け声を掛ける。だが、やがてこの滑稽な芝居は、諦められる。そして彼は、首から
縄をといて、いとも悲しそうな溜息をつく。」
彼は自分を取り巻く厳しい社会的・経済的・政治的状況をいかんともし難い現実
として絶対化することによって無力となり、また、死を絶対と意味づけすることによ
って虚妄となり、生きることに絶望し、文字通り、自ら命を絶とうと何度も試みた。
その行為は、復活したイエスと出会うことによって「自分の絶対と考えているもの
が全部ひっくり返った」彼から見れば、まさに落語『頭山』の描く男の行為であっ
た。その自殺は、自分の頭で考えたもの、頭で意味づけしたものによって、がんじ
がらめに縛られ、動きが取れなくなり、最後にはその「頭の池に自分で身を投げ
る」行為であった。しかし、幸いなことに、彼の自殺は未遂に終わった。
4.頭と足
彼の自殺は未遂であった。彼の自殺に抵抗したのは彼の足であった。上がりか
まちから離れることを拒否したのは彼の足であった。生を虚無とし、状況の困難を
絶対と意味づけした頭に対し、無意識のうちに、抵抗し、拒否したのは足であっ
た。私の一部である頭がでしゃばり、私の全体を支配しようとする傲慢さに、足が
果敢にも抵抗し戦ったのである。それでもなお、頭は自殺できなかった私を「生け
る屍」と軽蔑する。しかし、頭がどう軽蔑しようが、足は大地を踏みしめて生を肯定
し、頭に打ち勝っているのである。椎名麟三において、その傲慢な頭が自己の敗
北を認め、足の勝利を認めるのは、聖書を通して復活のイエスと邂逅したときで
あった。その聖書の箇所とは「ルカによる福音書24章」であった。
「イエスは言われた。「なぜ、うろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい。まさしくわたしだ。触ってよく見なさい。・・・」こう言って、イ
エスは手と足をお見せになった。」(ルカ24:38-39)
5.「自分を支える足の声 聞いて」(高 史明)
最近、35年ほど前に愛するひとり息子を自死で失った作家、高史明氏が「いじ
められている君へ 自分支える足の声 聞いて」という新聞のコラム(朝日新聞 06
/11/22)で次のように書いている。

「ある日、玄関に現れた女子中学生は、見るからに落ち込
んだ様子でした。『死にたいって、君のどこが言っているん
だい。ここかい?』と頭を指すと、こくりとうなずきます。私は
とっさに言葉をついでいました。
でも君が死ねば頭だけじゃなく、その手も足もぜんぶ死
ぬ。まず手を開いて相談しなきゃ。君は普段は見えない足
の裏で支えられて立っている。足の裏を良く洗って相談して
みなさい。…切羽詰った時こそ、足の裏の声に耳を傾けてみてください。
数ヵ月後、彼女からの手紙には大きな足の線が描かれ、『足の裏の声が聞こえ
てくるまで、歩くことにしました』と書かれてありました。」
6.死ぬまで生きる
最後に椎名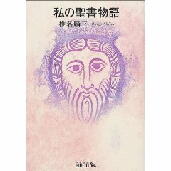 麟三の言葉を引用しよう。 麟三の言葉を引用しよう。
「死ぬまで生きる。死ぬまで十分に生きることができるよ
うにされている自分を知っているからである。それから
後のことは、私は知らない。天国に行くのか、地獄に行
くのか、それともどこへも行かなくて蒸発してしまうのか。
私にはわからない。ただ今の私は、今十分に生きられ
るようにされているので、死後のことなんかキリストに任
せてしまったのである」(『私の聖書物語』)
7.付録:椎名麟三の色紙
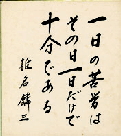  
参考文献
G.C.ホーマンズ(橋本茂訳)『社会行動』(誠信書房 1978)
橋本茂 『交換の社会学』(世界思想社 2005)「 第2章 一般命題」参照
飯島友治編『古典落語 正蔵・三木助集』 ちくま文庫 1994
山村浩二作品集 『頭山』 DVD GNBA-1138
林家正蔵名演集(6) 『しわいや 磯の鮑』 CD PCCG-00026
船橋克彦(文) 林恭三(絵) 『あたま山』 そうえん社 2008
『椎名麟三全集』 冬樹社 1970
|
|
|

インバスケット
|