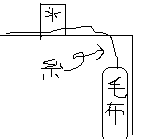星の下での殺人
プロローグ
赤い悪魔が全てを飲み込む。もうもうと立ち籠める黒い煙。何かの燃える臭いもしていた。辺りは真暗なためにその一軒だけがデフォルメされている。
「だ、ダメです」
一人の隊員が叫ぶ。
「火の回りが予想以上に速く、手を出せません」
隊員が報告している間にも、火の勢いはどんどん強まっていくばかりだった。窓に人影が見えた。野次馬が叫んだ。
「あっ、人がいる!女の子だ!」
年の頃、小学正高学年から中学生だろうか。お下げ髪の女の子がいるのが見える。彼女はしきりに助けを求めているらしく口をぱくぱくさせている。
「沙夜香(さやか)!」
母親は叫んだ。母親にしてみれば断腸の思いに違いない。
「どうか、どうか!」
彼女と同い年くらいの男の子が叫んだ。彼は手が真白になるほど手を組んで神に祈っていた。
「消防士さん、お願いです。沙夜香を救って下さい」
彼女の兄は泣き出さんばかりに懇願した。
「今、梯子車を呼んでいるよ。もう少し、待ってね」
消防隊員の一人は彼を安心させるために、努めて優しい口調で言う。しかし、三分掛かっても来ない応援に消防隊員たちも焦りの色が濃い。
「応援はまだなのか?」
隊長らしき男が苛ついた様子で呟く。飛び降りなさいとしきりに両親は少女に指示を出しているのだが、虚しいことに彼女の耳には入らないらしい。飛び降りる様子は微塵も見せない。野次馬の一人が口元を押さえる。窓際で助けを求めていた沙夜香と言う名の少女がついに力尽きたのだ。一家の目にはそれがスロー・モーションで映った。
「沙夜香!」
父親も狂ったように叫んだ。
出火原因は特に見当たらず不審火だということで消防は新聞社に発表した。警察は全力を上げて捜査しているが、未だ犯人は捕まっていない。あれから五年の月日が流れた・・・。
兄、俊行(としゆき)も高校二年になり、元気とは言えぬまでも落ち着いた生活をしている。
FILE1、飛行機(二月二十八日、午後十二時三十分)
飛行機はぐんぐん陸を離れる。帝都学園高校二年生一同は、わあという興奮の声や、見て見てと興奮したように歓声を上げた。彼女、浅香萌の胸も期待で一杯だった。九月のテロ事件以来、ずっと危惧されてきた沖縄への修学旅行がついに実現したのだ。
彼女は飛行機には何回も乗っていたので気流などで飛行機が揺れる事には慣れていた。アメリカへは二回程行っているし、語学研修で夏休み返上してニュージーランドまで出かけた。また、家族では中国の上海、北京、南京へも行った事があったので、飛行機が離着陸する際、クラスの殆どが歓声を上げたが、萌だけはそれを上げなかったのも納得できるだろう。
ただ、上空から自分の街を見下ろすのは実に爽快な気分である。まるで神様になったような感覚になるのだ。
「わあ」
と名古屋から離陸する際、そう歓声を上げた。そして、彼女はあの飛行機に乗った時に味わう胃袋がふわっと浮くような感覚を楽しんだ。萌の隣に座っている大野恵美(おおの めぐみ)は、
「落ちたりしないよね」
と不安げに言う。
彼女は漆黒の髪の毛を肩まで伸ばし、ポニー・テールにしている。細面の顔に桃色掛かったフレームの眼鏡を掛けていた。小柄で背は低く、眼鏡を取ると美人である。萌は何故コンタクト・レンズにしないのか不思議に思った事があった。丸っこい目は愛敬を醸し出している。落ちたりしないかという問いに萌は笑って、
「大丈夫だって」
やがて、高度も落ち着き、シート・ベルト着用サインが消えると記者会見さながらに飛行機の中で次々とフラッシュが焚かれた。
「ほら、ここまで来ると安心よ」
怯えていると思ったのか、萌は恵美に話し掛ける。
「おい!見ろよ。雲の上だぜ」
同じクラスの中尾圭志(なかお けいじ)が興奮したように叫ぶ。彼は細身で長身、髪はいが栗のように逆立っている。顔は端正で、均等が取れていた。
「ん?」
と軽く返事をして、『南海の魚』と言う釣りに関する本を読んでいた山野俊行(やまの としゆき)は窓の外に目をやる。彼は理知的な眼鏡をかけており、隣の中尾圭志とは正反対の性格だった。ただ、体型は好く似ていた。細身ではあるが、背は圭志ほど高くはない。
「本当だ」
と淡白な返答を返し、また本の字を追い始めた。圭志は舌打ちをすると、また窓の外に見入った。この釣り狂とでも思っているのだろう。実際、俊行は旅行バッグにクーラーボックス、釣り竿、ルアーなど釣り具一式を持っていた。
しかし、その景色は単調なので、しばらく経つと彼は関心を示さなくなった。萌とも好く話すので、理解を求めるように彼女に、その事を話すと少し苦笑して、
「山野君って釣り好きよねえ。本当に」
と言った。圭志は横から冷やかすように、あるいはからかうように、
「こいつの頭の中は釣りしかないんだぜ」
俊行はそれに抗議するように、
「そんなことないよ。僕の頭は・・・」
と言いかけて口をつぐんだ。
「僕の頭は・・・?」
ニヤニヤして圭志が言った。そこで、
「お飲み物は何が宜しいでしょうか」
スチュワーデスがトレイを運んで、やってきた。
「えーと・・・、オレンジ・ジュース下さい」
と萌は頼んだ。やがて、透明なグラスにオレンジ・ジュースが注がれる。ショート・ヘアの少女は礼を言って、軽く会釈した。
「僕、紅茶」
熱々の紅茶にスティック・シュガーとクリープが添えられ、俊行の前に運ばれた。
「熱いのでお気を付けて、召し上がって下さい」
スチュワーデスが行ってしまうと、
「で、何だったっけ?」
先ほどのドリンク・サーヴィスで手に入れたジュースに口を付けながら、恵美が言う。
「山野君の釣りの話」
失礼にも退屈そうに恵美は一つあくびをした。いや、わざとだったのかもしれないと萌は彼女を見ながら思った。
「でも、一つの事に熱中するのは好い事だと思うよ」
萌が老成めいた事を言う。俊行もそれに乗って、大袈裟に首を縦に振った。
「私の幼なじみにも推理小説好きがいるのよ。でも、彼それが高じて・・・」
「推理小説家になったのか!?」
圭志が驚いて叫んだ。萌は笑って首を振る。
「ううん。彼・・・」
「警察もお手上げの何事件を解決してる、でしょ?」
恵美が口を挟む。萌は恥かしそうに顔を赤らめる。別段恥かしい事なんてないのだが、“彼”の話題になると赤くなるのだ。
「う、うん」
俊行の顔が何故か一瞬、曇った。
二時間余りが経過し、沖縄上空に着いた。雨が降っており、萌は溜め息を付いた。恵美は漫画を前の女子から借りて読んでいたし、俊行は魚の本を読んでいた。また圭志は高鼾をかいて寝てしまっている。退屈なので仕方なしに窓の外を見ているのである。
「最悪の天候かしら」
窓の外を見て萌が鬱陶しげに呟いた。
FILE2、万座毛(二月二十八日、午後二時三十分)
那覇空港からバスまでは雨が降っていたので傘をささなければならなかった。しかし、万座毛(まんざもう)に着いた時は雨もすっかり上がり、南国に相応しい碧空が広がっていた。
「先生、晴れて好かったですね」
髪の毛を長く垂らした藤井啓子教諭にそう萌は言った。
「本当、午前中までは雨が降っていたものね」
感慨深げに藤井教諭は萌の言葉に同意する。
「海が綺麗よ!」
興奮したように突然、恵美が叫んだ。万座毛は海岸ではなく、切り立った崖なのだが、崖から見下ろす真青な海は実に壮麗である。切り立った崖は、まるで自殺の名所さながらだ。
「ここから多くの人が自殺したんだろうな」
萌と恵美を怯えさせるために、さも怪談を語る風に中尾圭志は言った。しかし、高校生にして数多くの死体を見ている浅香萌はそれをまるで、アイドルの話のように受け取った。
「やだー。もう」
彼は気分を害したのか、むっとした口調で
「あれ?知らない?俺、霊感あるんだよ」
「はいはい、じゃあ私の背後霊でも見てもらおうかしら」
全然信じない萌は笑って言う。
「ほらっ、そこ。後ろに霊が!」
早口に圭志が言った。その時、恵美と萌の首筋にひんやりと当たる物を感じた。これには流石に萌も焦ったらしく、さっと後ろを振り向いた。恵美に至っては、絶叫する始末だった。
「きゃあ!」
辺りの視線が彼女に集まったのは言うまでもない。藤井教諭は、慌てて駆け寄った。見事なチーム・プレイだった。
「いやあ、ごめんなさい。ちょっと驚かすつもりが」
中尾圭志はきまり悪そうに藤井教諭を見る。藤井教諭もほっと安堵の息を吐いた。
「なんだ。そういうこと」
「でもどうしたの?その氷」
萌が尋ねると釣り狂は目を輝かせて、
「僕のクーラーボックスは最新式なんだ」
と言って肩に掛けていた青いクーラーボックスを開けた。萌が覗き込むと、奥には家庭用冷凍庫のように氷を作る空間がある。
「なるほど。これで氷を作ったってわけね」
「その通り」
意外なほど真面目な顔をして、山野俊行が言った。
「さあさあ、もう時間よ。急ぎましょう」
と藤井教諭は四人を急き立てた。萌は地面にできた水溜りを飛び越しながらバスに向かった。
FILE3、ホテル(二月十九日、午後六時)
萌たちはそれから戦没者異例の碑として世界的に有名なひめゆりの塔や、二千円札の柄として有名な朱里城、そして戦争体験談を老人から聞いて、ホテルに戻った。ホテルはどっしりとした感じのいい白い建物だった。
「オート・ロックだから気を付けろよ」
萌は笑って大丈夫というと、係の金成陽介(かなり ようすけ)教諭は、
「でもな。毎年一組はいるんだよ」
親しみやすい先生と皆から人気のある金成は、さも残念そうに言った。彼はバスケット部の顧問で、背が高く、色は適度に小麦色に焼けている。
「ははは、大丈夫ですって」
と萌は笑って言った。
「あっ、それから海に行ってもいいですか?」
「いいよ。ただし夕飯七時三十分までには戻ってこいよ」
萌はルーム・キーを受け取ると恵美と自分たちの部屋、七階に行った。
部屋の扉を開けると、ウェディング・ドレスのように純白な白い壁が見える。そして、開けた空間に簡素だが寝心地の好さそうなベッドが二つ並んでいる。このホテルは海岸に面しているため、窓の向こう側は沖縄の青い海が一望できる。恵美も、萌もこの絶景に感激したようである。
「わあ、海だよ。真青」
しかも、沖縄の海は青い部分と水色の部分との境目がくっきりと見える。
「海、行く?」
恵美の問いに三十分位休憩してからにしようと提案した。萌はくたくただったのだ。彼女は白いスニーカーと靴下を脱ぎ捨て、雪のように白いシーツにダイブした。
「よほどお疲れなのね」
恵美はその萌の行動を見て、クスリと笑った。
「三十分経ったら言ってね」
まるで半分夢の世界にいるような、トロンとした目で言った。はいはい、と軽く返事をしたが、恵美は疲れている萌を起こさずにいるつもりだった。恵美はその日の彼女の行動を思い起こしてみた。
恵美は独り力なく微笑した。朱里城の売店でドリアン・ジュースなるものを発見して、珍しいと喜んでいたのは萌だったし、皆がへたばってるにも関わらず一番、朱理城内を見学していたのも彼女だった。
格闘技をやっているとは思えない程、華奢で色白な体付きのその少女はすやすやと寝息を立てている。その寝顔は、天使に喩えても差し支えないだろう。無邪気で純粋で、とても可愛い寝顔・・・。恵美は夕食の三十分前位に起こせば好いだろうと思った。
FILE4、圭志の部屋(二月二十八日、午後六時過ぎ)
「少し眩しすぎてくらっと来ただけだよ。心配しないで」
俊行は弱々しい微笑を口元に貼りつけた。緋色の太陽が今、正に落ちていこうとしていた。陽はまるで海を焼き尽くしているかのように、真赤に染めている。あるいは血を流したかのように。圭志がカーテンを閉めようとすると、引き止めた。
「大丈夫だって」
俊行がそう言う。その口調には強い意志がみなぎっていた。
「そうか?」
友人の体調を気遣って圭志が言った。
「ああ」
俊行は手に持っていたコカ・コーラのプルタブを起こした。ぷしゅっという音がして、泡が零れる。実を言うと、俊行は彼に対して嘘をついていた。眩しくて眩暈がしたのではない。彼は赤色、それも火のように赤い色を見ると眩暈を起こしてしまうのである。今日の夕日はまさにそれだった。
そもそもの原因は、五年前の放火事件に始まる。妹、沙夜香の死ぬ瞬間を見てそれからである。火がこんなに怖くなったのは。
「僕、少し疲れたみたいだから一寝するわ」
圭志は明らかに戸惑った様子で、
「お、おう。根岸が来た時のためにロックはかけないでおくぜ。俺、売店で何か飲み物買ってくるけど何かいるか?」
「いらない」
俊行は短くそう言うと布団の中に潜り込んだ。
「ああ、そうか」
中尾圭志は振られた直前の相手に言うように呟いた。圭志がドアの向こうへ行ってしまうと俊行は一人、偏頭痛のようなズキズキする痛みに耐えていた。医務の教師に言おうかとも考えたが、それ程の痛みでもなかったのでそうしなかった。彼は疲れすぎたのだろうと思ったのだ。
ミノムシのように布団に包まり、ぼんやりと時計を見つめる。ホテルのディジタル時計は六時十五分。彼は寝られずに、仕方なく布団からもぞもぞ這い出た。そして釣りの本を取り出すと、頭が痛いのに関わらず読み始めたのだ。
ドアが開く音がした。ふっと、俊行は注意を本からドアに向けた。だが、視線は本だった。彼は圭志が売店から帰って来たのだろうかと考えた。
「ういっす」
男子にしては高めのテノールの声だ。根岸一は俊行とも割と仲が好い。体格もほっそりとしているが、バレー部であるため背は高い方だ。髪の毛は坊主のように薄く、唇も薄い。悪戯好きで、滑稽な事をよく言う。宗教の教科書の釈迦の絵にサングラスやピアスを書いたりと色々、突飛な事をやっては笑わせる。
「山野ー」
始め、根岸はトイレの便器に呼びかけた。
「いや、そんな所にいないだろ」
と言う声もする。どうやら圭志も一緒のようだ。俊行は安堵の息を吐いた。淋しかったのである。
「大丈夫か?」
圭志が心配そうに言う。
「狂牛病か?」
と言ったのは勿論、根岸一だ。
「いや、違うから」
圭志がそう言う。だいぶ治ったと圭志に言う。
「好かった」
圭志は安堵の息を漏らした。しばしの沈黙。圭志は売店で買ったアクエリアスのキャップを捻った。だが、飲みはしなかった。
「あっ、そうそう。僕トランプ持ってきたんだ」
と思い出したように俊行が言った。というのも、一が暇そうだからだ。圭志がスポーツ・ドリンクを飲みながら、携帯でメールを送っている。
「おっ、じゃあ大富豪でもやろうぜ」
一は身を乗りだしてそう言った。実際、彼は暇で暇で仕方なかった。テレビも名古屋とはチャンネルが違うし、持ってきたエムディー・ウォークマンも友人に貸してしまっている。携帯でメール送るにしても充電器を持ってきていないのでバッテリーは無駄には出来ない。
「圭志はやるか?大富豪」
一は圭志に訊いた。
「おお、やるやる」
三人の元に手際よくカードが配られる。
「お金は?」
俊行が訊くと一は大富豪が十円を大貧民に渡すと言った。
「オーケー」
集計は後だと言う事は暗黙の了解になっていたので、ホテルの机の上にあるメモ用紙を一枚取った。これから起こる事件に多少、関わるので試合運びを描写することにしよう。
「おっ。強いよ。二が百枚もある」
俊行は抱腹絶倒した。
「いや。ないだろ。どう考えても」
圭志は冷静に突っ込む。ジャンケンの結果、俊行が一番最初になった。
「僕からだね」
俊行は確認した。
「まずは堅実に」
と言って三の二ペアを出した、その後、圭志が、
「じゃあ、俺も」
四を出した。
「俺も堅実に行こう」
一はジャックを出した。
「おい!どこが堅実なんだよ」
と圭志が突っ込む。俊行はクイーンを出した。圭志はキングを出すのだが、圭志に最強カード、二を出され、流されてしまった。一は次にエースの三枚出しをした。
「俺の名前は一だからエース」
単に二が二枚しかなかっただけだろう、と俊行は肚(はら)の中で思った。そして、彼が十を四枚出すと、俊行は最悪と笑いながら言った。 大貧民にならなければ好いのだし、もし、大貧民になったとしてもマイナス十円なので、さほど財布に支障はない。
「パス」
俊行は僕も、と言う。
「パス、パス、パス。ヤマハパス」
急に一がコマーシャル・ソングを歌い出した。俊行は大袈裟に身震いしてみせると、一は肩を竦める。
「不発だったみたいだな」
圭志が少し勝ち誇ったように言った。
「うん、米軍が落とした不発弾なの」
と根岸は言いながらを九を出した。俊行は三を出すべきではなかったと少し後悔した。その後も試合は順調に進み、四ゲーム目に突入した。
「おっ。もう五分前だ。大宴会場に行こうぜ」
五ゲーム程した後、ホテルのディジタル時計が六時二十六分となっているのを見て根岸一は言った。
FILE5、大宴会場(二月二十八日、午後六時三十分)
生徒は沖縄料理が出る物とばかり思っていた。しかし、蒸し餃子などの中華料理やカレー・ピラフなどのいわゆる「普通の」料理だった。ホテル側がゴーヤー・チャンプルは高校生の口には合わないと配慮した結果なのかもしれないと眠たい頭で浅香萌は考えた。起きたばかりの彼女はまだ目がトロンとしており、座りながら寝ると言う芸当が出来そうだった。
「浅香さん、隣、いい?」
浅香萌は事の事態を理解するのに五秒は掛かった。もう一度、俊行が言うと、目が覚めたように我に返った。
「全然平気」
萌はあくびを一つすると、水で口の中を湿らせる。
「ここ、結婚式場なのかな」
圭志が今いる部屋を見回して言う。雰囲気のいい純白のテーブル・クロスのかかった丸テーブル、上に設置したカメラなど結婚式場を思わせた。舞台が設置してあり、先生がこれからの予定を説明している。
「ええ、夜十時までは自由時間です。海に行っても構いませんが点呼の夜十時までには各自部屋に戻ってるように」
それから、明日の起床時間を告げて、食べ始めた。
「沖縄料理を期待してたのに」
萌が口の中で不平そうに呟いた。彼女はゴーヤー・チャンプル、ミミガーと呼ばれる豚の耳、沖縄ソバを期待していたのだ。更に言うなら、某ハンバーガー・ショップの沖縄限定、ゴーヤー・バーガーも。
「まあまあ。そう言わず」
恵美が口にピラフを運びながら言う。カレーの風味が口いっぱいに広がった。
「まあ、不満はないんだけどね」
自分の言った言葉で友人に迷惑を掛けていないだろうかと危惧した萌は、慌てて言う。
「部屋も最高だし、海からも見えるし・・・」
「そうそう、それに沖縄料理なら明日食べれるじゃん」
萌はピラフを口に運びながら無言でうなづいた。今、口を開けると食べかけピラフが出てきてしまいそうだからである。
「それに海も見えるし」
俊行は付け足した。
「あっ、そうそう」
彼は居住まいを正してこう言った。呼びかけられた浅香萌は、
「何?」
「今日の夜、九時半いい?」
萌は少し迷ったが、オーケーした。というのも愛の告白ではなかろうかと不安に思ったからだ。
「え、ええ」
「おっ、ナンパか?」
冷やかすように圭志が言った。迷惑そうに俊行は、
「違うったら」
「じゃあ、告るの?」
「それも違う」
冷淡に恵美の発言をあしらった。その冷淡ぶりに、その場にいた生徒たちは哄笑した。発言者は、はにかんで微笑をした。その後、食卓の話題は、ケミストリー、ポルノ・グラフィティなどの歌手の話題やドラマの話題に移った。
FILE6、海辺(二月二十八日、午後九時半)
「なあに?話って」
俊行に呼び出された萌は訊いた。辺りは真暗だが民家の灯などもあり、緑色のシートが掛かっているのが見える。工事中だろうか、と萌はぼんやり考えた。
「う、うん。実は・・・」
「何?」
やはり恵美の言う通り愛の告白だろうか、と思った。それだったらごめんなさい、とはっきり言えるかどうか心配だった。しかし一方で、しきりに時計を気にしている俊行を見て、誰か、例えば大野恵美と共謀して自分を驚かせるつもりではないだろうか、と身構えた。例えば一定時間になったら、恵美が出てきて驚かせる・・・。と言うような作戦に違いない。
「もしかしたら、点呼の時間を気にしてるかも知れないわね」
推理をする時はあらゆる可能性を考慮に入れなくてはならない事を有沢翔治が言っていた事を思い出して、呟く。
「でも、そうだとしたらなぜ八時半なんかに?」
萌の頭に疑問が残る。きっと彼の事だから釣りをしていたのだろうと思ったが、もしそうだとしたら、もっと早い時間に誘っても好いはずだ。
「ということは釣りじゃないわね」
あの時、なぜそんな点呼ギリギリの時間帯に呼び出すのか訊いておけば好かったと後悔した。「後悔先に立たず」とは好く言ったものだ、と浅香萌は自嘲的な微笑を口に貼りつけた。
「ねえ」
浅香萌は勇気を出して声を掛けた。間の抜けた声で俊行は、
「ん?何?」
「何で点呼ぎりぎりの時間に呼び出したの?」
鴎のものだろうか、白い羽根が空からふわりふわりと萌の足下に落ちた。
「ちょっとね」
俊行は悪戯っぽい笑みを顔一杯に湛えて、答えた。何か謀んでいると萌は確信した。そのようなことを話しているうちに俊行の携帯電話が急に鳴り出した。失礼、とジェスチュアで示し電話に応対する。
「もしもし」
あからさまに不機嫌な声を出す俊行。が、みるみるうちに焦りに変わった。
「お、おい。僕を驚かすつもりだよね」
自分に言い聞かせるように彼は言った。
「嘘だろ!圭志君。自殺だなんて、お、おい」
なるほど、こういう寸法かと萌は思った。中尾圭志が自殺した、と言って現場に着いてみたら彼がにこにこして立っている。
「もしもし!もしもし!」
俊行は電話が切れたと浅香萌に言った。彼の声は震えていた。山名俊行は演劇部なので、演技だろうと萌は思った。
「圭志君が・・・・、自殺するって」
ドッキリだと鼻から信じてる萌は動揺しない。
「私、騙されないんだから」
と呟き、胡散臭そうに疑いの眼差しで俊行を見つめた。
「ん?どうしたの」
焦っている様子で俊行は訊いた。浅香萌は「ドッキリでしょう」と言おうと思ったが、ここは手に乗ってやるかと思い直し、途中で口を噤(つぐ)んだ。そして、気付いてた事を告げ、中尾圭志、山名俊行・・・もしかしたら大野恵美も・・・を落胆させるつもりだ。
「浅香さん!あれ」
と言って圭志が工事中のビルを指差す。それは正に死体が落下する瞬間だった・・・。いや、正確に表現するなら、彼らは落ちる人影を見たと記すべきだろう。これでドッキリではないと解って、浅香萌の顔も蒼ざめた。
「今の人影・・・」
「浅香さんは先生に連絡を!」
「う、うん!」
先生まで巻き込むはずないと考えた萌は藤井教諭の所まで走っていった。
FILE7、藤井教諭の部屋(二月二十八日、午後九時四十五分)
「藤井先生」
相部屋の鈴木美香が呼びかける。まだ今年、教員になったばかりの新米教諭だ。担当は国語。髪をポニー・テールにしており、まだ学生気分が抜けきらないのか、髪の毛は茶色いものがちらほらと見えている。
「ん?何?」
藤井が呼びかけに応える。
「今晩の見回りの事なんですが、変わっていただけますか?私、疲れて少し仮眠を取りたいんです」
見回りと言うのは生徒が夜中にうろうろしていないか確かめるもので、交互に二時間づつ交互に行われる。つまり、夜十時以降は部屋を出る事が不可能となるのである。
「ええ、別に構わないけど」
「すみません」
鈴木は恭しく頭を下げた。
「私は夜十時から十二時に見回ればいいわけね」
藤井が念を押した。国語教師はそうです、と短く答える。
「オーケー」
しばし、沈黙。その沈黙を破るかのように、
「コーヒーでもお入れしましょうか?」
と鈴木がポットに向かう。自分の代わりに見回ってくれる藤井に申し訳なく思ったからだ。
「あっ、ありがとう」
藤井はテレビの天気予報を考え込むように見ている。明日の天気が気になるのだ。
「明日の沖縄は好く晴れるでしょう」
とサラリーマン風の天気予報士が告げると藤井は安堵の息を漏らした。生徒に取って、一生に一度の大イベントなので雨が降って欲しくないと願っているのだ。
「明日、晴れるみたいで好かったですね」
コーヒーカップを運びながら鈴木教諭は言った。
「ええ」
と短く答え、頂きます、と言うようにコーヒーカップを上に掲げた。
「まあ、雨が降っても私たちにはどうしようもないんだけどね」
藤井が言う。
「まあ、そうですよね」
鈴木も肩を竦めて言った。道化て藤井が、
「テルテル坊主を飾っておくとか」
藤井は自分の腕時計を見て、呟いた。
「もうそろそろ、点呼ね」
「あっ、じゃあ、私、藤井先生が点呼に行っている間、お風呂に入ってて好いですか?」
別に断ることもないのに。と藤井は思いながら、
「好いわよ」
その時、扉が勢いよく開いた。鈴木美香は風だろうか、と思って窓に目をやる。閉まっている。幽霊かと言う考えが空港のロビーで読んだホラー小説から一瞬、沸き上がった。しかし、そんな馬鹿なと自嘲して、ドアに向かった。
ショート・ヘアの快活そうな生徒が立っていた。顔は蒼ざめ、肩で息をしている。細身の身体の小さな心臓がドクドクと激しく波打っているのが聞こえるような錯覚に陥った。
「浅香さん。どうしたの?そんなに急いで」
鈴木はしばらくの沈黙の後答える。落ち着かせようとしたからではない。単に名前が思い出せなかったからだ。しかし、それは無理もない事だった。鈴木美香は彼女のクラスを教えてはいないのだから。
「鈴木先生」
彼女は喘息患者のように苦しそうに言った。
「中尾君が・・・」
「中尾君がどうかしたの?」
新米教師は風邪で倒れたのだろうかと想像した。
「中尾君が・・・」
「うん」
鈴木は苛立ちを抑えて優しく接した。
「自殺しました」
そう言い終えるとまるでマラトン(ギリシャの英雄の一人。ペルシャ軍を打ち破った事をアテネまで伝えた直後、死んだ)のように倒れた。
FILE8、圭志の部屋(二月二十八日、午後九時四十五分)
根岸はベッドに横になって漫画を読んでいた。圭志も俊行もどこへ行ったのだろう。もう点呼の時間なのに。と訝っている所へ、室内の電話が鳴り響いた。禁止されているのに妙だと思ったが大方、誰かが間違って掛けてきたのだろうと考えた。
「はい。もしもし」
と受話器を取り上げ不安と不機嫌さが入り混じった声で応対する。
「あっ、根岸君?」
鈴木教諭だったので一安心した。これで、怖い生活指導部からのお叱りは免れると。
「どうしたんですか?」
根岸は急な電話を不思議に思って言った。
「中尾君は?」
「圭志ですか?あいつなら」
鳩のようにクックと笑って、
「今頃、廃屋にいますよ」
「廃屋ね。ありがとう」
「どうしたんですか?」
再び鈴木に問う。一瞬、戸惑ったように、沈黙が流れる。
「何でもないわ」
妙によそよそしかった。根岸は何か隠し事をしていると直感的に感じた。
「じゃあね」
電話の相手が一方的に切ろうとしたので、
「もしもし」
と慌てて呼びかける。しかし、ツーツーと言う音が虚しく彼の耳に谺するだけだった。
「何かあったな」
と彼は独白する。しかし、何があったのだろうか?沖縄名産の酒、泡盛を呑んだのか?いかにも、中尾のやりそうな事だったが・・・
「いや、違うな」
と呟く。泡盛は三日目の国際通りでのショッピングでしか買えない事になっているからだ。それに、もし彼が教師を出し抜いて泡盛を買って、呑んだとしても厳重注意、もしくは精々停学処分で、根岸の所には直々に教師から電話など掛かってくるはずがないのだ。
「俊行なら何か知っているかもしれないな」
携帯を取り出し、慣れた手付きでメモリから「山名俊行」を探し出し通話ボタンを押した。ワン・コール、ツー・コール・・・五コールしても出ない。次第に根岸は苛立ってきた。
「はい、もしもし」
十コール目でようやく彼が出た。
「遅いぞ、何分待たせればいいんだ」
根岸は毒突くが、強張った声に興味を示し、
「圭志に・・・、何かあったのか?」
と尋ねる。
「落ち着いて聞いてね、根岸君」
「俺はいつも冷静だぜ」
しかし大阪人バリにボケていられるのも、ここまでだった。
「中尾君が・・・死んだ」
一瞬、根岸は何を言っているのか理解出来なかった。そして、彼と中尾のドッキリだと思った。しかし、先ほどの担任の態度を考えると、どうやら死んだというのは嘘ではないようだ。
「えっ?」
しばしの沈黙の後、聞き返す。
「だから、死んだんだよ」
「死んだ?自殺したのか?」
陽気に訊き返す。どうやらドッキリだと信じているらしい。
「解らない・・・。他殺かもしれない・・・」
声は震えている。根岸の頭に顔色が真蒼な俊行の姿が想像された。
「おいおい、俺を騙そうったってそうはいかないぜ」
彼の死を受け入れたくないのか妙に明るい声で答える。
「騙してなんかいないよ。僕の言う事が信じられないのも解るけど」
根岸は口許に引き攣った笑いを浮かべた。
「は、はは・・・今、お前どこだよ」
廃屋だと告げると根岸はそこまで走って言った。
FILE9、廃屋(二月二十八日、午後十時十五分)
藤井教諭と根岸、そして第一発見者の一人、山名俊行は廃屋にいた。昨夜降った雨のせいで廃屋の屋上の窪んだ所には水が溜っている。皆、一言も喋らなかった。重苦しい沈黙。
「あ、あのう・・・」
俊行は何か言おうとする。藤井教諭は目で促した。
「毛布くらい掛けてあげたらどうでしょうか?死んだとは言え、圭志が可哀想ですよ」
友人想いのこの発言も、許されなかった。なぜなら、死亡推定時刻が狂ってしまうからである。変死体はむやみに現場の状況を変えると、警察の捜査に混乱を来す恐れがある。変死体と言うと、一般の人々は他殺体しか想像しないが、自殺体、事故死の死体も変死体に含まれるのだ。
「そうですか。残念です」
と俊行は呟いた。やがて遠くでサイレンの音が聞こえた・・・。「沖縄県警」とボディに掛れたパトカーからは二人の刑事が降り立った。一人はがっしりとした筋肉質の体躯の刑事、もう一人はひょろりとした痩せ形の刑事だった。
「島袋です」
ボディ・ビルダーにもなれそうな筋肉質の刑事が挨拶した。顔は浅黒くいかにも沖縄育ちであるかのように思える。一方の澤村と名乗る警部補は本州の方から転勤になったのだろう。色白で誰もが想像する沖縄県民のイメージとは異なった。
三人は挨拶と簡単な自己紹介を終えると、島袋刑事は、
「ほう、修学旅行生さんですか」
「ええ。まあ」
藤井教諭も相手に合せて気のない返事をする。澤村警部補はハスキー・ヴォイスで、
「では、お話を伺いましょうか。まあ、自殺で間違いないでしょうが」
根岸、藤井も山名俊行に視線を向ける。この状況は彼が最も好く知っているのだから。俊行は深く息を吸って、気分を落ち着けると、
「はい、浅香さんと一緒に八時三十分ごろ海辺へ出かけました。彼女とはクラス・メートの女の子です」
喉がひりひりするのを堪えながらの発言だった。そうは言っても、風邪などではなく、獣の慟哭のような凄じい叫び声を上げながら走ったからだ。そうでもしないと気が狂いそうだったから。
「ほう」
これには澤村警部補も驚きの声を上げた。別に十七、八の高校生が女の子を夜の浜辺に呼び出して、何が意外なのだろうかと藤井は思った。しかし、この緊急事態にそのような茶々を入れるべきでないという事はもちろん解っていた。
「つまり、愛の告白をするためにですか?」
島袋刑事は無遠慮にずけずけと言った。恐らく、藤井もそう思っただろう。
「いえいえ。違いますって」
と俊行は否定した。目で根岸に刑事たちに説明するよう求める。俊行は自分で要領よく説明出来る自信がなかった。
「俺たち・・・いや、僕たちが浅香さんを呼び出したのは、彼女を少し驚かそうとしたからです」
「驚かす、とは?」
澤村は意外そうに眉を吊り上げる。
「はい、僕たちの計画はこうでした。まず山名君が浅香さんを海に連れ出します。次にあたかも僕が携帯電話に電話をして、それに出ます。後は中尾君が自殺するつもりだと言って彼女を不安がらせます。彼がにこにこ顔で立っていて、一件落着」
要領よく、そして少し道化て根岸が説明した。藤井教諭はあの時、彼がした電話の向こうでの含み笑いの意味をようやく理解した。
「でも、本当に自殺するとは」
溜め息混じりに根岸が言った。
「この悪戯を計画したのは?」
山名俊行が解るように少し、手を挙げた。
「お名前は確か・・・」
島袋刑事が口籠る。山名です、と名前を忘れられたのが原因だろうか、不機嫌そうに短く答えた。
「ああ、そうだ。山名君でしたね。失礼」
と一旦、詫びて、
「当時の状況を詳しく話して頂けますか?」
彼はありのままを出来るだけ詳しく説明した。浜辺からここまで走って大体三十分掛ったこと、そして、その時、中尾圭志はもう既に冷たくなっていた事などを時々言葉を詰らせながら語った。
「それで、そのビニール・シートから中尾君が飛び降りる所を見ました」
筋肉質の刑事が何時頃かと尋ねると、
「八時三十六分です」
「随分、正確に覚えてますね」
と澤村は驚いた。
「ええ、彼からの電話が中々来なくて腕時計を一分おきくらいに見てましたので」
と黒い腕時計を見せた。緑色のディジタルの文字で二十二時二十六分と表示されている。
「それで僕が藤井先生から電話を頂き、様子が変だなと思い山名君に電話しました」
根岸が言った。
「それは何時頃ですか?」
「十時頃だったと思います」
と根岸が答える。関係があるとは思えない事まで訊くので、藤井はもしかしたら警察は他殺も疑っているのではないかと思った。
「それで、自殺なんでしょうか?」
彼女は目に不安の色を漂わせて訊いてみた。
「ええ、ほぼ間違いないでしょうね、先生。遺書はまだ見つかっていませんが、後頭部に大きな裂傷がありますので、それが致命傷になって死に至ったと考えられます」
と澤村警部補が説明した。島袋刑事は、
「自殺する心当たりのようなものは」
三人は顔を見合わせた。お互いに心当たりはないかと確認しているようだ。しかし残念そうに、こう言った。
「ありません」
と。
FILE13、ホテルの廊下(二月二十八日、午後十一時〇分)
廊下には二人の刑事がいた。菫色の壁紙が貼ってあり、まだ蛍光灯が灯っていた。もしかしたら、ホテルの蛍光灯というものは消えないのかもしれない、島袋刑事はぼんやりとそう考えた。
「携帯、鳴ってますよ」
部下に言われて気がつき、電話に応対する。検察医の金城医師だった。
「ああ、金城か。どうした?解剖の報告か?」
本州の人にとっては沖縄弁は外国語のように聞こえるので、澤村に気を遣ってか標準語で話す。あるいは単に本州の人と長時間話したため、その癖が抜けず標準語になっているのかも知れない、
「はい、先輩。仏さんの司法解剖がたった今終わった所ですので報告しようと思いまして。後で正式に解剖所見を書かなければなりませんが、今のうちに先輩の耳に入れておこうと思ったんです」
金城医師と島袋刑事は割と仲が好い。というも、高校時代、先輩と後輩の間柄だったからだ。それが再び偶然再開した時の喜びといったらなかった。二人とも手を取り合って部屋中、跳び回って喜んだものである。
「そりゃ、どうも」
淡白に返すが内心、凄く感謝している。
「ええと・・・中尾圭志の頭蓋骨陥没によって、死んだと思われます」
メモを取れ、と澤村にアイ・コンタクトを送る。もう一度、復唱して確認を取る。
「死亡推定時刻は、六時から十時の間だと思われます」
「ああ、それは好い。正確な死亡時刻が訊き込みの結果、判明したからな」
と島袋が言うと何時かと訊いた。
「九時だ。というのも悪ガキどもが悪戯を決行した時刻なんだ」
「悪戯?先生の椅子にブーブークッションを仕掛けるとかですか?」
ブーブークッションとは、座ったらブーと屁の音がする座布団である。金城たちの時代に流行った悪戯と言えばその程度の物だったのだろう。
「いやいや、そんなチンケな物じゃないんだ」
そう言って山名俊行立案の偽装自殺計画について語ってきかせた。
「じゃあ、偽装でなく本当に自殺したというわけですか」
聞き終った後、金城はブラックな悪戯だな、と思った。快くは感じなかったが不快にも感じなかった。どうせ高校生の悪戯だ、敏感に反応していたら・・・・。金城医師は死体と日常的に、しかも検死というあまり気持ちの好くない形で向き合っていると死に対する感覚が麻痺しているのかもしれない、と自嘲気味に考えた。これが宗教家なら激しい不快感に包まれるだろう。
「そういう事になるな」
しばしの沈黙。自殺説を信じきっている島袋に言うのは少し気が悪いと思ったのか、言いづらそうに、
「実はですね。先輩」
「はい?」
と唐突だったので思い切り語尾上がりの間抜けな調子で言ってしまった。
「よく聞いて下さい。死班の出方と死後硬直が一致しないんです」
「死班?死後硬直?」
テレビの探偵ドラマでしか聞いた事のない島袋にとって、耳慣れない言葉だった。
「死班と言うのは、死後、血液の落下で紫色の斑点が出来る現象です。大体、これは二、三時間で現れます。ところがこの状態で動かすと死班は消えてしまいます。一方の死後硬直は二、三時間で顎、首筋から始まり、足、指という具合に上から順に固まっていきます。被害者の死体の場合・・・・」
苛々を我慢出来なくなった島袋はついに怒鳴った。その怒鳴り声に澤村も驚いて、ペンを止める。
「ええい、結論から先に言え!」
「はい」
と縮み上がってしまった金城医師は、
「死体が動かされた形跡があります」
「つまり、それは・・・」
島袋が言おうとしている事を金城医師が先に言ってしまった。
「ええ。自殺でなく、他殺です」
FILE14、ホテルの廊下(二月二十八日、午後十一時三十分)
「コーヒーでもどうぞ」
見回りをしていた藤井啓子は島袋、澤村両刑事にコーヒーを差し出す。
「ありがとうございます」
と言って島袋はコーヒーカップを一口すする。
「先生はこんな時間に何を?」
「夜回りです。時々、男子が女子の部屋に忍び込もうとするんです。それを防止するために夜回りを行っているんです」
「何か間違いがあったらいけませんからね」
澤村は笑いながら言う。しかし、藤井は今夜だけは笑う気にはなれなかった。
「私も高校時代は金城と女子の部屋に忍び込もうとしましたよ。ヴェランダを使って」
島袋も相槌を打つ。
「まあ、刑事さんたちの前でいくらなんでもそんな事はしないと思いますがね」
少し肩を竦めて、藤井が言う。刑事たちは哄笑した。
「いや、解りませんよ」
コーヒーを飲みながら澤村は言った。
「刑事さんたちに取り押さえてもらうから好いです」
藤井も笑いながら言うが、急に居住まいを正し、
「あっ、それでですね」
「はい。何でしょう」
島袋刑事が言う。
「明日の米軍基地見学は予定通り行っても差し支えないでしょうか?」
あと三十分で日付が変わるのだが、藤井はその心配をしているのだ。
「お泊まりになるホテルはどこでしょう?」
島袋刑事が事務的な調子で尋ねた。藤井は同じホテルだと告げた。
「解りました。どうか生徒さんたちに楽しい修学旅行を」
澤村はこの台詞を言った後、後悔した。しばしの沈黙。楽しい修学旅行なら自分たちがいないはずではないか。
「ええとですね」
澤村警部補は何とか弁解を試みるが、好い言い訳が思い浮かばない。
「すいません」
と素直に謝った。彼はそれが下手な言い訳よりも、好い方法だと考えたからである。
「いえいえ、いいんです」
滅相もないという具合に大袈裟に手を振った。
「中尾君が自殺しても、私たちの心で生き続けますから」
お決まりの台詞だ、と言った本人は心の中で自嘲した。しかし、頭の中ではこれしか思い浮かばなかったのだ。
「それですがね。先生」
胡座(あぐら)をかいていた島袋刑事は急に正座になり、
「他殺の疑いもあるんです。いや、むしろその方が濃いと言っても過言ではありません」
「えっ?」
藤井は口許を歪めた。正にどう言う表情を作って好いのか解らなかった時の顔だ。
「どういうことですか?」
「厳密に言うなら死体が動かされた形跡があるらしいんです。先程、検察医の知り合いから電話が掛かってきましてね、何でも死班と死後硬直が一致しないと言う事です。」
理科教師である藤井にとって、島袋の言葉の意味を理解するには難しい事ではなかった。
「そうなんですか?明日、あの子たちに訊いてみますね」
とは言う物の動かした可能性は零に等しいだろうと藤井は思った。いくら幼いといっても小学校低学年とは違う。高校二年生ともなれば死体を動かしてはならない事くらいは承知していて当然なのだ。そうすれば、他殺の疑いも出てくるだろう。
「お願いします」
しばしの沈黙。藤井の心中を考えると、両刑事ともとても気さくに話す気にはなれなかった。島袋は、「何か話せよ」と目配りをする。澤村は何を話せばいいか咄嗟には思い浮かばなかったので、何を話すべきか考えた。しばらくして、島袋はある事を思い付いて、提案した。
「どうでしょう、明日からの三日間、我々が同行すると言うのは。ガイドにもなりますしね」
私の一存では決められない、と藤井は言う。
「そうですよね」
「担当の先生と相談しないと・・・」
困ったように島袋の顔を見上げた。
「そうですよね」
提案者は悄然となり、再び同じ台詞を繰り返した。やがて十二時になり見回りの交代の時間が来た。
「それでは、私寝ますね」
「お休みなさい」
と島袋は言った。
「お休みなさい。ご苦労様です」
と別れ際に、会釈をして別れた。
「さてと、俺らもそろそろ署に戻ろうぜ」
島袋は伸びをしながら言った。
「そうですね」
澤村もあくびを噛み殺し、同意する。そして生徒たちを起こさないように、足音を消しながらエレベーターに向かったのだった。
FILE15、バス(三月一日、午前七時)
「ふぁーあ」
浅香萌は大きく開いた口を手で抑えようともせず、堂々とあくびをした。恵美は隣の席で「あくびする時位、手で抑えようよ」と言いたそうな視線をよこす。成績優秀、頭髪も規定通り、授業中に内職はたまにする事はあっても、他人の迷惑になる事はしない萌だが、こう言うところは意外とルーズなのである。視線に気付いたのか萌は、「だってー」と言い訳しようとするが、またあくびが出てしまい、
「ふぁっへー」
と外国語のような意味不明な言葉になってしまう。
「ほらほら、刑事さんも乗ってるんだし」
恵美は妹を窘(たしな)める姉のように言った。生徒の心を傷付けない範囲でという条件付きで島袋刑事は特別に同行の許可を得たのである。萌は事件の事が夜、遅くまで頭から離れず、一睡も出来なかったのである。
「そんなに気になるんだったら」
と大野恵美は言った。
「刑事さんに訊けば?」
それもそうかと萌は隣の補助席に座っていた、島袋に自分の意見を述べた。
「ふむ。だけどね、あの件は自殺という事で処理されたんだよ」
萌の意見を聞き終えた後、彼は言った。「ほらね、考えすぎよ」というように恵美は微笑する。
「自殺だとしたら、奇妙な点が二つあります。一つは遺書がない事」
「もう一つは?」
島袋は内心、焦っていたが、愛想笑いを浮かべて言った。
「二つ目は・・・刑事さんが同情している事です」
「それは、彼の自殺の原因を探るためにだね・・・」
萌は疑いの目で、澤村を見た。何か隠していると感じた萌はある作戦を決行する事にした。
「ふうん」
淡白にそう言ったので澤村警部補はひとまず安心した。だが次の瞬間、突然浅香萌が悲鳴を上げた。
「刑事さんが、私のお尻触った!」
身に覚えのない刑事は当然、動揺する。
「なっ、なっ」
浅香萌は耳打ちした。萌は恋人に迫るように妖艶な声で言った。
「これでも本当の事喋ってくれなきゃ」
首が飛ぶというポーズをにやりと笑ってしてみせた。澤村はかなり慌てている。
「おいおい。本当かよ」
とかなり動揺して呟いた。
「全く」
警部補は呆れてしまい、今まで知り得た情報を全て吐き出した。いや、「吐き出させられた」と使役の形にするのが適切だろうか。
「あっ、ごめん。何かの勘違いだったみたい」
と聞き終えた後、すぐさま訂正した。
「ほらね」
涼しい顔をして恵美に言った。彼女は別の意味で彼女を尊敬した。彼女の大胆さ、狐のような狡賢さ(ずるがしこさ)・・・。
「女優になったら?」
恵美は笑いながら言った。その回答はきっぱりとした物だった。
「いやよ。私、弁護士になるんだから」
「だったら、その癖何とかしたら?」
どの癖だろうかと萌は思った。
「どの癖?」
「色っぽい声で刑事さんに迫る癖よ、後、嘘を並べ立てて人に迷惑を掛ける癖も」
そんな癖、自分には思い当たらなかったので、少し攻撃的な口調で、
「あら。私守ってるじゃない?」
「ほら、さっき、お尻触ったって騒ぎ立てた事よ」
「捜査上、仕方のない事よ」
と萌は笑って言った。澤村刑事は彼女の言う通りだと深く思ったが、口には出さなかった。きっと、将来数々の男を騙していくのだろうかと呟いた。そんな目で無邪気のはしゃぐ萌の横顔を見つめた。
しかし、彼女、浅香萌は断じてそのような汚れた少女ではないのである。子供のように純粋で、天使のように潔らか(きよらか)で・・・。そんな少女だと言う事を大野恵美は知っていたので、澤村警部補の言葉をあえて無視した。
FILE16、バス(三月一日、午前十時)
「それで、島袋刑事」
と萌は呼びかけた。目的地の米軍基地はもう間近らしく、星条旗を掲げたF-15型戦闘機、通称トムキャットがバス上空を飛来している。
「あん?」
先程、萌に脅迫されたばかりの島袋刑事は不機嫌な声で言う。
「全員のアリバイはお訊きになったんですよね?」
「あ、ああ」
満面の笑みを浮かべて教えてくれるように頼んだ。彼は何でそんな事を教えなければならないのか、と思ったが、また悲鳴を上げられるのは嫌なので渋々、情報を提供した。
「まず、山名俊行。こいつのアリバイは一番確かだろうな」
君も解るだろう、と言うふうに浅香萌を見る。彼女は同意した。
「ええ、そうですね。中尾君の死体が落とされた時、私と一緒にいたんですから」
その通りと刑事はうなづいた。
「次に、根岸一だが、アリバイは不確かだ。部屋でテレビを見ていたんだからな」
浅香萌は一瞬、隣の部屋の生徒にテレビの音がしていたかどうかを訊いたら好いのではないかと思ったが、それはあくまでテレビが点いていたという証明にしかならない事が解った。つまり、例え隣の生徒にそう言う問いをしても、根岸はそこにいたかどうかは解らないのだ。
「では隣の部屋の生徒に・・・」
萌の発言を、刑事は遮った。
「いや、それはテレビが点いていたという証明にしかならない」
萌は嗤って、
「いや、違いますって。隣の部屋の生徒にドアの開く音がしたかどうかを訊くんです」
「残念ながら・・・」
島袋はかぶりを振った。
「我々もそれをやったが、隣の生徒は売店に出かけていていなかったということだ」
「ふうん」
「次に藤井啓子だが、アリバイがしっかりしている。鈴木美香と明日の予定の確認を雑談がてらしていからな、そう言う理由で彼女も鈴木美香も白」
島袋は、ドリンク・ホルダーにあった缶コーヒーを一口飲んだ。浅香萌は一先ず、安心した。
「大野恵美だが」
と言った時、浅香萌は微かに不快感を覚えた。しかし、疑う事が刑事の仕事だと解っていたのでその不快感は他の人よりも幾分、感じなかった。
「はい」
それでもやはり不平そうに言う。
「彼女は、根岸同様、アリバイがない。風呂に入っていたと言っていたが」
本人に気付かれないように小声で喋った。大野恵美は隣で変な二人だと視線を向けた。残る三十数名のアリバイは皆、完璧といって差し支えないものたった。楽しく談笑していたか、トランプをやっていたか、あるいは売店に買い物に行っていたかだったからである。
「外部犯の可能性はないんですか?」
大野恵美が訊いた。他殺と解った以上、せめて外部犯にしたいのだ。
「ええ、ありえませんね」
「どうしてですか?」
余りにも早く否定されてしまったため、むっとして尋ねる。
「だって」
島袋の代わりに萌が説明した。
「もし、メグの言う通り外部犯だとしたら、なぜ、自殺に見せかける必要があるの?」
メグこと、大野恵美は黙ってしまった。浅香萌は更に追撃を掛ける。
「なんで、死体を動かしたりしたのかしら」
彼女は合理的な説明が付かず、黙ってしまった。
「つまりこう言う事だ。犯人は大野恵美か根岸一のうちどちらかだ」
「しかし、この計画を実行出来るのは悪戯の計画を知っていた根岸一ということになるな」
「大野さんには知らせてなかったんでしょうか?」
浅香萌は質問するが、知らせた所で何になると一蹴された。萌は自分の手帳のページを破って、さらさらと今聞いた事を書きつけた。
六時〇〇分
↓ 自由時間
六時三〇分
↓ 夕食
八時〇〇分
↓
八時十五分 犯人、廃屋に向かう。
↓
九時四五分 私、山名に呼び出される。中尾殺害。
↓
十時〇〇分 藤井先生、根岸の部屋に電話を掛ける
↓
十時十五分 警察、到着
「こんな所でしょうか」
そのページを島袋に見せた。好くまとまっていると少し感心の意を示した。
「ちなみにホテルから廃屋まではどんなに急いでも、片道三十分かかる」
仏頂面で島袋は言った。
「ということは逆算すると・・・」
八時十五分に出発すれば好い訳であるのだが、八時十五分は大野恵美と一緒にいたのだから大野恵美は容疑者から外れる。
八時十五分から九時四十五分の時間帯でアリバイがないのは根岸一である。ある高名な探偵が言っているように、あらゆる可能性を考えて絶対にあり得ない物を消去していけばどんなに信じ難くともそれが真実である。
「でも・・・」
萌は呟いた。
「先生からの電話も考慮しなければならないよね」
確かに十時丁度に藤井教諭は電話していた。しかも携帯ではなく、部屋の電話に。藤井はこの理由を携帯の電源が切られているため、と告げた。
「もしも自転車を使ったなら?」
と萌は呟いた。自転車を使ったなら三十分で行ける所を十五分で行けるだろう。それに山道なら悪路なのでこれは使えないが、ここは砂浜なので難なく行ける。
「そうすれば着いた後で先生からの電話を受け取れば・・・」
つまり、九時半・・・殺す時間も考慮に入れると九時二十分頃に自転車で出発して廃屋に向かう。そして、中尾圭志を殺害したのが九時四十五分。
「これは私が見ているから間違いない」
と独白した。
「そして、その後自転車で再びホテルに戻る。そして十時ジャストの先生からの電話を受け取った・・・。」
しかし、何か引っ掛かった。
「でも・・・」
いくら折畳自転車と言っても旅行鞄には入り切らないのではないか。
「無理よね、それに先生からの電話は何時に来るか解らないし」
と浅香萌は独白した。
「もしも、殺害時刻がもっと前だったら?」
次にこう考えた。
「そう、例えば」
例えば八時ジャストに現場に向かい、前もって中尾圭志を撲殺する。
「これなら歩いてでも行けるわ」
そして死体を何らかの物理的なトリック、例えば糸を使う等といった方法で落とす。これは乱歩を始めとする古今東西の推理小説に登場している。
「そして、悠々と現れる・・・」
少なくとも死体が落とされたのは九時四十五分である事は間違いない、と浅香萌は思った。
「でも・・・」
高校二年生の男子の体重は少なく見積もっても六十キロである。そんな体重を支える強靭な糸があるだろうか?
「これも無理」
彼女は心の中で言った。
「ええと・・・」
別のトリックを考えているのだが、なかなか好いアイディアは浮かばない。また、一機の軍用機が上空を凄じい音を立てて飛行した。
フェンスの張った一つの都市がすっぽりと収まりそうな巨大な米軍基地が見える。いや、基地というよりも都市なのだ。基地の中には住宅、商店、そして、教会すらある。
「でも、よく近隣の人我慢できるわね」
大野恵美は感心したように言った。島袋刑事は、この事に対して発言する。
「いや、大野さん、私たちも我慢が出来ないんです」
妙に慇懃だと萌は感じたが、その事に関しては何も言わなかった。
「普天間(ふてんま)なんて、あなたたちの年代の人が基地問題に対して演説したのですから」
「へえ」
流石、現地の人だけあって詳しいと大野恵美は思った。
「でも沖縄の人って他の県よりも国際結婚、多そうですよね」
「私にも解りませんが、恐らくそうかと」
島袋は、言う。
「騒音と言えば昨日の山名君の叫び声も凄かったわよ、近隣付近の人から好くクレイムがつかなかったか不思議」
「いや、実はクレイム来たんだ」
後ろの座席に座っている張本人は恥かしそうに言った。
「へえ」
大野恵美は興味を示したらしい。
「窓を開けて怒鳴った人がいるんだ」
「でも、それでアリバイ成立したから好いじゃない」
「好いのかなあ」
と不安げに言う。
「だって、中尾君が殺されたのって九時四十五分でしょ?そんな時間のアリバイ成立しても何の意味も何の意味もないと思うんだけど」
「まあ、持ってて悪い物はないよ」
と大野恵美が笑いながら言った時、しばし黙っていた浅香萌が、
「あっ!」
突然、叫び声を上げた。どうしたのかと恵美が訊いた。
「いや、何でもないわ」
多少恥かしく思いながらも努めて平静を装って答える。トリックを思い付いたのだが、せっかく思い付いたトリックにも穴があった。
そのトリックと言うのは、九時四十五分の段階では、まだ中尾圭志は生きていて悪戯だと思って廃屋に身を潜めている。そして、浅香萌を教師の所に行かせ、犯人は走っていく振りをして、彼を殺害。
しかし・・・。浅香萌が中尾圭志の落ちる瞬間を見たのは九時四十五分である。彼女は困り果ててしまったのだった。とうとう、彼女は携帯を取り出し、有沢翔治に電話を掛けたのだった・・・。
FILE16、崩れるアリバイ
「そういうことなのよ、どう思う?」
この電話が私、有沢翔治の元に掛かってきた時、コーヒーを飲みながら仕事をしていた。これまで私が長々と書きつづってきた事は全て彼女の話を出来るだけコンパクトかつ、脚色なしに小説風にアレンジした物である。
「ふうん、つまり全員に完璧なアリバイがあるわけだね」
私は不謹慎にもわくわくした。アリバイ崩し。アリバイトリックといえばクロフツの『樽』が有名だ、などとこの際どうでもいい事を考えてしまう。
「うん。そう」
保護者としての立場なら、探偵ごっこは止めるよう忠告するのが筋だろう。しかし、美味そうで、豪華な“料理”が目の前に吊されているのに、それをみすみす味音痴の人に食べさせるのはもったいないので何も言わなかった。
面白い事件だと喉まで出かかった。しかし、クラスメイトの死を悼んでいるにも関わらず平気でそのような事を言える程、私とて鈍感ではない。
「ふうん」
私は興味を示している事をそれとなしに声の調子でアピールする。
「どう思う?」
彼女の話を聞いただけで大体トリックが解った私は、ヒントだけ与える事にした。
「うん、ねえ、萌ちゃん」
私はコーヒーを音を立てずに口に含んだ。
「萌ちゃんが見たのは本当に中尾って子だったのかい?」
「うん、間違いないと思う」
私は顔まではっきり見たのか尋ねた。
「歩いて三十分も掛かる距離で人の顔なんて見える訳ないじゃない。人影よ、私が見たのは何かが落ちる影」
彼女は不平そうに言ったが、やがて解ったように叫んだ。
「そういうことね!」
さも嬉しそうだ。そして、電話の向こうから刑事の話し声が漏れる。恐らく彼女の言う島袋刑事だろう。
「ねえ・・・」
と話し掛けてきたのを鋭い声で制する。ようやく聞き取れた単語は「毛布」という一語だけだった。しばらくして、萌ちゃんは言った。
「でも、もう一つ謎が残ってるよ」
と言ったので私はそれは何かと尋ねた。
「そのトリックを使えば私を含めて全員のアリバイが崩れるけど」
ちょうどの時間帯にアリバイトリックを実行するのは、ほぼ不可能ではないのか、という事だった。
「ああ、それは凄く簡単だよ。それに、ジャストでなくてもいいしね」
私はニヤリと不敵に笑って言った。
幕間~読者への挑戦状~
さて、ここで私は一旦あえて話を止める事にしようと思う。犯人を割り出すのに必要な証拠が全て出揃った。読者諸君は山勘などではなく論理的に犯人を考えることが出来るのである。
さあ、賢明なる読者諸君よ。解くべき方程式はただ一つ。誰が中尾圭志を殺したかである。
FILE18、名古屋空港にて
私は名古屋空港、国内便のロビーで浅香萌を待っていた。知り合いの西口警部には、空港の外で待機してもらっている。時計を見ると四時少し前である。やがて、萌ちゃんが姿を見せ、こちらに手を振った。
「お久しぶりです。藤井先生」
私は浅香萌の通っている高校に在籍していた身なので、理科の藤井教諭とは面識がある。
「久しぶりねえ、本当に」
本当に私に会えて嬉しそうだ。しかし、私はいわゆる探偵役としてやってきたのであり、恩師に会いに来たのではないのだ。そして、趣味で警察の捜査に首を突っ込んでいる事など、近況を報告した後、本題に移った。
「ええと・・・、藤井先生」
「何?」
と藤井教諭は訝しげに私を見つめた。
「殺人事件があったそうですね」
生徒を動揺させないように出来るだけ小さな声で言った。
「え、ええ。でも、何も知らないでしょう?」
私は浅香萌から全てを聞いていると告げた。
「ふう」
と大儀そうに溜め息混じりに、
「有沢君の推理好きもかなりのものね。でも今はダメ。生徒が動揺するから」
私は微笑して、
「解っています」
「生徒が帰ってからにしてくれる?」
教諭は私に頼んだ。私はそれで好いと言った。最後の生徒、山名俊行がいなくなるまで二時間掛かって六時になり、日の短い三月上旬の名古屋はもう既に暗くなっていた。
「それで、誰が犯人なの?」
藤井教諭は心配げに訊いた。教え子の未来が掛かっているので、相当心配しているようだ。
「まず、それを喋る前に事件の整理をしてみましょう」
私は空港の自動販売機に百円硬貨を投入して言った。
「最初に萌ちゃんは九時三十分に呼び出された。そして浜辺へ行ったら山名君が立っていた。そこまでは好いね?」
「ええ、間違いないわ」
と彼女がうなづくのを見て、私は話を進める。
「九時四十五分に死体発見。これは?」
再び萌ちゃんに話を振った。
「間違いない」
あえて肯定する。私の言う事を予想してくれたのだろう。私はそれに感謝の意を示しつつ、
「本当に?顔まで見えた?」
「顔は見えなかったけど、何かが落ちるのを見たのよ。山名君が電話で中尾君の自殺を止めてたから私てっきり彼だと思い込んじゃって」
浅香萌は申し訳なさそうに頭を掻いた。
「今の証言からでも解るように」
私は缶コーヒーのプルタブを起こしながら言った。
「正確には彼が落ちる所ではなくて、何かが落ちる所だったのです、先生」
「どっちでも一緒だと思うけど・・・」
私の言っている意味が好く解らない、と言いたげな顔付きをして私を見つめる。
「先生。それが大きく違うんですよ。犯人が落としたのは死体でなく、人形だったとしたら?」
「人形?」
藤井教諭はおうむ返しに言った。どうやらレスキュー隊が使う人工呼吸練習のためのダミー人形を想像しているらしい。漫画だったら頭の上にクエスチョン・マークがいくらか浮かぶだろう。
「人形なんて持っていってないけど・・・」
「いや、人形でなくても例えば毛布を丸めて紐で縛った物でも好いのです」
「なるほどね」
藤井は敬服したように呟いた。少し照れながら、私はコーヒーで喉を潤すと、
「幸運な事は、あの時、廃屋がビニールシートで覆われていた事です。人形を隠すのに最適な場所ですからね」
「それで?」
教諭は後を促す。
「はい、萌ちゃんが九時四十五に見たのは中尾圭志の死体ではなく、毛布だったのです。そして、彼は八時に殺害されたのでしょう」
「どうしてそんなに正確に解るの?」
藤井教諭が言った。
「廃屋から歩いて往復一時間は掛かります。そして九時半の時点ではアリバイを作るために誰かと一緒にいなければならない」
「誰か、って?」
浅香さんの事でしょう、と確認するように彼女の方へ視線を向ける。
「そうです。犯人はアリバイ作りのために彼女を利用したのです」
私は肯定する。
「じゃ、じゃあ・・・」
声は震えている。
「そう、犯人は山名俊行君です」
「先生」
と言う声が後ろでした。
「僕が犯人ってどう言う事ですか?」
割と落ち着いている。私にアリバイトリックが崩せるはずがないと高を括っているのかもしれないが、もう砦の一つは陥落した。
「確かに、そのトリックを使えば僕には犯行が可能です。しかし、僕だけでなくクラス殆ど全員のアリバイがなくなりますよ。浅香さんや先生のアリバイも、です」
いよいよ真打ちが出て来たと興奮していたが、口調は落ち着き払って、
「いや、あなたにしか出来ないんですよ」
「なぜです?」
噛み付くように山名は言った。
「人形を落とす必要があったからですよ」
「あっ、それ私も気になってた。どうやって人形を落とすのかって」
萌ちゃんが言った。
「つまりこう言う事だよ。彼の最新式のクーラーボックスで、中に釣り糸を通した氷を作る。そして、その先端に人形を取り付ける」
「どう言う事?」
と萌ちゃん言った。やはり口で説明するのは難しいと感じた私は、以下に示す図を書いて、
「つまりこういう事だよ」
と言って、紙を渡した。図はその紙をスキャナで取り込んだものだ。
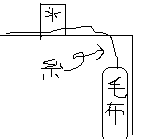
悪筆で大変申し訳ないのだが、見てイメージを掴んでほしい。氷が段々と融けて、そのうちに釣合が取れなくなり落下する、言わば自動落下装置である。
「あなたにとって幸運だったのは」
私は缶コーヒーを飲みながら言った。
「前日に雨が降った事でした」
「雨?」
萌ちゃんがおうむ返しに訊いた。
「うん。雨が降っていなければ、氷の痕跡も残るからね」
「なるほど、そのトリックを使えば僕が一番怪しいと言う事になります。僕は釣り糸も、自動的に氷が作れるクーラーボックスも持っているんですから。でもそれは僕が犯人だと言う前提で物事を進めているにすぎない。そうなんじゃないでしょうかね」
「つまり、あなたが犯人である証拠を見せろと」
山名ははい、と答える。
「好いでしょう、あなたが犯人である決定的証拠をお聞かせしましょう」
あるのかどうか訝しげに藤井教諭は見た。私は不敵な笑みを浮かべている。
「あなた、根岸さんにこう言っていますね。『解らない。他殺かも・・・』って」
「その通りに言ったのかどうかは解りませんが、根岸君に他殺の可能性もあると言ったのは・・・」
やがて、自分のミスに気付いたのか顔色が蒼くなる。
「そう、あの時点では誰がどう見ても自殺です。なのに、あなたは他殺かもしれないと言っていますね。どうして他殺だと言ったのでしょうか?」
最後の砦も陥落し、山名俊行は二〇〇二年三月二日、午後六時三十分に敗北宣言をしたのである。
「負けましたよ」
エピローグ
赤い悪魔が全てを飲み込んでから二年の月日が経った。妹を失って、まだ悄然としたまま、俊行も学校に上がった。そして意外な所で真犯人と出会うことにになる。
それは文化祭の打ち上げで、カラオケに行った時の事だった
「おい、俊行。お前も何か歌えよ」
圭志が隣の俊行を突く。酒が入っているらしく、呂律が回っていない。
「そうそう、校歌とか」
と言っているのはもちろん、根岸だ。そして、校歌の歌詞を口ずさみ始めた。
「入っていないって」
クラスの女子の一人が言う。
「う、うん」
居心地が悪そうに山名は言った。それを見て、気の優しい女子が話題を持ちかける、好きな歌手は何だとか、定番の話だった。
「ねえねえ、妹か弟、いる?」
本人にしてみれば何の気なしに訊いたのだろうが、彼にとっては衝撃を与えたのだった。
「妹が一人・・・」
「へー、可愛い?」
「うん、可愛かったよ」
無意識に過去形にしてしまった。
「何で過去形なの?」
彼は咄嗟に思い付いた言い訳でその場を切り抜けた。
「今は憎たらしくて」
酔いの回った中尾が難癖を付けた。
「違うだろう。死んだんだろ」
その場の雰囲気がまるで葬式場のように沈黙した。やがて、一人の男子が口を開く。
「死んだ、って?」
「ああ、火事でな」
素気なしに中尾が言った。その場が凍りついているのを皆が感じた。そう、酒によって理性を失った酔漢(よいどれ)以外は。彼はなおも続ける。
「俺が火を点けたんだ」
その口調からは謝る素振りなど、微塵も感じられなかった。テレビ・ゲームで高得点を出したかのような口調だった。そしてこの時、殺意が芽生えたのだが、この時は酔った勢いで口から出任せを言っているのだろうと思った。
「ねえ、訊きたい事があるんだけど」
八時頃海辺に呼び出し、事の真相を訊いた。
「あ、ああ。確かに放火したのは俺だよ」
幾分申し訳なさそうに言ったものの、その口からはきちんとした謝罪の言葉は出なかった。それどころか、彼は開き直り、
「俺にどうしろって言うんだ?」
と嘲けり嗤うように言った。この時、何かのスイッチが入ったように近くに落ちていた珊瑚の死骸で彼の頭を一撃殴ったのだった。
中尾の死体を置くために、走って廃屋へ向かう。人形のトリックを仕掛け、氷をセットする。
「これでよし」
と満足げに呟やき、三十分で海辺に戻った。海辺には浅香萌はまだ来ていなかったので一安心した。
「まあ。釣りに行った事になってるんだし、僕が廃屋側から走ってきたとしても、何の不思議もないよな」
と呟いた。やがて浅香萌がやってきたので、ここからが正念場だと思った。いかに自殺に思わせるか、いかに馬脚を現さないか・・・プレッシャーは増すばかりである。
「えっ!今から自殺する?」
根岸が掛けてきた電話に応対してそう叫ぶ。悪戯だと思っている彼は犯罪計画の一部だと当然知なかった。
「これでよし」
廃屋に行った時、人形を海に捨てた。前呼び出しておいた浅香萌にアリバイの証人になってもらうだけだ。しかし、九時四十五分から十時十五分までのアリバイは?
中尾はその時、まだ生きていて駆け付けた人物によって殺害されたと警察が考えたら、疑われるのは山名だ。肚を探られて、うっかり尻尾を出してしまうのが落ちだ。そう考え、こう思ったに違いない。
「それは嫌だ」
考えろ、考えろと彼は独白した。苦肉の策として、叫び声を上げて近隣の人にアリバイを証明してもらおうと考えたのだ。
案の定煩い、と叫んでくれたので彼は、ほっと一安心する。ところが十時頃、アクシデントが起きた。根岸からの電話だ。しばらく放っておけば諦めるだろうと思ったが、彼はなかなか諦めず仕方なしに出る。
「はい、もしもし」
犯罪を行っている最中なので、声が強張る。馬脚を現さないよう細心の注意を払っているつもりだったが、こう言ってしまったのだ。
「まだ、解らないけど、他殺かもしれない」
と。
「という訳です」
山名は大きく溜め息を吐いて言ったのだった。藤井教諭から、これは内密にするように頼まれた。私は彼のその後の人生も考慮し、電話した。
「あっ、西口警部ですか?」
「警部」という一語に藤井教諭は敏感に反応したのだが、山名はどうでもいいと言う様子でスポーツ・ドリンクを飲んでいる。
「沖縄での一件、やはり自殺みたいです。わざわざ足を運んで頂いて恐縮なんですが僕の勘違いでした」
「でも、沖縄県警の・・・」
「沖縄県警が言おうが、どこが何と言おうが自殺は自殺です」
私はきっぱりと言うと、警部は不服そうに電話を切った。
「これでいいんでしょう?先生」
私はにっこり笑って、彼女にウィンクしたのだった。
この作品はいかがでしたか?
一言でも構いませんので、感想をお聞かせください。